水村美苗『日本語が亡びるときー英語の世紀の中で』(筑摩書房)をやっと読了した。
少し読んでは本を閉じ、日をおいて続きを読むという具合で、ずいぶんと日数のかかった読書になった。著者の筆致は軽快で、けっして読みにくい文章ではない。しかし、語られる内容がずしりと重いのである。
読書はどこか潜水に似ていると常々思っているが、息苦しくなる前に、早々と息継ぎのために浮上を繰り返すような読書体験だった。内田樹氏が自身のブログで、この本を「肺腑を抉られるような慨世の書」と評されていたが、まことにそのとおりなのである。
水村美苗は書いている。「この本は、この先の日本文学そして日本語の運命を、孤独の中でひっそりと憂える人たちに向けて書かれている。(略)少なくとも日本文学が『文学』という名に値したころの日本語さえもっと読まれていたらと、絶望と諦念が錯綜するなかで、ため息まじりで思っている人たち向けて書かれているのである」
書名から、予断を抱いてはいけない。安易な日本語滅亡論のたぐいではない。たとえば埼玉大学の長谷川三千子教授は、廃刊間近の『諸君』5月号に『水村美苗「日本語衰亡論」への疑問』という論文を寄稿している。しかし「日本語衰亡論」という言葉でもすくいとれるような内容ではない。 長谷川論文の結語はこうである。
「…私は、水村さんと手を取り合って嘆かうとは思はない。私は、彼女の手を引っぱって、さあ、日本語はこれからよ!いざ!逆襲!と鬨の声あげたいと思ふのです」
能天気な学者である。「逆襲」などという語を使うところを見ると、それなりの危機感を抱いているらしいが、これでは水村美苗をなにも理解していないと同じだ。水村美苗は、「話し言葉」としての日本語が亡びると言っているわけではなく、「書き言葉」(つまり読まれる言葉)としての日本語の運命を憂えているのである。言葉というものを「話し言葉」を中心に考える弊害について、水村美苗はイヤというほど訴えているのに、そこのところが長谷川教授には届いてないらしい。
ところで漱石の『三四郎』について、水村美苗は意外な切り口からの解釈を披露している。こんな『三四郎』の読み方があったのかと、目から鱗の落ちるような思いだった。
少し読んでは本を閉じ、日をおいて続きを読むという具合で、ずいぶんと日数のかかった読書になった。著者の筆致は軽快で、けっして読みにくい文章ではない。しかし、語られる内容がずしりと重いのである。
読書はどこか潜水に似ていると常々思っているが、息苦しくなる前に、早々と息継ぎのために浮上を繰り返すような読書体験だった。内田樹氏が自身のブログで、この本を「肺腑を抉られるような慨世の書」と評されていたが、まことにそのとおりなのである。
水村美苗は書いている。「この本は、この先の日本文学そして日本語の運命を、孤独の中でひっそりと憂える人たちに向けて書かれている。(略)少なくとも日本文学が『文学』という名に値したころの日本語さえもっと読まれていたらと、絶望と諦念が錯綜するなかで、ため息まじりで思っている人たち向けて書かれているのである」
書名から、予断を抱いてはいけない。安易な日本語滅亡論のたぐいではない。たとえば埼玉大学の長谷川三千子教授は、廃刊間近の『諸君』5月号に『水村美苗「日本語衰亡論」への疑問』という論文を寄稿している。しかし「日本語衰亡論」という言葉でもすくいとれるような内容ではない。 長谷川論文の結語はこうである。
「…私は、水村さんと手を取り合って嘆かうとは思はない。私は、彼女の手を引っぱって、さあ、日本語はこれからよ!いざ!逆襲!と鬨の声あげたいと思ふのです」
能天気な学者である。「逆襲」などという語を使うところを見ると、それなりの危機感を抱いているらしいが、これでは水村美苗をなにも理解していないと同じだ。水村美苗は、「話し言葉」としての日本語が亡びると言っているわけではなく、「書き言葉」(つまり読まれる言葉)としての日本語の運命を憂えているのである。言葉というものを「話し言葉」を中心に考える弊害について、水村美苗はイヤというほど訴えているのに、そこのところが長谷川教授には届いてないらしい。
ところで漱石の『三四郎』について、水村美苗は意外な切り口からの解釈を披露している。こんな『三四郎』の読み方があったのかと、目から鱗の落ちるような思いだった。












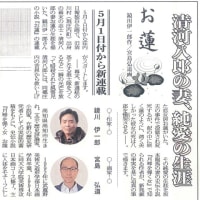
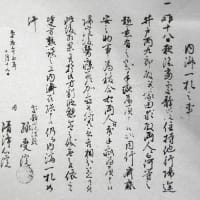
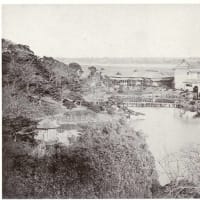
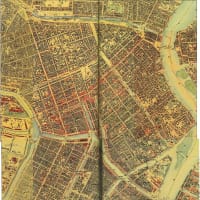
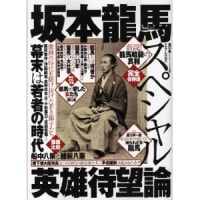


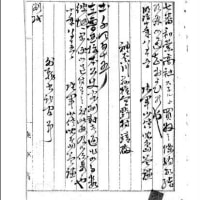





さて、私は事大主義というようなにおいは露ほども感じませんでした。
水村氏の著書は非常に要約の難しい本ですが、「…学校教育という、すべての日本人が通過儀礼のように通らなければならない教育の場において、〈国語〉としての日本語を護るという、大いなる理念をもたねばならないのである〉(285ページ)という主張に力点があると私は理解しております。
これをして事大主義、あるいは何をおおげさなことを言っているのだとは、私は思わないということです。
事大主義は日本人一般に見られることで特別ではありません。カタカナ語の氾濫なども事大主義と言える現象で他の国には奇妙な現象と見られているのではないでしょうか。問題は日本人が日本語をよく知らないという点です。日本語は中国語の現地語に過ぎないと言われて反論する人がいないのも日本語に対する無知が原因でしょう。
水村氏は「日本の〈書き言葉〉が漢文圏のなかの〈現地語〉でしかなかった…」(158ページ)と言っているのであり、こういう発言をされるときは〈書き言葉〉の日本語に限っておりますよ。いずれにせよ、水村本を再読する機会を与えていただいたコメントに感謝します。後日、機会があれば再度水村説についての私見を述べてみたいと思います。