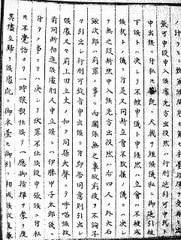大巡察の古賀十郎の証拠探しの結果については、後まわしにしておこう。ぜひとも見ておかなければならない別の事件がある。『岩倉公実記』中の資料名でいえば、「賀陽宮御不審一件」である。
横井小楠暗殺事件は、たんに一人の要人を抹殺したというだけでなく、実はもうひとつ別の側面を持っているからである。事件の黒幕は一石二鳥の手を打ったと思われるのである。
賀陽宮(かやのみや)とは朝彦親王のことであるが、親王は幕末維新史のそれぞれの局面でさまざまな通称でよばれた。たとえば青蓮院宮、粟田宮、中川宮、獅子王院宮、尹宮(いんのみや)、久邇宮、むろん皆同一人物である。ちなみに昭和天皇の皇后は朝彦親王のお孫である。
さて、その親王はいわゆる公武合体派の中心的人物だったが、孝明天皇の死をさかいに政治生命にかげりが生じ、王政復古のクーデタ後は失脚したも同然だった。
その親王の邸を明治元年8月16日の明け方、突如、広島藩兵が包囲した。謀反の嫌疑である。王政復古政府を倒して徳川幕府再興を計画しているのではないか、そういう疑いである。
親王を糾問したのは議定の徳大寺実則、刑法官判事の中島錫胤そして中島の上司で刑法官知事の大原重徳がいた。
糾問側は親王が前田某に渡したという文書を証拠物件としておさえていたが、これが偽物だったから親王に簡単に否定されてしまう。困った徳大寺が使いを岩倉のもとに走らせ指示をあおいだ。
岩倉はいらだった声で言う。「詮議はいいから、とにかく広島藩にお預けと申し渡せ」
そして付け加えた。「あの御方がいては御維新の邪魔になる」
親王は位と親王の称号をも剥奪され、朝彦王として即日広島に下った。京都からの強制追放だった。
朝彦王が広島から京都へ戻ることの許されるのは明治3年閏10月20日である。
つまり横井暗殺犯たちの処刑が終わってから、朝彦王は帰還を許されているのだ。もっとも、しばらくは他人との面会を禁じられていたらしく、新政府の警戒心はまだ完全にとけてはいない。
さて横井暗殺犯たちと、朝彦親王に実は接点があった。
横井小楠暗殺事件は、たんに一人の要人を抹殺したというだけでなく、実はもうひとつ別の側面を持っているからである。事件の黒幕は一石二鳥の手を打ったと思われるのである。
賀陽宮(かやのみや)とは朝彦親王のことであるが、親王は幕末維新史のそれぞれの局面でさまざまな通称でよばれた。たとえば青蓮院宮、粟田宮、中川宮、獅子王院宮、尹宮(いんのみや)、久邇宮、むろん皆同一人物である。ちなみに昭和天皇の皇后は朝彦親王のお孫である。
さて、その親王はいわゆる公武合体派の中心的人物だったが、孝明天皇の死をさかいに政治生命にかげりが生じ、王政復古のクーデタ後は失脚したも同然だった。
その親王の邸を明治元年8月16日の明け方、突如、広島藩兵が包囲した。謀反の嫌疑である。王政復古政府を倒して徳川幕府再興を計画しているのではないか、そういう疑いである。
親王を糾問したのは議定の徳大寺実則、刑法官判事の中島錫胤そして中島の上司で刑法官知事の大原重徳がいた。
糾問側は親王が前田某に渡したという文書を証拠物件としておさえていたが、これが偽物だったから親王に簡単に否定されてしまう。困った徳大寺が使いを岩倉のもとに走らせ指示をあおいだ。
岩倉はいらだった声で言う。「詮議はいいから、とにかく広島藩にお預けと申し渡せ」
そして付け加えた。「あの御方がいては御維新の邪魔になる」
親王は位と親王の称号をも剥奪され、朝彦王として即日広島に下った。京都からの強制追放だった。
朝彦王が広島から京都へ戻ることの許されるのは明治3年閏10月20日である。
つまり横井暗殺犯たちの処刑が終わってから、朝彦王は帰還を許されているのだ。もっとも、しばらくは他人との面会を禁じられていたらしく、新政府の警戒心はまだ完全にとけてはいない。
さて横井暗殺犯たちと、朝彦親王に実は接点があった。