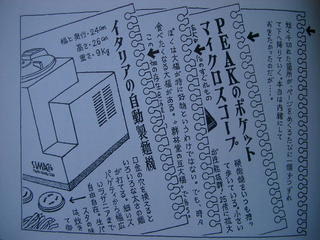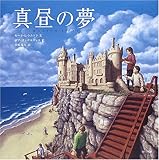KY式日本語―ローマ字略語がなぜ流行るのか
 なんていう本があるのです。
なんていう本があるのです。
KY=空気読め(Kuukiyome)の略、というのは知ってましたが、そのほかにもいろいろあるのですね。
携帯でメールを送るのに便利ということで若者に広まったというこの言葉。
本当に使われているのかどうかはわからないけれど、400個ほどが集められています。
日本語が乱れてる~と嘆く方もいるかと思いますが、まあ昔からCDとかTVとかTELとかATMとか英語の略語はありましたよね。
それを日本語をローマ字にして流用っていうのが新しい発想かも。
中には笑えるものが結構あります。
次のはなんだと思いますか?
1、IT
2、KA
3、PSI
4、ND
5、DD
答え~~
1、アイス食べたい
2、ケツあご(割れたあごの事)
3、パンツにシャツイン(ダサい服装のことらしい。ヴィゴ~~ )
)
4、人間としてどうよ
5、誰でも大好き(思わず「DDさん!」と叫びました・・・・本来はグループなんかの誰でもすき、という意味。「おっさんで汚れ系ならDD」とかも使うのか?)
ひとつの略語でいろいろ意味のあるものも。
JKは「女子高校生」「冗談は顔だけにして」「自主規制」「常識で考えて」「自分で考えて」
ミーハーのjesterなので調子に乗って
「メールのとき便利じゃない! じゃあさ、早く帰ってきなはHKKか! いまどこ?IDだね~ 何時に帰るの?はNKだし、ゴハン食べるの?はGT!・・・」
といろいろ考えていたら、家族B(大学生)に
「・・・IKS(いい加減にしてよ)・・・・」
とすごく醒めた目つきで言われました・・・・
 なんていう本があるのです。
なんていう本があるのです。KY=空気読め(Kuukiyome)の略、というのは知ってましたが、そのほかにもいろいろあるのですね。
携帯でメールを送るのに便利ということで若者に広まったというこの言葉。
本当に使われているのかどうかはわからないけれど、400個ほどが集められています。
日本語が乱れてる~と嘆く方もいるかと思いますが、まあ昔からCDとかTVとかTELとかATMとか英語の略語はありましたよね。
それを日本語をローマ字にして流用っていうのが新しい発想かも。
中には笑えるものが結構あります。
次のはなんだと思いますか?
1、IT
2、KA
3、PSI
4、ND
5、DD
答え~~
1、アイス食べたい
2、ケツあご(割れたあごの事)
3、パンツにシャツイン(ダサい服装のことらしい。ヴィゴ~~
 )
)4、人間としてどうよ
5、誰でも大好き(思わず「DDさん!」と叫びました・・・・本来はグループなんかの誰でもすき、という意味。「おっさんで汚れ系ならDD」とかも使うのか?)
ひとつの略語でいろいろ意味のあるものも。
JKは「女子高校生」「冗談は顔だけにして」「自主規制」「常識で考えて」「自分で考えて」
ミーハーのjesterなので調子に乗って

「メールのとき便利じゃない! じゃあさ、早く帰ってきなはHKKか! いまどこ?IDだね~ 何時に帰るの?はNKだし、ゴハン食べるの?はGT!・・・」
といろいろ考えていたら、家族B(大学生)に
「・・・IKS(いい加減にしてよ)・・・・」
とすごく醒めた目つきで言われました・・・・














 去年、フランスでこの本を原作とした映画が撮られ、それをみられた方のブログを読んで、映画も心待ちにしておりました。
去年、フランスでこの本を原作とした映画が撮られ、それをみられた方のブログを読んで、映画も心待ちにしておりました。









 だけは表紙がいただけませんねえ・・・・
だけは表紙がいただけませんねえ・・・・
 )
)