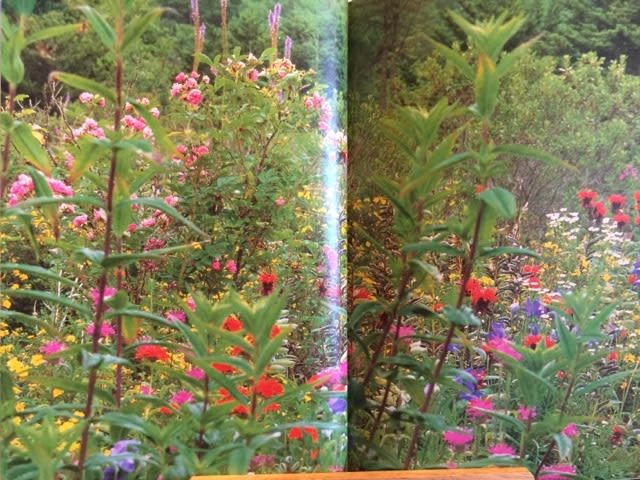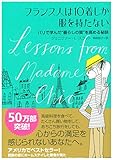コロナ禍を粛々と本を読むことで過ごしているjesterでございます。
若竹七海さんの『葉村晶シリーズ」もその中に入っておりまして、
一作目の『プレゼント』

プレゼント (中公文庫)
から始まって、
2作目『依頼人は死んだ』

依頼人は死んだ (文春文庫)
3作目『悪いうさぎ』

悪いうさぎ (文春文庫)
と惰性で読み進んで、正直もうこのシリーズはいいかな・・・という気分でした。
これらが短編集ということもあって、まあ最後に全体が繋がる構成の本もあるのですが、どの事件もいや〜〜な人間の悪意みたいなのが漂っていて、必ずしも読後感がいいとは言えないものが多かったのです。
では4作目の『さよならの手口』

さよならの手口 (文春文庫)
はどうなのか。
これが面白かったのです。
ヒロインの葉村晶さんはハードボイルド系の女探偵さんで、4作目では40代に入っています。
『世界で最も不運な探偵』というあだ名がつくほど、行く先々でトラブルが待っている探偵。
(去年、NHKで、シシド・カフカさんが主演してドラマ化もしております)
探偵もやめて、古本屋でアルバイトをしながら漫然と日々を過ごしていた彼女が、古本の回収に行ったボロ屋で、本を取り出していた物入れの床が抜けて、床下に隠してあった水分を含む白骨に顔からダイブして怪我をする・・・・というスタートから、話はスピード感を持って展開していきます。
入院した病室で、警察官が事件について話し、同室だった女性がそれを聞いて、元探偵と知って、探偵を依頼してくる・・・という辺はちょっと強引ですが、その後、葉村晶が皮肉を込めた呟きを漏らしながら、次々と体を張って謎に挑戦していくところは、昔読んだスー・グラフトンのキンジー・ミルホーンシリーズや、サラ・パレツキーのV.I.ウオーショースキーシリーズを彷彿とさせるタフ・ガイさ。
日本でもこんな女性探偵の女性事件を扱ったものを女性の著者が描く、『Witten by, about and for Womem 』って奴の傑作があったとは。
コロナ禍の梅雨に、女探偵のハードボイルド謎解きに浸ってみるのもいいかもしれません。
まだ葉村晶シリーズを読んだことがない方なら、『さよならの手口』から読み始めて、葉村ワールドに浸ってから、1作目に戻って読む、という読み方もおすすめします。
この後、『静かな炎天』

静かな炎天 (文春文庫)
『錆びた滑車』

錆びた滑車 葉村晶シリーズ (文春文庫)
『不穏な眠り』

不穏な眠り (文春文庫)
とシリーズが続いていきます。まだ読んでいないので楽しみ。
すっかり『女探偵』マイブームがわき起こり、懐かしのスー・グラフトンやら

サラ・パレツキーを

本棚から引っ張り出して、埃を払って、読んでみようかな、なんて思う、雨の1日でした。
若竹七海さんの『葉村晶シリーズ」もその中に入っておりまして、
一作目の『プレゼント』

プレゼント (中公文庫)
から始まって、
2作目『依頼人は死んだ』

依頼人は死んだ (文春文庫)
3作目『悪いうさぎ』

悪いうさぎ (文春文庫)
と惰性で読み進んで、正直もうこのシリーズはいいかな・・・という気分でした。
これらが短編集ということもあって、まあ最後に全体が繋がる構成の本もあるのですが、どの事件もいや〜〜な人間の悪意みたいなのが漂っていて、必ずしも読後感がいいとは言えないものが多かったのです。
では4作目の『さよならの手口』

さよならの手口 (文春文庫)
はどうなのか。
これが面白かったのです。
ヒロインの葉村晶さんはハードボイルド系の女探偵さんで、4作目では40代に入っています。
『世界で最も不運な探偵』というあだ名がつくほど、行く先々でトラブルが待っている探偵。
(去年、NHKで、シシド・カフカさんが主演してドラマ化もしております)
探偵もやめて、古本屋でアルバイトをしながら漫然と日々を過ごしていた彼女が、古本の回収に行ったボロ屋で、本を取り出していた物入れの床が抜けて、床下に隠してあった水分を含む白骨に顔からダイブして怪我をする・・・・というスタートから、話はスピード感を持って展開していきます。
入院した病室で、警察官が事件について話し、同室だった女性がそれを聞いて、元探偵と知って、探偵を依頼してくる・・・という辺はちょっと強引ですが、その後、葉村晶が皮肉を込めた呟きを漏らしながら、次々と体を張って謎に挑戦していくところは、昔読んだスー・グラフトンのキンジー・ミルホーンシリーズや、サラ・パレツキーのV.I.ウオーショースキーシリーズを彷彿とさせるタフ・ガイさ。
日本でもこんな女性探偵の女性事件を扱ったものを女性の著者が描く、『Witten by, about and for Womem 』って奴の傑作があったとは。
コロナ禍の梅雨に、女探偵のハードボイルド謎解きに浸ってみるのもいいかもしれません。
まだ葉村晶シリーズを読んだことがない方なら、『さよならの手口』から読み始めて、葉村ワールドに浸ってから、1作目に戻って読む、という読み方もおすすめします。
この後、『静かな炎天』

静かな炎天 (文春文庫)
『錆びた滑車』

錆びた滑車 葉村晶シリーズ (文春文庫)
『不穏な眠り』

不穏な眠り (文春文庫)
とシリーズが続いていきます。まだ読んでいないので楽しみ。
すっかり『女探偵』マイブームがわき起こり、懐かしのスー・グラフトンやら

サラ・パレツキーを

本棚から引っ張り出して、埃を払って、読んでみようかな、なんて思う、雨の1日でした。