
ミスター・ピーノの【見るが勝ち通信】その109
私の知り合いであるミスター・ピーノさんは
海外滞在が長く、
外国語にもご堪能な方ですが、一週間程度で
物凄い量のものを、見る、読む、聴く。
私も見習いたいと思っております。
ピーノさんからいただいているメールマガジンを
ご本人の承諾を得てこのブログに転載しているものであります。
読者の皆様、感想等ございましたら
私が責任を持ってお伝えしますので
ぜひコメント欄にお願いします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◇商工会議所が定期的に発行する広報誌に、地元ミニシアター・オーナー
の連載コラムがあり、売上の5~6割を配給会社に支払っている、とのこと。
裏を返せば、40~50%の利益があるわけで、そこから家賃・宣伝・人件費
や光熱費などを差し引いたものが最終的な利益になるんですね。 もっとも、
映画館施設(座席、映写機)の維持にそれなりの費用がかかるはずですし、
ビジネスとして考えると、ただでさえ減少している観客動員をどうするのか、
上映作品や企画も含めて魅力的なサービスを提供することが大切ですね。
◇メキシコに行く前、大学のスペイン語の授業とは別に、JR信濃町駅から
徒歩1分の日本スペイン協会に通っていたことがあり、同じクラスに津田塾
を卒業して、国会に勤めていた女性がいて、彼女も荻窪に住んでいました。
たまに総武線で一緒に帰ることがあり、国立競技場の近くによく行くジャズ
喫茶があるという話を聞いていて、年末年始に彼女が実家に帰省するとき
「トント tonto:西語で“とんま”」という名前の三毛猫を預かったりしましたが、
千駄ヶ谷のジャズ喫茶『ピーター・キャット』って、村上春樹の店でした(笑)
◇母と兄と実家近くのお寿司屋でお任せランチ。家内はメキシコ駐在時代
の奥様方と広尾のメキシコ料理店にて「女子会」、兄嫁は登山のため欠席。
5人での食事は年に1、2回あるものの、親子3人の外食は本当に久しぶり。
実家は10数年前二世帯住宅に建て替えられて母が1階、兄夫婦とたまに
帰ってくる甥が2階です。今でも最寄のバス停まで歩いてバスに乗り病院
の検査や買い物に行く母は一人自炊しており、兄は来年定年を迎えます。
杉並区在住のある世代の典型的な家族ともいえ、高齢化の波がここまで。
◇ぼくは千駄ヶ谷の産院で生まれたんですが、そのころ家族は中目黒に
住み、それからすぐ荻窪に移ったんですね。千駄ヶ谷というと国立競技場
や東京体育館など東京オリンピック(1964)のために作られた施設が多く、
信濃町駅との中間にあった神宮外苑のプールは、夏場は客席スタンドが
開放されて屋外プールになり、冬場はアイススケートのリンクでした。今は
京都在住のTさんと中学時代二人でそのプールに泳ぎに行ったことがあり、
あの状況は今思い出しても、なんというのか不思議なできごとでした(笑)
【演劇】
■東京セレソンDX 「笑う巨塔」(サンシャイン劇場、12/10/06 ★★★★)
結成15年で解散公演。 作・演出・主宰の宅間孝行(サタケミキオ)は映画
やテレビドラマの脚本家としても知られ、記念すべき最終公演は10年前の
初演コメディの再演。 病院のロビーを舞台にして代議士と秘書たち、医者
と看護士、親方と家族と弟子たちの間で起きる「勘違い」と行き違いによる
ドタバタ喜劇。 まるで松竹新喜劇の世界で、金田明夫も、デビット伊東も、
松本明子も自分の役柄を楽しんでおり、何よりも宅間さんの観客に対する
最後の挨拶に感謝の気持ちがこめられ、惜しまれるベテラン劇団の終幕。
http://ts-dx.com/wp/waraukyotou/
■劇団鹿殺し 「田舎の侍」(下北沢駅前劇場、12/10/07 ★★★★☆)
脚本:丸尾丸一郎、演出:菜月チョビのコンビに、オレノグラフィティ主演の
ロック・オペラ。 西遊記に織田信長と徳川家康の歴史を合わせた時代劇。
侍にあこがれる金髪少年(オレノグラフティ)と幼馴染(山岸門人)の二人
が動乱の戦国時代を生き抜く話で山本光二郎(コンドルズ)のダンスあり、
チョビの歌ありのいつもの全力投球の舞台です。 たまたま最前列の座席
で、数mの距離で彼らの額の汗を間近に感じながら、ある到達点に達して
またひとつ上のステップに登って行く劇団の「分岐点」ともいえる作品です。
http://shika564.com/inaka/
■「K・ファウスト」(世田谷パブリックシアター、12/10/07 ★★★★)
作・演出・美術:串田和美による、元オンシアター自由劇場のサーカス版。
メフィストフェレス(串田)に魂を売って若返ったファウスト博士(笹野高史)
とその後を追う道化師(小日向文世)の珍道中。 舞台上で実演する空中
ブランコの妙技と迫力に圧倒され、旅芸人の曲芸パフォーマンスも楽しく、
音楽は、coba(小林靖宏)のアコーディオン中心の楽隊アンサンブルです。
「若さ」と「お金」を手に入れた悪魔との契約が、果たして幸せだったのか、
楽しみながらも考えさせられるテーマで、徹底して娯楽にこだわった舞台。
http://k-faust.com/
【映画】
■ツナグ (★★★☆)
辻村深月の小説を映画化。亡くなった死者と一度だけ満月の夜に会える
ようにスケジュール調整を行う、“現代版イタコ”のような不思議な霊力を
持つ祖母(樹木希林)の仕事を手伝い始める高校生(松坂桃李)の物語。
この世にいなくなってしまった人たちとのほんの数時間の再会は、生きる
者の都合で心残りや後悔から生じたエゴと釈明するための機会じゃない
かと思ってしまうと、このファンタジー(お伽噺)は成り立たなくなりますが、
最後まで友だちに本音トークができなかった女子高生(橋本愛)に共感。
公式HP ⇒ http://www.tsunagu-movie.net/
■アウトレイジ ビヨンド OUTRAGE BEYOND (★★★★)
前作は末端組織の代理戦争でしたが、本編はその後巨大化した親元の
暴力団「山王会」の会長(三浦友和)の下で起きる内部抗争。 ○暴担当
の刑事(小日向文世)が、山王会と関西指定暴力団「花菱会」と出所した
元組長(ビートたけし)を巻き込み紛争の火種に油をそそぐ姿が絶妙です。
加瀬亮と西田敏行のそれぞれドスの効いた迫真の演技と、最後の最後、
上司から離れていく松重豊が好演。「完結。」と言いながら、まだまだ続き
そうな、そんな結末であり、バッティングセンターのオチには唖然とします。
公式HP ⇒ http://office-kitano.co.jp/outrage/start.html
【Book】
■小澤征爾×村上春樹 「小澤征爾さんと、音楽について話をする」
(新潮社、11/11/30 ★★★★★)第11回小林秀雄賞を受賞。マエストロ
と小説家による音楽対談。 村上春樹が所有するクラシックLP盤を二人で
聴きながら、グールドと内田光子のピアノ演奏、バーンスタインとカラヤン
の指揮者としての違い、フロイトとマーラーの関係と特異性、ウィーン音楽
事情、オーケストラとオペラと室内楽の違いなどが小澤征爾により語られ、
彼の人生が凝縮しており、ここまで掘り下げたのは村上春樹の功績です。
「小澤征爾スイス国際音楽アカデミー」の詳細レポートも、読み応え充分。
http://www.shinchosha.co.jp/wadainohon/353428/
 |
小澤征爾さんと、音楽について話をする |
| 小澤 征爾,村上 春樹 | |
| 新潮社 |
■平松洋子 「焼き餃子と名画座」(新潮文庫、12/10/01 ★★★★☆)
西荻窪に住む著者による東京の食べ物屋さんガイド。ハンパじゃない数
の食べ歩き情報満載で、グルメというより徹底的な“食いしん坊の記録”。
例えば、たった6ページで30軒を超えるカレー店を紹介したり、彼女の頭
の中には、常に「場所」と「店」と「料理」と「季節」により、どこに誰と行くか、
何を注文すべきか、きちんと整理されています。荻窪駅北口の「川勢」は、
何度も前を通っているのに入ったことがなかったり、新しい発見の連続。
巻末の東海林さだおとの食対談は食べ物コラムの内容分析が可笑しい。
http://www.shinchosha.co.jp/book/131656/
 |
焼き餃子と名画座: わたしの東京 味歩き (新潮文庫) |
| 平松 洋子 | |
| 新潮社 |
【オマケ、今週の気になった言葉】
■音楽好きの友人はたくさん居るけれど、春樹さんはまあ云ってみれば、
正気の範囲をはるかに超えている。 クラシックもジャズもだ。
(by 小澤征爾、上掲『小澤征爾さんと、音楽について話をする』P373より)
「彼はただ音楽好きだけではなく、よく識っている。 こまかいことも、古い
ことも、音楽家のことも、びっくりする位。音楽会に行くし、ジャズのライブ
にも行くらしい。 自宅でレコードも聴いているらしい。 ぼくが知らないこと
もたくさん知っているので、びっくりする。」 【あとがきです】の初めの書き
出しです。 小澤さんの人柄がよく出た文章で、京都での夜がきっかけと
なり、この本の誕生秘話に触れ、春樹さんと奥様の陽子さんに感謝の辞
を述べてます。個人的な付き合いから音楽の話になり、一冊の本になる
まで。 クラシック音楽の世界で「巨匠」「マエストロ」と呼ばれる音楽家に、
自分の意見と感想を言いながら、貴重なエピソードや思い出を引き出す
ことができたのは、音楽と小説という、異なるベクトルを持つ二人が互い
に信頼して、謙虚な姿勢で記録に残そうとした「成果」です。 ここで掲載
された作品を聴くよりも、もっと根本的な音楽の楽しみかたに触れており、
この本から学ぶべき点は多く何を理解して活かすかは読者の課題です














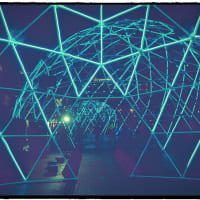




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます