親友Kへ。二次ケーデンスについて
以前のツイートで「バッハは二次ケーデンスの名人だった、だからベースラインが動くようになり、対位法が生まれた」
という説明を菊地成孔さんのメソッド講座で聞いた話を書いたら、クラシックの演奏家をやっている親友Kから説明を求められたので、それを書いておきます。
これはジャズ理論の「バークリーメソッド」の講義、および独習によるもので、間違っている場合すべて私の責任ですので。ご了承くださいね。
※「二次ケーデンス」は僕が通っているジャズトランペッター原朋直さんのレッスンでは
同じことを「セカンダリドミナント」と言っていました。同じ内容だと思います。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●ケーデンスとは。
クラシックだとカデンツァというのではないだろうか。
起立、礼、着席の音楽。
C-G7-C.
この和音の動きが持っている動的なエネルギー。
それがケーデンス。あるいはドミナントモーションともいう。
西洋の伝統的な音楽はこのケーデンスを曲の動力としている。
理由は
G7(ドミナント、または属音)の時には非常に不安定な響きがある。その不安感が、Cに戻ることで解消される。これが曲を動かす動力となっている。(ドミナントモーション)
●1次ケーデンスとは。
ケーデンスはドレミファソラシド、というCの環境内には1カ所G7-Cしかない。これを一次ケーデンスという。
●2次ケーデンスとは
V7→I、あるいはV7→Im
という動き(ドミナントモーション)は非常に強いので、
(なぜ強いかは音響学的に説明できる)
これを利用し、あるコードをIと仮に見立てて、
そのV7(ドレミファソラシドの環境外の)から動かす、ということをするようになる。
これが二次ケーデンス。
たとえば上の図の場合、
A7はドレミファソラシドのコードからは導き出されないコードだが、DmにいくV7として入ってる。そのためド#が和声には入る。
これはこの1小節だけ一時的に転調していると考えることもできる。この時にベース音がド#になると半音して上向するベースラインができる。
これはドレミファソラシドの環境だけでは出てこないベースラインになる。
つまり
●ケーデンスとはCでいえばG7→Cの動きである。
●一次ケーデンスはG7→Cしかない。これはドミナントモーションともいう。
●二次ケーデンスはドミナントモーションの力を利用して、Cの環境にない和音をもってくることができる。
たとえばC→A7→Dm7、G7という構造。
●二次ケーデンスはどこまでも増設できる。G7→C7→F7→B♭7とどんどん4度で動いていくこともできる。
ということであります。
違っていたらスイマセン。
※以降は菊地成孔さんのレクチャーを聞いての自分の推測。
バッハまでの前期、中期バロックまでは二次ケーデンスがなく一次ケーデンスだけで曲が作られていた。
低音部は主にドローン(通奏低音)が演奏されていて、キー(主調)を明示する役割を果たしていた。
そのため、低音部がメロディアスに動くことはなかった。
バッハが二次ケーデンスを導入して、短い単位での転調が入るようになり、
低音部は以前よりずっとダイナミックに動くようになる。
それが発展して、メロディと対旋律という対位法的なアプローチが可能になってくる。
ということではないだろうか。
※ジャズのケーデンスはIIm7を伴うことが多い。
つまりDm7-G7- Cと動く。
このDm7はバロックでは用いられない。
IIm7が入ると急にジャズっぽくなる。
●用語解説。
【前提としてのダイアトニックコード】
キーをCのメジャー(ハ長調)で考えたとき、
ドレミファソラシド、これを三度ずつ4つの音を積み重ねると
(ピアノで言えば白鍵だけを一つ飛ばしで押せば)
C、Dm7、Em7、F△7、G7、Am7、Bm7♭5
という7つの和音ができる。
これをダイアトニックコードという。
 |
憂鬱と官能を教えた学校 |
| 菊地 成孔,大谷 能生 | |
| 河出書房新社 |
 |
憂鬱と官能を教えた学校 下---【バークリー・メソッド】によって俯瞰される20世紀商業音楽史 旋律・和声および律動 (河出文庫 き 3-2) |
| 大谷 能生,菊地 成孔 | |
| 河出書房新社 |
 |
憂鬱と官能を教えた学校 上---【バークリー・メソッド】によって俯瞰される20世紀商業音楽史 調律、調性および旋律・和声 (河出文庫 き 3-1) |
| 菊地 成孔,大谷 能生 | |
| 河出書房新社 |














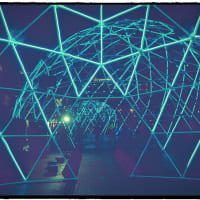




FBではありがとうございました。どうぞよろしくお願いします!