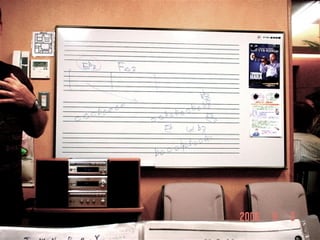
原朋直さんのレッスン講義録は、ご本人の承諾を受けて
ウェブに公開しています。
本稿はかなり古い2006-10-02にポストしたコンテンツ
『モーダルインターチェンジ』とはですが、
原さんより修正依頼がありましたので改訂します。
赤字が修正点
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『モーダルインターチェンジ』とは
銀座アネックスでレッスンを受けている原朋直先生のジャズトランペット教室での講義録です。
ダイアトニックスケール、
ダイアトニックコード、
ドミナントモーション、
セカンダリトミナント
までは以前に書きました。
今回はモーダルインターチェンジです。
練習している曲は「There will be never another you」 Key In Fです。
ジャズで頻繁に使われるドミナントモーションやセカンダリトミナントはクラシックの作曲でも使われている技法だった。
しかしモーダルインターチェンジとは、クラシックにはない技法である。
これが生まれたのはおそらく、クラシック的な楽典知識がないままに音楽を作ったことに由来する。ジャズならではのもの。
モーダルインターチェンジもクラシックで使われている手法である。
何をするか。そのキーの(F)の中で無理矢理違うスケールを使う。
たとえば「There will be never another you」はFメジャーだが、そこにFナチュラルマイナーを無理矢理使う。そこに違うモード(旋法)をはめ込む。
厳密にはこれは転調(この場合は同主調)なのだが、それを転調とせずに脱線しつつもまた元に戻すというスリリングなものにするのが味噌。たとえばC-A♭7-C-A♭7とか、C-B♭7-C-B♭7とか、C-C#-C-C#とか。
曲のキー、ダイアトニックコードと全く無関係のモード、コードを入れることができるので、これによってセカンダリドミナントよりもさらにインパクトを与えることができる。一瞬キーとダイアトニックの線路から離脱させる感じ。
練習している曲は「There will be never another you」 Key In Fの場合はE♭7である。
さて「モーダルインターチェンジ」とは楽典上は転調なの、転調していないとする考え方。なので、モーダルインターチェンジを起こしている小節の中では、転調しているキー・モードをモロに吹くのは、今ひとつ、と考える。
もちろんドンズバでも音楽的には問題ない。むしろそれが正直なんだが、なんとか転調していない風を装うわけである。
「There will be never another you」はFだが、当該のモーダルインターチェンジを起こしている部分は、たとえばFのメロディックマイナーを吹くとドンズバだが、それは転調だ、コードはE♭なのでE♭ミクソリティアンというモードを使うとメディックマイナー。それをFのダイアトニックスケールに近づける作業をする。この場合はE♭リディアン♭7thで吹くといい。転調感を弱めることができる。
リディアン♭7thと大事なスケールで、のちのち出てきます。
ちなみにE♭のリディアン♭7thとはB♭のメロディックマイナーと同じスケールの構成音になる。
モードとは
* ドリアン Dorian
* フリジアン Phrygian
* リディアン Lydian
* ミクソリディアン Mixo Lidyan
* エオリアン Aeorian
* ロクリアン Locrian
が代表。
普通のドレミはアイオニアンモードであり、キーのドレミで吹くことは、アイオニアンモードというモードでのモーダルなアプローチといえる。つまりモーダルなプレイは誰もが無意識にやっていると言っていい。
 |
金管楽器奏法革命~出せなかった音が出る~ |
| 村松 匡 | |
| ヤマハミュージックメディア |
 |
金管演奏の原理―クラウド・ゴードンによる自然科学的解明 |
| Claude Gordon,杉山 正 | |
| 聖公会出版 |
 |
ジャズスタディ 渡辺貞夫 |
| エー・ティ・エヌ | |
| エー・ティ・エヌ |
 |
初心者のための実践ジャズ理論 |
| サーベル社 | |
| サーベル社 |
 |
ギター・マガジン 最後まで読み通せるジャズ理論の本 (CD付き) |
| 宮脇 俊郎 | |
| リットーミュージック |
 |
ピアニストのための ジャズピアノ理論の基礎 これだけは知っておきたいジャズ理論を完全網羅 |
| 遠藤 尚美 | |
| 自由現代社 |














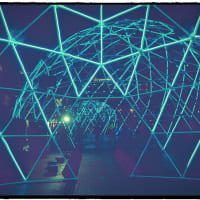




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます