『淮南子』(えなんじ/わいなんし)、前漢の武帝の頃、淮南王の劉安が学者を集めて編纂した思想書です。日本へはかなり古い時代から入ったため、漢音の「わいなんし」ではなく、呉音で「えなんじ」と読むのが一般的である。色々な言い方がありますね。国士無双の韓信は劉邦の意向を被って淮南の地の王になったので淮南王(わいなんおう)韓信と呼ばれましたからね。この淮南王の劉安も「わいなんおう」と読むのが合っていると思います。(針外しはね。)その中に「人間万事塞翁が馬」と言う言葉があります。
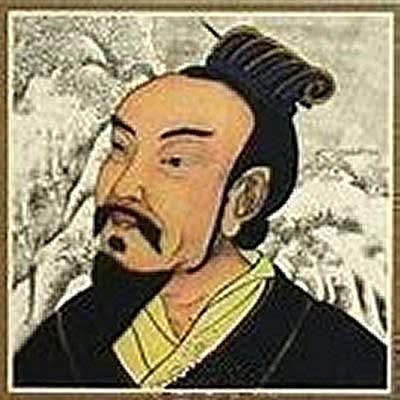
淮南王 劉安
普通「人生」(じんせい)とか「人間」(にんげん)間違って覚えている事が多いのですが、人間(じんかん)が正しい。でも「世間」を意味するので、誤りではありません。でその意味は
「人間万事塞翁が馬」とは幸せが不幸に、不幸が幸せにいつ転じるかわからないのだから、安易に喜んだり悲しんだりするべきではないというたとえです。 また、人生において、何がよくて何が悪いのか、後になってみないとわからない。 という事です。。
昔、中国北方の塞(とりで)近くに住む占いの巧みな老人(塞翁)の馬が、胡の地方に逃げ、人々が気の毒がると、老人は「そのうちに福が来る」と言った。

やがて、その馬は胡の駿馬を連れて戻ってきた。人々が祝うと、今度は「これは不幸の元になるだろう」と言った。すると胡の馬に乗った老人の息子は、落馬して足の骨を折ってしまった。
人々がそれを見舞うと、老人は「これが幸福の基になるだろう」と言った。一年後、胡軍が攻め込んできて戦争となり若者たちはほとんどが戦死した。しかし足を折った老人の息子は、兵役を免れたため、戦死しなくて済んだという故事に基づく。単に「塞翁が馬」ともいいます。
「が」は所有を表す格助詞だが、「塞翁の馬」と言いません。
人間を「にんげん」と読むのは間違いで、正しい読みは「じんかん」であるとの指摘も多いが、どちらの読み方をしても「世間」の意味があり、「にんげん」が誤読ということはないですね。
ま、普通にこういう老人がいると、変にひねくれ者と感じてしまうでしょね。物の道理を問うたもので、どっちが正しい事か何て人智では測れないと思っていた方がいいね。













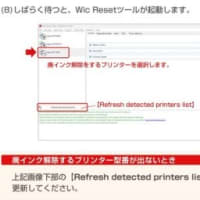





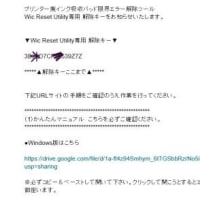
逆も真なりみたいで
読み方もいろいろあるのですね
面白くて勉強になります
先人の知恵には敬服ですね
全部と言って良いほど「パクリ」なんですが。私も、勉強の積りで書いています。
中国語の音は漢音もあれば呉音もありでどれが正しいかを問うても意味がありませんね。