 (美しい姿で保存されるキハ11)
〔キハ11 25 : 鉄道博物館〕
写真をクリックすると大きな画像でご覧になれます。
(美しい姿で保存されるキハ11)
〔キハ11 25 : 鉄道博物館〕
写真をクリックすると大きな画像でご覧になれます。
キハ10系気動車のうち、両運転台車でトイレ付の車両がキハ11を名乗る。
北海道などの極寒地向けはキハ12であり、本州の寒冷地向けはキハ11の100番代に区分されている。
“てっぱく”に保存されたキハ11は、茨城交通で晩年を過ごした元国鉄真岡線で活躍したキハ11 25である。
0番代初期車の最終番号になる。
昭和31年度(1956年度)の途中で、キハ11(当時はキハ48000)の仕様が少し変わったのだ。
キハ11 1~25 までは、トイレ窓はバス窓のような形で窓下に旅客用窓と同様の帯が付く。
また、屋根上のベンチレーター(通風器)はすべて同型である。
キハ11 26~63 は、トイレ窓がHゴム化され窓下の帯は省略された。
屋根上ベンチレーターは、両端が押込式のものとなった。
保存されたキハ11 25は、ベンチレーターなどは改造されているようである。
トイレ窓は確認していない。
キハ10系気動車は、国鉄時代の地方ローカル線には全国どこにでも走っていた系列であり、馴染み深い。
残念ながら写真撮影の記録は無いが、鉄道模型では1/80および1/45スケールの車両を購入して楽しんでいる。
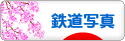 クリックをお願いします
クリックをお願いします
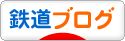 にほんブログ村
にほんブログ村
 (信越本線横川・軽井沢間の碓氷峠で活躍したED40形電気機関車)
(信越本線横川・軽井沢間の碓氷峠で活躍したED40形電気機関車)































