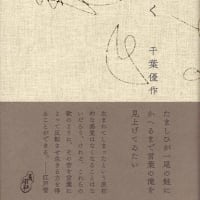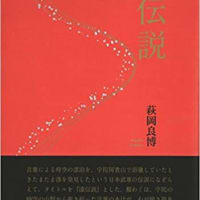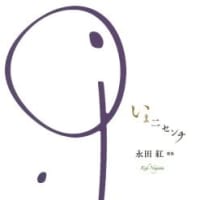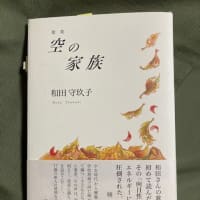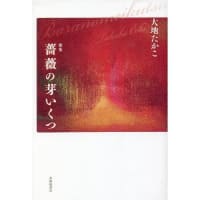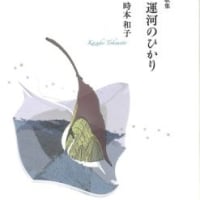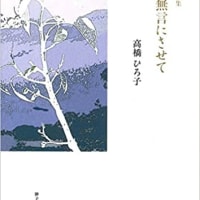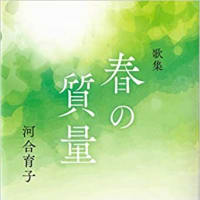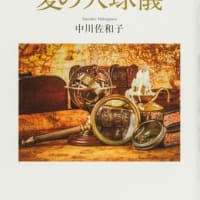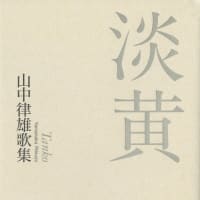「お大事に」と書かれし白き袋ありおおつごもりの妻の机に
軽トラの渡りたるのち吊橋はしばらく渓(たに)の時間を揺らす
海の色に指は触れつつ地球儀を回せばうすく埃がつくも
フランクフルト、都市の名前をささやいて縁日に買う腸詰の肉
ほんのりと記憶に触れる指先のモスコミュールはモスクワの騾馬(らば)
円柱のふとき陰よりまたひとりひと湧き出してロビーを歩く
冬の日がぼんやりあって地上とはあるいは地下よりさびしきところ
種を播くように読点打ちながら子は文字を書く大きなマスに
一字だけ漢字まじりとなりし子が声だして読む春の教科書
紅葉の頃ともなれば膨らんでゆく駅があり谷間深きに
若返るために人魚の肉を買うあるいは遠いしおかぜの色
春の字のなかに日の差すやさしさの京都三条小橋を渡る
(午前3時を過ぎて 松村正直 六花書林)
***********************************
松村正直の第三歌集『午前3時を過ぎて』を読む。作者、35歳から40歳までの作品555首が収められている。
過去に出された歌集にも言えることだが、家族詠を鋭い視点で詠む人だ。
一首目の妻の机の薬袋。「お大事に」は、印刷された言葉だろう。おおつごもりに病気になって薬をのむ状態なのに、袋に書かれた「お大事に」は、そらぞらしい。袋の白、おおつごもりという古風な言い方もそらぞらしさを補強する。それを見つけて一首にするところが鋭い。
九首目も同様。小学校低学年だと習った漢字を使って名前を書くので、漢字とひらがなが混じってしまう。上句の内容は、子供のノートなどを見ていないと気がつかない発見だ。春の教科書も明るくて元気な様子が窺われて楽しい。
また、四首目のフランクフルトの歌は、都市の名前として、またソーセージの名前としての二つの意味を繋げるようで面白い。縁日で食べ物を買うときの、浮き浮きしながらも、ちょっと後ろめたいような気分を思い出させる。
二首目。吊橋が揺らすのは、渓の時間という把握に納得させられる。六首目。四句目の「ひと湧き出して」の「湧き」が巧い。たまたまロビーで座った位置から円柱が見え、その辺りを人が通ったということだが、「湧き」で別世界が出現している。
十一首目は、「人魚の肉」という一連の歌。人魚の肉などないのだが、あると仮定しての連作になっている。短編小説を読んだ気分になる。
「静かな職場」と題された一連も、職場での同僚の事故死を扱って、面白く読んだ。
軽トラの渡りたるのち吊橋はしばらく渓(たに)の時間を揺らす
海の色に指は触れつつ地球儀を回せばうすく埃がつくも
フランクフルト、都市の名前をささやいて縁日に買う腸詰の肉
ほんのりと記憶に触れる指先のモスコミュールはモスクワの騾馬(らば)
円柱のふとき陰よりまたひとりひと湧き出してロビーを歩く
冬の日がぼんやりあって地上とはあるいは地下よりさびしきところ
種を播くように読点打ちながら子は文字を書く大きなマスに
一字だけ漢字まじりとなりし子が声だして読む春の教科書
紅葉の頃ともなれば膨らんでゆく駅があり谷間深きに
若返るために人魚の肉を買うあるいは遠いしおかぜの色
春の字のなかに日の差すやさしさの京都三条小橋を渡る
(午前3時を過ぎて 松村正直 六花書林)
***********************************
松村正直の第三歌集『午前3時を過ぎて』を読む。作者、35歳から40歳までの作品555首が収められている。
過去に出された歌集にも言えることだが、家族詠を鋭い視点で詠む人だ。
一首目の妻の机の薬袋。「お大事に」は、印刷された言葉だろう。おおつごもりに病気になって薬をのむ状態なのに、袋に書かれた「お大事に」は、そらぞらしい。袋の白、おおつごもりという古風な言い方もそらぞらしさを補強する。それを見つけて一首にするところが鋭い。
九首目も同様。小学校低学年だと習った漢字を使って名前を書くので、漢字とひらがなが混じってしまう。上句の内容は、子供のノートなどを見ていないと気がつかない発見だ。春の教科書も明るくて元気な様子が窺われて楽しい。
また、四首目のフランクフルトの歌は、都市の名前として、またソーセージの名前としての二つの意味を繋げるようで面白い。縁日で食べ物を買うときの、浮き浮きしながらも、ちょっと後ろめたいような気分を思い出させる。
二首目。吊橋が揺らすのは、渓の時間という把握に納得させられる。六首目。四句目の「ひと湧き出して」の「湧き」が巧い。たまたまロビーで座った位置から円柱が見え、その辺りを人が通ったということだが、「湧き」で別世界が出現している。
十一首目は、「人魚の肉」という一連の歌。人魚の肉などないのだが、あると仮定しての連作になっている。短編小説を読んだ気分になる。
「静かな職場」と題された一連も、職場での同僚の事故死を扱って、面白く読んだ。