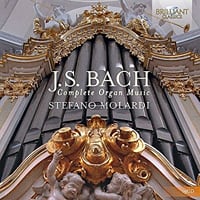先週からきいているステファノ・モラルディの「J.S.Bach Complete Organ Music」(15CD)。今後、おりおりに楽しむ予定で、まずきいてきたのはCD1です。今日きいたのは、そのCD1の最後に収録されたト長調のプレリュードとフーガ。使用楽器は、T.H.G.トロストが建造した、ドイツのヴァルタースハウゼン市教会のオルガンで、2013年の録音です。オルガンは、奏者の個性がつかみにくい楽器ですが、モラルディは、プレリュードのはじめとおわりに「Cimbelstern」を鳴らし、おもしろい効果をあげています。
CD : 95105(BRILLIANT CLASSICS)