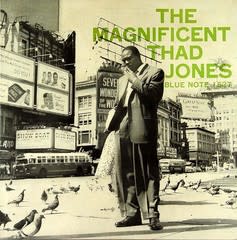今年もあとわずかになりましたですね。フッと今頃、実感しています。というか、全然、年末という雰囲気に浸れないことが、もうずぅ~っ前から続いているのですが……。
ということで、本日は――
■Warne Marsh (Atlantic)
ウォーン・マーシュは唯一無二の個性派テナーサックス奏者だと思います。
ご存知のようにレニー・トリスターノ(p) の門下生として、リー・コニッツ(as) と並び称されるクール派ですから、そのスタイルは時としてエキセントリックで難解ではありますが、一端、その虜になると、最後まで抜け出せない魅力があります。
それは白人らしく流麗なフレーズ展開とスカスカの音色が持ち味ながら、その元祖たるレスター・ヤングの影響が、あまり感じられません。全く独特の浮遊感に満ちたアドリブが、歌心というよりは異次元の閃き♪ そういうところはスタイルこそ違いますが、ウェイン・ショーターと一脈通じるのではないでしょうか。
さて、このアルバムは師匠のレニー・トリスターノが監修したワンホーン盤で、当時最先端の黒人ジャズ=ハードバップの人気ベース奏者だったポール・チェンバースを全面的に起用した傑作盤!
バンド編成は2つに分かれており、ウォーン・マーシュ(ts) 以下、まず1957年12月12日のセッションにはロニー・ボール(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds) が参加♪ また1958年1月16日にはポール・チェンバース(b) とポール・モチアン(ds) がサポートしています――
A-1 Too Close For Comfort (1957年12月12日録音)
寛いだ曲調のスタンダードですから、白人系モダンジャズにはもってこいの素材ですが、ここではポール・チェンバースとフィリー・ジョーのグルーヴィなリズムコンビが本領発揮!
まずグワァ~ンというイントロからポール・チェンバースがテーマメロディを巧みに変奏する熱演となり、続けてウォーン・マーシュが絡みながらアドリブに入れば、バックではフィリー・ジョーが独特のクッションを活かしたドラミングを聞かせてくれます。ポール・チェンバースの4ビートウォーキングも最高♪
そしてウォーン・マーシュは何を吹いているか、ちょっと理解不能なところもありますが、これは原曲メロディを知っていれば、その異次元飛翔が痛快に思えるはずです。
ところが残念ながら、盛り上がったところでフェードアウトが勿体無い!
A-2 Yardbird Suite (1958年1月16日録音)
チャーリー・パーカーが書いたにしてはリラックスしたテーマが楽しいビバップの名曲で、ウォーン・マーシュ独自のアドリブ感覚が存分に楽しめます。
ここではドラマーがポール・モチアンに交代していますが、ポール・チェンバースの強靭なウォーキングがリズムとビートをリードしていますから、演奏は早いテンポでもグルーヴィなジャズ本来の魅力に満ちています。
いゃぁ~、本筋を離れて浮遊していくウォーン・マーシュ! 最高ですねぇ♪
A-3 It's All Right With Me (1957年12月12日録音)
コール・ポーターが書いた、これも楽しいジャズの見本という名曲ですから、フィリー・ジョーの素晴らしいシンバルワークとスネアのコンビネーションに煽られてフワフワと吹きまくるウォーン・マーシュに歓喜悶絶させられます。
全く芯が無いような音色とアドリブ展開は、本当に異端だと思いますが、決してモダンジャズの本質から離れていないと思います。むしろ自由な発想と頑固な思い込みがあってこその輝きというか、一瞬の煌きがフラッシュバックしていくようなフレーズの積み重ねは、確実に中毒症状♪ 文字通り「私は満足」です。
そしてもちろんフィリー・ジョーが魂の快演で、十八番の釘打ちリムショットや独自のタイミングで炸裂させるバスドラとスネアのコンビネーションが、たまりません。ポール・チェンバースのアルコソロの背後で暴れる4ビートやクライマックスでのウォーン・マーシュとの対決も、スリル満点なのでした。
B-1 My Melancholy Baby (1958年1月16日録音)
これも和み系スタンダード曲を素材にしたウォーン・マーシュだけの名演だと思います。それは自在に飛翔するフレーズの面白さ、変幻自在のリズム感と音色のコントロールが、凄いんですねぇ。
尤もそれが破綻していないのは、ポール・チェンバースの強烈な存在があってこそで、力強いベースソロも聞き逃せないところでしょう。本当に最高のピチカットソロです♪
終盤ではポール・モチアンも含めて、トリオによる暗黙の了解という演奏が見事だと思います。
B-2 Just Squeeze Me (1958年1月16日録音)
デューク・エリントンが書いた有名曲ですから、ウォーン・マーシュもリスナーがオリジナルメロディを知っているという前提で吹奏しているのでしょうか……?
そういう、ちょっと突き放した演奏姿勢が、所謂トリスターノ派の長短所だと思うのですが、それがここでは良い方向に作用していると感じます。
なにしろポール・チェンバースのウォーキングが基本に忠実ながらも奥深く、やや卑小に暴れるポール・モチアンまでもがスジを通したドラミングに聞こえるほどですから、ウォーン・マーシュも忌憚の無いところを披露しているのでしょうねぇ~♪
聴くほどに地獄へ引き込まれるような恐い演奏ですが、スバリ快感!
B-3 Excerpt (1958年1月16日録音)
これだけがウォーン・マーシュのオリジナル曲で、多分、原曲は「四月の思い出」でしょう。それをトリスターノ派だけのスリルとスピードでアドリブしていくという、全くの「お約束」がたまりません。
もちろんウォーン・マーシュは意味不明のフレーズを自在に飛翔させ、独自の美学で積み重ねていきますが、実はポール・チェンバースのウォーキングベースにばかり耳を奪われる私です。
するとますますウォーン・マーシュのテナーサックスが気持ち良く聞こえてくるんですねぇ~~~♪ ところが、この曲もまたブツ切れというか、盛り上がったところで突如終了……。あぁ、完全版が聴きたいと願っているのでした。
ということで、このアルバムの魅力の一端は、明らかにポール・チェンバースの活躍でしょう。
ところがアトランティック特有のプレス&盤質の悪さから、アナログ盤ではイマイチ、音質に満足出来ません。ちなみに私有盤はモノラル仕様のアメリカプレスながら、盤質というか、素材の塩ビの悪さがモロに影響したようなシュワシュワな音……。
しかし近年のCDはステレオバージョンですが、それが解消されており、各楽器の分離と定位は右と左に泣き別れながらも、クッキリとしたリマスターですから、演奏そのものの凄さに素直に感銘出来るはずです。
特にポール・チェンバースのベースワークは最高! モノラルミックスのCD化を熱望しております。