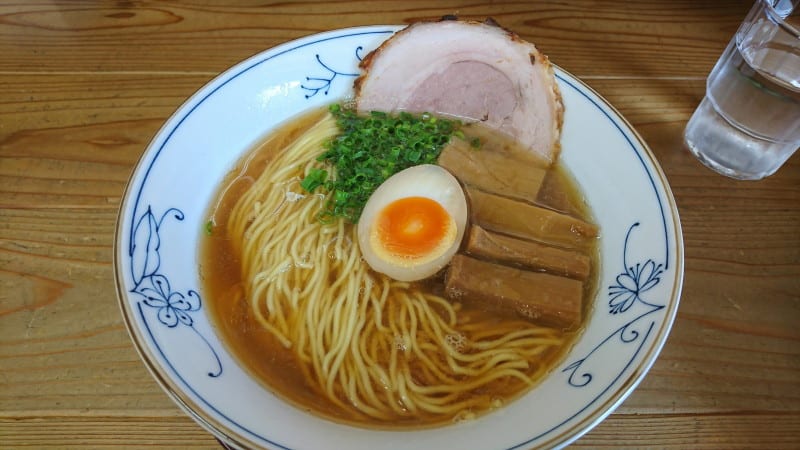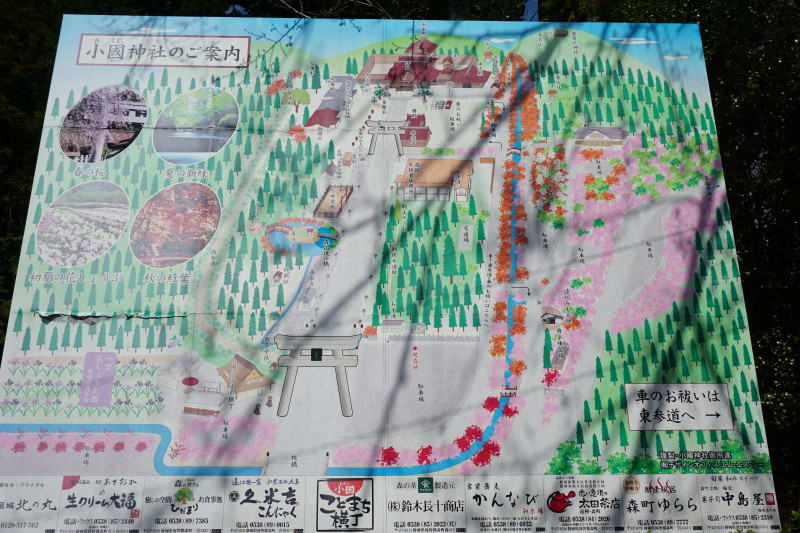2018年4月22日。
伊豆急行の最古参車両100系クモハ103号が個人向け貸し切り運転を募集している旨を聞きつけました。
100系は一度は引退して車庫の入換車として余生を送っていましたが、2011(平成23)年の伊豆急行50周年記念事業として本線走行への復帰を果たしました。その後は幾度も臨時列車等で走っていたものの撮影したことが1度しかありませんでした。しかもその時は何かのついでで撮ったものでした。
当時既に、近々実施される伊豆急行線のATS更新に100系は対応できないらしくてそのまま引退するらしい・・・みたいな噂はまことしやかに流れていて(そしてそれは後に現実になったのです)、いい加減行かないとなぁと最近重くなってきたようなする腰を上げて伊豆へと赴いたのでした。
今回は電車で行きました。静岡駅7:00発の373系「ホームライナー沼津」2号で出発です。この電車は終点沼津に着くとそのまま普通熱海行に化けて熱海まで行くので、実に乗り得列車です。熱海から先東京方面へ行く際はグリーン車に乗り換えれば快適な鈍行旅を楽しめるので、時間が合う時はこれを使う場合が多いです。
373系で熱海まで来ました。なんとなくE233系3000番台(E-17)。
乗り換えるのはこちら。8:26発伊東線の伊豆急下田行。2100系(R4)黒船電車です。リゾート21は、よく減車しないで7両編成を堅持しているなと乗るたびに思います。
何度目になっても乗る時は少し楽しくなりますね。
しかし乗車時間は少し。伊東駅で下車します。
これは、閑散期に発売される伊豆急行線の乗り放題乗車券「伊豆満喫フリーきっぷ」を購入するためです。伊豆急行線全線往復が3,240円のところ、この切符は1,700円(当時の価格)で乗り放題となってしまうので、社員は算数できないのかと疑うほどの値引きになっています。その代わり伊東駅の窓口でしか購入できない縛りがあります。しかしそれを加味しても魅力ある切符なので、どんどん下車して買ってしまおうね。
どうにか切符を購入しました。
あの黒船電車の次発は9:00発伊豆高原行ですが、両者の間の時間は10分だけ。ただ一度改札外に出て窓口で切符を買うだけなので10分あれば間に合うんですが、同じことを考える人はいるものでして、既に何人かの鉄オタが同じ行動を取って窓口に並んでいました。鉄オタの前に並んでいる一般人が存外時間がかかっていたので間に合うかドキドキでしたが、結果はセーフセーフでした。これを逃すと次は26分後なのだ・・・。
東急テクノシステムの自信作の内装。私は割と好きですが、ボックスシートのうち約半分は車窓の相模灘ではなく戸袋の壁を眺めることになってしまうのは、ちょっと良くないよねと。なので私はロングシートに座ることの方が多い気がします。
富戸駅で2100系(R3)キンメ電車と交換。初めて見たけれども、あまり魚臭くなくて良いですね。
終点の伊豆高原駅に到着しました。併設の車庫には2100系(R5)「ザ・ロイヤルエクスプレス」が寝ていました。今日初めて遭遇したので少し見ていくことに。
例によって水戸岡鋭治の手による装飾がされています。水戸岡列車も予算によりピンキリだそうですが、これはピンの方でしょうね。車体が青いのはロイヤルブルーに引っ掛けているんだろうなぁくらいしかここから読み取れる情報はありませんでした。言うてそんなに時間無いですし。
伊豆高原駅を出て、下田方面へと歩いていきます。乗り放題切符なので駅を出て沿線撮りしようという趣旨。最短距離を抜けるためにこんな未舗装路も歩いたりして。
国道135号線と伊豆急行が交差する地点に着きました。ここから撮影しようと思います。この時間はまだ100系は動いていないですが、185系の引退も今やという状況でしたので豆に記録しておきます。
初めに来たのが8000系(TB-6)伊豆急下田行。伊豆高原以南で6両編成とは珍しい。所定の編成なんでしょうけども。
251系(RE-4)特急「スーパービュー踊り子」2号東京行。後追いです。
10両編成がぎりぎり入って一安心。この頃はまさか185系よりも早くに全廃されてしまうとは思いもよらず・・・。
251系特急「スーパービュー踊り子」3号伊豆急下田行。下り251系が撮れたところでここからは撤収。
伊豆高原への帰り際に185系(A8)特急「踊り子」伊豆急下田行と遭遇。
再び伊豆高原駅から乗車します。乗ったのは2100系(R3)キンメ電車の伊豆急下田行。
片瀬白田駅で下車します。片瀬白田で一つの地名だと思っていましたが、白田川を挟んで両岸に広がる片瀬と白田でそれぞれ別の地区なんですね。池尻大橋駅に近いですかね。
駅を出て下田方面へ歩いていきます。海沿いを走る電車を撮影できる例のお立ち台へ向かいました。初めての場所だったので最初は道順が分からず、少しの間国道沿いを歩いていたのは公然の秘密であります。
で、ぼけっと電車を待っていたら、100系が上っていったじゃありませんか。なぜ、どうして、ほわい。よく調べてみると、貸し切り電車の前に臨時列車「伊豆急100系水族館でんしゃの旅」として片瀬白田~伊豆急下田を往復していたんだそうな。なんで片瀬白田なんて半端なところから・・・?
今通っていったのは往路なので、この後また時間を置かずに復路が運転されます。知らんかったことでしたが撮影機会が1度増えましたのでこれを逃す手はありません。100系がやって来るまで待つことにします。
185系(A3)特急「踊り子」107号伊豆急下田行。お立ち台で185系を手堅く撮影です。
8000系(TA-3)も撮影。
185系(A8)特急「踊り子」106号東京行を後追いで。
そして100系クモハ103号。1両編成なので定番構図は使いにくいですね。ちゃんと撮っていないですが、特製ヘッドマークも付いていました。
片瀬白田駅に戻りました。意外にも有人駅でした。伊豆急行は意外と有人駅が多いのですよね。昼間だけの営業という駅も多いですけど。
ホームで電車を待っていると、さっき乗ってきたキンメ電車が折り返してきていました。
8000系(TB-2)に乗って次の撮影地へ移動します。
というところで今日はここまで。
後編へ→