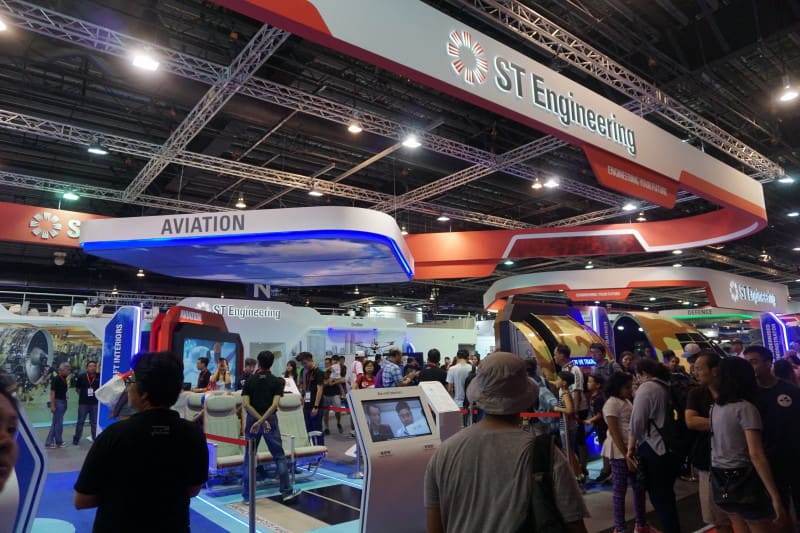シンガポールエアショーの続きです。あとは残りの地上展示機を順番に見ていきます。シンガポールエアショーは、軍事関連の展示物が目立ちますが民間航空の見本市の側面もあります。今回の記事からは民間機が多くなります。民間機でもいける私には嬉しい。

まずこちら。ロシアのスホーイスーパージェット100 (SSJ100)です。スホーイといえばSu-27フランカー軍団の開発製造で知られるメーカーですが、このSSJでもって民間航空市場にも参入しています。
機体規模はエンブラエルやCRJと同じくらいの60~100席クラスのリージョナルジェットです。近年は、旅客機市場に新規参入しようと思うとリージョナルジェットから始めるところが多いですね。
ロシアというかソ連の旅客機というとあんまりいいイメージがないんですが、SSJはソ連時代の純国産品使用の思想を捨て去って、西側の技術や部品も取り入れているんだそうな。
畑違いの戦闘機とはいえ自力で航空機を開発製造している企業だからなのか、2004年に開発を始めてから4年で原型機が初飛行、2011年に型式証明取得、就役しています。どこぞの極東の重工業とは開発スピードが違いますよ。
ただ2012年5月にデモ飛行中に墜落事故を起こしてしまったんで思うように運んでいないようですが・・・(その事故はヒューマンエラーが原因なんですけどもね)。

エンジンはロシアとフランスの合弁企業パワージェットがSSJ用に新規開発したSaM146です。

風防は最近流行りの銀の窓枠のないやつです。精悍な顔立ちです。ソ連っぽさが少ないのがちょっと趣味的にはマイナスですが、最近の旅客機の機首はもう形状が突き詰められて煮詰まってしまったのかだいたいどれも似たような形状になっていますので、そんなもんなのかな。

垂直尾翼が少し前に出ているようなそんな配置。

マレーシア空軍のエアバスA400Mアトラスです。軍用輸送機ですね。初めて見ましたし、見れると思っていなかったなぁ。
確かドイツ、フランス、イギリス、アメリカの合同でC-160の後継機として1980年代前半に開発を始めた輸送機です。が、機体設計が始まったのは1996年、機体が初飛行したのは2009年・・・・・・。おわかりだろうか。毎度おなじみ多国籍共同開発からの足並みの揃わなさによる大 炎 上である。
問題を端的に言うと幾度も仕様変更しているうちに重量過多となり搭載量が減り、しかも専用に開発されたターボプロップエンジンは大問題なのだそうな。

C-130をやや大きくしたような感じです。今どきターボプロップかよと思いましたが、これはC-130のような不整地での離着陸を想定しているためだとかで。なお実際に飛ばしてみたところ出来ない模様・・・。
最近はよく川崎C-2と比較されたりします。

機首は割とイケメン。空中給油のプローブがおでこから突き出ているのがなんだか一角獣みたい。なお中心線からは少しずれていますが。

問題のエンジン・・・。
プロペラはエンジン1発につき8枚生えています。最近の主流である長さの短いプロペラを多数生やす方式です。これだけ生やすと従来では重量が増えてしまってイカンかったのですが、炭素繊維素材でプロペラを成形することで減量に成功したとかで。

ペラの先端が少し後退角が付いているのも特徴です。プロペラ先端が超音速を超えるのを少し遅らせる効果があるとかで(先端が超音速を超えると推力を生まなくなるのだ)
この最近のプロペラは個人的には好きです。プラモデルで作るとなると地獄ですが・・・。

例のターボプロップエンジン、TP400です。
出力は足りん、20時間ごとにオーバーホールが必要、挙句の果てにエンジン制御のバグで墜落死亡事故を起こしています。
飛行機の開発はエンジン開発が炎上すると機体そのものもコケてしまうことが今までの航空史からも見て取れますが、これもそのひとつとなったのでした。

尾翼は輸送機でよくあるT字型です。
マレーシアの国籍章は初めて見ました。あんな模様なのね。
しかしマレーシアもなんでこれを買うことに決めたのやらですが。

エンジンを後ろから。

貨物扉も輸送機でよくあるやつです。中は入れないどころか見せてもくれませんです。

オーストラリア空軍のボーイングE-7Aウェッジテイル 。さっきも見たやつですが、もっと近づいたところでもう一度。

この手の機体はアンテナがあちこちから生えています。

レーダーです。尾部には追加の垂直安定板が付いているんですな。

中国航空工業の翼竜IというUAVです。名前通り、中国製です。Iということは翼竜IIもいるっつーことです。じゃあIIIもいるんかと思えばこれはいなくて、なぜか次は翼竜10まで飛びます。しかも数字の書き方も変わっているし。
既に100機以上量産されているところが、最近の中国すげーという点です。
UAVとはいえ中国製の航空機を見るのは初めてですかね(ミグのライセンス生産機は除く)。

中華UAVなので詳しいところはよく分かりませんが、偵察と軽攻撃能力を持つUAVでしょうね。地面には搭載できるであろうミサイルや爆弾も一緒に展示されています。アメリカのプレデターと同じような機体規模と役割を持っているんじゃないでしょうか。

ここからいよいよ民間航空の区画です。こちらはご存知ホンダジェットです。まあこれは説明不要だと思います(手抜き)

エンジン配置についても私から話すことはないでしょう(手抜き)
この機体規模のビジネスジェット機としては最もシェアが大きいんだそうですが、この機体規模の機体って他にはセスナの機体があるくらいで市場はそれほど大きいわけじゃないんです。なのであんまりシェアナンバーワンとドヤ顔されてもと思わんこともないですが、それでもビジネスジェットの本場アメリカでうまくやっているのは驚嘆すべきことでしょう。

ホンダジェットの実機を見れたことに実はけっこう興奮しています。これのプラモデルも作ったしね。愛着みたいなのはあるわけですよ。

というところで今日はここまで。
その28へ→