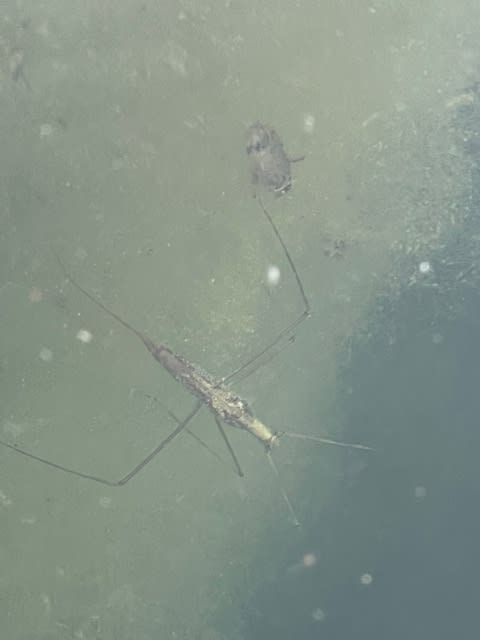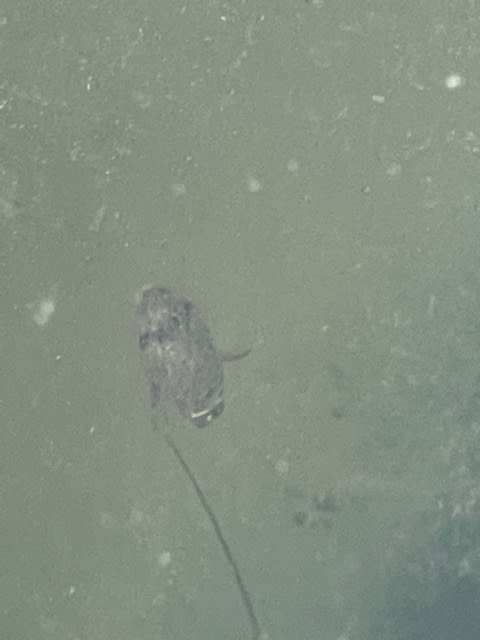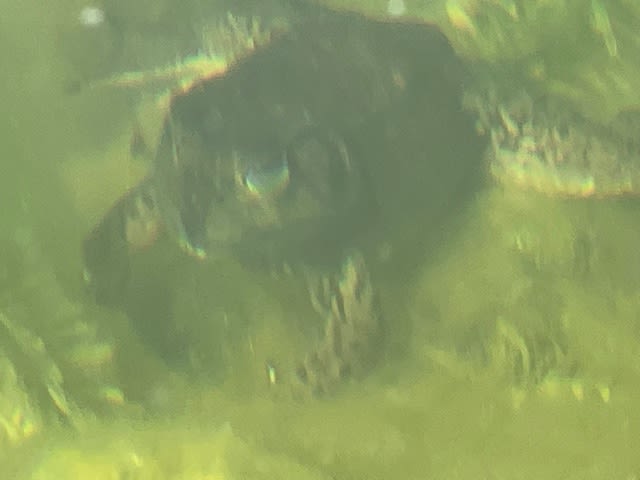滑川へ行ったとき友人が、山のミカン畑にサルが来て、デコポンをほとんど食べてしまったと言っていました。今まではこんなことはなかったそうです。そこには伊予柑とか八朔とかいろいろな種類の柑橘を植えていて、これからおいしくなるというデコポンが収穫かごに一杯くらいしかないのだとか。
いったんサルが出だしたら防ぎようがないと、落胆していました。あ~あ~ 毎年届けてくれるのを楽しみにしていたのに。私もがっかりです。
サルと聞いて、わたしも自分のうちの畑に行ってみました。サルらしき者にサツマイモを取られた場所です。
この足跡は?
直径3~5センチ、といったところでしょうか。

足跡は二日後にはすごいこと増えていました。ということは毎日やってくるのかな?

こうなると心配なのはここに植えてある作物です。畑半分はキャベツですが見たところキャベツを食べられた様子はありません。もう半分は小豆を植えてあります。キツネやタヌキやサルが小豆を食べるものでしょうか。もしかしたら単に通り道になっているだけかもしれません。あたりには柑橘畑があり、捨てられた柿が甘くなっている頃ですから。
ともあれそろそろ小豆も何とかしなくては。 が、この小豆、うちのものではなくて弟が植えたもの。あまり手間がかからないからとうちの余った畑に植えて、ときどき世話をしに来ていたのですが、収穫期を迎えて茎ごと引き抜いたまま畑に積み重ねていたのです。その辺のいきさつは、ちょっと訳ありなのですが省略。
「さやが爆ぜて地面に実が落ちてるよ。どうするの?集めてコンテナに入れておこうか?」
「暇なん?」
「いや、暇じゃないけど、去年もいっぱいもらったからお金の代わりに労働奉仕をしとこうかと思って・・・」
わたし、小豆大好きなんです。一度に1キロくらい煮て、赤飯用、あんこ用、お汁粉用、その他調理用にと小分けして冷凍します。そんな作業が2,3回出来るほどもらっているのですから。
それに、こんなややこしい状態にしてしまったのは夫なので、ちょっとばかり申し訳もなくて。(なんで私がーと、夫には腹も立ててますが)
このままだとどんどん爆ぜて地面に落ちてしまいますから、どうにかしなくてはいけないことは確かなのです。わたしは抜いて地べたに積み重ねてあるのだけでもコンテナに入れておくことにしました。
虫も何もいなそうな畑でテントウムシ発見。
集めた小豆の枝の下に数匹集まっていました。 ごめんね、寝床を壊しちゃったね。けっこう動き回るのでうまく撮れませんでした。
もう一度その辺の枯草を集めてかぶせておきましたけど、積み上げた小豆ほどには暖かくなかったと思います。
何匹も見かけたのはこのクモ
背中に白い筋があります。
こんな風にほかのことにも気を取られながらコンテナ4,5個はやってみたのだけど、とにかく量が多すぎます。わたしは、ウマオを雇うことにしました。地域のイベントがあるからウマオはお小遣いが欲しかったのです。
次の日、ウマオを連れて畑に行ってみたら・・・
20羽ほどのハトが一斉に飛び立ちました!
あんなにたくさんのハト、どこに住んでたんだろう? 大被害というわけではありませんが、早く取り入れるに越したことはなさそうです。
用意していた10個ばかりのコンテナがいっぱいになりましたので作業終了。
翌日、今度はトラオにお小遣いを前貸しして、イベント終了後に手伝ってもらいました。なんと彼は助っ人を二人もつれて来ました。
子どもって生き物を見つけるのが上手。イナゴを2匹も見つけました。
「空気が気持ちいい。」いいお天気だものね。天気が崩れる前の晴天でした。
「おれ、小さいときはじいちゃんの手伝いしてたけど、農作業は久しぶりじゃ。稲の作業が一番面白かった。」
「ゲームばかりしてるよりこっちのほうがいい。」
なんだか3人で楽しそうに集めていました。 さすがに高学年男子3人の馬力はすごかった。用意したコンテナ12個分、1時間もかからないうちに満杯にして、小さなお菓子を一個ずつ上げたらとても喜んで(わかってたらもっと用意してたのに)元気よく遊びに行きました。
そのあとは私一人でちまちまと落穂ひろいならぬ落ち鞘拾いをしてみたけど、まだまだ残っています。
ところで、この近くの畑で見慣れない鳥を見つけたのですけど・・・・

スマホではこれが限界です。トリミングしたらぼやけてしまいました。
トビは見慣れているからわかります。 トビよりも小さくハトよりは少し大きいくらい。 あたりを見回している姿が猛禽類かなとおもうのですけど。
追記
書き忘れていたことがありました。
固まって落ちていたハトの毛。何者かがハハトを連れ去ったようです。もしかしたらこの鳥だつたかも。
写真はありませんがキツネも見ました。去年このあたりで見かけた動物はやはりキツネだったはないかと思います。今年はすでに2回見ています。ものすごく走るのが早いです。そしてこんがりキツネ色ではなくてやや黒っぽいです。けど、顔がキツネ。
そうそう、弟の話ではイタチもいたんですって。ということは野ネズミなんかもいるのでしょうね。ここでは、人間のすぐそばでいろいろな生き物が暮らしています。