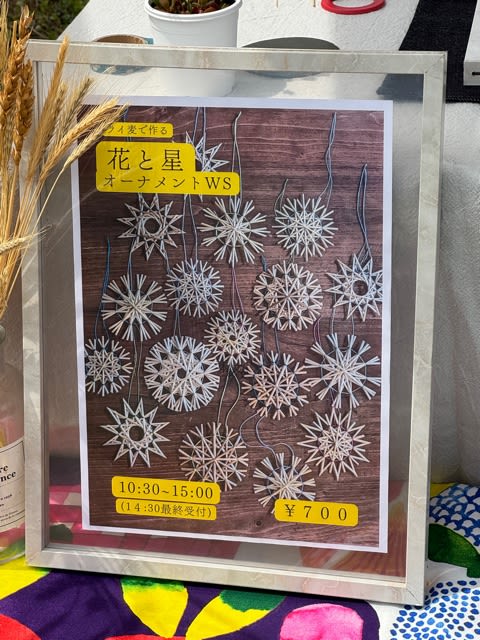わたしにとっては毎日が休日でも、世間では休日と言えば土曜日、日曜日。5月6月のお出かけを2回に分けて紹介します。
まずは革染色仲間のAさんの作品展示会。
東予に住む私 中予に住むNさん 南予に住むAさん
同じ県内とはいえ3人が揃うことはめったにありません。今回は松山市郊外でNさんと落ち合って南予への道に詳しいNさんの運転で伊予の小京都大洲へ。
新緑の美しい季節。国道を避け、山の中の信号のない一本道は快適で楽しいドライブでした。
ところがあと少しで臥竜荘、という所で工事のため通行止め。会場は臥竜山荘のふもとにあるのです。仕方なく道の駅に車を置いて観光案内所で道を聞いて歩いて行きました。
古い趣のある建物が並ぶきれいな通りは「おはなはん通り」?多分
もう60年も前に大人気を博した朝ドラ「おはなはん」の生まれ育った町という設定でロケが行われた所です。もう知らない人の方が多いんですけどねえ~
私はそのころ高校生、バス停から高校までの路地を家々から聞こえてくるエンディングの音楽と競争しながら走っていました。音楽が終わってⅠ、2分までが勝負です。半分閉じかけた校門を、「バスが遅れましたぁ。」と叫びながら駆け抜けていました。仲間が何人もいたから助かった。もう一便早いバスに乗れば問題はなかったのですけど。
この水路、津和野の町に似ています。水は肱川から引いているそうで、鯉も住んでいます。
ここは確か郷土料理のおいしい店だったと思います。「帰りにここで食べようね、」と言っていたのに帰るころには閉店していました。残念。
行ってみたら別の道から車で来ることができたのです。画廊の庭でAさん発見。今回は小さな作品展ということで、40号の大作は一つ、バッグや小物の作品が主でした。けど、今年2月にNさんの作品展を見てきた私には、作品展を開くこと自体がすごいと思うのです。わたしなんぞは作品展どころか、春の県展にも出品せず。レザークラフトは停滞ぎみなんです。頑張らねば。良い刺激になりましたが、作品鑑賞よりも近況報告に花が咲きました。けっこう長い間おしゃべりしてお暇しました。
さて、昼ご飯を、と思ったら先ほどの郷土料理のお店は早々と閉店、どこで食べましょうか。同じ道を2度往復して結局ハンバーガーがたべられるカフェに入りました。そこの鱧フライハンバーガーがとってもおいしかったのです。鱧は小骨がいっぱいある魚、それを細かく骨切して料理します。よく湯引きして酢の物で食べますが、フライで食べたのは初めてでした。骨切したとは思えないほどふわふわで上品なうまみ。こんど鱧を見つけたらフライかてんぷらにしてみましょう。
食べる間も、帰りの車の中でもしゃべり通しだった私たち、なかなか思うようにならなくなった自分の体とか、日々の暮らしとか、お世話になった共通の知人の訃報とか、親の介護とか、話題は尽きませんでした。
その2週間後、私は県民文化会館で開かれたコンサートに行きました。

もう去年の暮れから楽しみにしていました。以前反田恭平さんのには抽選漏れで行けなかったこともあり、人気のある人の時は自分で取るべしと悟りました。なので今回はローソンで自分でチケットを買いました。座先指定はできません。S席にもかかわらず2回中央あたりでした。その後まもなくチケットは完売だったようです。
今回は余裕をもって行けたこともあり、会館前の安い駐車場に止めることができました。開場ぴったり位に入ったときはすでに長蛇の列。
お花は全部HIMARIさん宛でしたね。

うしろから「楽しみ」という声が。
「顔もいいだろ?」「うん、うん」
そっちか~い。
そりゃあねえ、よっぽどの音楽好きでないかぎり、指揮者の腕がどうのこうのなんてわかりませんもの。テレビで見たことがあるとか、今人気らしいとか、そんなことがコンサートにいくモチベーションになる・・・地方都市ならではのアルある、です。
で、二階席からは顔の良しあしはあまりわかりませんでしたが、やはりかっこよかったです。こんな言い方があっているかどうかわかりませんが、「体全体で音楽を表現する人」
膝の使い方は縦ノリだし、どのパートにどんな指示をしているかは上半身全体でするためわかりやすい。見ている方も指揮者の意図はよくわかります。演奏者もきっとそうだろうなと思いました。
でも、ベートーベン交響曲7番2楽章では、あれ、指揮をやめた?と思うくらい動かなくなり、ただ演奏者の感情に身をゆだねて、自分は何もせず音楽の中を揺らいでいる感じ。ろくに指揮をしてないのに演奏者の心が一つになって盛り上がっていくさまが心地よかったです。
さて、HIMARIさんのこと
13歳のバイオリニストということは知っていましたが、パンフレットを読むとその経歴のすごいこと。天才とはこういう人のことを言うんだと納得です。
一部のシベリウス作バイオリン協奏曲が終わった後舞台袖に引っ込んだ彼女を、何回も盛大な拍手で呼び戻した聴衆ですが、ここで原田さん登場。なんと彼はテレビ録画のディレクターのごとく腕を振り回してもっと拍手を、と合図します。しまいには「もっと、もっと」の掛け声とともに頭上で手を回しだし・・・おもむろに指揮台の端っこに腰かけてしまいました。
アンコールは
作曲家も曲も知りません。でもすごい技巧だということはわかりました。一つの楽器なのに何台もが演奏をしているように聞こえるのです。バイオリンは1717年製ストラディバリウス。前澤友作氏貸与ですって。弦は宗次コレクションより貸与。超一流の楽器の音色を聞けてめちゃくちゃ得した気分でした。だって、生まれて初めて本物のストラディバリウスを聞いたんですよ。力強い深みのある音でした。
アンコールというよりはバイオリン独奏としてプログラムに入れるような力のこもった演奏でした。原田さん結局指揮台に座ったまま最後まで聞いていましたよ。
「アンコールってふつうみんながよく知っているような軽い曲が多いよね。あんなにすごいのをアンコールでしてもらったら、なんだか申し訳ないというか・・・」と出がけに言っている人がいました。
帰りは何回も何回も行列に出くわしました。
駐車場の精算機の前は長蛇の列。昔は地下駐車場に車を入れると1時間は余分にお金を払わなければなりませんでした。それからいうと、精算機の行列はまだましになったのかな。
会館の外に出ると目の前が路面電車の乗り場です。そこも人があふれて線路にまでならんでいます。あの調子では何便も待たないと乗れないよねえ、などと思いながら駐車場に着いてはっと気が付きました。
車を出すまでにどれくらい待つんだろう。
出庫する車が場内にぐるっと行列を作っていたのです。結局40分待って帰路につきました。