



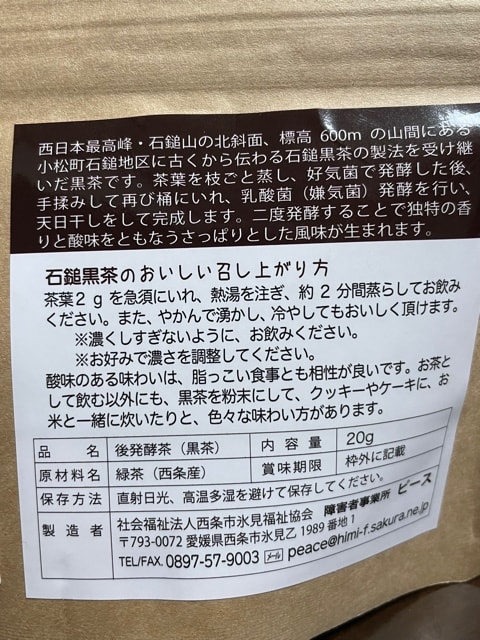

中身はこんなの






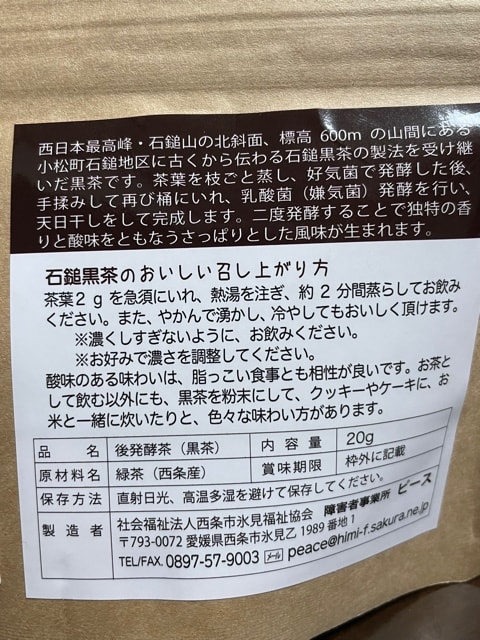




















































































新聞でちょっと寂しい記事を見つけました。
大洲市のポポー農家さんが20年続いた栽培を縮小するというのです。
大洲市にはたしかポポーの産地があったはず。十年位前かな、ニュースで、地域の人が集まって産地化をすすめ、ポポーアイスなどの開発も進めていると言っていました。では、それが産地化には至らなかったってこと? そして、一人で栽培をしていた人が本格的な栽培委はやめたとー 高齢で後継者いないそうです。
う~ん、やっぱりポポーって流通させるのは難しいんだなあ、と、これが私の実感です。
第一に、好きな人と嫌いな人とがはっきりと分かれます。人と会うときは必ずポポー持参で押し付けてきましたが、その感想を聞くと、家族で分けて食べても好き嫌いがはっきりと分かれていたそうです。嫌いな人は全く食べません。 なかなか消費拡大がしにくいのではないかと思います。
第2に 痛みやすいこと。 9月初めころはネットに落ちたポポーは1,2日で傷みだしました。台風が過ぎて朝晩の気温が下がりだしてからわりと青くかたいまま落ちてるので3日は大丈夫かな。しかし、青いのは追熟させないとおいしくありません。追熟させても採れ始めたころのような甘さにはなりません。追熟させすぎると味に苦みがでてきます。

下の方が1日目。黒いのは3日目。真ん中のやや黄色いのが二日目くらいたった食べごろ。
第3に、苦みのもとは皮と種にあるのではないかと思っています。じつは、私は食べた後唇が荒れてきます。はじめはそれに気づかずたくさん食べていたのですが、どうもおかしい、これはポポーのせいではないかと思い調べてみましたら、ポポーの皮と種にかぶれる成分が含まれているらしいです。わたしはひどく荒れるわけではないので一日はに1,2個は食べています。これも体質に寄るらしく、何ともない人もいるようです。
人にあげるときは極上の実を、「スプーンでざっとすくってざっと種を出して食べるように。子供がすいかを食べるときのように皮の際までこそげないこと、種も周りのゼリー状のところまで食べつくさないこと。」と言ってあげます。が、おいしいのでついつい皮が薄くなるまでこそげてしまう、という人もいて、そういう人は平気なのだと思います。
大量のポポーをどう消費するか。大きいのはこんなにもあります。甥っ子が「糖尿になりそう」というくらい甘くて、栄養価も高いので、非常食になればいいのですけどねえ。

結論から言うと生で食べるのが一番。余ったのは種を取り除きペースト状にして冷凍しておきます。

このまま砕いてシャーベット状にしてもいいし、アイスクリームに混ぜてもいいです。けど、種を残したまま放置すると苦みが出るような気がするのです。早く処理して素早く冷凍すべし。
牛乳との相性はとてもいいと思うのですが、スムージーは私にはきついみたい。ちょっとお腹が緩むのです。ならば火を通したらいいのではないかとポポー入りミルクジャムを作ってみました。去年、ポポーだけでジャムを作りましたがこれは大失敗しましたので。
牛乳をとろっとするまで煮詰めます。

あとからポポーのペーストを混ぜてさらに火を通します。すると

なんだか色がどす黒くなったようです。食べてみると・・・さらに苦みが増して匂いもきつくて・・・食べられませんでした。ああ、牛乳がもったいない。
あと、どなたかのブログで干しポポーというのを作っていましたのでお天気のいい日に3日ほど干してみました。が、種を取ると実が崩れるし、種ごと干せば乾きにくい。食べてみると、中に味が凝縮されておいしいのもありましたが、手間がかかる上にお天気に左右されます。
というわけで、これぞ幻の果物の王者。 気難しい王様です。プロの農家さんは多分上手に扱っておられるのだと思いますが、ほったらかしの我が家ではそのまま畑に帰す(捨てる)しかありませんでした。
これが大都会に近い道の駅などに出荷できるのであればねえ、消費拡大も見込めたでしょうが。残念ながら田舎ではポポーを収益作物として栽培するのはなかなか難しかったのではないでしょうか。