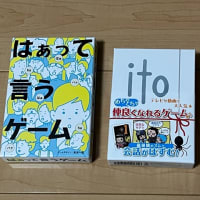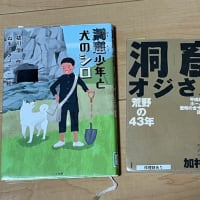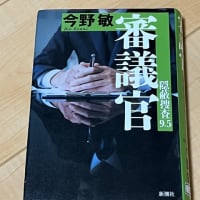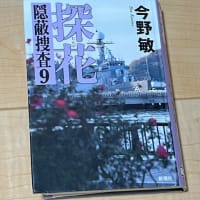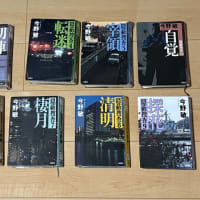給特法の改正について思うことがある。
なぜ教職調整額の増額をするのか?
教職調整額とは、時間外勤務の多少に関わらず、一律に支給される手当である。これまでは、給与の4%だったが、今回の改定で10%となった。
30万円の給与をもらっている人は、4%だった1万2千円から、10%の3万円に増額となる。
だからと言って、
「これまで45時間の時間外勤務を1万2千円で働いていたから3万円にしますね」
と言われてもうれしくないだろう。
(45時間だった場合、「4%で時給266円だったから 10%の時給666円にしますよ」ということである。)
それよりも、時間外勤務を必要としないような環境作りをしてほしい。
何よりも教職調整額の増額では、勤務していても勤務ではない「自主的」な
時間外勤務手当を支給するというのは、時間外勤務に対してコスト
定額で支払う
文科省をはじめとする行政は、学校の職員が疲弊していることに気
このままでは、人材確保ができずに、公立学校の教育力は低下する
私は、これからの公教育にはかなり悲観的な見方をしている。
教員の長時間労働が社会問題化され、深刻な教員不足にまで至って
もしくは、正規雇用の人数を増やし、学級担任が授業づくりに集中できるような人員配置が望まれる。
教職は、本当にやりがいがある職である。
しかし、そのやりがいを感じる前に疲弊してしまっている人が多くなってしまっている。