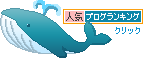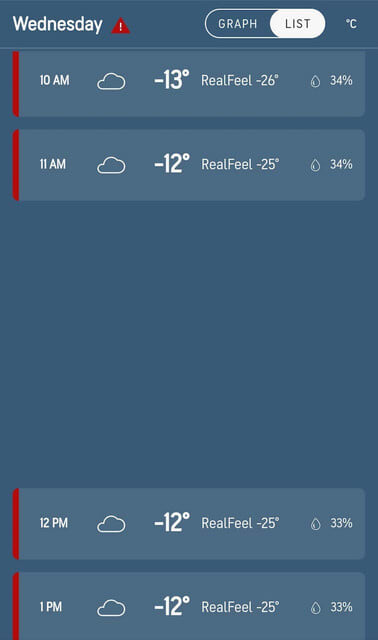世界各地に、日本語学校というのがあると思うのですが、その中には日本での学習と同じカリキュラムが受講できるという学校もあります。
そういったカリキュラムの学校は主に駐在で数年間の海外滞在の為に、日本へ帰国した際に日本での学業についていけるようにという目的があると理解しています
平日は現地の学校に通い、週末は1日使って1週間分の学習をし、キャッチアップできるようにと、宿題も多いと聞きます。
日々の現地校で慣れない英語&フランス語漬けの時間でも疲れると思われる中、日本語学校のたくさんの宿題にも取り組み、友達と遊んだり、ゆっくりできるはずの週末も1日つぶして学校へ行く事を続けている子供達がすごいなと感心させられます。
そして、ご家族も週末なのに学校への送迎やお弁当作りがあったりと 毎週大変だろうなあ。。と思います。
ただ。。。。私が聞いてる話は幼稚園でのお話ですが、その貴重な週末の時間と学費を費やしてまで通っている学校の学習へやり方に、大いに疑問を抱く事があり、これが「日本の幼児教育」だとすると、これも大いに疑問を抱く話があります
みなさんはどう思われるでしょうか。
言葉の習得には、聞く力から話す力が育ち、絵本の読み聞かせや日常目にする情報から読む力が育ち、そして書くという力が育つ。
「書く」というのは一番ハードルの高いスキルです。さらに自分が伝えたいことを簡潔にまとめ、相手にわかりやすく伝える。というのは難易度が上がりますよね(私は苦手)。
書くためには、今はタブレットやPCを使って文字をタイプする方法も子供達の学校でも主流になってきているようですが、 伝統的な書き方としては、筆記具を持ち、それを自分の意思で動かして線を引くことで、文字を書くことができる
ステレオタイプな発言かもしれませんが、日本の学校の宿題はこっちの方が主流では!?
そして恐らく、その初めのステップとして、「なぞりがき」の課題があるのかなと予想しますが、問題はその取り組み方。
なぞりの線からはみ出てはならない。というルールがあるそうで
少しでもはみ出すと、今まで書いた分も消して最初からやり直し。
これを幼稚園生に求める意図はなんでしょう。
恐らく通わせている親御さん達の中にも疑問を抱いている方達が少なからずいるのでは?
「書く」というのは、一番ハードルの高いスキルであり、それに取り組むということは、その姿勢をまず認め誉めてあげてもいい取り組みです
中には「書くこと」が好きなお子さんもいます。プリント学習が好きなお子さんもいます。また、お子さんによって、「書く」という事に関心を持つ発達段階にあるお子さん達は、自ら「書いてみたい」「書けるって楽しい」という感覚と共に、書く学習を遊び感覚で取り組むと思います。
こういったお子さん達には、どんどん書かせていいと思うし、プリント学習が好きなお子さんには、どんどんやらせていいと思います
だけど中には、全く興味が持てない子。筆記具を上手に持ったり それを扱うスキルを十分に得ていない発達段階にある子達もそれなりの数いるはずです
その発達段階のお子さん達にも、「丁寧に書く」「線からはみ出さない」「はみ出たら消して書き直し」。そして宿題の量は全員同じ。
想像していただくと、お子さん達が抱えるストレスわかりますよね。
鉛筆を持って書かせたいと思うのなら、以前にも書きましたが「お絵描き」はとってもおすすめの遊びです。
今はタブレットに指で絵を描いたりもできますが、それはそれでやめさせる必要はないけれど、クレヨン、マーカー、絵の具、色鉛筆、筆やスポンジなど様々な筆記具を使い、道具を使って「描く楽しさ」を体感することは、「書ける楽しさ」にもつながっていきます
描く場所も、紙だけに限らず、砂、柔らかいジェルの入った袋、路上、石、木など 何でも良い。 自分の手を使い、それを動かすことで、何かが描ける/書ける。形に変化が起こる。自分が伝えたい事が表現できる。こんな体感はとっても大切
「みんながやってるから。宿題だから。と無理やり 指定されたやり方でやらされる」この取り組みは、「書く事が好きじゃない」「書く事にまだ興味を持てない」お子さん達の「書くことへの意欲を損失させる」アプローチでもあると思います
ここは想像ですが、その宿題は、鉛筆で書かないときっとダメなんですかね。。。。
もし書く事がうまくできない子が、「マーカー」や、好きな色を使った「色鉛筆」でなら書きたいと言ったら、ここの学校の先生達は「いいですよ」と言えるでしょうか。その子の取り組みに花丸をあげられるでしょうか。
例えば「ほ」の2本線が1本だったら、これは「ほ」にならないから2本だと教える必要がある。
「い」と「り」の違いをはっきりさせるには、右側の線の長さに注意する必要があること。
これらは、自分が書いた文字を、自分以外の人が正しく読み取れ、伝えたいことを伝えるために習得した方が良いスキル。
この教え方も「それ、間違ってるよ。こうだよ」と教えるよりも書いたことへの努力を認め、自分が書いた物と、お手本を本人に見比べさせて「似てるけど、何か違うね。どこが違うかわかる?」と間違い探しを本人にさせると、幼稚園生でも自ら間違いに気がついた場合は直すと思います。この時も消して直さなくてもいいんじゃないかな(本人が消したいならそれで良いと思うけど)。 間違いでも一生懸命書いた物をあっさり承諾なく消されたら、幼稚園生も悲しいよ。1つの努力の軌跡として、間違いに気がついて次に書いたものは正しく書けた。これぞ学習では!?
と、私は思いますが。。。。。
ちなみに、我が子達はある程度日本語の読み書き(ひらがな、カタカナ、漢字)もできますが、強制して書かせて教えたりはしていません
うちの子達に限らずだともいますが、2歳ー4、5歳の時に、文字に興味を持つ=読む、自分の名前を書いてみる。などをきっかけに、読む、書くに興味を持った時期が二人ともありました。
そのタイミングに、我が家の場合は絵本とベネッセの通信教材がとてもいい仕事をしてくれて、それこそ発達と興味のタイミングに合わせて ひらがな&カタカナ、数字は勝手に(笑)習得してくれた。感じです。
「はみ出さないように書く」事に目くじら立てずに、「子供が書いてみよう」と試みた姿勢を評価し、取り組みに花丸をあげる方が、子供達はもっと意欲的に「書く」事にも取り組むようになると思うんですけどね。。。。
もう1つ、子供達の発言に対しての先生の対応も、え?軍隊!? ちょっと精神的虐待とも思うような事を聞いて驚いた私です。
学校へ通わせているご家族で、授業参観やお子さんからの発言で疑問を感じた親御さん達がいらしたら、その感覚は間違っていないと思いますよ。
日本語環境という現地校では得られないメリットや、カナダの学校では体験できない日本文化に関する経験などもあると思いますが、1日そこで過ごすお子さん達の事を考え、おかしいと感じて、先生との面談でも納得いかないと思うなら、ご家庭や日系コミュニティとの時間でも 特に幼稚園から低学年の間は学業も心も健やかに育めるのではないかと感じてしまいました。
日本の幼児教育がもしも「型からはみださいこと」や「お行儀」を重要視するのであれば、、、本当にそれが一番大事??と疑問を抱きます。
特に駐在で滞在されているご家族は、せっかくの機会なので是非、現地校の良さを日本へ持ち帰ってほしいです。カナダの学校にも課題はあると思いますが、人権の尊重、多様性とは何か。インクルーシブ教育とは何か。カナダの教育現場から学べる事が沢山あると思うので、親子で体感してみてほしいです。