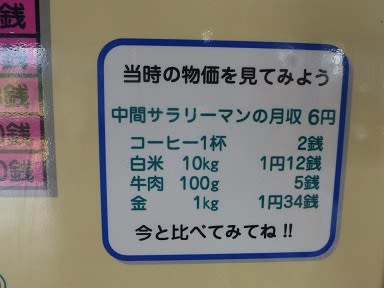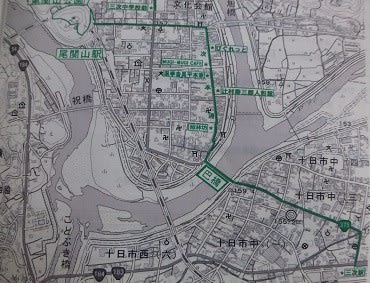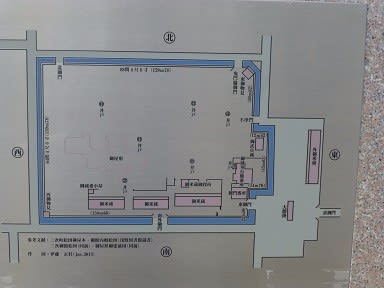中国山地の山間(やまあい)に、すべての構造物がピンク色に塗装され、ハートマークに溢れている駅があります。智頭(ちず)急行株式会社(以下「智頭急行」といいます)智頭線の恋山形(こいやまがた)駅です。写真は駅を見下ろす丘から見たその恋山形駅の全景です。平素は、どちらかといえば、山間にひっそりと建っている駅に魅力を感じているのですが、今回は、山間にある明るい駅を訪ねてきました。

JR岡山駅から早朝に出発する、ディーゼル特急”スーパーいなば”に乗車しました。この列車は、自由席1両(キハ1871502号車)と指定席1両(キハ187502号車)の2両編成で、岡山駅からJR山陽本線を大阪方面に向かいます。そして、兵庫県に入って最初の駅であるJR上郡(かみごおり)駅で、第三セクター鉄道である智頭急行智頭線に入って智頭駅に、その後、JR因美線を通ってJR鳥取駅に向かって進みます。この智頭急行と因美線を通って鳥取駅に向かうルートは、江戸時代、鳥取藩が参勤交代のときに通ったルートでもありました。これから訪ねる恋山形駅は、途中の鳥取県八頭郡智頭町大内にあります。上郡駅で、運転士と車掌がそれぞれ反対側に移動して、”スーパーいなば”は、ここまでと反対方向に向かって走ることになります。

智頭急行は、平成6(1994)年12月3日に開業した新しい鉄道で、最近の鉄道らしく、”スーパーいなば”も高架上に設けられた線路を、時速120kmで疾走しています。しかし、恋山形駅には特急列車は停車しません。そのため、大原駅で、智頭駅行きのディーゼルカーの普通列車(HOT3507号車)に乗り継ぎました。この車両は、智頭急行が保有する車両で、形式記号の”HOT”は、英語の”hot”と沿線の兵庫県、岡山県、鳥取県の頭文字を取ってつけられているそうです。

岡山駅を出発してから約1時間20分、杉の大木の前にピンク色をしたホームが見えてきました。恋山形駅です。列車は、そのまままっすぐ進み、右側の2番ホームに停車しました。2面2線の駅でしたが、2番ホームに接した線路がまっすぐ智頭方面に向かっており、通過する特急列車もこちら側の線路を疾走しています。反対側の1番ホームは、行き違いがあるときだけに使用されているようです。

下車した2番ホームです。待合スペースの壁には、ピンク色の壁面に赤いハートのマークが踊っています。ホームの標識もハートの形です。ピンク色が目立つホームですが、これは白色でした。

恋山形駅は、平成6(1994)年の智頭急行の開業時に設置されました。当初は「因幡山形駅」と命名する予定だったそうですが、たくさんの方に来てほしいという意味で「来い山形」、そこから「恋山形駅」にと変わっていったそうです。その後、平成25(2013)年6月に、駅の活性化をめざす「恋えきプロジェクト」の一環として、待合スペースなど地上施設をリニューアルして、ピンクに塗り替えたそうです。ここの駅名標示も白色でした。

大きなハート型の駅名標示です。ローマ字のほか、中国語(繁体字)とハングルの表示もありました。やまさと(山郷)駅から2.8km、次のちず(智頭)駅まで6.1kmのところにあります。ちなみに、「智頭」のかな表記は、会社名と駅名は「ちず」、地名(町名)は「ちづ」を使用しているそうです。

向かいの1番ホームの待合いのスペースです。2番ホームと同じようなつくりです。さて、智頭急行智頭線は、明治25(1892)年に始まった鉄道敷設運動に始まります。明治時代につくられた鉄道敷設法には「兵庫県姫路から鳥取県鳥取に至る鉄道」が定められていましたが、その後、山陰への鉄道は和田山から建設されることになり、姫路からの敷設は白紙になってしまいます。大正11(1922)年に改正された鉄道敷設法では「兵庫県上郡から佐用を経て鳥取県智頭に至る鉄道」が規定されました。しかし、太平洋線戦争によって実現にはいたりませんでした。

ホームからの出口は、大原駅側にある階段を下り、構内踏切を渡った先の1番ホームの脇にあります。恋山形駅はメディアでもよく採り上げられているためか、訪ねる人も比較的多い駅です。しかし、列車でこの駅まで来られる人は多くはないようです。この日も、駅前の広場に若いカップルが来られていて、写真を撮影しておられましたが、車で出発して行かれました。さて、戦前から始まっていた智頭線の敷設を求める運動は、戦後も続けられ、昭和41(1966)年に運輸大臣(当時)から上郡・智頭間の「工事実施計画」の認可を受け、昭和41(1966)年に着工しました。しかし、順調には進まず、昭和55(1980)年に成立した国鉄再建法によって、進んでいた工事は中止となってしまいました。残された道は、地方自治体による第三セクター方式による開業だけでした。昭和58(1983)年に就任した西尾邑次鳥取県知事によって第三セクターによる建設への道筋がつき、同年6月に工事が再開されました。こうした地元の人々の熱意と粘り強い努力によって開業したのが、智頭急行智頭線でした。

踏切の中央部分から見た智頭駅方面です。まさに、ピンク色の駅だと感じます。青い空、緑の杉林、ピンクの駅施設。見て楽しい駅になっていました。

こちらは1番ホームです。階段の手すり、フェンス、ホームの上屋、柱、壁面も、ホームミラーもゴミ箱も、すべてピンク色でした。階段を利用して1番ホームに上がると、たくさんのハート形の絵馬が吊り下げられている一角がありました。

正面の「恋」と書かれたハート形の上に鐘があります。「恋がかなう鐘」だそうです。大きなハートマークの「恋」の字の上に、赤色のハートの部分が見えます。願い事を書いた絵馬をその赤い部分にはめてから、「恋がかなう鐘」をならしてお祈りをした後、絵馬を吊り下げると願いがかなうそうです。「早朝や夕方以降と、列車が到着しているときは、ご遠慮ください」とのこと。「恋がかなう鐘」は、この駅がピンクの塗装でリニューアルされた翌年の、平成26(2014)年3月15日に設置されたそうです。ハートマークの下の扉の中には「恋山形ノート」が置かれています。「思いを残してほしい」という願いから置かれているもののようです。

1番ホームにいたとき、6両編成の特急列車”スーパーはくと”が通過していきました。「はくと」は「白兎」です。東海道本線から智頭急行に入るルートで、京都駅と鳥取駅・倉吉駅間を結んでいます。智頭急行が所有するHOT7000系車両で運行されています。JR西日本の鳥取鉄道部西鳥取車両支部に常駐し車輌の管理がなされているそうです。智頭急行は「第三セクターの優等生」と称賛されるほど、経営が順調であることで知られています。好調な経営を支えているのが、この”スーパーはくと”なのだそうです。

待合いスペースに書かれていた「鉄道むすめ」の”宮本えりお”です。智頭急行の”スーパーはくと”の車掌で、上郡駅から鳥取・倉吉駅間に乗務しています。「落ち着いた性格、ていねいな対応が好印象。利き手は両手で、学生時代には剣道部に所属していたそうです。趣味は天体観測で、さじアストロパークや西はりま天文台にもよく通っているそうです。「みやもとえりお」という名前は、智頭急行の宮本武蔵駅と、上郡駅の反対読み(きえりおごみか)から名づけられたといわれています。

1番ホームの脇から駅前広場に出るところにあった「恋ポスト」です。平成28(2016)年に設置されました。このポストは智頭急行が設置したものです。そのため、週一回、毎月曜日だけに回収され、地元の山形郵便局に届けられます。そこで、ハート型をした風景印で消印をつけることになっています。「切手を貼るのを忘れないように」と書かれていました。

広場の塀につくられていたハートのマーク。この駅に到着したとき、若いカップルが「インスタ映え」するようなポーズで、何回も何回も撮影をされていたところです。

1番ホームの待合いスペースの裏側にあたるところです。「恋がかなう駅 恋山形駅」の掲示と、その先に大きなハートのマークがありました。

ハートのマークの前方の地面に、ハート形のマークが描かれています。そこに足を置いて、こちら向きに立って・・・

その前にあった、構造物の上にカメラをおいて、セルフタイマーで撮影ができます。一人旅の人も記念撮影をすることができるようになっていました。

1番ホームの裏の道を下っていきます。線路の法面(のりめん)には、芝桜が植えてありました。春先には、おそらく、ピンクの花が咲いてピンク色の駅に色を添えることになるのでしょう。

駅への取り付け道路の入口から、幅1メートルのピンクに塗装された道がつくられています。平成29(2017)年4月1日に設置された「恋ロード」です。法面につくられていた芝桜のハートマークも見えます。

日本には、「恋」の字がつく駅は、恋山形駅以外に3ヶ所あります。JR北海道室蘭本線の「母恋(ぼこい)駅」、三陸鉄道南リアス線の「恋し浜(こいしはま)駅」、西武鉄道国分寺線の「恋ヶ窪(こいがくぼ)駅」です。「恋えきプロジェクト」は、「この4駅が連携して地域の活性化を図ることを目的として」行っている活動です。ここ恋山形駅が行っている駅施設のピンク塗装、「恋がかなう鐘」、「恋ポスト」と「恋ロード」などは、この「恋えきプロジェクト」の一環として行われているものでした。

恋山形駅の楽しみ方も掲示されていました。 「①ハート絵馬はお持ちですか? ②絵馬に願いごとは書きましたか? ③絵馬をハートのモニュメントにはめましょう ④恋山ノートにコメントしましょう ⑤写真スポットで写真を撮りましょう ⑥ホームのベンチでゆっくりお過ごしください」と書かれていました。
ピンク色の駅、恋山形駅は、JR上郡駅とJR鳥取駅を結ぶ第三セクターの智頭急行の駅で、中国山地の奥深いところにあります。
智頭急行は総延長56.1kmの鉄道ですが、京都駅と鳥取駅・倉吉駅を結ぶ”スーパーはくと”と、岡山駅と鳥取駅を結ぶ”スーパーいなば”の運行により、第三セクターの優等生といわれるぐらい好調な経営で知られています。しかし、普通列車の利用は快調とはいえず、特色ある駅をつくることによって活性化を図っています。恋山形駅も、「恋」をテーマにした新しい駅づくりに努力しています。
恋山形駅は、「恋がかなう鐘」「恋ポスト」「恋ロード」と、次々に新しい企画を打ち出していています。次はどんな企画が出てくるのか楽しみでもあります。せめて、この駅だけでも、列車で訪ねる人が増えていけば・・と願いながら、歩いた旅でした。