
■「ラ・ラ・ランド/La La Land」(2016年・アメリカ)
●2016年アカデミー賞 監督賞・主演女優賞・撮影賞・歌曲賞・音楽賞・美術賞
●2016年ヴェネチア国際映画祭 主演女優賞
●2016年NY批評家協会賞 作品賞
監督=デイミアン・チャゼル
主演=ライアン・ゴズリング エマ・ストーン キャリー・ヘルナンデス ジェシカ・ローゼンバーグ
※結末にちょっと触れてるし、ほめてないので注意ww
世間の評判がよいだけに言いにくいのだけれど、
正直申し上げると僕が期待したものとは違った。
往年のクラシック映画へのオマージュでありながら、
かつてのハリウッド製ミュージカル映画がもたらしてくれる(と僕らが期待してしまう)
この上ない楽しさと極上のハッピーエンドがここにはない。
「ラ・ラ・ランド」は、確かにカッコいい音楽映画だ。
ではあるけれど、黄金期のハリウッドミュージカル映画を期待すると、
それはちょっと違う。
引用されたジミー・ディーンの「理由なき反抗」、
登場する映画スタアの華やかさなど、この映画はハリウッド黄金期の香りを匂わせている。
それなのに、iPhoneの着信音が鳴り響き、プリウスの鍵がズラッと並ぶ現代劇だから
違和感が最後まで消えない。
今どきフィルムが焼けちゃうグラインドハウスな映画館がハリウッドにあるの?
そりゃ潰れるよね。
それに現実に引き戻される着信音だけでなく、火災報知器の音とか映画館の大音量で聴きたくない音も、
僕がこの映画に入り込めない一因かも。
でも、チャゼル監督の演出は前作同様、カッコいい。
ワンシーンワンカットでカメラが走り回るオープニング、
プールの真ん中でカメラが回転し続ける驚きのカメラワーク、
コミカルなタップダンス、
「世界中がアイラブユー」のラストシーンみたいな空中浮遊、
映画館で重なる手と手の胸キュンな場面、
そしてショービジネスの裏側の厳しさ。
ラストで彼が奏でた曲は、
「カサブランカ」の As Time Goes By みたいに二人にしかわからない思い出。
映画はそこで締めちゃえばいいのに、
さらに未練がましい二人の別な展開を観せてさらに切なくしてくれる。
音楽と映画と恋に2時間溺れてハッピーになりたかった僕のような方は、
ちょっと裏切られたのでは。
ラ・ラ・ランド(予告編)












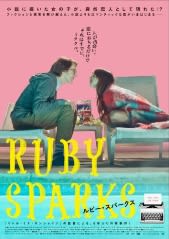



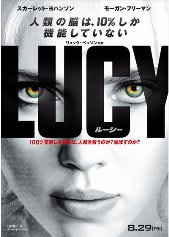








![ラスト、コーション [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/510FixgvgLL._SL160_.jpg)

![ラブソングができるまで [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51t+hYvrahL._SL160_.jpg)




