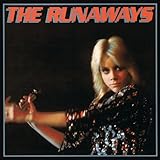◼️「ローラ殺人事件/Laura」(1944年・アメリカ)
監督=オットー・プレミンジャー
主演=ジーン・ティアニー ダナ・アンドリュース ヴィンセント・プライス クリフトン・ウェッブ
ずーっと観たかった「ローラ殺人事件」。オットー・プレミンジャー監督のデビュー作にして、ミステリー/サスペンス+メロドラマのクラシック。
冒頭、いきなりローラが散弾銃で顔面を撃たれて死んだと観客は伝えられる。その捜査をする刑事マークが、ローラと親しかった文筆家ウォルドを訪れる。ローラに活躍のチャンスを与え、立派なレディに成長させたウォルドは、フィアンセだったシェルビー、叔母のアンと共にローラ殺しの容疑者。やがて刑事マークは殺害現場であるアンの部屋で長い時間を過ごすようになり、「君は死人に恋をしている」と言われてしまう。果たして犯人は誰なのか?
ジーン・ティアニー主演作観るの初めてかも。バイタリティある美女役で周りの注目を浴びる存在だが、周囲の男性を振り回すようないわゆるファムファタールとはちょっと違う印象。でも肖像画だけで虜になる男も出てくるわけで、運命の女と呼んでもよいのかな。
後半に話が急展開してからの面白さは、90分弱の尺でも十分に満足させてくれる。登場人物と舞台が限られているからこそ、観客を集中させられた構成。お見事。
プレイボーイのシェルビー役は数々の怪奇映画で知られるヴィンセント・プライス(ヒゲがなかったから最初はわからなかった💧)。アン叔母さんは「レベッカ」の怖い女中ジュディス・アンダーソン。この2人のキャスティングがいい。刑事マークが殺害現場で過ごすようになり、ローラの肖像画を見つめる場面は無言で彼の心境を示す。上手いなぁ。そしてその先の場面…え、えっ!?🫢💦
この映画、フーダニットの古典ミステリーとして味わうだけでは、ちょっともったいないと思えるのだ。
(以下、結末に触れます)
ミステリーの面白さはもちろんなのだが、本作はピグマリオン・シンドロームを描いた作品の系譜でもある。以下、ネタバレもネタバレで申し訳ありません💧
私ごとだが、むかーし「歳をとって女に夢中になると狂うぞ」と身近な人に言われたことがある。ある種の呪縛のように自分には思えた言葉だった。実生活でそんな事態には陥っていないが、目にする映画ではそうした人物をあれこれ見てきた。「北斎漫画」や「痴人の愛」で、その言葉の重さを感じてゾクッとし、「昼下がりの情事」でこの後おっさんゾッコンになるんだろなと冷ややかな気持ちになった(笑)。
そして本作でオスカー助演賞を獲得したクリフトン・ウェッブもその例に加わる。度を越した執着が行き着く果てを見事に演じている。「マイ・フェア・レディ」のヒギンズ先生も「プリティ・ウーマン」の大富豪エドワード・ルイスも、ヒロインを華ある女性に育てただけのつもりが結局心が揺れてしまったじゃない。最後までクールだったのは「舞妓はレディ」の長谷川博己くらいではなかろうか。
本作でクリフトン・ウェッブが演じた役の言動は、映画を思い返してみるとローラへの気持ちがいかに強かったかが理解できる。刑事に言った「死人に恋をしている」も、思えば燃え上がるジェラシー。映画後半、そりゃ平静な気持ちではいられなかっただろう。
最初から見直したら、切ない初老男の物語に見えてしまうかもしれない。
「彼女に恋を?」
と刑事に尋ねられた後の台詞は、とんでもない強がりに聞こえるのでは。そんなことを考えてしまったのは、自分もそんな年齢に近づいているからかもしれないな💦
シェルビーがローラの帽子を褒める場面。
「いい帽子だ」
「気に入った?」
「かぶる人がいい」
おお、使えそうな台詞♡
メモしとこっ📝(笑)
冒頭、いきなりローラが散弾銃で顔面を撃たれて死んだと観客は伝えられる。その捜査をする刑事マークが、ローラと親しかった文筆家ウォルドを訪れる。ローラに活躍のチャンスを与え、立派なレディに成長させたウォルドは、フィアンセだったシェルビー、叔母のアンと共にローラ殺しの容疑者。やがて刑事マークは殺害現場であるアンの部屋で長い時間を過ごすようになり、「君は死人に恋をしている」と言われてしまう。果たして犯人は誰なのか?
ジーン・ティアニー主演作観るの初めてかも。バイタリティある美女役で周りの注目を浴びる存在だが、周囲の男性を振り回すようないわゆるファムファタールとはちょっと違う印象。でも肖像画だけで虜になる男も出てくるわけで、運命の女と呼んでもよいのかな。
後半に話が急展開してからの面白さは、90分弱の尺でも十分に満足させてくれる。登場人物と舞台が限られているからこそ、観客を集中させられた構成。お見事。
プレイボーイのシェルビー役は数々の怪奇映画で知られるヴィンセント・プライス(ヒゲがなかったから最初はわからなかった💧)。アン叔母さんは「レベッカ」の怖い女中ジュディス・アンダーソン。この2人のキャスティングがいい。刑事マークが殺害現場で過ごすようになり、ローラの肖像画を見つめる場面は無言で彼の心境を示す。上手いなぁ。そしてその先の場面…え、えっ!?🫢💦
この映画、フーダニットの古典ミステリーとして味わうだけでは、ちょっともったいないと思えるのだ。
(以下、結末に触れます)
ミステリーの面白さはもちろんなのだが、本作はピグマリオン・シンドロームを描いた作品の系譜でもある。以下、ネタバレもネタバレで申し訳ありません💧
私ごとだが、むかーし「歳をとって女に夢中になると狂うぞ」と身近な人に言われたことがある。ある種の呪縛のように自分には思えた言葉だった。実生活でそんな事態には陥っていないが、目にする映画ではそうした人物をあれこれ見てきた。「北斎漫画」や「痴人の愛」で、その言葉の重さを感じてゾクッとし、「昼下がりの情事」でこの後おっさんゾッコンになるんだろなと冷ややかな気持ちになった(笑)。
そして本作でオスカー助演賞を獲得したクリフトン・ウェッブもその例に加わる。度を越した執着が行き着く果てを見事に演じている。「マイ・フェア・レディ」のヒギンズ先生も「プリティ・ウーマン」の大富豪エドワード・ルイスも、ヒロインを華ある女性に育てただけのつもりが結局心が揺れてしまったじゃない。最後までクールだったのは「舞妓はレディ」の長谷川博己くらいではなかろうか。
本作でクリフトン・ウェッブが演じた役の言動は、映画を思い返してみるとローラへの気持ちがいかに強かったかが理解できる。刑事に言った「死人に恋をしている」も、思えば燃え上がるジェラシー。映画後半、そりゃ平静な気持ちではいられなかっただろう。
最初から見直したら、切ない初老男の物語に見えてしまうかもしれない。
「彼女に恋を?」
と刑事に尋ねられた後の台詞は、とんでもない強がりに聞こえるのでは。そんなことを考えてしまったのは、自分もそんな年齢に近づいているからかもしれないな💦
シェルビーがローラの帽子を褒める場面。
「いい帽子だ」
「気に入った?」
「かぶる人がいい」
おお、使えそうな台詞♡
メモしとこっ📝(笑)













![列車に乗った男 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21HHKVNZNNL._SL160_.jpg)



![リトル・ダーリング HDリマスター版 ブルーレイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51YoBz6JlmL._SL160_.jpg)

![龍拳 日本劇場公開版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Mc8OzFMCL._SL160_.jpg)