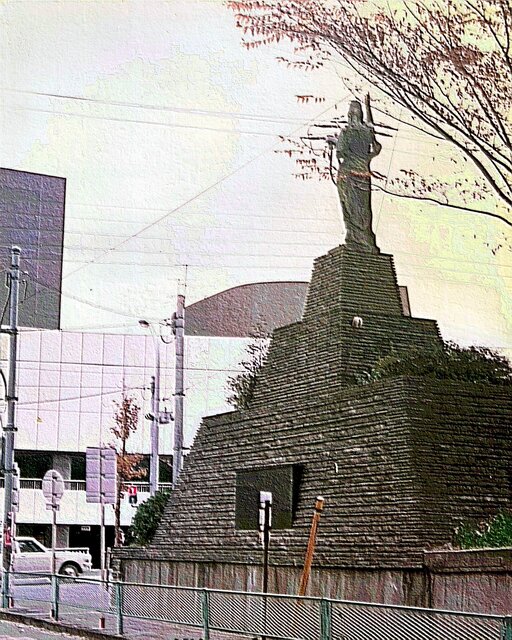「 男子にしかできないのは戦爭と革命だ 」と 佐々木二郎の言葉に
磯部淺一は大きくうなずき
「 ウーン、俺は革命のほうをやる 」と 答えた。
これは陸軍士官學校本科のころ、ある土曜日の夜、
山田洋、佐々木二郎、磯部淺一、三人で語り合った時のやりとりである。
佐々木二郎 ササキ ジロウ
『 男子にしかできないのは戦爭と革命だ 』
目次
クリック して頁を読む
・ 「 大佐殿は満州事變という糞をたれた。尻は自分で拭かずに人に拭かすのですか 」
・ 佐々木二郎大尉の相澤中佐事件
・ 佐々木二郎大尉の四日間
・ 昭和11年7月12日 (番外) 佐々木二郎大尉
昭和十二年三月、
二・二六で無罪で帰隊したが停職になったので、
羅南在住十年の名残りに町を散歩し、美代治を思い出して三州桜に訪ねた。
彼女は芸妓をやめて仲居をしていた。
大広間で二人で飲んだ。
話が磯部にふれた。
「 サーさん、あの人はどうなりました 」
「 ウン、今頃は銃殺されとるかも知れん 」
「 私はあのとき、初めて人間らしく扱われました。
誰が何といってもあの人は正しい立派な人です。一生私は忘れません 」
「 佐々木、芸妓にも料理を出せよ 」
といった磯部の一言が、これほどの感動を与えているとは夢にも思わなかった。
底辺とか苦界とか、口にいってもただ単なる同情にしか過ぎなかった。
磯部のそれは、苦闘した前半生から滲み出た一言で、彼女の心肝を温かく包んだのであろう。
当時、少し気障なことだとチラリ脳裡を掠めた私の考えは、私自身の足りなさであったと思い知らされた。
・・・「 佐々木、芸妓にも料理を出せよ 」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下
佐々木二郎 著 一革新将校の半生と磯部浅一 から
・ 虎ノ門事件 「 少なくともここしばらくはなりませぬ 」
・ 君側 2 「 日本を支配したは宮廷の人々 」
・ 桜田門事件 「 陛下にはお恙もあらせられず、神色自若として云々 」
昭和の聖代 ( ・・・番外編 / 昭和二十年八月十五日 を 主題としたもの )
・ 佐々木二郎大尉の八月十五日
・ 「 挙国の士以て自立するなくば即ちその国倒る 」
・ 亡き戦友の声
前頁 君側 1 『 大命に抗したる逆賊なり 』 の 続き
陛下
日本は天皇の独裁国であつてはなりません、
重臣元老貴族の独裁国であるも断じて許せません、
明治以後の日本は、
天皇を政治的中心とした一君と万民との一体的立憲国であります、
もつと ワカリ易く申上げると、
天皇を政治的中心とせる近代的民主国であります、
左様であらねばならない国体でありますから、何人の独裁をも許しません、
然るに、今の日本は何と云ふざまでありませうか、
天皇を政治的中心とせる元老、重臣、貴族、軍閥、政党、財閥の独裁国ではありませぬか、
いやいや、よくよく観察すると、
この特権階級の独裁政治は、天皇をさへないがしろにしてゐるのでありますぞ、
天皇をローマ法王にしておりますぞ、
ロボツトにし奉つて彼等が自恣専断(ジシセンダン)を思ふままに続けておりますぞ
日本国の山々津々の民どもは、
この独裁政治の下にあえいでゐるのでありますぞ
・・・磯部浅一 獄中日記 (三)
二十六日の朝に、
・天皇は叛乱を絶対に認めてはいけません、
・そして 叛乱をすぐ弾圧しなければなりません、
・弾圧内に新しい内閣を組織することは絶対に許してはいけません
と 決定しました。・・・木戸幸一日記から
木戸は 湯浅宮内大臣と広幡侍従次長を通して、天皇に強い影響を与た。
・・・リンク→ 天皇は叛乱を認めてはいけません・・・
・・・リンク→ ・・・こんなことをしてどうするのか


西園寺公望 木戸幸一 原田熊雄
宮廷の人々
此処では西園寺、木戸、原田、侍従長、内大臣、宮内大臣 等を謂う
前頁 君側 1 『 大命に抗したる逆賊なり 』 の 続き
問題の、軍部大臣は現役将官に限るという寺内陸相の提案に対し、
原田は四月二十日、広田首相を訪ね
「 どうせ陸軍大臣の言うことをきかなければならないのなら、
なるべくあっさりきいてしまった方がいいじゃないか 」と、西園寺の言を伝えている。
いわゆる 『 原田日記 』 『 木戸日記 』 『 本庄日記 』 『 近衛手記 』 等々を読むと、
敗戦に至るまで、昭和の政治の実権は西園寺を中心とする華族の一派の手中に在ったようだ。
そして便宜上一部の官僚を利用した。
即ち宮内省、内大臣府、侍従職等の要点にこれ等華族を配置して側近を固め、反対勢力の侵入を断固として抑えた。
明治維新に使われた 「 宝 」 を手にしたのだ。
只一人の元老西園寺を中心とする宮廷派の動きを大観すると、一口にいえば軍人いじめであると私は考える。
ロンドン条約が問題になれば条約派に肩入れし、陸軍が強いとみれば海軍を支援して対抗せしめるという方策をとった。
このため、海軍部内の分裂を深め、陸海の対立を激化せしめ、敗戦に至るまでその亀裂は塞がらなかった。
・・・リンク→ロンドン条約問題の頃 1 『 民間団体の反対運動 』
この方策は、何百年という長い間、武家政権に対抗した無力無責任の公家のやり方であり、
身分意識からくる武家軍人に対する蔑視、反感からではなかろうか。
西園寺個人としては、首相時代、増師問題による陸軍の倒閣に対する反感もあったであろう。
しかしこのやり方は、天皇のもつ機能の反対の方向である。
ロンドン条約で海軍部内が二つに割れたのは、比率問題以上の打撃であり、米国を喜ばせたであろう。
この頃私は中尉であったが、師団より中少尉に対し、軍縮問題を論ずる課題作業があった。
在職二十年間、この様な事はただ一度だけであった。
昭和動乱の根源ともいうべきロンドン条約を、冷静にもっと広く深く研究して、当局者は対処すべきであったと思う。
斎藤内閣から岡田内閣にかけて国体明徴運動が起きた。
一面は精神的であるが他面では政治問題として取り扱われた。
当時、国内政治の革新が叫ばれ、現実の社会と、政治の動向との間にある矛盾を克服する運動として起きたのだ。
したがってこの運動は、政治、社会の各方向に大きな影響を与えた。
その一つに美濃部博士のいわゆる天皇機関説問題がある。
・・・リンク→国体明徴と天皇機関説問題
軍は、その精神的影響をおそれ、三長官協議の上、真崎教育総監の名をもって、国体明徴の訓示を全軍隊に行った。
・・・リンク→『 国体明徴 』 天皇機関説に関する真崎教育総監の訓示
政治問題として取り扱われると、直接的には岡田内閣の倒閣、間接には重臣層の勢力の紛争にあった。
国体明徴運動の政界における中心は平沼騏一郎にあったという。
岡田は海軍の条約派で宮廷派に親近し、平沼は西園寺の最も嫌いな人物。
それでなくとも荒木、真崎と皇道派の領袖として、宮廷グループより嫌われていたのが、
この一件にて真崎敵視は決定的になったと思われる。
・・・リンク→「 武官長はどうも真崎の肩を持つようだね 」
宮廷派は当然、北の改造法案を読んだのであろう。
最も彼らが嫌ったのは、「 国民ノ天皇 」 の項であろう。
そこには華族制度廃止がうたわれ、皇室財産の国家下附が書かれている。
彼らが二・二六事件の将校や、これと重ね合わせて真崎を敵視した理由はよくわかる。
衆議院で多数を獲得した政党の総裁が首相になるのではなく、西園寺がこれが適任と推薦したものがなる。
「 強力内閣 」 「 挙国 」 「 挙国一致内閣 」 等の空名を掲げるが、既記の如く、分割統治の上に成立するのであるから、
基礎薄弱で、国家国民のために何等なすところなくして終るのである。
首班指名という、最も強大な権力を握っているから西園寺詣でが行なわれ、原田、木戸らの勢威は高まる。
したがって宮中における自己勢力の維持には、周到な準備と配慮が行なわれているようだ。
昭和七年三月二十七日 『 木戸日記 』 に、原田熊雄の 西園寺の言 として次のように記している。
「 老公の御考として、近衛公をなるべく早く議長とし、・・・・必要を生じたる場合には
出て組閣せしむるも可ならずやとの御話あり。
又、余を矢張り早き機会に侍従次長あたりの位置に就かしめ、
将来は側近にて働かする様になすを可とせしむとの話なりし由。
老公の御胸中を推察するに、本邦の現状は既に革命の過程に踏込みつつある様に考へ居らるるものの如く、
元老の重責を荷はれて御心労察するに余りあり 」
爾後の進展を見ると、大体その通りに配置している。
ただ革命の過程に入ったと見ながら、その対応策がなかった。
勝海舟がいなかったわけである。
・
昭和十年十二月二十一日の 『 木戸日記 』に、
「 反対陣営の内閣の手にて内大臣の更迭を行はるるは極力避けたきを以て
此際是非決行したき旨を希望す。宮内大臣も大体同感なりき 」とある。
そして二十六日牧野の代りに斎藤実が内大臣となり、運命の日を迎えることになる。
・
二 ・二六事件直後の四月十日の 『 木戸日記 』 は次のように記している。
「 左の如き家族制度改革の骨子を示し高橋敏雄爵位課長に其研究を求む。
華族制度改革要旨
適度に新陳代謝を行ひ華族の数をある程度に調整すると共に、清新の気を加ふること
一、永代世襲の制を廃す
一、左の代数を経たる後は平民に復す
公爵九代 侯爵八代 伯爵七代 子爵六代 男爵五代
一、特殊の家柄に就ては勅旨を以て代数の延長 又は永続を認むること 」
さらに六月二十五日の日記には、
「 高橋課長に家族制度改革の別案として、
一、既得権には変更を与へず
二、今後の華族を男爵三代 子爵四代 伯爵五代 侯爵六代 公爵七代とする案を研究以来 」
としている。
今からみれば馬鹿げた考えだが、木戸ですらこの程度である。
当時の生活環境のためといえばそれまでだが、革新の困難さをよくあらわしている。
・
戦前世界一といわれた皇室財産。その収支は明らかにされていない。
天皇家や皇族の家系的支出、災害等の救恤金、学習院や帝室博物館の経営等は知られているが、
いわゆる機密費、特定の人に対する給付が行なわれたようだ。
大臣経験者などに 「 前官礼遇 」 という待遇が与えられた。
これは在官当時の俸給相当額を、退職後も皇室財産から与えたことである。
戦後、『 華族 』 という本の中で木戸は、「 明治天皇は、大変公卿というものに御関心が深く、
これを守り立てて、・・・・堂上華族のための資金をおつくりになって、
・・・中略・・・
僕が宗秩寮総裁をしていた昭和八年ごろから十年ごろ、公爵で年間六千円の配分があった。
六千円というと当時の大臣の俸給。爵位によって金額がちがっているのです。
それくらいの配分ができる程資金が貯っていた 」と 述べている。
また後継内閣をつくるため、重臣を集める考えの案の時、重臣--前総理大臣で、
「 はじめは前総理大臣では多過ぎるから、総理大臣の前官礼遇を受けたものということで考えた。
おかしなことに、海軍出身者はみな前官礼遇をもっているのに陸軍出身はいない。
カーキ色をツンボ桟敷なおいて内閣をつくったら、これは大さわぎになる。
仕方なく前総理ということになった 」と 金沢誠氏らに答えている。
・・・挿入・・・
天皇財産の国家下附
天皇は自ら範を示して皇室所有の土地山林株券等を国家に下附す。
皇室費を年約三千万円とし、国庫より支出せしむ。
但し、時勢の必要に応じ議会の協賛を経て増額すめことを得。
註。
現時の皇室財産は徳川氏の其れを継承せることに始まりて、
天皇の原義に照すも斯かる中性的財政をとるは矛盾なり。
国民の天皇は其の経済亦悉く国家の負担たるは自明の理也。
・・・リンク→日本改造法案大綱 (5) 巻一 国民の天皇 ・・・
天皇家の財政が明らかになれば、昭和史も、否、明治以降敗戦に至る歴史も一段と明らかになると思う。
政治的の機密費として相当なものが流れていて、宮廷グループは、権力---奥ノ院の---と共に、
物質的なものに左右していたと想像される。
彼らの掌中に軍部も政党も財界も、極端にいえば踊らされていたのではないか。
・
『 華族 』 という本の中で木戸は、大正十一年十一月十一日に始めたので十一会といった会名の説明をして、
会員は近衛、原田、阿部長景、外務政務次官浅田信恒、逓信省の局長広幡、
有馬頼寧、貴族院の副議長佐々木行忠など十二、三名で、
はじめは主として華族出身で役人になった連中の集りで終戦まで続いたと、いっている。
この十一会の連中--もちろん、こればかりではないが-- の情報、話し合いの結果が西園寺を動かし、
首相を決定し、側近の重臣、枢密院の議長副議長を決定したと見て大過ないであろう。
そう考えると、敗戦までは、表面はともかく、実際は宮廷政治---貴族政治ではなかったか。
しかりすると 「 一君万民 」 の標語の意味する万民平等への志向は、彼らにとっては好ましくなかった。
守りを固めたのは当然である。
北、西田に親しい磯部は、このような貴族の動きは摑んでいたと思われる。
「 陛下、日本は天皇の独裁国ではあってはなりません。 重臣元老貴族の独裁国であるも断じて許しません。
明治以後の日本は、天皇を政治的中心とした一君万民との一体的立憲国であります。
もっとワカリ易く申上げると、天皇を政治的中心とする近代的民主国であります 」と言い切っている。
・
敗戦によって家族廃止。
貴族院も当然なくなり、皇室財産も、その主要な御料林等も国有に帰した。
農地解放等も行われた。
これらの多くは、磯部が信奉する 「 日本改造法案大綱 」 の中にあるもので磯部の実行したく思った事だ。
これらの改革は戦争による数百万流血の上に行われたものであり、決して無血革命ではない。
問題は、今の日本人はこれ程の血を流さねば、改革が行われない国であり人であるのかということだ。
江藤淳著 『 もう一つの戦後史 』 の農地改革の成功の項に興味ある記事がある。
戦前の農林官僚の中に、地主的土地所有の矛盾を痛感し、なんとかしなければ 「 農民がかわいそうだ 」
と 考えた多くのすぐれた官僚かいた。
中心人物は大正九年当時の農政課長の石黒忠篤である。
現実に農地制度の病根にメスを入れるような立法措置が行なわれるのは、
日華事変が勃発し、統制経済を強化する戦時立法が行なわれるようになってからだ。
昭和十三年の内調整法、次いで小作料統制令等、戦局の激化と共に進んで昭和二十年六月、
戦時緊急措置法が成立すると、この緊急立法を利用して、一挙に小作料の金納化を中心とする制度改革を、
農林省は行わんとした。
石黒農林大臣はさすがにこれにはおどろいて、「 もう少し慎重にやり給え 」 と指示して
勅令案から小作料金納化の規定を落とし、
「 国内戦場化に伴う食糧対策 」 に切り替えさせたという。
このように戦前からの準備が積み重なって戦後の農地改革は成功したということだ。
右の記事で、戦時になって初めて病根にメスを入れたことと、
小作料金納化は最後まで踏み切れなかったことは考えさせられることだ。
・
宮廷派は秩父宮を如何に見ていただろう。
秩父宮は歩三で安藤が士官候補生時代からの関係で、
安藤に対する信頼が深く、刑死する時安藤は、天皇陛下万歳に続いて秩父宮万歳を唱えている。
「 まあ 自分なんかがいなくなってから後のことだろうけれど、
木戸や近衛 ( 時の首相 ) にも注意しておいてもらいたいが、よほど皇室のことは大事である。
まさか、陛下の御兄弟にかれこれということはあるまいけれど、
しかし 取巻の如何によっては、日本の歴史にときどき繰返されるように、
弟が兄を殺して帝位につくというような場面が相当に数多く見えている。
かくの如き不吉なことは無論ないと思うけれども、また、今の秩父宮とか高松宮とかいう方々に、
かれこれいうことはないけれども、或は皇族の中に変な者に担がれて、
何をしでかすか判らないような分子が出てくる情勢にも、
平素から相当に注意して見ていてもらわないと、事すこぶる重大だから、
皇室のために、また 日本のために、この点くれぐれも考えておいてもらわなければならん 」
・・・『 西園寺公と政局 』
昭和七年六月二十一日の 『 木戸日記 』 によると
「 六月二一日宮内大臣官邸にて夕食、近衛公、原田男
秩父宮の最近の時局に対する御考が稍々もすれば軍国的になれる点等につき意見を交換す 」
秩父宮はスポーツを御愛好になり、庶民的で、妃殿下も今までの例を破って皇族や公卿ではなく
会津の松平家より来られ、皇太后陛下は秩父宮を大変可愛がられたといわれる。
「それから、これは他のことだけれど、皇太后様を非常に偉い方のように思って、あんまり信じ過ぎて・・・・というか、賢い方と思い過ぎておるというか、
賢い方だろうが、とにかくやはり婦人のことであるから、
よほどその点は考えて接しないと、陛下との間で或は憂慮するようなことが起こりはせんか。
自分は心配している 」 ・・・『 西園寺公と政局 』
宮内省に永らく務めた小川晴信の口述手記 「 三代宮廷秘録 」 ・・・「 文藝春秋 」 昭和二十五年十一月号
によると、
西園寺公望の子 八郎は、ある時、天皇陛下のゴルフのお相手をしていたが、
休憩の時、八郎はねころんで、頬杖ついて陛下と話をしていた。
陛下はゴルフ棒をもって立ってお話しをしていらっしゃる。
そこへ秩父宮がお見えになって、「 西園寺 」 と、大声で呼ばれ、
「 いかに御運動中とはいえ、陛下の御前ではないか、貴様の無作法は何事か 」と、お叱りになった。
西園寺は平気な顔で立ち上がったが、恐縮の態には見えなかった。と。
側近の、天皇観の一端が判る。
・
昭和八年四月十日の発令で西園寺八郎は職を去る。
ただしこの事のためか否かは不明だが 『 木戸日記 』 で見ると事件の性質を官紀問題としている。
西園寺八郎の進退問題は大分前から近衛、甘露寺らと相談し、三月十五日、湯浅宮内大臣と一時間半に亙って相談。
西園寺の性格から、他人を交えず大臣が本人に説示し辞任せしむること、
まず内大臣、侍従長と十分意見の交換を希望し、元老に及ぼす影響を十分考慮せられたし と木戸は言っている。
西園寺八郎は毛利家から西園寺の養嗣子になったもの。
木戸も湯浅も長州出身である。
もしも西園寺八郎の官紀問題が前記の秩父宮の叱責事件も含まれているのであるならば、
宮廷グループに与えた影響は無視できぬものがありそうだ。
二 ・二六事件における天皇の激怒の中に、
宮廷グループから、前まえから、秩父宮に関しての話が陛下にあったのではないか。
佐々木二郎 著 一革新将校の半生と磯部浅一
宮廷グループの動き から

昭和七年一月八日、櫻田門事件 が起きた。
恒例の陸軍始めの観兵式を終えて、帰還の途につかれた天皇陛下一行の馬車に、
李奉昌という朝鮮人が爆弾を投げつけた事件である。
陛下は幸い御安泰であった。
犬養内閣は、陛下より「 時局重大の時故に留任せよ 」とのお言葉を賜ったという理由で留任した。
野党の民政党は
「 さきの虎ノ門事件では、 関東大震災直後の重大事局下にあつて、留任の優諚を拝したが山本内閣は総辞職した。
当時閣僚であった犬養は 『 責任は絶対だ 』 と強硬に辞職を主張した。
しかるに今回は全く同じ状況にありながら優諚に名をかりて留任するとは、 政治道徳上許し難き行為である 」
と、強く非難した。
このように内閣が留任したため、警衛責任者に対する処分も寛大で、
長警視総監が懲戒免職となった外は、いずれも減棒処分以下ですんだ。
これは虎ノ門事件と日垣してみると明瞭に軽い処分である。

この事件に際し一木 宮相が
「 陛下には お恙もあらせられず、神色自若として云々 」という「 謹話 」 を発表したことを捉え、
今泉定助 ( 皇漢学者として重きをなしていた ) は これを問題にした。
矢次一夫の 『 昭和動乱私史 』 に拠れば、「 これは表面こそ出なかったが当時の政界裏面にて大紛議を惹き起し、
前内務省社会局長官で協調会常務理事だった吉田茂 ( 戦後首相となった吉田茂とは別人 ) が調停に動き、
遂に翌八年一月、一木宮相が辞任するまでに騒ぎを発展させた。
今泉が問題にしたのは、不祥事件とのみ見るのは間違いで、
神国日本として、これは八百万の神々の意志と見るべしというのである。
しかるに宮相は『 お恙もあらせられなかったこと 』のみが、
あたかも『 神の意志 』であるかのように喜んでいるのは 神国日本の本質を解せざるもの。
さらに『 神色自若云々 』というにいたっては、言語道断、
歴代の天皇は、民にして一人着ざるものあり、食せざる者あれば、『 これ皆朕の責任 』と仰せられている。
しかるに着ないとか、喰わぬどころの問題ではなく、国民の一人から ( 朝鮮人でも当時は国民 ) 爆弾を投げつけられたのに、
『 神色自若 』 というのでは、もはや 天皇というべき存在ではない。
これは 『 化物 』 か 『 馬鹿者 』 と申すべきであると、いうのだ。
仄聞そくぶんしたところによると、一木は、さすがにこの一語には憤激したということで、
化物とは、陛下に無礼であろう、と一喝したそうだ。
そして陛下に責任をとれ、ということかと鋭く訊したところ、
今泉は、もちろん、と答え、
但し、陛下が責任を負われるのは、国民に対してではなく、歴代皇祖皇宗の神霊に対して負われねばならぬ。
神皇連綿として三千年、しかるに図らずも朕の代にいたり、前古未曾有の不祥事を見る。
朕まことに不徳の極まるところ、とし伊勢大神宮をはじめ、歴朝の神前に身を投げうち、泣いて万謝せらるべく、
そして日本に皇室のあらん限り、再び不祥事を起こさないために、神前に固く誓願せらるることこそ当然、
と切言したのである。
そして仲介者の吉田に、ことは国体の本義にかかわる大問題ですぞ、この本義を守り、貫く為には生命をかけています。
貴下の得意とする労働争議の調停のようなつもりで、動き回られるのは困る、
といったそうだから、当時としては、相当な人物である 」と。
今泉の側近一木宮相に呈した苦言は、次のように要約できると思う。
即ち、
天皇は国民全員の生活に関し無限の責任を歴代の神霊に負うている。
この根本義から輔佐する人々の言動は発せねばならぬ。
この義を守るためには、私としては生命をかけている、と。
・・・挿入・・・
天皇陛下
何と云ふ御失政でありますか、
何と云ふザマです、
皇祖皇宗に御あゆまりなされませ
・・・磯部浅一 『 獄中日記 』
この事件の責任者に対する懲戒に関し、内大臣秘書官長の木戸は、一月十三日の日記に次のように記している。
「 内大臣より今回の不祥事件に責任の地位にありしものの懲戒に関し、
其処分決定前に何等かの方法にて陛下より御優諚を賜りては如何との議あり。
・・・中略・・・
苟も行政組織上之等の事件を判定する夫々の機関の存する以上、
其の決定を左右するが如き御言葉等のあるは面白からずと思考す。
行政官として懲戒委員会に附議さるべき事態を惹起したる以上、其の判定を待つの外方法なきは当然なねべし。
彼の幸徳事件の際の如きも、其の大赦は裁判の判決後に於て初めて行はれたものなり、
決して事前に陛下の御動きのあるは不可なりと述べ置きたり 」
この木戸の見解は至当である。
幸徳事件の大赦とは、幸徳秋水以下二十四名が死刑の判決を受けたが、
明治天皇の特赦により、十二名が無期徒刑に減刑されたことである。
わが身に危害を加えんとした国民の罪すら、わが身の責として祖宗の神霊に拝謝する態度
---普通の人間に出来ぬこと---は、国民の無限の業を自ら負われることである。
このことは必然的に国民の感謝と敬仰の念を生み、その誠心まごころは天皇に集中連繋する。
ここに神が生ずるのである。
ただ普通のありきたりの人間、字が上手であったり、一つの学問に秀れたりしておるということは、
天皇の本質ではない。
それだけならば他に秀れた人物はいくらでもいる。
千年余に亘る長い伝統のうちに つちかわれたるものはそんなものではない。
一億の民のまごころの集まる身、世襲の皇位でなければならぬ。
そこには対立抗争を超越し、至公至平、寛恕かんじょにして綜合統一に向わしむるものがある。
今泉はこの義を守るためには生命をかけているという。
天皇側近にありて輔佐する人々、当然この義を守るために生命をかけるべきである。
・
天皇の機能は何か、私は次のように考えていた。
第一は、綜合統一の機能である。
分裂せるもの、対立抗争するものを克服して統一に向わしめる機能である。
明治維新の混乱動揺を、最も損害少なく短期間に収拾し得たのは、天皇のもつこの社会的機能のおかげである。
第二は、権力者がともすればおちいりやすい権力行使の行き過ぎを、調節抑止する機能である。
幸徳事件における明治天皇による大赦がその一例である。
第三は、日本民族が長い年月をかけて体系化されるうちに、血の通った同胞感が生れ育つ。
一君万民の平等感を内心に味わうからである。
この平等感は前二項の基底に流れているが、変革期になると変革論の拠りどころにもなる。
・
昭和七年夏、磯部は主計転科のため上京、桜田門事件の動揺未だ収まらざる時である。
北、西田との接触が始まる。
政界裏面の事情に通ずる北は、また矢次一夫とは熟知の間柄である。
当然前記の今泉の話は北、西田より聞いたであろう。
佐々木二郎 著 一革新将校の半生と磯部浅一
桜田門事件 から
大正十二年十二月二十七日、
摂政宮 ( 昭和天皇 ) 殿下が議会開院式ヘ行啓のため、虎ノ門外御通過中を、
難波大輔が仕込杖銃をもって襲った事件である。
宮内省は、兇変と殿下の安泰を発表したが、犯人の名前を発表せず、新聞も事件の概要を伝えたのみで、
一切の記事は翌年の九月まで差し止めとなった。
難波大助は山口県選出の代議士難波作之進の四男である。
明示の末年に幸徳秋水事件があり、今、また生命をかけて皇室を狙う日本人がある。
しかも左派の波高き折柄である。 このショックは大きかった。
ことに同じ山口県出身の磯部、山田は深刻であったと思う。
・・・中略・・・
事件の事後処理を、池田進、本山幸彦編の 『 大正の教育 』 に拠れば概要次の通りである。
(1) 逮捕された大助は、同日午後十一時、大審院予審に付される。
(2) 同日午後五時、山本内閣総辞職を表明。
(3) 十二月二十八日、大助の父 難波作之進、衆議院議員を辞職、自宅に蟄居。
(4) 大正十三年一月六日より五日間、大助の出生地山口県周防村は全村謹慎。
(5) 一月七日、清浦内閣成立。
警視総監湯浅倉平、刑務部長正力松太郎、愛宕警察署長弘田久寿治の三名 懲戒免官。
内務省警保局長ほか警視庁幹部四名が罰俸、内務次官が譴責の処分 ( 文官高等懲戒委員会の発表 )
警備直接担当者の処分は、警視庁懲戒委員会によって一月八日発表、
愛宕署の巡査部長、巡査ら四名が懲戒免職、署幹部三名が罰俸に処せられた。
(6) 二月一九日、大助予審終結、起訴。
(7) 二月二十~二十一日、清浦内閣、思想善導のため各宗教、教化団体代表を招集。
(8) 四月四日、文部省、国民精神作興に関する諮問機関設立を発表、五月七日、文政審議会官制公布。
(9) 十月一日、大助の公判開始、十一月十三日、死刑判決、十五日死刑執行。
(10) 大正十五年六月四日、大森山口県知事と謹慎中の難波家当主正太郎と会見 (神本熊毛郡長同行 )
爾後 大森知事の主導の形で、難波家の謹慎、村八分の解除の方向に動き、
さらに難波家の廃家にまで進展する。
大森知事の談話によれば、難波家絶家のことは、六月四日の会見の際、難波正太郎が申し出たという。
・
(5) の処分発表三週間後の一月二十六日には、
皇太子の結婚を機として、「 懲戒懲罰免除勅令 」 が公布され、
湯浅、正力らに対する処分は取り消されている。
さらに湯浅は六月十一日 加藤高明内閣の内務大臣次官に就任する。
大助の出生地の周防村では、村長および小学校長が引責辞職している。
校長は大助の小学校時代の担任であり、かつて難波家に寄寓して大助を訓陶監督 していただけに
非常に責任を感じたといわれている。
また 九月二十八日、同村では村寄合を開いて
「 今度の事件に対する態度その他を決定 」 判決時の十一月十三日を 「 反省日 」 とし、
周防村を含む熊毛郡全町村において 「 詔書奉読式 」 を挙行するなど、
厳しい責任追及が何ら関係なき人々にまで及んでいる。
この跳ね返りが難波一家に及んだことは想像に難くない。
右の如き事件処理を見ると、国民全部に責任を負わしめ、支配層の人々には軽くという風に思われる。
大助の弁護人 今村力三郎 ( 幸徳秋水事件の弁護も担当 ) は、湯浅の内務次官就任を
「 恩命に籍口して自家を回護するが如きは、初より自責の念なきものなり 」と 批判している。
湯浅はニ ・ニ六事件直後に、内大臣に就任する。
小島襄著 『 天皇 』
第一巻に拠ると、
親王 ( 昭和天皇 ) は 忠良なる臣民の中に皇室打倒の思想をもっている者がいたことには強いショックをうけたとみえ、
珍田東宮大夫、入江侍従長の二人に、
「 自分は日本においては、陛下と臣下との関係は、
義においては君臣であるけれども、 情においては親子であると考えている。
しかるに今日の出来事をみ、遺憾にたえない。
自分のこの考えは、何卒徹底するようにしてもらいたい 」と 述べている。

そして珍田大夫からこの報告を耳にした奈良武官長は、
「 少なくともここしばらくはなりませぬ 」と 即座に、親王のお言葉発表に異議を申したてた。
「 奈良武官長は、 親王のお言葉は、きわめて遺憾の意を表明されている以上、
少なくとも国民の社会主義者、共産主義者に対する怒りを激化させる可能性がある、 と判断した。
・・・中略・・・
おそらく内閣の瓦解はさけられないであろうし、さらに国内の興奮と動揺もつづくであろう。
そのさいに、もし裕仁親王のお言葉が、主義者対策 にたいする 公許 とみなされ、
はねあがり政策がとられるとするならば、 政情と世情の不安をさらにかきたてることにもなりかねない 」
この奈良武官長の判断と輔佐の仕方はなかなか立派なものである。
・
この事件の反響や対処の仕方 特に同じ山口県出身の磯部、山田は、郷里における反応はよく知っていた。
また、公表されなかったが、大助は最後まで自己の行動の正しきを主張して志を変えなかったことを、
うすうす洩れ聞いてわれわれは知っていた。
事件発生の原因は何か、共産党は皇室打倒を目指しているのではないか、
貧窮に苦しむ国民が増える現状では、左翼は増加する一方ではないか、われわれはこれに如何に対処すべきか、
外国の指導する勢力によらず、国を愛する日本人自身の手にて改革すべきではないか、等々が三人の議論の種であった。
・
大助に対する死刑は已むを得ぬことで、また ある程度の父親の謹慎も判るが、
家族に対する村八分や、村長、小学校の先生までの追及は酷に失するのではないかなどの話が出た。
今村弁護人によれば、幸徳事件の折は、村八分はなかったという。
私が男の仕事として 「 戦争か革命か 」 と言ったのに対し
「 俺は革命にゆく 」 と、磯部が叫んだのはこのような状況下である。
佐々木二郎 著 一革新将校の半生と磯部浅一
虎ノ門事件 から
八月十二日、相沢中佐の永田軍務局長斬殺事件が突発した。
○○中佐と名前が紙上で伏せてあるので、私のように深い関係のない者は誰がやったのかわからなかった。
今その人を思い出せぬが佐官の人が 「 相沢中佐 」 だというのを聞いた。
数日後、将校集会所の黒板に斬殺現場の図面入りのものを張り付けた者がいた。
若い者は 「 やるなー 」 といったような口吻を洩らし、
左官級は ちょっと とまどった表情でこれを眺めていた。
リンク
・ 永田伏誅ノ眞相
いろいろの文章が流れて来た。
永田が切られて隣室へ逃げようと把手をとるとき、向う側で把手を握っていた者がいたとか、
同室の憲兵大佐が一振りに振り飛ばされて気絶したとか、
事が終わって相沢中佐が階段を下りかかると、根本中佐が飛んで来たとか、
胸のすくような相沢中佐の斬撃振りと、周章狼狽の幕僚の行動を冷笑したものである。
この事件は、今まで権力の座にふんぞり返っていた幕僚に対する、
見方の眼の色を変えたようであった。
暗殺! 単身 白昼堂々と陸軍省の軍務局長室で局長を斬る、
ちょっと類のない珍しい暗殺だ。
用心とか、緻密な計算とか、およそ そんなもののない やり方、
しかも それで人心の虚をついている。
この人は 何かを掴んでいる信念の人だなと思った。
と ともに 軍の危機を感じた。
・
この事件と磯部はいかなる関連にあるのだろうか?
たぶん知らぬだろう。
知っておれば磯部自身がやるだろう。
この後、磯部はかき立てられる思いをするだろうが、
西田、大蔵、村中、安藤もおるから軽挙はないと判断した。
ただ、この事件を機に、その原因を徹底的に究明して、これを最後の直接行動にすべきだと思った。
「 相澤中佐の片影 」 が 送られて来た。
リンク
・ 行動記 ・ 第一 「 ヨオシ俺が軍閥を倒してやる 」
・ 相澤中佐片影
興味を覚えた人物であったから、私と池田中尉とでガリ版で刷って配布した。
これが初めての行動である。
私は元来陸軍部内の派閥というものには関心はなかった。
荒木、柳川、小畑とか、宇垣、南、小磯、永田とか、
このような上層部の人々には一面識もなければ、彼らが何を考え何をなそうとしているのか知る由もない。
田舎の隊附将校とは およそ そんなものである。
ただ、怪文書 ( 双方から来る ) によるものや、上京した折の大蔵、村中たちの話で、
幕僚の権力欲、出世欲には嫌悪の念を抱き、
磯部ら ( 士官学校事件 ) に対する不公平の弾圧には憤慨していた。
この根底には隊附十年間の幕僚に対する認識が根を下ろしていたことは事実である。
秋、間島地方で大尉以上の現地戦術が行われた。
統裁官は連隊長である。
出発の朝、羅南駅にて乗車すると、ホームに柳下参謀長が来て、頭に包帯した連隊長と何か話していた。
昨夜、赤穂家での宴会で連隊長が転んで頭にちょっと怪我をした。
それを参謀長が突き倒したと思ったらしく、帰途合同面に立ち寄り チョンガー連中に、
将校団長が怪我させられたのに黙っておるかと、酔った勢いでいったらしく、
池田、鳥巣憲俊中尉らの血の気の多いのがさっそく立ち上がった。
参謀長を促えて連隊長官舎に行き謝らせた、という一幕があったので、
参謀長がわざわざ駅まで来て、おれは一切君に手を触れてないよと、酔いが醒めた早い時期に釈明して、
しこりを残さないようにしたのだったと車中で聞いた。
・ 佐々木二郎
佐々木二郎
佐々木二郎 著
一革新将校の半生と磯部浅一 から
昭和八年五月、
野戦瓦斯隊要員として科学研究所と歩兵学校に派遣された。
その出発前、四月の異動で中野直三大佐が聯隊長として着任した。
戸山学校の大蔵中尉から
「 今度行く中野大佐は士官候補生を弾圧した男だ 」
と いってきた。
五 ・一五事件のときの士官学校の生徒隊長をしていたからであろう。
私は士官候補生のたちばで実際運動に加わるのは早いと思っていたので、
中野大佐がどのような弾圧を加えたかは知らぬが、原則としては当然と思っていた。
中野大佐が着任し その招宴のあった翌日、羅南を出発、上京した。
牛込の砲工学校の近くで、磯部浅一と同じ下宿で二週間科学研究所に通った。
磯部は主計転科のため、経理学校に通っていた。
「 おれは革命を一生の仕事にする。そのためには東京にでなければならぬ。主計転科は東京に出るための手段だよ 」
磯部と主計、これほど不似合いのものはない。
磯部の転科の理由をきいてはじめてわかった。
夜は二人で新宿に出て 「 タイガー 」 で よく飲んだ。
ある日、例のごとく 「 タイガー 」 で 飲んでいると、西田税の話が出た。
磯部は 「 立派な男だ、ぜひ会え 」 という。
陸士時代、赤枝らが西田を訪ねようといったときに反対した磯部が、今はだいぶ深くなっているなと思った。
千駄ヶ谷の西田宅を二人で訪ね、はじめて西田に会った。
同じ広島幼年学校出身で私より四期先輩である。
第一印象は、鋭い感覚の持ち主だな、ということであった。
その後大蔵と北一輝宅を訪問した。
例の風貌で支那服を着、ドスの利いた声、なかなか魅力のある人物であった。
あるとき、北のところで偶然相澤中佐と同席した。
異相の偉丈夫で信念の人と思われた。
私は改造法案で、私有財産百万円を限度とするのはなにを根拠としてですかときいた。
同席していた二、三の人は、「 腰だめだよ 」 「 直観だよ 」 といったが、
北御本人はニコニコと私を見つめただけで返答しない。
「 『 然り 然り、否ナ 否ナ 』 似て足りる 」 の 文句どおりの態度である。・・・リンク → 日本改造法案大綱 (1) 凡例
ビールが出た。
相澤中佐----この人は冬服を着ていて、東京は暑いですねといって上半身裸体となっていた
----が、スットントン節を歌い出した。
調子外れの大声で一座を圧倒するばかりであった。
・
科研の二週間が終り 千葉の歩兵学校に移ることになった。
科研では学問研究で、歩兵学校では実施での用法の教育である。
いよいよ千葉に移る前の夜、磯部が
「 今まで毎晩貴様にお世話になった。今日はおれが送別会をやる 」
というので一緒に下宿を出た。
見ると彼は正装を入れた鞄を提げている。
近くの質屋で正装を質入れした。
磯部は経理学校在学中、昼飯抜きであった。
彼に幼年学校時代の学費を出してくれた恩人の家が没落し、その子息が商船学校?在学中である。
その学費の一助にと昼食抜きにして援助していたのだ。
「 佐々木、経理学校はその点よいぞ、料理の実習があるのでそいつを食うのだ。ハハハ。
天道人を殺さず、よくできているよ。
しかし実習のないときは腹がへるなー ハハハ 」
事情を知っているだけに彼の友情が嬉しく、この夜はスッカリ酔った。
・
戸山学校に来ている大蔵中尉とはよく会い、彼の家での会合にも一、二度出席し、
そこで香田清貞、村中孝次中尉らを知り、同期の安藤輝三とは陸士卒業以来はじめて会った。
鋭敏な村中の頭脳と温厚誠実な安藤の成長ぶりが印象に残った。
ある日、村中など二、三人と石原莞爾大佐を訪ねた。
兵器本廠附きで、ジュネーブの会議から帰ったところで欧州の事情を話してくれた。
「 近頃 若い者がだいぶ動いているようだが、ドイツやイタリアでは とって代わる勢力ができていたのだ 」
これはもっともな言である。
しかし私は満州事変の立役者石原参謀の言として、それきりの話では少し納得できなかった。
そのあとに続く大佐の言葉がないので、
「 大佐殿は満州事変という糞をたれた。尻は自分で拭かずに人に拭かすのですか 」
「 なにーー 」
小僧奴がと 私を睨みつけた。
佐々木二郎 著
一革新将校の半生と磯部浅一
から