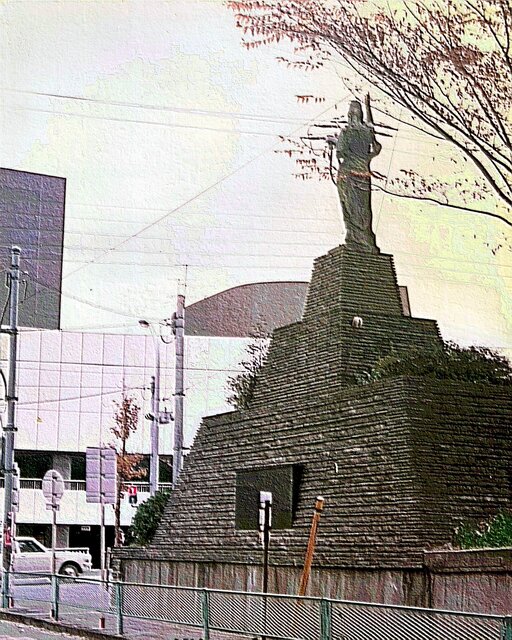たまたま web上でみつけたもの、
此も亦 出逢いかしら・・と、私流に吟讀し、
茲に、私流に 『 書写 』 するものである

海軍側法廷 陸軍側法廷
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旧陸海軍軍法会議の意義と司法権の独立
五・一五及びニ・二六事件裁判に見る同法の本質に関する一考察
山本政雄
要約
大正デモクラシー下の、1921( 大正10 ) 年に制定された陸軍軍法会議法及び海軍軍法会議法によって、
軍法会議にも人権擁護の遵守と司法権の独立が宣明されていた。
しかし、昭和期の五・一五及びニ・二六の両事件を審理した軍法会議の実態は、
同法がその原理とした「 統帥権と司法権の調和 」
や、理念に掲げていた司法権の独立が、
実は有名無実なものに過ぎなかったことを示唆している。
はじめに
現代の我が国で軍法会議といえば、
戦前の帝国陸海軍における、非人道的な統治制度としてのイメージが想起されるものの、
法制面を含めた制度の実態は、ほとんど知られていないのが実情であろう。
このため、戦前の我が国にあった軍法会議制度とは、どのようなものであったのか、
これを法制史と軍政史の観点から、体系的に解明することを企図した。
その最初の研究成果の一つとして、
本制度誕生の背景や軍法会議法の制定経緯等の歴史的側面を考察した、
「 旧陸海軍軍法会議法の制定経緯 -立法過程から見た同法の本質に関する一考察 -
を『 防衛研究所紀要 』 第9巻第2号 ( 2006年12月 ) に発表した。
すなわち、我が国の軍法会議は、「 統帥権と司法権の調和 」を図ることを目的に、
軍隊内の刑事裁判制度として、フランス軍制度の模倣によって誕生した。
そして、その最初の根拠法として、陸軍治罪法が1883( 明治16 ) 年に、
またその翌年に海軍治罪法が制定されたが、これらの陸海軍治罪法が依拠したのは、
同じくフランス法を起源とする、一般法の治罪法 ( 80 ( 同10 ) 年制定による我が国初の近代的刑事訴訟法 ) であった。
然るに、これらの母法であるフランス型刑事法は、糺問主義的構造を有していたため、
明治期の刑事司法の人権擁護など、その概念すらなかったのが実態であった。
糺問主義 刑事訴訟について、裁判官と訴追者の分離がなく、裁判官が職権で手続きを開始し、被告人を取調べ、審理し、裁判する方式。
その後、1889 ( 明治22 ) 年の 大日本帝国憲法 の発布を境に、
我が国の刑事司法制度は、より国情に合致したドイツ型への傾斜を強めていき、
紆余曲折を経て、1921 ( 大正10 ) 年に陸海軍治罪法の改正法として、
陸軍軍法会議法及び海軍軍法会議法が制定された。
さらに翌22 ( 同11 ) 年には、一般法も旧刑事訴訟法に改められ
( 現行の刑事訴訟法に対する呼称であり、大正刑事訴訟法とも呼称される ) 、
ここにドイツ型に倣った戦前の我が国の刑事司法制度は完成を見た。
これら諸法の成立によって、我が国の刑事司法制度は、
少なくとも形式的には、近代的裁判制度の象徴とされる、弾劾主義に移行したのである。
弾劾主義 刑事訴訟について、裁判所以外の者の請求によって訴訟を開始するもの。
また、訴訟が裁判所、訴追者、被告人の間で進められるものをいう場合もある。
常設軍法会議 戦時・平時を問わず恒常的に設置されていた軍法会議で、陸軍には「 高等軍法会議 」や「 師団軍法会議 」があり、
海軍には、「 高等軍法会議 」や「 鎮守府軍法会議 」があった。
特設軍法会議 戦時事変等に際して必要に応じて設置され、陸軍の「 軍法会議 」や「 合囲地軍軍法会議 」等が、
また海軍には「 艦隊軍法会議 」及び 「 合囲地軍軍法会議 」等があった。
この軍法会議法が規定する、常設軍法会議における基本的訴訟手続きは、
戦地での裁判を想定した特設軍法会議における例外規定を除いて、
概ね旧刑事訴訟法の規定に整合されていた。
さらに、大正期以降の軍法会議の特徴として、
明治期の軍法会議には認めていなかった「 弁護人の関与 」、「 審判の公開 」及び「 上告 」等の各規定が新たに加えられ、
被告人の人権擁護に配慮した制度に刷新されたことが挙げられる。
上告 上級裁判所への上訴のうち、憲法違反や判例違反を理由とするもの。
これに対し、法令違反や事実誤認、量刑不当等、広い範囲の理由を認めるものを控訴という。
すなわち、
大正デモクラシーの風潮下で成立した陸海軍軍法会議法とは、
一般法の規定に整合し、被告人の人権擁護と司法権の独立を宣明した、
民主主義的な刑事裁判を規律する法律であった。
そうであるならば、
軍法会議というものに対するイメージは大幅な修正を迫られるわけであり、
同法の制定経緯を考察した前掲紀要論文では、この点についての検証の必要性を提起した。
よって本稿で、実際の裁判事例を通じて軍法会議法運用の実態を考察し、
さらなる本質解明を試みることとした。
とはいえ、軍法会議における訴訟記録の多くは、終戦時に破棄されたようであり、
特に戦地の特設軍法会議に関する記録は、ほぼ現存しない。
また、終戦時国内にあって破棄を免れたものも、戦後各地方検察庁やその他の司法官署に移管され、
所在そのものが判然としないことに加え、さらにプライバシー上の問題も相まって、簡単には閲覧できないのが現状である。
このような狀況にあって、
歴史上の大事件として記録されている1932 ( 昭和7 ) 年の五・一五事件や、
1936 ( 昭和11) 年の二・二六事件に関しては,比較的資料が豊富なこともあって、
歴史研究の分野においては極めて多数の先行研究があり、この分野ではほぼ研究され尽くしている観もある。
その一方で、刑事司法の視点に立った法学分野での専門的研究、
就中、両事件の軍法会議の法律論に特化した考察に関しては、歴史分野ほどの研究の蓄積は見られない。
然るに近年になって発見された新資料、
いわゆる「 匂坂資料 」は、これらの事件に対する法学分野での研究を大いに促した。
匂坂資料は、当時の軍と砲当局の内部資料ともいえる第一級の資料であり、
審理に当たった軍法会議の法的側面を考察する上で、極めて貴重な示唆を与えてくれる。
さらに、防衛研究所には、これらの事件裁判の判決謄本や、
その他の訴訟記録に類する、歴史的に極めて貴重な資料が現存していることも判明した。
このため、軍法会議法運用の実態を考察する事例として、
このような刑事司法の視点から先行研究が比較的少ない、当該両事件の裁判を対象とすることとした。
次頁 軍法会議 2 『 世論に迎合した 五・一五事件裁判 』 に 続く
たまたま web上でみつけたもの、
此も亦 出逢いかしら・・と、私流に吟讀し、
茲に、私流に 『 書写 』 するものである

海軍側法廷 陸軍側法廷
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旧陸海軍軍法会議の意義と司法権の独立
五・一五及びニ・二六事件裁判に見る同法の本質に関する一考察
山本政雄
前頁 軍法会議 1 『 司法権の独立は有名無実 』 の 続き
1 公判審理の実態 -五 ・一五事件事件裁判 -
( 1 ) 事件の概要
昭和初期の慢性的不況は、労働者や農民といった一般大衆の生活困窮を招き、国民の政治不信が増大していた。
陸海軍の青年将校や民間の右翼主義者らは、
これを我が政財界の腐敗に由来すると考え、急進的な国家改造運動を展開していた。
こうして勃発したのが、民間右翼井上日召率いる右翼団体 「 血盟団 」による、
1932年 ( 昭和7 ) 年2月7日の前蔵相井上準之助の暗殺と、3月5日の三井財閥の巨頭團琢磨の暗殺、
世にいう血盟団事件であり、以後のテロ事件の嚆矢となった。・・・リンク → 井上日召 ・ 五、一五事件 前後
次いで、古賀清志や三上卓良海軍中尉を中心とする、海軍青年士官が蹶起計画を策定したが、
陸軍側の大勢は時期尚早としてこれに同調せず、・・・リンク → 五・一五事件 『 西田ノ存在ハ純眞ナ陸軍靑年將校ヲ毒スル 』
結局、海軍士官6名と陸軍士官学校生徒11名 及び民間人10名 ( 元陸士生徒1名を含む ) が行動を開始した。
同年5月15日の未明、彼らは首相官邸、内大臣牧野伸顯邸、政友会本部、日本銀行及び三菱銀行を襲撃し、
ときの首相政友會総裁犬養毅と官邸警備の警察官1名を射殺した。
さらに、この日の日没には、東京電燈淀橋変電所等6カ所の変電所と警視庁も襲撃したが、
その被害は微々たるものだった。
そして、決行行動もここまでで、古賀らが企図した戒厳令の布告や、
変電所襲撃による東京市内の混乱も生起せず、一隊は自ら憲兵隊等に出頭した。
この事件の裁判は、直接行動に加わった海軍士官6名に加担者4名を加えた10名については海軍東京軍法会議、
陸軍士官学校生徒11名については陸軍第一師団軍法会議、
また民間人11名 ( 直接行動者に2名を追加する一方、1名は予審中に病死 ) は東京地方裁判所で、
それぞれ審理された。
このとき、軍人側の刑罰が最高でも禁錮15年であったのに対して、
民間側では無期懲役を含む重い刑が科せられているように、本事件裁判は、不可解な結末を迎えることとなる。
そして、五・一五事件の意義は、戦前における我が国の政党政治が終焉を迎えたこととともに、
この4年後に勃発したニ・二六事件への影響、
すなわち「 この事件がなければニ・二六事件は起き得なかった 」と考えられることにある。
( 2 ) 軍法会議の構造 - 法務官の立場 -
本事件に対する海軍側の裁判は、常設軍法会議たる海軍東京軍法会議において、
高須四郎大佐を裁判長として、1993 ( 昭和8 ) 年7月24日に公判が開始された。
同軍法会議の裁判官は、
判士4名 ( 裁判長高須大佐のほか、大和田昇少佐、藤尾勝夫大尉及び木阪義胤大尉 ) と高頼治法務官 ( 文官 ) であった。
法務官 軍法会議法で新設された制度であり、
大正10年勅令第98号陸軍法務官及び海軍法務官任用令によって、終身官高等官二等以上の勅任官又は高等官三等以下の奏任官とされた。
検察官及び予審官は法務官から任命し、また原則として5名で構成する裁判官のうち1名は法務官を充てることとされた。
陸海軍治罪法下にはなかった制度で、軍法会議の法的正当性が高まったとされる。
一方、陸軍側については、西村琢磨砲兵中佐を裁判長とする、陸軍第一師団軍法会議において、
海軍より1日遅れて、7月25日から、
さらに、民間人については、東京地方裁判所で神垣秀六を裁判長に、9月26日からそれぞれ公判が開始された。
海軍軍法会議の検察官には、
高法務官と同じく海軍省法務局所属の山本孝治法務官が任命された。
検察官 公訴権を有する行政官。裁判所では検事と呼称し、旧刑事訴訟法で大きな捜査権限が認められていたが、
現行法では司法警察職員に第一次的捜査権限を認めている点が異なる。
軍法会議長官 ドイツ軍法に由来する呼称で、陸海軍大臣や師団長、鎮守府長官あるいはその他の部隊指揮者等、
軍法会議法の規定に従い、すべての訴訟手続を主宰する者を意味する。
そもそも軍法会議検察官とは、
軍法会議長官に隷属し、捜査を為し、公訴を行う
( 海軍軍法会議法第67条。以下、海軍又は陸軍軍法会議法の条文番号のみを掲示する )
のであって、検察官は法務官中より長官が命じるのである。( 68条 )
つまり軍法会議の特色として、臨時に任命される将校裁判官意外の、裁判官としての法務官 ( 47条 ) も、
検察官としての法務官 ( 68条 ) も、さらには予審官としての法務官 ( 62条 ) も、
当該軍法会議を主催する組織の同一法務部局に所属する、いわば同僚であったということができる。
予審官 予審とは、旧刑事訴訟法で規定されていた訴訟手続きであり、被告人を後半に付するか否かを決し、
併せて公判で行い難い証拠保全、取調べを目的として行う訴訟手続きをいい、
裁判に捜査を連繋させることを目的とした、西欧大陸諸国 ( 大陸法 ) の裁判制度である。
予審判事 ( 予審官 ) は、裁判所判事と同等の権限を有する一方、強制力を持った捜査活動の権限も有しているため、
被告人の人権上の問題や、捜査手続と裁判手続の混同といった理論的な理由によって、多くの問題ある手続とされた。
このため、英米法の影響を強く受けている我が国の原稿刑事訴訟法では、本制度は廃止されている。
ここでいう軍法会議主宰組織の法務部局とは、海軍の場合は海軍省法務局や鎮守府法務部を意味し、
したがって海軍東京軍法会議の場合、軍法会議長官は海軍大臣であったから ( 10条 )、
予審官、検察官及び裁判官に任命される法務官は、いずれも海軍省法務局所属の法務官であるということになる。
また、陸軍についても同様に、
本事件を審理した陸軍第一師団軍法会議の検察官は、同師団法務部の匂坂春平法務官であり、
匂坂はこの後の陸軍省法務局員当時、二・二六事件裁判にも、検察官として関与している。
このように、司法及び捜査・検察機関の関係者が、同一組織に属していたという事実を由来として、
もともと軍法会議に於ける法務官の立場には、法的に非常に微妙な問題が潜在していたことが推察される。
このため、本事件裁判の状況を確認する前に、
このような法務官の性格を通して、軍法会議の構造について考察しておきたい。
通常、彼ら法務官は法務局又は法務部に所属し、
陸海軍大臣や、陸軍であれば師団長等及び海軍であれば鎮守府司令長官等の部下として、
固有の司法行政を行っている。
軍法会議を開催するに際して、軍法会議長官は、裁判官たる判士を部下の将校から選出する一方、
裁判官としての法務官に加え、検察官及び予審官としての法務官を、例か所属の法務官から指定した。
軍法会議とは、刑事裁判に関する特別裁判所であって、そこでは通常裁判所と同様に、
審判機関に属する裁判官及び予審機関に属する予審官は、他の干渉を受けないこととされていた。
( 46、176、218、228、265、279、287 条 )
したがって、公訴提起後の裁判官はもとより、
検察官からの予審請求を受けて ( 313条 ) 予審の処分に入った予審官には、
長官といえども これらの訴訟上の行為には干渉することはできなかった。
しかしながら、予審官に相当する通常裁判所の予審判事には、
裁判終結の権限が付与されていた ( 旧刑事訴訟法第309~315条 ) のに対して、
軍法会議予審官は、あくまでも予審結果の検察官への送付義務があるのみであった。( 330条 )
そして、予審官の報告に検察官は意見を添えて長官に報告することとなっていたので ( 331条 )、
この各段階で、予審官の行為に検察官の意向が大きく反映される余地があった。
このように、軍法会議では裁判官に比べて予審官の独立性は低かったが、
もともと裁判官も予審官も、ともに組織固有の指揮監督権に服する法務官であり、
これらの法的独立性がどこまで担保されていたのか、大いに疑問が残る。
これら裁判官や予審官とは別に、訴追者たる検察官についても、
法務官としての視座から、その位置付けについて見てみたい。
軍法会議においては、検察官に犯罪捜査や予審結果の長官への報告を義務づける一方、
長官に起訴又は不起訴の最終判断の権限を集中して ( 308、332条 ) 、
長官への隷属性を明確にしているように、
独自の判断で検察権を行使する、通常裁判における検事とは、大いにその性格が異なる。
そもそも軍法会議の理念として、統帥権と司法権は明確にそれぞれが独立し、
そのうえで軍検察権は、これらとは別の軍政に含まれるものとされていた。
陸軍軍法会議法案と海軍軍法会議法案の審議記録 『 陸軍治罪法海軍治罪法改正案共同調査委員會議事録 』によれば、
陸軍省法務局長志水小一郎の
「 檢察權ハ軍政ノ範囲ニ屬ス・・・固ヨリ長官隊長ハ統帥權ノ側ヨリシテ
形式ニ於テ檢察權ト類似シタル權ヲ有スレトモ這ハ檢察權ト稱スヘキモノニ非ス 」との見解で合意された。
その一方で、海軍省法務局長内田重成は 「 固ヨリ統帥權ノ側ニ附テ規定スルコト必スシモ絶對不可能ニ非ス 」との補足意見を述べており、
軍検察権の本質が、如何に難解な性格のものであったかを象徴している。
こうした理論構成によって、軍検察及び統帥並びに司法の各権の独立、
つまりは軍法会議の司法官署としての法的正当性が宣明されていた。
しかしながら、軍事裁判の場においては、軍政と統帥権の境界が曖昧であり、
軍検察権が統帥権の立場から発動される素地が十分にあったといえる。
このことは、軍法会議という裁判が、実は統帥権と司法権の相克の場であることが予想されていたのであり、
まさにそのために「 統帥権と司法権の調和 」を目的とした軍法会議法が、立法化されていたとの背景がある。
以上のような、法務官の性格を通じて確認した、軍法会議の基本的構造を踏まえ、
次にその裁判の実態を考察していく。
( 3 ) 論告求刑とその背景
五・一五事件裁判の特徴として、
同一事件につき陸軍軍法会議、海軍軍法会議及び通常裁判所の3カ所で審理されたという事実を挙げられる。
そして本事件裁判は、後年多くの批判を受けることとなるのであるが、
その理由は、各裁判所の量刑に著しい不均衡があったからであり、ここでこの点について詳しく見てみたい。
検察官による論告求刑は、陸軍側が最も早く、1933 ( 昭和8) 年8月26日に行われた。
匂坂陸軍検察官は、陸軍士官学校生徒は海軍士官に従属して事件に関与したものとして、
陸軍刑法第25条第2号後段 ( 以下の下線部 ) を適用して、禁錮8年を求刑した。
なお軍刑法では罪名を「 叛乱 」としながらも、条文中では「 反乱 」と表記しており、
以下、罪名を指す場合は「 叛乱 」 と記述する。
叛亂ノ罪
第二十五條 黨ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反亂を爲シタル者ハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一 首魁ハ死刑ニ處ス
ニ 謀議ニ參輿シ又ハ群衆ノ指揮ヲ爲シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ處シ
其ノ他諸般ノ職務ニ從事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
三 附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス ( 下線部は引用者 )
一方、海軍側の論告求刑は、
同年9月11日に山本海軍検察官から申し渡された。
陸軍刑法第25条と同一内容の海軍刑法第20条を適用したが、
山本はその第1号及び第2号前段を適用して、3名に死刑、
その他の者には同条及び第27条叛乱予備等を適用し、無期懲役から禁錮3年を求刑した。
これに対し、同年11月30日の民間側の求刑は、殺人、殺人未遂及び爆発物取締罰則違反等によって、
無期懲役から懲役7年であった。
まず、この段階におけるそれぞれの求刑で気付くのは、
軍法会議では軍刑法の叛乱罪を適用しているのに対し、
通常裁判所は叛乱罪に相当する刑法の内乱罪を適用せず、殺人等の罪によって求刑している。
この罪状の相違が、結果的には民間側の重い科刑に繋がるのであるが、
これについて
「 東京地方裁判所と東京控訴院は、
民間側被告人に対し陸 ( 海 ) 軍刑法の叛乱罪を適用せず、殺人幇助、騒櫌罪などを適用したのだが、
大審院はこれを覆し民間人にも叛乱罪を適用すべきであると判決した」
とする記述が見られる。・・・原・澤地・匂坂 『 検察秘録五・一五事件 Ⅰ』60頁等
しかしこれには疑問があり、
殺人よりも罪が軽減される可能性のある内乱罪の適用を訴えた3名の被告人に対し、
大審院は当時の刑法第77条第1項
「 政府ヲ顚覆シ又ハ邦土ヲ僣窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシテ暴動ヲ爲シタル者 」
とする内乱罪の適用を否定とーした。
すなわち、
「 本條ニ云フ朝憲ノ紊乱トハ、國家ノ政治的基本組織ヲ不法ニ破壊スルコトヲ云ヒ、
從テ、其ノ例示テアル政府ノ顚覆トハ、内閣制度ヲ不法ニ破壊スルヤウナコトヲ意味シ、
單ニ内閣ヲ更迭スル目的テ首相ヲ殺害スルコトハ之ニ當ラナイ 」と判示し、・・・大判昭10・10・24 刑集14・1267
一心及び二審判決を支持しているから、指摘のような判決変更の事実はなく、裁判所の判断は一貫している。
ともに叛乱罪を適用しながら、首魁に対して死刑を求刑した海軍側の求刑に比べて、
陸軍側の求刑は、著しく軽いものだった。
陸軍検察官がこのような求刑を行った背景には、軍上層部の強い意向があったといわれているが、
それには、政党政治の腐敗に対する国民の不満と不可分の、軍部に対する支持も大きく影響していた。
このため、世論は概して被告人たちに同情的であり、
本事件裁判を穏便に処理しようとする軍上層部の意向も相まって、その軍法会議は異様な光景に包まれていた。
特に
「 陸軍側の減刑嘆願書は三十五万通に達し、
・・・西村裁判長はこの減刑嘆願書を法廷の裁判官の前の机に積んで審理を行った。
この減刑嘆願書は陸軍省新聞班が
新聞を煽り在郷軍人会を動員して陸軍大臣のもとに集めたものといわれ・・・
陸軍大臣が先頭になって行う輿論捜査の昻まり 」という様相を呈した。
あたかも陸軍軍法会議判決を報じる1933 ( 昭和8 ) 年9月20日付の東京日日新聞夕刊の一面には、
裁判官席前の机に嘆願書が山のように積まれた、第1師団軍法会議公判廷の写真が掲載されている。

このような雰囲気は海軍側も同様で、
事件から1年後の1933年 ( 昭和8 ) 年5月17日に発表された海軍大臣の談話は、
被告人たちを擁護する趣旨では共通しており、
「 海軍においても、青年将校の犬養首相殺害と、国憲に対する反乱行為を是認する空気が昂まっていた 」
しかし、山本の論告求刑内容は、匂坂のそれとは大いに趣が異なっていた。
山本の論告求刑を報じた33 ( 同8 ) 年9月12日付の時事新報には、その論告要旨が掲載されている。
それによると、
「 本件は海軍部内に於ける國家革新を企圖する團體、
陸軍部内に於ける同種の團體及び民間に於ける同種の各團體が共通な目的に向って合流結合したるもの 」
であると、事件の本質を明確に指摘している。
そして、陸軍刑法第25条と同一の海軍刑法第20条の叛乱罪を適用し、
古賀中尉には同条第1号の「 首魁 」と認定して死刑を、さらにその他の5名の者についても
同条第2号の前段
「 謀議ニ參輿シ又ハ群衆ノ指揮ヲ爲シタル者 」
として死刑から無期禁錮を求刑し、
これ以外の4名については 叛乱予備罪を適用して禁錮6年から同3年を求刑した。
当該時事新報は、「 血涙法を護る 」 との見出しを付け、
山本の顔写真とともに「 陸軍側とは異なる印象 」
との表現を用いて、海軍側の論告求刑を極めて肯定的な記事を添えて掲載している。
山本の行った論告の内容は、次のように要約される。
すなわち、被告人の事件に対する動機として、
① 政党・財閥の堕落、
② 農村の窮状、
③ ロンドン条約問題に端を発する統帥権干犯問題
―の三つを挙げている。
そのうえで、① 及び② について、彼らの認識不足と無謀さを糾弾し、
さらに③ については、
法廷で論じるものではないと切り捨て、事件における被告人の責任の重大さを指摘した。
また山本論告の際立った特徴は、
論告の中で1931 ( 昭和6 ) 年の十月事件 について
「 某事件 」と表現することによって、本事件の背景を鋭く指摘したことにある。
山本論告をして「 十月事件 にはほとんど指一本ふれ得なかった陸軍軍法会議との歴然とした差がある 」
と、今日でも高く評価する見方がある。
叛乱罪で断罪しようとしたことは匂坂と同様であったが、
事件の本質について言及するばかりか、
首魁1名を含む主動的立場にあった者3名に死刑を求刑したことは、
士官と候補生の違いがあるにせよ、陸軍側とは大いに異なっていた。
ともあれ、陸軍側の論告に象徴されるように、軍内外に対する配慮が滲み出た、
五・一五事件裁判の公判審理の状況をあらためて見ると、
軍法会議における司法権の行使とは一体何であったのか、甚だ疑問に感じざるを得ないのである。
( 4 ) 判決とその意義
1933 ( 昭和8 ) 年9月19日、陸軍第1師団軍法会議において、陸軍側の判決が言い渡された。
西村裁判長は、匂坂検察官の論告に沿って、陸軍刑法第25条叛乱罪の第2号後段を適用しつつ、
「 その原因動機目的については諒とすべきものある 」として、
11名の被告全員に、禁錮8年の求刑に対して、同4年の刑を言い渡した。
これを伝える翌20日付の東京日日新聞には、「 寛大の裁斷にただ號泣 」する特別弁護人の談話や、
この陸軍判決に力を得た海軍側弁護団の状況とともに、
「 任務は終わった 批判は後世に待つ 」との西村の談話が掲載されている。
本事件がニ・二六事件に繋がっていく、その後の我が国の歴史を振り返るとき、
この西村談話には灌漑深いものがある。
一方、同年11月9日に東京軍法会議で言い渡された海軍側の判決も、
山本検察官の当を得た指弾にも拘らず、
陸軍側と同様に、あるいはそれ以上に刑が軽減されていた。
すなわち、叛乱罪によって死刑を求刑された3名については、
禁錮15年から同13年、無期禁錮を求刑された3名には禁錮10年が、
また叛乱予備の罪な問われて禁錮6年から同3年を求刑された者には、
それぞれ執行猶予付きの禁錮6年から同3年が言い渡された。
判決謄本には、
「 黨ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反亂ヲ爲シ謀議ニ參輿シタル所爲ハ各海軍刑法第二十條第二號前段ニ該當シ
其ノ罪責實ニ重大ナリト雖 憂國ノ至情諒トスヘキモノアルヲ以テ右所定刑中有期禁錮刑ヲ選擇 」
したとあり、またしても求刑とは大きく異なる判決となった。
この判決で特に注目すべきは、山本の重要な主張部分を無視、
つまり、事件の背景を為す核心部分には全く言及していないことにある。
また、1名の者を事件の首魁とした論告に対しても、
他の被告人と同様に海軍刑法第20条第2号の
「 謀議ニ參輿シ又ハ群衆ノ指揮ヲ爲シタル者 」として認定し、しかも死刑判決を回避している。
その理由は、
「 被告人一同ハ故海軍少佐 藤井齊 ヨリ直接又ハ間接ニ感化指導ヲ受ケ
又 井上日召 等ト相識ルニ及ヒ愈其ノ所信ヲ鞏固ナラシムルニ至 」ったことにあるとして、
事件の首魁は、事件前の上海事変で既に戦死していた藤井少佐と、民間右翼であると断定したのである。
軍法会議検察官の論告求刑は、陸軍側では上層部の意向を強く反映とていたと見ることができるのに対し、
海軍側は厳正かつ峻厳なものと思われたが、
結果的には、両軍法会議ともに軍当局の意向に沿った結末を迎えることとなった。
旧法下における訴訟構造では、検察官に挙証責任がなく、したがって検察官の主張如何に拘らず、
裁判所が職権で犯罪事実の究明を行う構造になっていた。
挙証責任 訴訟において一定の事実の存否が確認されない場合に、その存否が確認されないことにより当事者の一方に帰せられる不利益。
現行法では、検察官に犯罪事実の挙証責任がある。
しかし、事件の真相は十分に究明されていないばかりか、
極めて不可解な判決であり、これが軍法会議の実態だった。
それにしても、当時の風潮にあらがうような論告求刑を行った、山本の真意は分らないが、
ただ一つ確かなことがある。
それは、山本は海軍軍法会議判決のあった翌年、
1934 ( 昭和9 ) 年7月28日に急逝したという事実である。
死因は可能性耳下腺炎とされているが、陸軍内部の対立やクーデター計画にまで言及し、
さらに統帥権干犯問題で揺れる海軍内部にも一石を投じた論告後の、心労によるものともいわれている。
ともあれ、
本来は長官に隷属する、
即ち、軍統帥系統の係累から逃れられないはずの検察官が、当局の意向とは異なるような求刑を行う一方、
司法権の独立が保障されていたはずの裁判官が、
当局の意向と世論に迎合するような判決を導き出したともいえる。
ここに、行政組織と司法官署が一体となった、軍法会議の歪んだ本質が見えてくる。
いずれにせよ、陸軍軍法会議も海軍軍法会議も、事件の核心に迫ることなく、
陸海軍内外への配慮を重視した、極めて政治的な意図を看取できる判決で決着した。
このような歴史的大事件の軍法会議を主導した、陸海軍の法務部局の性格について、
興味深い論考がある。
それによれば、陸軍省法務局は
「 戦闘兵科、あるいは・・・戦闘支援科に直接する軍政サイドの部局と異なり、
支援勤務機関とも称すべき、地味な部局 」であり、
「 軍政サイドの部局を中核にせざるを得ない陸軍省内部で、表立って認識される機会はそう多くはなかった 」。
したがって、司法に関わる事案が生起したような場合こそ
「要綱に沿った軍政サイドの期待に敵う法理を提供することで、
平常の業務において等閑視されていたのとは対照的に、そのレーゾンデートルを示すに至る 」
のであるという。
法務官で構成する陸軍省法務局の実態を示唆する分析であるが、
海軍についても同様の状況であって、
法理論に則り純粋に司法を掌る組織としては、本来的に限界のあったことがうかがわれる。
そして、このような政治決着を図った五・一五事件軍法会議判決の2年後に、
またしても軍による大事件が生起するのである。
次頁 軍法会議 3 『 定められた方針 二・二六事件裁判 』 に 続く
たまたま web上でみつけたもの、
此も亦 出逢いかしら・・と、私流に吟讀し、
茲に、私流に 『 書写 』 するものである

海軍側法廷 陸軍側法廷
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旧陸海軍軍法会議の意義と司法権の独立
五・一五及びニ・二六事件裁判に見る同法の本質に関する一考察
山本政雄
前頁 軍法会議 2 『 世論に迎合した 五・一五事件裁判 』 の 続き
2 司法権独立の実態 -ニ・二六事件裁判 -
( 1 ) 事件の概要
満洲事変勃発当時、陸軍内では天皇中心の国体至上主義を信奉し、
直接行動による国家改造を企てる「 皇道派 」と称するグループと、
財閥、官僚と手を結び、軍部勢力の伸張と総力戦体制の構築を目指す「 統制派 」と称するグループが対立していた。
前者は荒木貞夫、真崎甚三郎両大将を支持する、主として現場の部隊で勤務する青年将校によって構成され、
これに対して後者は、軍務局長永田鉄山少将をリーダーとして、
陸軍省や参謀本部といった、陸軍中枢部の幕僚将校を主体としていた。
香田清貞、安藤輝三歩兵大尉らの皇道派青年将校は、民間の北一輝らの影響を受け、
1936 ( 昭和11 ) 年2月26日の早朝、
歩兵第1、第3聯隊及び近衛歩兵第3聯隊等の兵力1、400名を率いて行動を開始し、
首相官邸等を襲撃した。 二・二六事件 の勃発である。
この襲撃によって、斉藤実内相、高橋是清蔵相、渡辺錠太郎陸軍教育総監及び警察官数名が犠牲となり、
さらに反乱部隊は国会、首相官邸、陸軍省及び参謀本部周辺地域を占拠して、昭和維新の断行を目指した。
この蜂起に対し、当初の陸軍中央は確たる収拾策を採らなかったが、
天皇の断固鎮圧の内意が示されるや迅速な対応に転じ、事件は発生から3日後に終息した。
そして、この事件の軍法会議は、極めて特異なケースとして記憶されることとなる。
すなわち、平時において、しかも国内で生起した事案であったにも拘わらず、
この事件は、戦地等において臨時に設置される、特設軍法会議に準じた軍法会議で審理されることとなったのである。
同年3月4日の緊急勅令第21号「 東京陸軍軍法會議ニ關スル件 」によって、
陸軍軍法会議法に規定しない「 東京陸軍軍法会議 」が臨時に設置された。
そこでの審理は、陸軍軍人のみならず、本事件に関与した民間人にも管轄権が及び、
さらに当該軍法会議は、特設軍法会議と見なすこととされた。
特設軍法会議と見なすということは、
被告人に弁護権の保障はなく、また審判は公開されないばかりか、
さらに上訴権もみとめられなかったことを意味する。
このような、極めて政治的な陸軍中央の超法規的措置によって、
19名の被告人は刑場の露と消えるとともに、ここに皇道派と呼ばれたグループは壊滅した。
そしてこの事件を境として、統制派の陸軍内での主導的立場が確立し、
我が国はこの陸軍統制派による軍閥支配の下、支那事変、大東亜戦争へと突入していくこととなる。
( 2 ) 東京陸軍軍法会議の設置
事件鎮圧の翌3月1日、
陸軍大臣は 「 事件關係者ノ摘發竝捜査ニ關スル件 ( 陸密第一四○號 ) 」を発出した。
それは
「 今次ノ叛乱事件ニ關シ、其ノ發生ノ原因ハ極メテ廣汎深刻ナルモノアルノミナラズ、
此種禍根ヲ將來ニ絶滅スル爲ニハ、部ノ内外ニ亘リ迅速且徹底的措置ヲ施スヲ必要トス 」
というものであった。
・・・・挿入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
陸軍が、司法當局の反對を押し切って東京陸軍軍法會議の管轄権を民間人にまで及ぼした最大の狙いは、
北 ・西田の斷罪と抹殺にあったと推測される。
三月一日附の陸軍大臣通達
( 陸密第一四〇號 「 事件關係者ノ摘發捜査ニ關スル件 」 )
は、次のように述べる。
この通達が、豫審も始まっていない段階のものであることに注目する必要がある。
北 ・西田を張本人とする路線は、最初から敷かれていたのである。
叛亂軍幹部及其一味ノ思想系統ハ、
過激ナル赤色的國體變革陰謀ヲ機關説ニ基ク君主制ヲ以テ儀装シタル北一輝ノ社會改造法案、
順逆不二ノ法門等ニ基クモノニシテ、我ガ國體ト全然相容レザル不逞思想ナリトス。
檢察官は、このシナリオに則って、論告の中で、事件の動機 ・目的として次のように述べる。
本叛亂首謀者ハ、日本改造法案大綱ヲ信奉シ、
之ニ基キ國家改造ヲ爲スヲ以テ其ノ理想トスルモノニシテ、
其企圖スルトコロハ民主的革命ニアリ・・・・集團的武力ニ依リ 現支配階級ヲ打倒シ、
帝都を擾亂化シ、且帝都樞要地域ヲ占據シ、戒嚴令下ニ導キ 軍事内閣ヲ樹立シ、
以テ日本改造法案大綱ノ方針ニ則リ政治經濟等各般ノ機構ニ一大變革ヲ加ヘ、
民主的革命ノ遂行ヲ期シタルモノナリ。 ・・・ニ ・二六事件行動隊裁判研究 (ニ) 松本一郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
然るに、この示達には「 極秘 事件處理要綱 」が添付されており、
同要綱の内容と日付から
「 緊急勅令によって東京陸軍軍法会議を特設して厳罰主義によって叛乱者を速やかに処断することなど、
事件処理についての陸軍省当局の基本的態度は、二月二十九日段階でほぼ固まっていた 」
と見ることができる。
同処理要綱には、
緊急勅令による軍法会議の特設に加え、
下士官兵に対しては情状を酌量する一方で、
部内外の事件関係者の徹底的な摘発検挙によって、
事件の厳正な処分に臨むことが示されている。
また、高級将校の人事刷新、さらには後継内閣の構想等にまで言及しており、
事件後に陸軍当局が推進する諸施策のほぼすべてが、この時点で策定されていたことには驚き入る。
ニ・二六事件の本質として、実は周到に仕組まれたものであったとする説があり、
「 統制派の幕僚たちが、青年将校の暴発による非常事態に乗じて軍部の指導力を確立し革新を断行 」
すべく計画していたのだというのである。
さらに
「 五・一五事件ののち、この種の非合法手段による軍事クーデター対策が軍中央部で研究された。
・・・右翼又は青年将校のクーデターに対し、戒厳令をもってする詳細なカウンタークーデターの計画であり、
いわば非合法の反乱を軍事力で鎮圧するという合法的な手段によって、事実上の軍事政権を樹立することを目的とした計画 」
であったとまでいわれている。
現に、本事件の後に真崎、荒木両大将らは待命となって皇道派は陸軍から一掃されるとともに、
陸海軍大臣現役制の復活 ( 昭和11年勅令第63号 ) や
陸軍省機構の改正 ( 同第211号 ) 等が次々に実行に移されたという事実がある。
陸海軍大臣現役制の復活 政党勢力の軍部内への浸透を防止する趣旨で、
1900 ( 明治33 ) 年の陸軍省・海軍省管制改正で、陸海軍大臣は現役の大・中将とすることが明記された。
その後、第一次護憲運動等を背景として1913 ( 大正 2 ) 年に現役武官制が廃止され、任用範囲は予備役、後備役の将官にも拡大された。
然るに、本事件後に旧制に復したのであり、これによって軍部は内閣の死命を制する武器を手にした。
この要綱には、軍中枢部の幕僚らによって策定された
「 ただ、事件を起した将兵をどうするかといった目前の療法を記したに止まらず、
事後を見据えた陸軍当局の長期的な政策的決意 」
示されていたと捉えられる。
事件処理の方針に従って、特別の軍法会議設置への動きが始まった。
陸軍大臣示達のあった3月1日の午後には、
「 不祥事件ニ對スル軍法會議構成ニ附、緊急勅令ヲ仰グベク閣議 」
が開かれた。
勅令 勅令とは大日本帝國憲法下で天皇により制定された法形式の一つであり、大権事項について法規を定立する場合に用いられた。
また、公共の安全等のために、緊急時に発せられるものを緊急勅令と称した。
翌2日には枢密院において
「 東京陸軍軍法會議ニ關スル件審査委員會 」
が開催され、
「 岡田内閣總理大臣ヨリ本案ノ勅令ヲ必要トスル理由及其ノ内容ニ附説明アリ
更ニ川島陸軍大臣及小原司法大臣ヨリ補充的説明 」
のあった後、
「 委員間ノ協議ニ入リ各員ヨリ夫々意見陳述ノ後本案ハ此ノ儘可決セラレ然ルベキ旨全會一致ヲ以テ議決 」
した。
そして3日、
委員長枢密院顧問官荒井賢太郎から枢密院議長一木喜徳郎に
「 東京陸軍軍法會議ニ關スル件審査報告 」
が提出された。
それによれば、このような陸軍軍法会議法に規定しない軍法会議の設置理由として、
被告人の軍人が複数の部隊に所属し、また民間人も含まれていることから、
「 各所屬軍法会議に分けて審理する事の不便さ 」
及び
「 軍法会議と通常裁判所に分けることの不適切さ 」の2点を挙げ、
さらに
「 この種の裁判では被告人の法廷闘争の場となる 」
ためであるとする。
軍法会議特設の理由としたこれらの事項には、
まさに五・一五事件裁判の再来に対する危惧を、明確に読み取ることができよう。
ちなみに、東京陸軍軍法会議設置に関するこれらの理由について、
法的側面から、多くの問題があるとする論考がある。
論考 松本一郎「 東京陸軍軍法会議についての法的考察」 『 獨協大学法学部創設25周年記念論文集 』( 第一法規出版、1992年)
及び同 『 二・二六事件裁判の研究 』( 緑蔭書房、1999年 ) ・・・リンク → 松本一郎 『 二・二六事件裁判の研究、記錄 』
当該論考は、法学の専門的見地からの玉稿であり、
同軍法会議の設置について、極めて示唆に富む論点が提示されている。
しかしながら、本稿では紙面の制約もあることから、
憲法解釈を含むこの点に関する詳細な考察は、稿を改めることとしたい。
ともあれ、事件の解決からわずか4日の3月4日、
次の6箇条からなる「 東京陸軍軍法会議に関する緊急勅令第21号 」が公布された。
東京陸軍軍法會議ニ關スル件 ( 昭和十一年勅令第二十一號 )
第一條 東京ニ東京陸軍軍法會議ヲ設ク
第二條 東京陸軍軍法會議ハ陸軍大臣ヲ以テ長官トス
第三條 東京陸軍軍法會議ハ陸軍軍法會議法第一條乃至第三條ニ記載スル者ノ犯シタル昭和十一年二月二十六日事件ニ關スル被告事件ニ附管轄權ヲ有ス
第四条 師團軍法會議ノ長官ハ捜査ノ報告ヲ受ケタル前條ノ被告事件ヲ東京陸軍軍法會議ノ長官ニ移送スベシ
前項ノ規定ニ依リ東京陸軍軍法會議の長官移送ヲ受ケタルトキハ捜査ノ報告アリタルモノト見做シ處分スベシ
第五條 東京陸軍軍法會議ハ陸軍軍法会議法第一條乃至第三條ニ記載スル者意外ノ者ガ同法第一條乃至第三條ニ記載スル者ト共ニ昭和十一年二月二十六日事件ニ於テ
犯シタル罪ニ附裁判權ヲ行フコトヲ得
第六條 東京陸軍軍法會議ハ陸軍軍法會議法ノ適用ニ附テハ之ヲ特設軍法會議ト見做ス
ここにある、陸軍軍法会議法第1条ないし第3条に記載した者とは、
陸軍軍人及び軍属等をいい、それ以外の者とは、民間人を指していた。
つまり、これによって、本事件に関する被告人全員を、
一つの軍法会議で審理する態勢ができあがったのである。
しかも、その軍法会議は特設軍法会議と見なされたため、
弁護人の関与、審判の公開及び上告に関する規定はもとより、
裁判官の除斥・回避等、被告人の人権擁護のための重要な規定がすべて適用されなかった。( 86条、93条、417条、418条 )
排斥 排斥とは、裁判官等が事件の当事者又は事件と特殊な関係にあり、その公正につき客観的疑念を生じさせる場合には、その職務執行から排除されることをいい、
回避 回避とは、裁判官等が排斥等の理由があると考える場合に、自発的に裁判への関与を避けることをいう。
( 3 ) 判決と東京陸軍軍法會議の終結
被告人数の多さから、東京陸軍軍法会議は、五つの公判廷に分けて審理されたが、
公判廷の内訳 第一、将校班 第二、下士官班甲 第三、下士官班乙 第四、兵班 第五、常人 ( 民間人 ) 班 ・・・リンク → 松本一郎 『 二・二六事件裁判の研究、記錄 』
「 検察官を指揮・総括した者は匂坂春平法務官であり、公訴提起はすべて彼の名で行われた 」
また、各部隊に判士要員の派出を依頼した文章
「 東京陸軍軍法会議判士出頭ニ關スル件 」
によれば、
判士、すなわち裁判官としての将校が、
陸軍省や参謀本部、教育総監部、さらには師団隷下の各部隊から、
合計26名も召集されていた。
法務官についても、陸軍省法務局はもとより、高等軍法会議と各師団軍法会議の33名が集められ、
それぞれ裁判部と検察部に振り分けられたが、
訴訟手続上は全く独立しているはずの予審官と裁判官を兼ねる法務官がいたことが、
匂坂資料によって明らかとなっている。
兼務の法務官とは、民間人の北一輝や西田税の予審官を務めた伊藤章信法務官であり、第五公判廷の裁判官でもあった。
裁判官が除斥される場合の一つである、
「 裁判官事件ニ附捜査、豫審又ハ前審ニ干輿シタルトキ 」( 81条 )であり、
通常ならば
「 法律ニ依リ職務ノ執行ヨリ除斥セラレヘキ裁判官審判ニ干与輿シタルトキ 」( 424条の2 )
に該当するものとして、上告理由に相当した。
上告規定が除外されていたとはいえ、捜査の延長との性格を併せ持つ予審に従事する予審官が、
裁判官を務めるのであるから、裁判とはまさに名ばかりの状況であったろう。
審理は迅速に進められ、1936 ( 昭和11 ) 年7月5日の第一次判決から
37 ( 同12 ) 年8月14日の第三次判決によって、
民間人4名を含む19名もの被告人に死刑が、
またその他の被告人にも極めて重い刑を言い渡して、
ニ・二六事件裁判は終わった。
閣僚を殺害し、首都の治安を大混乱に陥れた責任は免れないが、
それにしても峻厳に過ぎる判決ではなかったか。
判決のうち、5名の判決は求刑を上回っていたうえ、
この事件に19名もの死刑判決者を数えねばならないほどの、
刑事責任を問うべき兇悪性があったとは、到底思えない。
事件の組織性や計画性において、歴然とした差があったにせよ、
同様の背景によって引き起された五・一五事件裁判の、不可解ともいえる軽い判決と比べるとき、
一層その不条理さを感じざるを得ない。
特に、元将校の2名以外の4名の民間人にも死刑が言い渡されているが、・・北一輝、西田税、澁川善助、水上源一
このうち3名は「 事件の実行計画にほとんど関係なく、行動にも参加していない 」・・北一輝、西田税、澁川善助
とまでいわれているのである。
ともあれ、7月7日付東京日日新聞の記事によれば、
7月5日の第一次判決について、陸軍省は7日午前2時になって初めて発表している。
その記事は、陸軍省の発表内容をそのまま伝えるもので、
五・一五事件判決当時の「 名判決 」などと讃える大様な論調は、全く見られない。
あまりにも無機質な紙面が、この事件に対する峻厳な判決内容を一層際立たせていて、
報道には不気味な印象さえ抱かせるのであるが、
同時にそれは、軍の措置に対して一切の批判を許さない、当局の意思表示とも受け取れよう。
さらに、本裁判が不条理なものであったことを象徴する事例として、
北や西田ら民間人の第三次判決までに長期間を要したという事実があり、
それは「 陸軍省と判士の意見が対立したためおくれ 」たのであって、
軍法会議の「 合議の紛糾にあったことは明らかである 」といわれている。
すなわち、
「 北、西田に対して陸軍省では最初から死刑にせよと主張した。・・・リンク → 暗黑裁判 ・幕僚の謀略 1 西田税と北一輝 『はじめから死刑に決めていた』
裁判長は吉田悳少将であるが、
調べてみるとどうしても首魁とするには証拠が不十分である。
もしこれを極刑に科すなら、同列な嫌疑のある真崎大将や山口大尉も極刑にすべきだ。
さらに香椎中将もおかしいと、強く陸軍省の干渉に反対した。
しかし裁判官中には陸軍省の方針を支持する者があって結局、両人は首魁として極刑を科せられた 」
というのである。
これは、吉田裁判長が、陪席の判士に宛てた書簡の内容に基づいたものとされているが、
これが真実だとすれば、軍法会議の実態、ここに極まれりの観がある。
ちなみに、
この記述に表れている真崎甚三郎大将、香椎浩平中将及び山口一太郎大尉のその後の状況についても確認しておきたい。
山口大尉は、本事件の協力者の一人として、
東京陸軍軍法会議で陸軍刑法第30条「 反亂者ヲ利スル 」罪で起訴され、
第二次判決において無期禁錮の刑を言い渡されている。
一方、真崎大将は、皇道派の総帥のように考えられていたため、
当初から事件の黒幕の一人として捉えられており、
同人に対する公判は、1937 ( 昭和12 ) 年6月1日から、
常設軍法会議である第一師団軍砲会議で始まった。
罪名は、同じく「 反亂者ヲ利スル 」罪である。
真崎の公判に際し、陸軍当局は厳重な警戒態勢をとっていたことが、
「 眞崎大將公判ノ際ニ於ケル警戒ニ關スル件 ( 昭和十二年陸密第八三六號 ) という、
同年5月29日付の陸軍次官から憲兵司令官への依命通牒からうかがい知ることができる。
この依命通牒によれば、真崎に対する裁判は、
陸軍軍法会議法の
「 安寧秩序若ハ風俗ヲ害シ又ハ軍事上ノ利益ヲ害スル虞アルトキハ辯論ノ公開ヲ停ムル決定ヲ爲スコトヲ得 」( 372 )
の規定を適用し、非公開で定められていたことが分る。
さらに、陸軍当局は憲兵隊を動員して警戒を強め、
処刑された被告人らの同調者による過激行動等、
不測の事態に備えていたことも判明する。
ことほどさように、ニ・二六事件裁判に対する判決が理不尽なものであり、
これが新たな反乱行動の原因となり得る可能性について、
当局自身が十分に認識していたことを示している。
ともあれ、公判審理の状況は史料がなく不明であるが、
結局、真崎には9月25日に無罪判決が言い渡されている。
・・・リンク → 眞崎甚三郎大將判決全文 (九月二十五日陸軍省公表)
・・・リンク →「 被告人眞崎甚三郎ハ無罪 」
また、東京警備司令官で、戒厳司令官に任ぜられていた香椎中将はどうであったか。
事件勃発直後から香椎は不可解な行動をとっていたが、
特に2月27日に反乱部隊を戒厳下の警備部隊に編入したことが、
その嫌疑を一層強くしていた。
本事件の背景を強く示唆する「 陸軍大臣告示 」なるものがあり、これには反乱部隊の行動を正当化する表現が含まれており、当日の午後3時頃に各師団に下達されたというのが定説だった。
ところが、1989( 平成元 ) 年に公表された匂坂資料によって、香椎中将が既に午前10時50分頃に近衛師団に伝達していた可能性を捉え、
匂坂検察官が香椎司令官を「 叛軍一味 」 として追求しようとした事実を明らかにした。 ( 『 検察秘録 二・二六事件 Ⅰ』33頁 )
その後、東京地方検察庁で関係資料が発見されるのに及んで、ほぼこのことが裏付けられたとされている。( 原秀男 『 二・二六事件軍法会議 』( 文藝春秋、1995年) 37―39頁 )
このため、匂坂は陸軍刑法第30条「 反亂者ヲ利スル 」罪と
同第46条「 部下多衆共同シテ罪ヲ犯スニ當リ鎭定ノ方法ヲ盡ササル 」罪の容疑によって、
香椎の身柄を拘束したうえで予審に付そうと考えていた。
ところが、東京地検に保存されていた、匂坂による捜査報告に添付された意見書には
「 辱職及叛乱共ニ證據備ハラス 」
との朱書き訂正の跡があり、捜査が打ち切られたことを示している。
このことはすなわち、
「 大臣の意図に従って香椎中将に対する強制捜査を断念せられ 」
たことを意味すると解釈されている。・・・リンク → 戒嚴司令官 香椎浩平 「 不起訴處分 」
真崎は起訴された一方、
香椎は予審に付されることもなく、捜査は終結したという違いがあり、
この点に関連して、
陸軍上層部の圧力を背景とした、匂坂の司法判断に関する論争が行われたことがある。
1988 ( 昭和63 ) 年の、澤地久枝による「 法の理論に徹した大法務官 」とする説と、
池田俊彦の「 憐れむべきオポチュニスト 」とする説の対立である。
しかし、陸軍法務官の本質的立場からすれば、
そのような論争には意味がないことを、次の理由によって論破した考察がある。
すなわち、
「 法技術者として、定められた方針に従い、その方針が全うせられるように法的側面から助力すべき役割を課せられているのが、陸軍法務官 」であって、「 匂坂はこれ以上でも以下でもない 」
と指摘したのである。・・・北博昭 「 東京陸軍軍法会議検察官匂坂春平法の虚実 」『 日本歴史 』第516号 ( 1991年5月 ) 73-74頁
つまり、真崎の場合も香椎の場合も、
匂坂が捜査と予審の結果に対する意見書をニ通り作成していた事実を捉え、
「 陸軍当局の意向に適うよう、選択的に、真崎へは『 案1』の起訴と『 案2』の不起訴を、
香椎へは身柄拘束案と身柄不拘束案=真相追求中止案を出す。
その上、各選択肢それぞれにコメントを付ける。陸軍法務官の分をわきまえたやり方 」
とするこの論者の分析には、説得力がある。・・・北博昭 「 東京陸軍軍法会議検察官匂坂春平法の虚実 」『 日本歴史 』第516号 ( 1991年5月 ) 75頁
真崎裁判終結から4日後の1937 ( 昭和12 )年9月29日、
「東京陸軍軍法會議審理完了ノ件 ( 陸密第一一〇三號 ) が発出された。
陸軍省から陸軍全般宛て
「 今次眞﨑大將ニ對スル裁判終結ヲ以テ東京陸軍軍法會議ニ於ケル 二・二六事件ニ關スル被告事件一切ノ處理ヲ完了セリ 」
と通知された。
そして翌38( 同13 ) 年4月9日に、
東京陸軍軍法会議の設置を定めた昭和11年勅令第21号は、法律第80号によって廃止された。
また、これを受け、
「 軍法會議を廢シタルトキハ陸軍大臣ハ後繼軍法會議ヲ指定スヘシ 」( 29条 )
との規定に基づき、同日付で陸軍省告示第18号が発出された。
それは、
「 東京陸軍軍法會議ノ後繼軍法會議ハ陸軍高等軍法會議トス 」
というものだった。
後継軍法会議として高等軍法会議が指定されたということは、
再審の請求は高等軍法会議に行うことができる ( 484条 )ことを意味していた。
しかし、この措置はあくまでも法規定に基づく形式的なものであって、
当時の情勢下で、刑死者の遺族等が再審請求することなど現実的にはあり得ず、ニ・二六事件裁判は終わった。
こうした一連の措置によって、
「 軍の政治的干渉ないし政治支配実現のためのもっとも有力有効な装置の一つ 」
となり、
「 およそ裁判の名に値しない、権力による殺人のための密室のセレモニイ 」
とまで形容された東京陸軍軍法会議は、終結したのである。
次頁 軍法会議 4 『 軍検察権は軍政に属するもの、軍上層部の意嚮に從う 』 に 続く
たまたま web上でみつけたもの、
此も亦 出逢いかしら・・と、私流に吟讀し、
茲に、私流に 『 書写 』 するものである

海軍側法廷 陸軍側法廷
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旧陸海軍軍法会議の意義と司法権の独立
五・一五及びニ・二六事件裁判に見る同法の本質に関する一考察
山本政雄
前頁 軍法会議 3 『 定められた方針 二・二六事件裁判 』 の 続き
おわりに
両事件は、それぞれ海軍及び陸軍の青年将校が、
民間右翼と連繋して惹起したクーデター未遂事件という、本質的な性格では共通しているが、
事件に対する軍法会議の判決内容において、その相違はあまりにも大きい。
すなわち、五・一五事件は一国の首相を暗殺したテロ事件であったにも拘らず、
一人の被告人にも死刑の言い渡しがなかったのに対して、
ニ・ニ六事件では犠牲者の数が多数にのほべるとはいえ、実に19名もの被告人が極刑に処されている。
ここに、通常裁判所の司法判断とは異質の、軍法会議における、政治的意図に由来する司法判断を看取できる。
五・一五事件裁判の特徴は、陸海軍ともに常設軍法会議の公開法廷で審理されたため、
そこでは活発な法廷闘争が展開され、これが被告人に同情的な世論を煽る結果となった。
さらに、陸海軍上層部の、本事件を穏便に処理しようとする意向も作用して、
同裁判は、およそ適正な司法権行使の場とはいえ いい難い様相を呈することとなる。
このことは、特に陸軍軍法会議における、検察官の対応が強く示唆しているのであるが、
もともと軍検察権は軍政に属するものとされていた。
つまり、軍法会議検察官とは軍法会議長官、ひいては陸海軍大臣の指揮監督を受けるのであり、
したがって個々の検察権を執行する一般の検事とは異なり、軍上層部の意向に従うという本質的な性格を有していた。
軍法会議長官をして「 県知事が地裁所長、地検検事正を兼ね、且つ、県警本部長を兼任するようなもの 」
と比喩される所以である。
このような、上層部の意向が検察官に強く影響していたことを示唆する陸軍軍法会議に対して、
海軍軍法会議の検察官の対応は対照的に捉えられる。
すなわち、海軍上層部の意向に反するかのように、
その論告求刑は、死刑を含む峻厳かつ適正なものであるとともに、
そこには軍内部の闇を照らすかのような、核心に迫る内容を含んでいた。
しかしながら、海軍軍法会議の下した判決には、
陸軍側と同様に、またしても世論への迎合と陸海軍部内への政治的配慮の痕跡を、
明確に読み取ることができるのである。
結局、本件の陸軍軍法会議は、
検察、司法の双方が、上層部が示した方針に忠実に行動したと結論づけることができる。
これに対して、海軍軍法会議では、統帥権の係累から逃れられない検察官が、
上部の意向に反するかのような求刑を行い、
逆に司法権の独立が保障されていたはずの裁判官が、
上層部の意向と世論に迎合した判決を導き出したといえる。
このように、両裁判は対照的に捉えられるものの、
いずれの場合も、行政組織と司法官署が一体となった、
軍法会議の歪んだ本質が浮かび上ってくる。
一方、ニ・二六事件を審理した東京陸軍軍法会議は、法の想定しない枠組みを以て設置された。
それは、国民の裁判を受ける権利を保障した、大日本帝國憲法の規定に抵触した可能性も否定し得ない。
当時の方感覚からしても極めて不条理な裁判であった。
同軍法会議設置の背景に、世論への配慮を強いられた五・一五事件裁判への反省と、
軍検察権を掌る、軍政からの強い要求があったことは間違いない。
一般論上の解釈はともかく、司法作用の場においては、軍政と軍令の境界は非常に曖昧であり、
したがって、軍政に属する軍検察権が、統帥権から発動される可能性を避けることはできなかった。
であるからこそ、司法権の統帥権からの独立を保障するのが軍法会議であって、
その目的は、まさに「 統帥権と司法権の調和 」を図ることにあった。
しかしながら、ニ・二六事件裁判の実態は、軍政・軍令のいずれの側面からであるにせよ、
軍の政治的意図を露骨に体現した検察と、同じく軍当局の方針に支配された司法の、
合議体といっても過言ではなかった。
軍法会議法が理念とした司法権の独立が、実は全く機能していなかったことを、
同事件裁判は いみじくも示しているのである。
このように、両事件裁判の考察から判明するのは、
軍法会議法が軍当局の軍政、ないしは統帥の一手段として運用されていたという側面である。
確かに、軍という一種の行政機関が司法権を行使していたことは、厳然とした事実であり、
今日では到底許されるものではない。
しかしながら、旧憲法下における当時の方感覚からすれば、
軍法会議とは
「 實質的には國の司法機關たるよりも、寧ろ軍令機關たる要素を多分に含んで居る 」、
特殊な司法行使の場として容認されていた。
さらに「 特別裁判所の制は、行政權と司法權との分離に對する一つの例外を爲すもの 」
と受け止められていたことも、理解しておく必要はあろう。
そして、旧陸海軍の軍法会議法が、あくまでも当時の法体系の枠内で、軍特有の要求を反映しつつ、
旧刑事訴訟法という一般法の規定に、最大限の整合が図られていたことも、紛れもない事実である。
しかし、同時にそのことは、軍の要求に対して一般法の規定を糊塗的に適用することによって、
形式的に一般法に準拠する体裁を採っていたと見ることも、不可能ではない。
就中、司法権独立は軍法会議法立法時の理念であったが、
長官を頂点とする裁判構造が象徴するように、
同法の規定そのものに、自らこれを否定するような根本的な欠陥が潜在していた。
つまり、五・一五事件やニ・二六事件のような裁判を可能にした、軍法会議法の本質とは、
それが原理とした「 統帥権と司法権の調和 」というよりは、
むしろ「 統帥権を泉源とする司法権を具現化 」するための手段であったとの結論に到達する。
軍法会議法が掲げていた司法権独立の理念とは、このように有名無実なものに過ぎなかったのである。
本稿は、昭和の激動期における歴史的事件を通じて、旧陸海軍軍法会議法の本質の一端を考察するものであった。
しかし、以上の分析が、同法に対する適正、かつ普遍的な評価と結論づけることは、尚早であろう。
というのも、これらの事例が空前絶後の特異な事案であって、軍法会議法に対する、極めて否定的な評価を下さざるを得ない、
特殊なケースであったかもしれない。
したがって、これを適正に評価するためには、膨大な数にのぼる旧陸海軍軍法会議の実相を、
つぶさに分析する必要がある。
しかしながら、もともと現存するこの種の裁判史料が、非常に希少であることに加え、
歴史の風化にともなう、さらなる史料の散逸という状況も相まって、
その作業は確実に困難になりつつある。
( 元防衛研究所戦史部所員 防衛大学校防衛学教育群 准教授 )