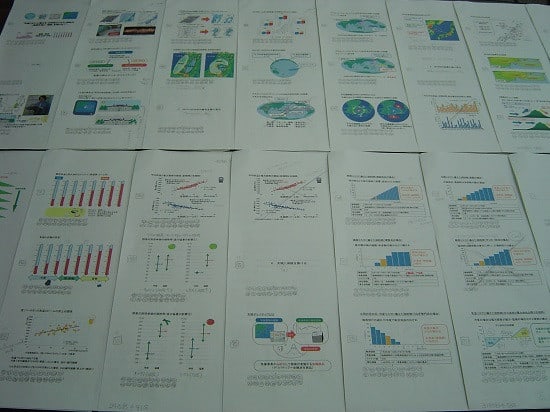昨日は、社団法人の会合の場をお借りして『 「天候リスク」に備える「お天気ビジネス」新時代 ~異常気象に「保険」をかける?~ 』と題した講演を行いました。
実はちょうど半月前には、仙台で開催された気象学会において、15分程度の時間枠で「ニューラルネットワークを用いた新潟県内の冬期降水域の解析」と題した研究発表を行いました。こちらは「冬の季節風の条件に応じて、新潟県内で雪が降りやすいのはどこか?」をAI(ニューラルネットワーク)で学習および予測するという取り組みです。
一方、今回の時間枠は「約60分」と長きに渡る講演ということもあり、前半では「2018年の顕著な気象現象」を振り返り、そのメカニズムについて概観しました。先の冬の新潟県内の大雪や夏の猛暑、さらには西日本の豪雨に関する事例を取り上げ、解説を試みました。
また、後半では「気象変化と経済活動に関わり」を念頭に、気温と売れ筋商品の傾向や天候に伴う様々なリスクを概観しました。具体的には、昇温期・降温期における売れ筋商品のトレンドや夏と冬の電力需要、さらに猛暑の野菜価格への影響を取り上げ、さらに「天候デリバティブ(天候リスク保険)」の契約例を幾つか御紹介しました。
肝心の「保険の掛け金」に相当する「(オプション)プレミアム」については触れませんでしたが、この辺も関心を持たれた部分です。実際、天候デリバティブに関する研究では「プレミアムの算定(プライシング)」が重要なテーマとなることが多いのですが、さすがにそこまで行くとCAMJ等のレベルになってしまいます。
このように、これまでの講演の中では余り扱ってこなかったテーマを多く含んでいるので、その意味では「チャレンジ」でもあり、「博打」のようなところもありました。また、所謂「懇親会」の講演(卓話)の場で、災害を及ぼす気象現象という「ネガティブ」な話題や、生々しい「カネ」の話をするのもどうかと・・・正直、一抹の不安はありました。
しかし幸いなことに、参加された皆様にも興味・関心を持って頂き、盛況の内に終わることができました。思い起こせば、このオファーを頂いたのが4月の事でした。それから、企画・構成を思案し、試行錯誤を重ね、ようやく講演講師の大役を果たすことができました。
先の学会発表に続いて、今回の講演も終わり、今年最大のイベントは閉幕しました。
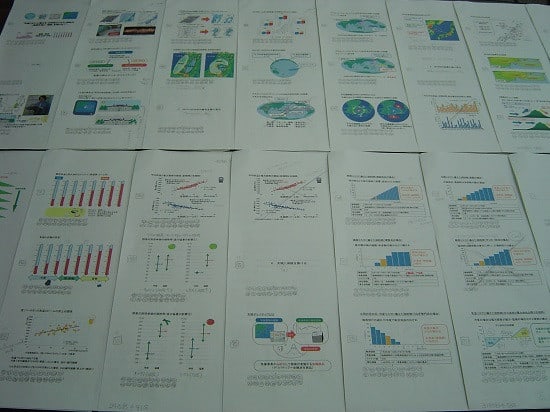
実はちょうど半月前には、仙台で開催された気象学会において、15分程度の時間枠で「ニューラルネットワークを用いた新潟県内の冬期降水域の解析」と題した研究発表を行いました。こちらは「冬の季節風の条件に応じて、新潟県内で雪が降りやすいのはどこか?」をAI(ニューラルネットワーク)で学習および予測するという取り組みです。
一方、今回の時間枠は「約60分」と長きに渡る講演ということもあり、前半では「2018年の顕著な気象現象」を振り返り、そのメカニズムについて概観しました。先の冬の新潟県内の大雪や夏の猛暑、さらには西日本の豪雨に関する事例を取り上げ、解説を試みました。
また、後半では「気象変化と経済活動に関わり」を念頭に、気温と売れ筋商品の傾向や天候に伴う様々なリスクを概観しました。具体的には、昇温期・降温期における売れ筋商品のトレンドや夏と冬の電力需要、さらに猛暑の野菜価格への影響を取り上げ、さらに「天候デリバティブ(天候リスク保険)」の契約例を幾つか御紹介しました。
肝心の「保険の掛け金」に相当する「(オプション)プレミアム」については触れませんでしたが、この辺も関心を持たれた部分です。実際、天候デリバティブに関する研究では「プレミアムの算定(プライシング)」が重要なテーマとなることが多いのですが、さすがにそこまで行くとCAMJ等のレベルになってしまいます。
このように、これまでの講演の中では余り扱ってこなかったテーマを多く含んでいるので、その意味では「チャレンジ」でもあり、「博打」のようなところもありました。また、所謂「懇親会」の講演(卓話)の場で、災害を及ぼす気象現象という「ネガティブ」な話題や、生々しい「カネ」の話をするのもどうかと・・・正直、一抹の不安はありました。
しかし幸いなことに、参加された皆様にも興味・関心を持って頂き、盛況の内に終わることができました。思い起こせば、このオファーを頂いたのが4月の事でした。それから、企画・構成を思案し、試行錯誤を重ね、ようやく講演講師の大役を果たすことができました。
先の学会発表に続いて、今回の講演も終わり、今年最大のイベントは閉幕しました。