軌道エレベータ -宇宙へ架ける橋-
石原藤夫・金子隆一共著
(1997年 裳華房=画像左、新書版)
(2009年 早川書房から復刊=同右、文庫版。タイトルは「軌道エレベータ"ー"」に変更。下記の本文は復刊前のママ)
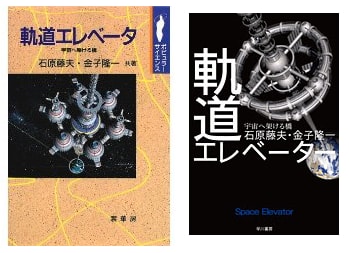 サイエンスライターの金子隆一氏と、作家の石原藤夫氏の共著による軌道エレベーター(本書では軌道エレベータ。OEVと略す)専門書。
サイエンスライターの金子隆一氏と、作家の石原藤夫氏の共著による軌道エレベーター(本書では軌道エレベータ。OEVと略す)専門書。
間違いなく日本初、そしておそらくは世界初であろう単独のOEV専門書であり、本来なら筆頭に挙げるべき、OEV史上決して外せない1冊である。
現在OEV専門書の代表格はブラッドリー・C・エドワーズ氏の「宇宙旅行はエレベーターで」(ランダムハウス講談社)といえるが、同書がOEV実現構想をあらゆる側面から考察した「OEV総合計画書」とでもいうべき趣を呈しているのに対し、こちらはOEVの原理と構造を丁寧に説明した「OEV教科書」といった印象を受ける。自然科学系の教科書を数多く出している裳華房らしいとも言えるかも知れない。
あとがきにもある通り、「OEVとは何か?」を知る上での必要十分条件をまさにぴったり満たしており、この点においてエドワーズ氏の著書を凌ぐ親詳さを有している。
驚くのはそのわかりやすさ。それなりに数式が盛り込まれているのだが、地球重力圏からの脱出速度やOEVの強度など、読めば自分で計算して検証が不可能ではない程度のレベル。厚さも手ごろで、新しい知識に触れる喜びを感じ、わくわくしながら読んだものだ。
本書で説明されるOEVの基本原理は、当サイトの「軌道エレベーター早わかり」で説明している通りだが、OEVの建造プランとして小惑星を捕獲し、アンカーウェイト兼炭素材料の供給源に使用することや、昇降機にリニアを使用し、位置エネルギーを電力として回収する(つまり上りエレベーターのコストの大半を下りが供給してくれる、またはその逆)などのアイデアが大きな特徴。
金子氏はこれに先立つ「アインシュタインTV」書籍版(1991年 双葉社)、その後の「新世紀未来科学」(2001年 八幡書店)などでもこの構想に触れている。この点もエドワーズ氏と大きく異なる点だろう。小惑星については、その後もっと簡便な建造プランが多数提案されたのでもはや見られなくなった感があるが、その他の構想は10年以上経った今もOEV理論の重要な基礎を成している。
また、マスコン(重力ポテンシャルの異常箇所)にOEVの重心が徐々に引きずられてしまうという問題点(現存する静止衛星もこの問題を抱えている)を、複数のOEVを静止軌道上のリングで連結して解決するというアイデアを紹介しており、実現すれば実に理想的な構造であろう。個人的には、このオービタルリングの構想は、OEV特有の弱点である、エレベーターの上下運動の反動によるコリオリの作用の解消にも利用できると考えている。
さらに遠心投射機としてのエレベーターの価値も強調しているほか、後半では月や火星のOEV構想、非同期型軌道型のOEVや極超音速スカイフックなどのアイデアも紹介している。
アーサー・C・クラーク氏の「楽園の泉」(早川書房)でOEVを知り、この書で本格的知識を身に付けた人は多いだろう。暫定的な分類だが、この本の読者はいわばOEV支持者の「第2世代」なのではないかと感じる。K.ツィオルコフスキーやY.アルツターノフ(いずれもOEVの発想を発表した研究者)など、ゼロからOEVを発案した人々は第1世代、私のような「楽園の泉」の読者以降が第2、そして今、「宇宙旅行はエレベーターで」や、日本科学未来館制作のアニメ「宇宙エレベータ~科学者の夢みる未来~」などで増えている人たちが第3世代である。
非常に残念なことだが、本書は現在絶版状態で現在手に入らない。当時はOEVの認知度はあまりにも低く、時代がついてくるのに時間がかかり過ぎ、人々の無知の中に埋もれてしまった名著だった。だからといって古典扱いするのはふさわしくない。「宇宙旅行はエレベーターで」を翻訳した関根光宏氏も、本書で調べてOEVの価値への認識を深め、出版社に「宇宙旅行─」の日本での刊行を勧めたという。この本が欲しくて復刊を望むOEVファンは多いことだろう。
本書を、もはや最新情報に追いつかなくなった、時代遅れな書と位置づける意見も聞くが、決してそんなことはない。それらは基礎と応用の差でしなかく、本書で述べられているOEVの基礎が変化したり無効になるようなものでは決してない。本書は今なお、OEVの知識への入り口として、その基礎知識や原理を学ぶのに、もってこいの良書であり続けていると考える。
石原藤夫・金子隆一共著
(1997年 裳華房=画像左、新書版)
(2009年 早川書房から復刊=同右、文庫版。タイトルは「軌道エレベータ"ー"」に変更。下記の本文は復刊前のママ)
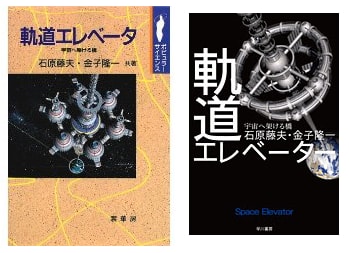 サイエンスライターの金子隆一氏と、作家の石原藤夫氏の共著による軌道エレベーター(本書では軌道エレベータ。OEVと略す)専門書。
サイエンスライターの金子隆一氏と、作家の石原藤夫氏の共著による軌道エレベーター(本書では軌道エレベータ。OEVと略す)専門書。間違いなく日本初、そしておそらくは世界初であろう単独のOEV専門書であり、本来なら筆頭に挙げるべき、OEV史上決して外せない1冊である。
現在OEV専門書の代表格はブラッドリー・C・エドワーズ氏の「宇宙旅行はエレベーターで」(ランダムハウス講談社)といえるが、同書がOEV実現構想をあらゆる側面から考察した「OEV総合計画書」とでもいうべき趣を呈しているのに対し、こちらはOEVの原理と構造を丁寧に説明した「OEV教科書」といった印象を受ける。自然科学系の教科書を数多く出している裳華房らしいとも言えるかも知れない。
あとがきにもある通り、「OEVとは何か?」を知る上での必要十分条件をまさにぴったり満たしており、この点においてエドワーズ氏の著書を凌ぐ親詳さを有している。
驚くのはそのわかりやすさ。それなりに数式が盛り込まれているのだが、地球重力圏からの脱出速度やOEVの強度など、読めば自分で計算して検証が不可能ではない程度のレベル。厚さも手ごろで、新しい知識に触れる喜びを感じ、わくわくしながら読んだものだ。
本書で説明されるOEVの基本原理は、当サイトの「軌道エレベーター早わかり」で説明している通りだが、OEVの建造プランとして小惑星を捕獲し、アンカーウェイト兼炭素材料の供給源に使用することや、昇降機にリニアを使用し、位置エネルギーを電力として回収する(つまり上りエレベーターのコストの大半を下りが供給してくれる、またはその逆)などのアイデアが大きな特徴。
金子氏はこれに先立つ「アインシュタインTV」書籍版(1991年 双葉社)、その後の「新世紀未来科学」(2001年 八幡書店)などでもこの構想に触れている。この点もエドワーズ氏と大きく異なる点だろう。小惑星については、その後もっと簡便な建造プランが多数提案されたのでもはや見られなくなった感があるが、その他の構想は10年以上経った今もOEV理論の重要な基礎を成している。
また、マスコン(重力ポテンシャルの異常箇所)にOEVの重心が徐々に引きずられてしまうという問題点(現存する静止衛星もこの問題を抱えている)を、複数のOEVを静止軌道上のリングで連結して解決するというアイデアを紹介しており、実現すれば実に理想的な構造であろう。個人的には、このオービタルリングの構想は、OEV特有の弱点である、エレベーターの上下運動の反動によるコリオリの作用の解消にも利用できると考えている。
さらに遠心投射機としてのエレベーターの価値も強調しているほか、後半では月や火星のOEV構想、非同期型軌道型のOEVや極超音速スカイフックなどのアイデアも紹介している。
アーサー・C・クラーク氏の「楽園の泉」(早川書房)でOEVを知り、この書で本格的知識を身に付けた人は多いだろう。暫定的な分類だが、この本の読者はいわばOEV支持者の「第2世代」なのではないかと感じる。K.ツィオルコフスキーやY.アルツターノフ(いずれもOEVの発想を発表した研究者)など、ゼロからOEVを発案した人々は第1世代、私のような「楽園の泉」の読者以降が第2、そして今、「宇宙旅行はエレベーターで」や、日本科学未来館制作のアニメ「宇宙エレベータ~科学者の夢みる未来~」などで増えている人たちが第3世代である。
非常に残念なことだが、本書は現在絶版状態で現在手に入らない。当時はOEVの認知度はあまりにも低く、時代がついてくるのに時間がかかり過ぎ、人々の無知の中に埋もれてしまった名著だった。だからといって古典扱いするのはふさわしくない。「宇宙旅行はエレベーターで」を翻訳した関根光宏氏も、本書で調べてOEVの価値への認識を深め、出版社に「宇宙旅行─」の日本での刊行を勧めたという。この本が欲しくて復刊を望むOEVファンは多いことだろう。
本書を、もはや最新情報に追いつかなくなった、時代遅れな書と位置づける意見も聞くが、決してそんなことはない。それらは基礎と応用の差でしなかく、本書で述べられているOEVの基礎が変化したり無効になるようなものでは決してない。本書は今なお、OEVの知識への入り口として、その基礎知識や原理を学ぶのに、もってこいの良書であり続けていると考える。














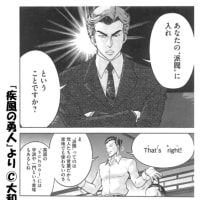






 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


