今月から始めたアイデアノートの2回目です。
今回も、私のこだわり部分であり、軌道エレベーターの本体に、いかに付随施設を設けるか、力学的に可能かという点についてです。
当サイトをご覧下さっている方の多くはブラッドリー・C・エドワーズ氏らの「宇宙旅行はエレベーターで」(ランダムハウス講談社)をお読みになっていると思います。本書のモデルで設けられている中間ステーションは、静止軌道の「ジオステーション」と末端付近の「ペントハウスステーション」のみ。ペントハウスでもプレイボーイでもいいですけど、これはカウンター質量の一部を成していて、低軌道や高軌道の任意の位置にはステーションがない。
つまるところ、第1世代のモデルで完結しているエドワーズプランでは、本体に軽量でペラペラのケーブルを使用しているので、負荷に耐えられず、静止軌道以外にステーションが造れない。現実問題として低軌道や高軌道にステーションを設けるのは不可能です。これでは、軌道エレベーターのあるべき価値の半分も有していないのではないか? なんか違うよ! ずっとそう考えてきました。
当サイトや宇宙エレベーター協会で使用している私が作った図でも、低軌道部や高軌道部にステーションを設けていますが、私なりに考えがあってやっているのです。前回述べたFontain工法によって、大きな荷重に耐えられまで一気に太くしてしまえ! というのがその一つの答えのつもりなのですが、これに加えて、今回もう一つのアイデアを紹介します。
簡単に言うと、低軌道ステーションをはじめとする、低─高軌道域に設ける様々な付随物を、静止軌道を挟んで力学的にシンメトリーにして独立させてしまうという方法です。今回の案も、軌道エレベーター学会コーナーの「Fountain式(工法)とOrbital Shield」で紹介した案を簡略化、多様化して紹介するもので、「学会」で述べたのはその一つの完成形のようなものだと考えていただければ嬉しいです。
以下、いくつかのプランを段階的に紹介します。ここでは、軌道エレベーター本体の建造方法は前回のFontain法で造るものとして話を進めます。

(1) 低軌道と高軌道のステーション同士をケーブルで繋ぐ
OEV建造の初期の段階から、低軌道と高軌道にステーションを設けることは求められと思われます。ここでは各1基ずつ設けるとします。
低軌道と高軌道のステーションを、本体とは別のケーブルで繋ぎ、静止軌道を挟んでお互いに引っ張り合う構造を持たせます。静止軌道からの距離はそれぞれ異なりますが、大きさや高度の調節、必要に応じて大小のステーションを増やしたりするなどしてバランスをとります。
これにより、各ステーションの高度維持は本体に依存せず、負荷をかけずに済みます。
(2) 低軌道部と高軌道部を繋いだケーブルを筒状に成長させる
前述の「学会」で紹介したのは構想の中心はこれです。建造方法は異なりますが、どちらでもいい。とにかく、いったん低軌道部と高軌道部をケーブル等でつないでバランスをとる構造を実現したら、線を面にして、本体に負荷をかけないまま筒状にする。本体はトンネルの中を通るような構造になるわけです。理論上は、素材の量に応じた強度に見合う範囲であれば、無限に大きくすることが可能なはずです。
筒状になって、その筒自体が様々な負荷に耐えられるほど成長したら、耐放射線構造や耐衝突構造を持たせる。これにより、軌道エレベーターの大きな課題でもある、デブリの衝突やヴァン・アレン帯に対する放射線対策を施すことを目指します。
(3) 力学的に対称性を持つリニアレールを設ける
シールドが成長する一方で、本体も成長を続けてどんどん太くなっていきます。本体が、内部を中空にするほどの太さや強度に達したら、この空洞の中に、シールド同様、静止軌道を挟んで力学的にシンメトリックな構造で、電磁気推進システムを設ける。
大きなメリットを生む軌道エレベーターの機能として、位置エネルギーの利用による電力の回収が期待されるリニア昇降システムがありますが、これを導入する最大の問題は、電磁気推進の機構自体がものすごい重さになるため、とても本体に取り付けられないという点にあります。電磁誘導体を備えたレールを敷かなければならないからです。いま一つは、ただでさえ重いリニアの乗り物を垂直方向に動かすには、相当な技術発展が必要だという点です。これは、本体を相当太くしてもなかなか解決できない問題でしょう。遠い未来でもない限り、1Gの地上からリニアで昇るというのは不可能だと思われます。
そこで、ひとまずリニアを使用するのは、重力と遠心力がが十分に小さくなる高度の間とし、この間に設けるという構想です。シールド同様、このレールもまた、本体内部にありながら、本体に負荷をかけない構造になっています。そして、素材の改良やリニアの軽量化の発展に応じてその範囲を広げていくということを想定しています。リニアを使わずして何の軌道エレベーターか!

このリニアを、シールドの方に設けても構いません。ここでの要点は、静止軌道を挟んだ力学的な対称構造によって、本体に負荷をかけずにOEVを大型化、多機能化していくことですので、色んなバリエーションが考えられます。シールドを二重三重の構造にすることも可能ですし、高度に応じて退避施設や武装、非常時に本体を補強する材料の保管庫やその展開装置などを備えることも夢ではないはずです。多様な広がりをもつものであろうと自負しておりマス、はい。
おわかりいただけると思いますが、上記(1)から(3)はすべて、設備が本体に負荷を与えない構造になっています。位置を保つために多少なりとも接続(べつにベッタリくっつけちゃってもいいですが)するでしょうが、基本的には力学的に依存していません。
つまり別の見方をすれば、地上から高軌道に達する長大なモデルと、静止軌道を挟んだ短いモデル、大きさの違う複数の静止軌道エレベーターが、力学的にそれぞれ独立した状態で同居しているのです。
上記をひとくくりにして、またまた勝手に"Orbital Shield"と名付けたわけですが、センスの悪さで失笑を買うのは覚悟しております。
軌道="Orbital"ってのをどっかに入れたかったんだよう(´Д`)
とはいえ、このオービタルシールドは、長年軌道エレベーターの情報を集め、その特有の問題点について、自分なりに思考を重ねた末、自分で考え出した一つの回答です。私はこの方法にけっこう自信を持っていて、このやり方であれば、第1世代の段階から、様々な展開や利用ができるはずだと考えています。
もちろん、高度に応じた重力と遠心力の増減率はそれぞれ異なりますし、数万kmもある軌道エレベーターは屈曲が避けられませんし、口で言うほど簡単ではないのはわかっています。ですが、前回のFountain式にしろ今回にしろ、エドワーズプランのよりも基本原理がシンプルであろう、と自負しています。シンプルな計画ほど成功率は高く、実現が早いと思うのです。
実は今回の案は、今度更新する予定の「豆知識」のテーマとリンクしています。そちらもぜひご覧ください。ここまでお読み下さり、ありがとうございました。
今回も、私のこだわり部分であり、軌道エレベーターの本体に、いかに付随施設を設けるか、力学的に可能かという点についてです。
当サイトをご覧下さっている方の多くはブラッドリー・C・エドワーズ氏らの「宇宙旅行はエレベーターで」(ランダムハウス講談社)をお読みになっていると思います。本書のモデルで設けられている中間ステーションは、静止軌道の「ジオステーション」と末端付近の「ペントハウスステーション」のみ。ペントハウスでもプレイボーイでもいいですけど、これはカウンター質量の一部を成していて、低軌道や高軌道の任意の位置にはステーションがない。
つまるところ、第1世代のモデルで完結しているエドワーズプランでは、本体に軽量でペラペラのケーブルを使用しているので、負荷に耐えられず、静止軌道以外にステーションが造れない。現実問題として低軌道や高軌道にステーションを設けるのは不可能です。これでは、軌道エレベーターのあるべき価値の半分も有していないのではないか? なんか違うよ! ずっとそう考えてきました。
当サイトや宇宙エレベーター協会で使用している私が作った図でも、低軌道部や高軌道部にステーションを設けていますが、私なりに考えがあってやっているのです。前回述べたFontain工法によって、大きな荷重に耐えられまで一気に太くしてしまえ! というのがその一つの答えのつもりなのですが、これに加えて、今回もう一つのアイデアを紹介します。
簡単に言うと、低軌道ステーションをはじめとする、低─高軌道域に設ける様々な付随物を、静止軌道を挟んで力学的にシンメトリーにして独立させてしまうという方法です。今回の案も、軌道エレベーター学会コーナーの「Fountain式(工法)とOrbital Shield」で紹介した案を簡略化、多様化して紹介するもので、「学会」で述べたのはその一つの完成形のようなものだと考えていただければ嬉しいです。
以下、いくつかのプランを段階的に紹介します。ここでは、軌道エレベーター本体の建造方法は前回のFontain法で造るものとして話を進めます。

(1) 低軌道と高軌道のステーション同士をケーブルで繋ぐ
OEV建造の初期の段階から、低軌道と高軌道にステーションを設けることは求められと思われます。ここでは各1基ずつ設けるとします。
低軌道と高軌道のステーションを、本体とは別のケーブルで繋ぎ、静止軌道を挟んでお互いに引っ張り合う構造を持たせます。静止軌道からの距離はそれぞれ異なりますが、大きさや高度の調節、必要に応じて大小のステーションを増やしたりするなどしてバランスをとります。
これにより、各ステーションの高度維持は本体に依存せず、負荷をかけずに済みます。
(2) 低軌道部と高軌道部を繋いだケーブルを筒状に成長させる
前述の「学会」で紹介したのは構想の中心はこれです。建造方法は異なりますが、どちらでもいい。とにかく、いったん低軌道部と高軌道部をケーブル等でつないでバランスをとる構造を実現したら、線を面にして、本体に負荷をかけないまま筒状にする。本体はトンネルの中を通るような構造になるわけです。理論上は、素材の量に応じた強度に見合う範囲であれば、無限に大きくすることが可能なはずです。
筒状になって、その筒自体が様々な負荷に耐えられるほど成長したら、耐放射線構造や耐衝突構造を持たせる。これにより、軌道エレベーターの大きな課題でもある、デブリの衝突やヴァン・アレン帯に対する放射線対策を施すことを目指します。
(3) 力学的に対称性を持つリニアレールを設ける
シールドが成長する一方で、本体も成長を続けてどんどん太くなっていきます。本体が、内部を中空にするほどの太さや強度に達したら、この空洞の中に、シールド同様、静止軌道を挟んで力学的にシンメトリックな構造で、電磁気推進システムを設ける。
大きなメリットを生む軌道エレベーターの機能として、位置エネルギーの利用による電力の回収が期待されるリニア昇降システムがありますが、これを導入する最大の問題は、電磁気推進の機構自体がものすごい重さになるため、とても本体に取り付けられないという点にあります。電磁誘導体を備えたレールを敷かなければならないからです。いま一つは、ただでさえ重いリニアの乗り物を垂直方向に動かすには、相当な技術発展が必要だという点です。これは、本体を相当太くしてもなかなか解決できない問題でしょう。遠い未来でもない限り、1Gの地上からリニアで昇るというのは不可能だと思われます。
そこで、ひとまずリニアを使用するのは、重力と遠心力がが十分に小さくなる高度の間とし、この間に設けるという構想です。シールド同様、このレールもまた、本体内部にありながら、本体に負荷をかけない構造になっています。そして、素材の改良やリニアの軽量化の発展に応じてその範囲を広げていくということを想定しています。リニアを使わずして何の軌道エレベーターか!

このリニアを、シールドの方に設けても構いません。ここでの要点は、静止軌道を挟んだ力学的な対称構造によって、本体に負荷をかけずにOEVを大型化、多機能化していくことですので、色んなバリエーションが考えられます。シールドを二重三重の構造にすることも可能ですし、高度に応じて退避施設や武装、非常時に本体を補強する材料の保管庫やその展開装置などを備えることも夢ではないはずです。多様な広がりをもつものであろうと自負しておりマス、はい。
おわかりいただけると思いますが、上記(1)から(3)はすべて、設備が本体に負荷を与えない構造になっています。位置を保つために多少なりとも接続(べつにベッタリくっつけちゃってもいいですが)するでしょうが、基本的には力学的に依存していません。
つまり別の見方をすれば、地上から高軌道に達する長大なモデルと、静止軌道を挟んだ短いモデル、大きさの違う複数の静止軌道エレベーターが、力学的にそれぞれ独立した状態で同居しているのです。
上記をひとくくりにして、またまた勝手に"Orbital Shield"と名付けたわけですが、センスの悪さで失笑を買うのは覚悟しております。
軌道="Orbital"ってのをどっかに入れたかったんだよう(´Д`)
とはいえ、このオービタルシールドは、長年軌道エレベーターの情報を集め、その特有の問題点について、自分なりに思考を重ねた末、自分で考え出した一つの回答です。私はこの方法にけっこう自信を持っていて、このやり方であれば、第1世代の段階から、様々な展開や利用ができるはずだと考えています。
もちろん、高度に応じた重力と遠心力の増減率はそれぞれ異なりますし、数万kmもある軌道エレベーターは屈曲が避けられませんし、口で言うほど簡単ではないのはわかっています。ですが、前回のFountain式にしろ今回にしろ、エドワーズプランのよりも基本原理がシンプルであろう、と自負しています。シンプルな計画ほど成功率は高く、実現が早いと思うのです。
実は今回の案は、今度更新する予定の「豆知識」のテーマとリンクしています。そちらもぜひご覧ください。ここまでお読み下さり、ありがとうございました。











 銀河英雄伝説
銀河英雄伝説 1. 本作に登場する軌道エレベーター
1. 本作に登場する軌道エレベーター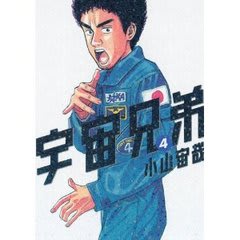 宇宙兄弟
宇宙兄弟 一昨日からきょうまで、千葉で開かれた宇宙エレベーター協会(JSEA)主催の技術競技会に参加してきました。昨年より1日多い3日間、暑い上に早朝から始めたので体力的にもしんどく、けっこうトラブルも多く大変でした。
一昨日からきょうまで、千葉で開かれた宇宙エレベーター協会(JSEA)主催の技術競技会に参加してきました。昨年より1日多い3日間、暑い上に早朝から始めたので体力的にもしんどく、けっこうトラブルも多く大変でした。
 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。



