民間月面着陸 来年再び挑戦
宇宙スタートアップのispace(アイスペース)が民間初を目指して26日に挑んだ月着陸船による月面着陸は失敗した。日本勢の「月面ビジネス」始動はお預けとなったが、宇宙開発に失敗はつきものだ。アイスペースは着陸直前までのデータを収集しており、失敗を糧に民間ならではのスピード感で2024年の再挑戦を目指す。
(日経新聞2023/4/27 一部抜粋)
注目されていたispaceの月面着陸ですが、発表を見る限り、ランダー(着陸機)が降下中に地表までの距離の測定を誤り、いわば地面スレスレで最後にひと吹きするための推進剤を、もっと高い位置で使い切ってしまい、あとは自由落下して地面に衝突したと考えられるようですね。
これが大気のある天体なら、パラシュートも併用して軟着陸を図ることができますが、いかんせん月面はほぼ真空ですので、移動は推進剤の噴射で制御するほかありません。いくら月の表面重力が地球のおよそ1/6で弱いといっても、仮に高度100mで最後の噴射をしていったん静止状態になったとして、そこから自由落下したらおよそ時速65km衝突することになると思われます。とにかくも本当に惜しまれます。

9年前にHAKUTO(そのころは「HAKUTO」に「R」がなかった)を取材したことがありまして、現ispaceCEOの袴田武史さんにお話をうかがいました。今やすっかり時の人となり、先方はもう覚えておいでではないでしょうが。
当時はランダーではなく、着陸後に月面を走り回るローバーの開発がもっぱら話題の中心で、試作機を見せてもらい、その後、会見などで展示される度に段々改良されていくのを興味深く拝見しました。そのころは月への到達が遥かな道のりに見えましたが、事業が拡大して遠い存在のようにもなりつつも、着実に邁進していく様子を応援する持ちも込めて注目しておりました。
それだけに、本当に最後の一歩で断念せざるをえなかったのは、どれほど無念だったことかと、見ているこちらも非常に残念に感じます。
同社の取り組みを見ていると、「できることと、できないことがある」のではなく、「できるまでやる」のが大事であり、万事に通底する姿勢だよな、と再認識させられます。
今回の知見を活かし、報道にある通りぜひ再チャレンジしてほしいものです。
宇宙スタートアップのispace(アイスペース)が民間初を目指して26日に挑んだ月着陸船による月面着陸は失敗した。日本勢の「月面ビジネス」始動はお預けとなったが、宇宙開発に失敗はつきものだ。アイスペースは着陸直前までのデータを収集しており、失敗を糧に民間ならではのスピード感で2024年の再挑戦を目指す。
(日経新聞2023/4/27 一部抜粋)
注目されていたispaceの月面着陸ですが、発表を見る限り、ランダー(着陸機)が降下中に地表までの距離の測定を誤り、いわば地面スレスレで最後にひと吹きするための推進剤を、もっと高い位置で使い切ってしまい、あとは自由落下して地面に衝突したと考えられるようですね。
これが大気のある天体なら、パラシュートも併用して軟着陸を図ることができますが、いかんせん月面はほぼ真空ですので、移動は推進剤の噴射で制御するほかありません。いくら月の表面重力が地球のおよそ1/6で弱いといっても、仮に高度100mで最後の噴射をしていったん静止状態になったとして、そこから自由落下したらおよそ時速65km衝突することになると思われます。とにかくも本当に惜しまれます。

9年前にHAKUTO(そのころは「HAKUTO」に「R」がなかった)を取材したことがありまして、現ispaceCEOの袴田武史さんにお話をうかがいました。今やすっかり時の人となり、先方はもう覚えておいでではないでしょうが。
当時はランダーではなく、着陸後に月面を走り回るローバーの開発がもっぱら話題の中心で、試作機を見せてもらい、その後、会見などで展示される度に段々改良されていくのを興味深く拝見しました。そのころは月への到達が遥かな道のりに見えましたが、事業が拡大して遠い存在のようにもなりつつも、着実に邁進していく様子を応援する持ちも込めて注目しておりました。
それだけに、本当に最後の一歩で断念せざるをえなかったのは、どれほど無念だったことかと、見ているこちらも非常に残念に感じます。
同社の取り組みを見ていると、「できることと、できないことがある」のではなく、「できるまでやる」のが大事であり、万事に通底する姿勢だよな、と再認識させられます。
今回の知見を活かし、報道にある通りぜひ再チャレンジしてほしいものです。













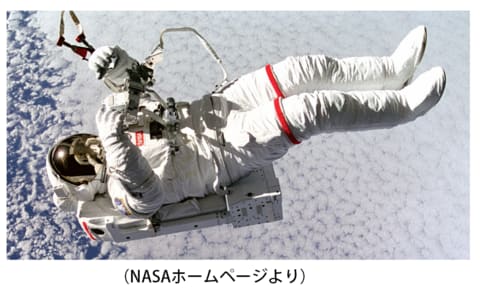

 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


