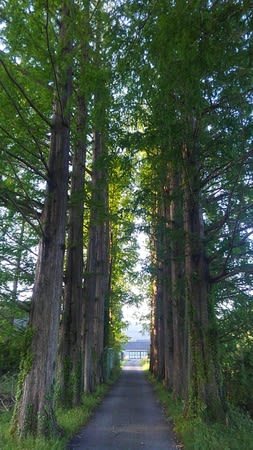朝の連ドラ「ごちそうさん」あたりから、それとそれに続く「あさイチ」の有働アナとイノッチたちの感想を見ないと、その日が始まらない様になってる。掛け合い漫才みたいなところがあって、ついつい見なきゃとなる。それが、もちろん悪意あっての発言ではないが、「だんだん畑に行くのが遅くなっちゅう」と周囲のオンチャンたちの噂話を生む。言い訳しないの? 連ドラとあさイチを見たいがためにって言える? だいたい、本人だって、野菜たちが待ってると焦ってる。どちらに重点を置くのかって、聞かれたら・・・。まぁまぁ、答えぬが華、か。で、あるところであるが、この「あさイチ」、朝にしては重いテーマ、があるときある。例えば、今朝のテーマもそう。「女性リアル どう思う?“子どもがいない”生き方」。数か月前に、女優・山口智子さんが雑誌のインタビューに答えた言葉。NHKのサイトから拾うとこんな文句:
「子どもを産んで育てる人生ではない、別の人生を望んでいました。今でも、一片の後悔もないです」、 女優、山口智子さんが雑誌のインタビューに答えた言葉が、今、多くの女性の支持を得ています。夫婦の生活を大事にしたい、経済的に子育ては無理・・・。 さまざまな理由で子どもがいない人生を選択する女性たち。 しかし、「女は子どもを産んで一人前」という価値観が生み出す“子なしハラスメント”に、日々直面します。 さらに、不妊治療が身近になったことで、「妊娠するための努力」を求められることも・・・。 “子どもがいる幸せ”があれば、“子どもがいない幸せ”もあっていいのでは? “オンナの幸せ”について、トコトン考えます(スペースや改行は庵主が入れた)!
早く山に上がりたかった。ところが、いつものように見ていたら、こんなテーマで「連ドラ」の話しのあと、ふるさと納税に関する有働アナのコメント(結構、これはこれでかなりイケてた)に続き始まった。「“子どもがいる幸せ”があれば、“子どもがいない幸せ”もあっていいのでは」、あれ? どうしてそれが“オンナの幸せ”の議論になるん? つまり、なぜ“オンナの”になる? 子供がいる・いないの問題は、“オンナ”だけが背負うことじゃない、抱え込むものじゃない。“オトコ”だってかかわってる。「いない幸せ」をどのように選んだのか、「いる幸せ」をどのように選んだのか。その選択の時に、どうだったのか。今朝は気が急いていたせいか、聞き逃したろう。が、結局「自分(女性)のキャリアとの兼ね合い」「(女性視視点での)夫婦の生活を大切」ばかりが耳に残る。
とっても個人的なことになるが、怒られること・批判されることを承知で言おう。「いない幸せ」は“オンナ”にしか選べない。“オトコ”には「いない幸せ」の選択はできない。もちろん、パートナーだったら話に話を重ね理解しあう。で、「いない」ことに同意はできる。だが、だが、だがなんだ、そこにやがてギャップがあると気付くこともある。タイミングがあわなかったと言われたら? 子を「産める」のは“オンナ”しか持てないこと、“オトコ”には何ともしがたい。人類は「未来」を捨て始めたんだろか。だいいち、「子供」という「将来を担う資産」が「いる幸せ」「いない幸せ」と議論される自体、社会が狂ってきてないだろか。「いる幸せ」「いない幸せ」を、‟オンナ目線“だけじゃなく‟オトコ目線”も入れ、一つの番組にして議論せねばならなくなったじゃないだろか。
今日の一枚:麦を収穫した、稲架を立てた。16時ころ、圃場にて。
今日のもう一枚:ロメインレタスが、残り8株になってしまった。薬は使わぬ、昔はどうしてた?ネットで調べると糠に卵の殻。試すしかない。ロメインレタスの株下に卵の殻を蒔く。
お次はパクチーの根元に卵の殻。

で、トマトやキュウリには米糠を。