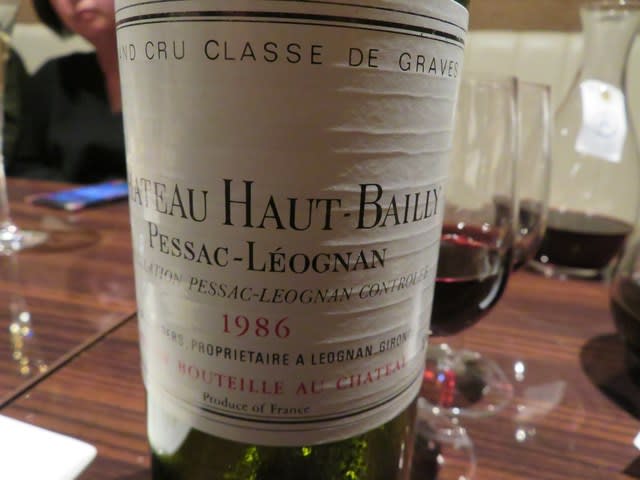これは若人たちとワインを飲もう、という秘密会があって、その時にタケちゃんがブラインドで持って来たものだ。
どうも当方がルーシー・マルゴーを持って行くと言ったので、このセレクトになったようなのだ。
そんなことなどトーゼン知らないワタクシは、えれえレベルのブルゴーニュ・ピノノワールなのだろう、と信じて疑わなかった。
しかも物凄く古いヤツ♪
それはナゼかと言えば、シュッとしたボディに香りが正しくブルピノ熟成香の最たる物で、エロスありの、オレンジのピールありの、熟したプラムの様相まであると来たもんだ!

じゃあそれは何だと思う?と聞かれれば、ミッシェル・ゴーヌーあたりの90年代のクロ・デ・ゼプノーと答えたかもしれない。
だから心底オッタマゲの状態になったのは説明するまでも無い。
まあこれは後で分ったことなのだけれど、ニュージーランドでは知る人ぞ知る1980年設立の由緒あるドメーヌとのこと。
それにしても、ニュージーとは・・・
人知の仕業は実にも恐ろしき物かな、ということなのだろう。
どうも当方がルーシー・マルゴーを持って行くと言ったので、このセレクトになったようなのだ。
そんなことなどトーゼン知らないワタクシは、えれえレベルのブルゴーニュ・ピノノワールなのだろう、と信じて疑わなかった。
しかも物凄く古いヤツ♪
それはナゼかと言えば、シュッとしたボディに香りが正しくブルピノ熟成香の最たる物で、エロスありの、オレンジのピールありの、熟したプラムの様相まであると来たもんだ!

じゃあそれは何だと思う?と聞かれれば、ミッシェル・ゴーヌーあたりの90年代のクロ・デ・ゼプノーと答えたかもしれない。
だから心底オッタマゲの状態になったのは説明するまでも無い。
まあこれは後で分ったことなのだけれど、ニュージーランドでは知る人ぞ知る1980年設立の由緒あるドメーヌとのこと。
それにしても、ニュージーとは・・・
人知の仕業は実にも恐ろしき物かな、ということなのだろう。