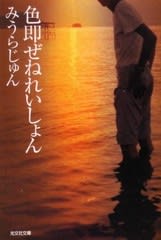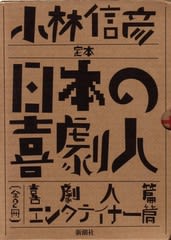<いつか、渥美清のテレビ番組にゲスト出演して、変装してストリップを見にゆく小心なユーモア小説家を演じていたが、こういうインテリ役をやったら彼の右に出る者がない。
すなわち、森繁は、二枚目半というタイプを自ら開拓したのであり、彼が念じていたとおり、<喜劇によし、悲劇によし>というユニークな役者として大成した。……が、『三等重役』から『夫婦善哉』へのチェンジが--すなわち、上質なコメディアンから性格俳優への変化が、あまりに鮮やかだったので、その後の日本の喜劇人にとんでもない異変を起こさせたのである。
<森繁病>と私が呼んでいるこの病状は、まず、一人の喜劇人が、彼を売り出すに至った原因である<動き>を止めることに始まる。パーキンソン氏病みたいなものである。(中略)--これが第一期。
第二期は、その存在理由であるところの珍芸・扮装・奇抜な動きを全部やめてしまい、それをどうしてもやらねあならぬときは、しぶしぶ、ふてくされてやる。
(まだ、こんなこと、やってます……)といった、照れた、しかし、若干、誇らしげな眼で、こちらを見る。
第三期になると、赤ん坊を抱いたり、踊り子や花売り娘を遠くから眺め、夜道をとぼとぼと去ってゆくピエロといった役を、大張りきりで演ずるようになる。(中略)
第四期--以上のような芝居は、チャップリンが……あるいはモリシゲがやったことであるからして、当然、そのタレントは人気を失ってゆく。(モリシゲは、運が良かったんだ!)と心の中で叫びながら。(中略)
人を笑わせるという結果においては似ているかも知れないが、ジャック・レモンとジュリー・ルイスが、ちがうジャンルの人であるように、森繁は<別格>なのである。
コメディアンから演技派に転身したという一点だけをとりあげて、他人がその生き方を真似ようとするのは、無謀、命とりというほかなく、森繁のインテリぶりを真似て、随筆を書いたり、涙ぐましい次第である。(しかも、森繁の長い不遇期間は計算に入っていないのだから、ムシがいい。>
(小林信彦『日本の喜劇人』第三章 森繁久弥の影 新潮文庫より)
すなわち、森繁は、二枚目半というタイプを自ら開拓したのであり、彼が念じていたとおり、<喜劇によし、悲劇によし>というユニークな役者として大成した。……が、『三等重役』から『夫婦善哉』へのチェンジが--すなわち、上質なコメディアンから性格俳優への変化が、あまりに鮮やかだったので、その後の日本の喜劇人にとんでもない異変を起こさせたのである。
<森繁病>と私が呼んでいるこの病状は、まず、一人の喜劇人が、彼を売り出すに至った原因である<動き>を止めることに始まる。パーキンソン氏病みたいなものである。(中略)--これが第一期。
第二期は、その存在理由であるところの珍芸・扮装・奇抜な動きを全部やめてしまい、それをどうしてもやらねあならぬときは、しぶしぶ、ふてくされてやる。
(まだ、こんなこと、やってます……)といった、照れた、しかし、若干、誇らしげな眼で、こちらを見る。
第三期になると、赤ん坊を抱いたり、踊り子や花売り娘を遠くから眺め、夜道をとぼとぼと去ってゆくピエロといった役を、大張りきりで演ずるようになる。(中略)
第四期--以上のような芝居は、チャップリンが……あるいはモリシゲがやったことであるからして、当然、そのタレントは人気を失ってゆく。(モリシゲは、運が良かったんだ!)と心の中で叫びながら。(中略)
人を笑わせるという結果においては似ているかも知れないが、ジャック・レモンとジュリー・ルイスが、ちがうジャンルの人であるように、森繁は<別格>なのである。
コメディアンから演技派に転身したという一点だけをとりあげて、他人がその生き方を真似ようとするのは、無謀、命とりというほかなく、森繁のインテリぶりを真似て、随筆を書いたり、涙ぐましい次第である。(しかも、森繁の長い不遇期間は計算に入っていないのだから、ムシがいい。>
(小林信彦『日本の喜劇人』第三章 森繁久弥の影 新潮文庫より)