皇帝ダリアが咲いています。

花数がふえて、今年は約30輪。

高さは4メートルくらいあります。

ピンクの花は片手を拡げたより大きくて、
青空とのコントラストにほれぼれ。


この場所が気に入ってくれてようで、
花が終わると地上部は枯れますが、
根は生きていて、春になると芽を出してぐんぐん大きくなります。

年を重ねると株が大きくなって、
茎数と花が増えるようです。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで、
土曜日の朝日新聞beに掲載される
連載「悩みのるつぼ」の回答者は上野千鶴子さんでした。
おひとりさまで生きる女性への的確なアドバイスです。

最後まで読んでくださってありがとう
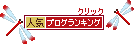
人気ブログランキングへ
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね


花数がふえて、今年は約30輪。

高さは4メートルくらいあります。

ピンクの花は片手を拡げたより大きくて、
青空とのコントラストにほれぼれ。


この場所が気に入ってくれてようで、
花が終わると地上部は枯れますが、
根は生きていて、春になると芽を出してぐんぐん大きくなります。

年を重ねると株が大きくなって、
茎数と花が増えるようです。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで、
土曜日の朝日新聞beに掲載される
連載「悩みのるつぼ」の回答者は上野千鶴子さんでした。
おひとりさまで生きる女性への的確なアドバイスです。
| 【悩みのるつぼ】女ひとり生きるには何が必要? 2015年11月28日 朝日新聞be 相談者 女性 43歳 当方は、いま43歳になる独身の女性です。 私は43歳の今の今まで、一度たりとも恋人がいたことがありません。 おつきあいした男性も一人もいません。 でもそれでも、自分には恋人がいないのが当たり前の状態になっていたので、その辺はとくに寂しくもなく、楽しんで生きていますログイン前の続き。 そんなこんなの私なのですが、悩みがあります。 というのは、この分だと、当然この先も、ずっと女ひとりで生きてゆかなくてはならないと思うからです。さらに、そのうえにいろいろな問題も重なってきます。 私の母はすでに亡くなっています。 私は一人っ子なので、これからはきっと父親を介護するという問題も出てくると思います。さらに、これは当然ですが、自分自身の老後はどう迎え、どう過ごせばいいのか、という問題も出てきます。 そこで上野先生にお聞きしたいと思います。 女がひとりで生きていくために絶対に必要なもの、大切なものは何でしょうか。 そして、今の年齢のころから将来のために備えていたほうがいいものは、何かありますでしょうか。 教えていただけたら、さいわいです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○回答者 社会学者・上野千鶴子 親介護で離職や同居はダメ おめでとうございます、43歳までこの道一筋、何の迷いもなくおひとりさま街道を歩んでこられたのですね。お仕事も収入も確保しておられるようですし、友人や趣味にも恵まれて「楽しんで」生きていらっしゃるご様子。おひとりさまのかがみです。 そう、これまでおひとりさまで生きてきた実績と自信のあるあなたは、これから先だっておひとりさまで生きていけます。もしこれから結婚だの出産だのがありうるとしたら、その分、介護リスクと育児リスクを背負うだけ。将来の夫と夫の両親の介護負担に加え、還暦になっても成人しない子どもの育児負担を抱えるほうがずっと不安要因が高くなります。これまでだって低リスクの生活を選んできたのですから、今さら高リスクの人生を選択する必要はないでしょう。 不安なのは加齢に伴う親の介護と自分自身の老後。このふたつは誰にでも降りかかってきます。残された父の介護は、ご本人の年金がおありでしょうからそれで負担してもらいましょう。子どもの役割は手や足を出すことではなくここぞというところで意思決定する司令塔の役割を果たすこと。自分自身の老後の予行演習にもなりますから、介護保険のことはしっかり勉強して使いこなしてください。 まちがっても介護離職や同居をしないこと。あなたの老後を心配してくれるのは、親ではなくあなた自身だけ。要介護になった親は自分のことでアタマがいっぱい。子どもに対する配慮など吹き飛んでしまう、と観念してください。同居をすれば追いつめられて余裕を失います。別居して通いでパート介護すればじゅうぶん。残りの時間をサポートしてもらえるのが介護保険。不足分は自己負担でサービスを購入し、それでも足りなければ資産をフロー化しましょう。どのみち親の金ですから親のよいように使ってもらいましょう。 で、その経験があなたの老後の教訓になります。老齢年金、健康保険、介護保険の3点セットを手放さず、自分の住まいを確保しておくこと。日本の高齢者福祉は諸外国にくらべて決して低くありません。問題は、この3点セットが、この先、切り崩されるかもしれないこと。それを引きおこすのは政治という名の人災です。あと、いくらかの蓄えと、孤独が怖ければ人持ちになること。費用がいくらでもないことは新刊の『おひとりさまの最期』(朝日新聞出版)を参照してください。 |

最後まで読んでくださってありがとう

人気ブログランキングへ
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね



















 水分が多いので、パスタもそのまま投入。
水分が多いので、パスタもそのまま投入。



 クリックを
クリックを




























































