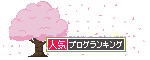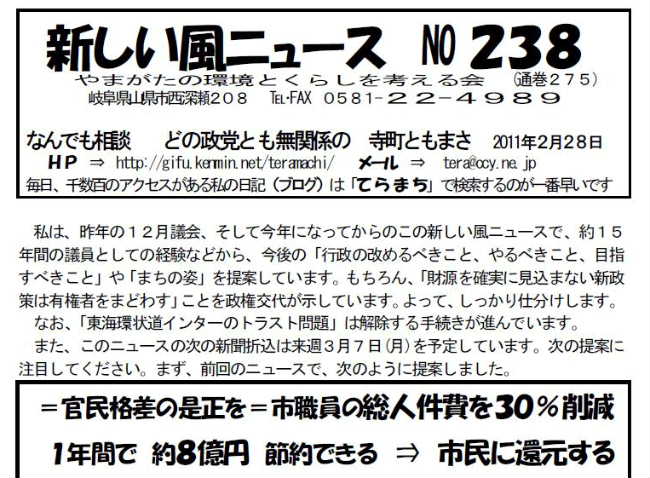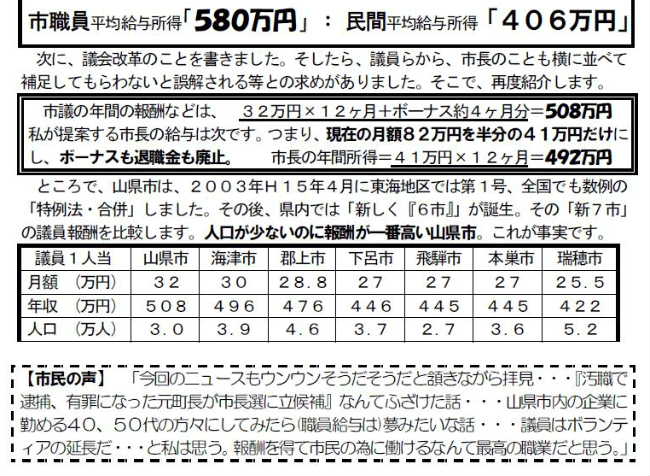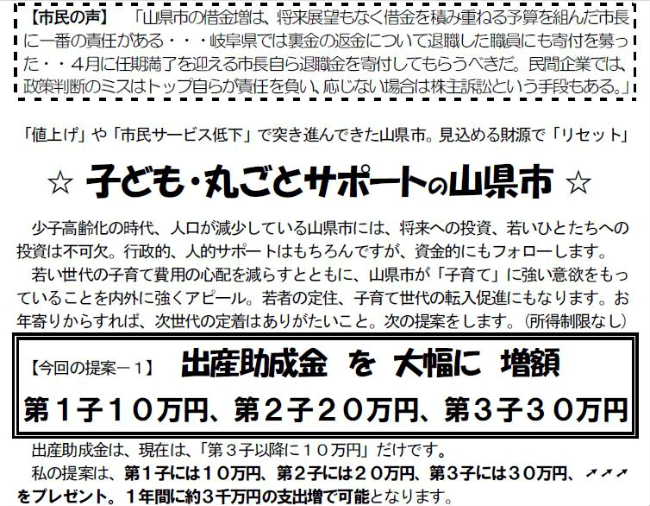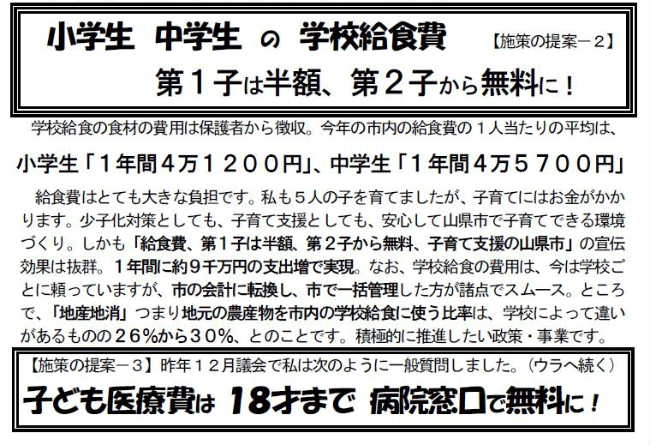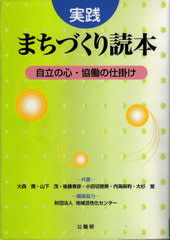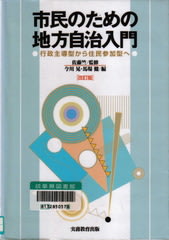民主党の新代表に野田氏が決まった同じ日、
文部科学省が福島第一原発から半径100キロ圏内の土壌の汚染度を調べた地図を公表した。
わたしには、次の総理大臣より、このニュースのほうがよほど重要だ。
こういう重大事は、政局のどさくさに紛れて公表するのはいつものことか。
朝日新聞は、今朝の社会面に地図入りの記事が載っていた。
文科省が公表したセシウム汚染土壌マップについて - NAVER まとめ
【文部科学省放射線モニタリング情報】
文部科学省および栃木県による航空機モニタリングの調査結果について(2011.7.27 文部科学省)
ドイツZDF-Frontal21 福島原発事故、その後(日本語字幕) (2011.8.28)
ドイツのTV局ZDF「フロンタール21」シリーズが 8/26 放送した番組 Die Folgen von Fukushima。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
セシウムの土壌汚染は、34地点でチェルノブイリ移住基準を超えているというのに、
野田新代表からは何のコメントもない。
っていうか、この人は「脱原発」ではなく、むしろ、既存の原発の再稼働にも意欲を見せている。
野田氏は今日の午後、第95代首相になったが、代表選に向けた政権構想の中で
「安全性を確認した原子力発電所の活用により、エネルギー制約を克服し、電力の安定供給を確保する」とした。
この一点だけでも、わたしは、野田新首相を支持できない。
原発政策の行方は 民主党新代表選出(2011年08月30日 朝日新聞)
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

文部科学省が福島第一原発から半径100キロ圏内の土壌の汚染度を調べた地図を公表した。
わたしには、次の総理大臣より、このニュースのほうがよほど重要だ。
こういう重大事は、政局のどさくさに紛れて公表するのはいつものことか。
朝日新聞は、今朝の社会面に地図入りの記事が載っていた。
| セシウム汚染土壌マップ発表 文科省、原発百キロ圏内 2011年8月29日 朝日新聞  東京電力福島第一原発から半径100キロ圏内の土壌の汚染度を調べた初の地図を、文部科学省が29日公表した。全国の大学や専門機関が約2200カ所の土を採取し、事故から3カ月後の放射性セシウムの濃度を調べた。除染や避難区域の見直しなどの基礎資料とする。 東京電力福島第一原発から半径100キロ圏内の土壌の汚染度を調べた初の地図を、文部科学省が29日公表した。全国の大学や専門機関が約2200カ所の土を採取し、事故から3カ月後の放射性セシウムの濃度を調べた。除染や避難区域の見直しなどの基礎資料とする。 文科省の調査には延べ129機関、780人が協力した。80キロ圏内は2キロ四方、80~100キロ圏内は10キロ四方に1カ所の割合で、それぞれ5地点で深さ5センチの土を採取。6月14日時点の、半減期が2年のセシウム134と、30年の137の値を出した。 汚染度が高い地域は、原発から北西方向の半径40キロ圏内に集中していた。最も高い大熊町の1地点では、セシウムの合計値は1平方メートルあたり約3千万ベクレルに上った。 チェルノブイリ原発事故では、55万5千ベクレルを超えた地域は「強制移住」の対象となった。今回の調査では、この値を超えた場所は約8%に上った。多くは警戒区域や計画的避難区域などに指定されている地域だが、福島市や本宮市、郡山市などの一部でも超えていた。 チェルノブイリでは、汚染地図が完成したのは事故3年後だった。 一方、農林水産省は29日、福島、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉の6県の579地点を調査した農地の汚染地図をまとめた。このうち、福島県内の40地点で、イネの作付け禁止の基準を超える汚染が確認された。基準を超えて汚染された農地の面積は、推計で8300ヘクタールにのぼるとした。また、福島県は同日、警戒区域内の水田の放射線量を初めて調査した結果を発表。警戒区域、計画的避難区域などの計89地点のうち20地点でイネの作付け基準を超えた。 |
文科省が公表したセシウム汚染土壌マップについて - NAVER まとめ
【文部科学省放射線モニタリング情報】
文部科学省および栃木県による航空機モニタリングの調査結果について(2011.7.27 文部科学省)
ドイツZDF-Frontal21 福島原発事故、その後(日本語字幕) (2011.8.28)
ドイツのTV局ZDF「フロンタール21」シリーズが 8/26 放送した番組 Die Folgen von Fukushima。
| 土壌汚染、34地点がチェルノブイリ移住基準超 東京電力福島第一原子力発電所事故で拡散した放射性物質による土壌汚染の状態を調べた地図がまとまり、29日に開かれた文部科学省の検討会で報告された。 立ち入りが制限されている警戒区域や計画的避難区域で、チェルノブイリ原発事故での強制移住基準(1平方メートル当たりの放射性セシウム137が148万ベクレル)を超える汚染濃度が測定されたのは、6市町村34地点に上った。住民の被曝(ひばく)線量などを把握するのが狙い。菅首相が27日、「長期間にわたり住民の居住が困難になる地域が生じる」との見通しを示したが、それを裏付けた。 測定結果によると、6月14日時点で、セシウム137の濃度が最も高かったのは、警戒区域内にある福島県大熊町の1平方メートル当たり約1545万ベクレル。セシウム134と合わせると、同約2946万ベクレルとなった。 同300万ベクレル超となったのは、セシウム137で同町、双葉町、浪江町、富岡町の計16地点に上った。高い濃度の地点は、原発から北西方向に延びており、チェルノブイリ事故の強制移住基準を超える地点があった自治体は、飯舘村、南相馬市を加えた計6市町村だった。同省は約2200地点の土壌を測定した。 (2011年8月30日03時05分 読売新聞) |
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
セシウムの土壌汚染は、34地点でチェルノブイリ移住基準を超えているというのに、
野田新代表からは何のコメントもない。
っていうか、この人は「脱原発」ではなく、むしろ、既存の原発の再稼働にも意欲を見せている。
野田氏は今日の午後、第95代首相になったが、代表選に向けた政権構想の中で
「安全性を確認した原子力発電所の活用により、エネルギー制約を克服し、電力の安定供給を確保する」とした。
この一点だけでも、わたしは、野田新首相を支持できない。
原発政策の行方は 民主党新代表選出(2011年08月30日 朝日新聞)
| 民主・野田新代表 脱原発 議論素通り 民主党代表選の決選投票で「親小沢派」の海江田万里氏を破り、次期首相となる新代表に選ばれた野田佳彦氏。「ノーサイドにしましょう、もう」と党内融和を呼び掛けたが、代表選の舞台では原発を含むエネルギー政策について一言も発しなかった。菅直人首相が宣言した「脱原発依存」の行方はどうなるのか。震災復興は加速させられるか。有権者には不安と期待が交錯する。 民主党代表選の論戦では、「脱原発依存」をめぐる議論は深まらず、子どもを抱える母親や新エネルギー産業の関係者からは、期待と失望が入り交じった声が聞かれた。 「どの候補が『脱原発』を推進してくれるのか」-。二児の母の伊藤恵さん(41)は二十九日、東京都葛飾区の自宅で、期待を込めながら、五人の候補が演説する様子をテレビで見ていた。 しかし、原発存続の是非やエネルギー政策について自説を展開した候補はなく、「避けて通れない大事な問題なのに、どうして誰も触れないのか。不利になることを恐れているのだろうか」といぶかしんだ。 福島第一原発事故の後、高い放射線量が都内で計測されたとの情報を知って、放射線から子どもを守るための活動に取り組んできた。 新代表となった野田佳彦氏はこれまで、「新しい原発をつくることは困難」とする一方、現存する原発は「安全チェックして、再稼働できるものはしていく」としている。 「経済や財政問題を優先する人。原発問題では期待できないのでは」と話す伊藤さんは、こう注文をつけた。「原発を止めないと、安心して暮らせない。少なくとも、現在止まっている原発はそのままにしてほしい」 十八歳まで故郷の福島県いわき市で過ごし、今は千葉県内で夫(31)と娘(1つ)と暮らす主婦(26)は「脱原発依存は良いことだが、国民の関心を引くためにとりあえず出た話のように思える」と話した。 原発事故で、関東も放射能で汚染されていたことを知り「娘に影響が出たらと不安になった」。市民団体が開く勉強会などに参加するうちに知り合った専門家と、小さな勉強会も開いた。 主婦は「原発は次の世代に負の遺産を残す。新政権には、限りある資源を上手に使っていく社会をつくってほしい」と期待した。 仙台市で光の吸収に有機化合物を使う太陽電池の開発をしている「イデアルスター」の表研次・副社長(43)は「日本の新エネルギー技術を集めれば原発分の電気は作れる。発電コストはかかるかもしれないが、原発事故の処理費用などを考えればどっちもどっち」。 脱原発依存については「新首相次第。新エネルギー産業を復興、雇用対策の柱にしてほしい」と訴えた。 |
| 海江田氏、なぜ敗れたのか…1回目投票で1位 29日の民主党代表選は、1回目の投票で1位だった海江田万里経済産業相を、野田佳彦財務相が決選投票で破る大逆転劇となった。 野田氏は、下位の陣営とどのように連携を組んだのか。党内最大の小沢一郎元代表グループの支援を受け、基礎票で優位に立っていた海江田氏はなぜ敗れたのか。逆転の構図を検証する。 ◆糾合◆ 「決選投票になったら、『非海江田』で票を集中させたい」 29日朝、国会内で開かれた菅首相グループの会合。座長の江田法相は約30人の出席者にこう呼びかけ、了承を取りつけた。 菅グループは、代表選の対応を自主投票としていたが、菅首相の意向もあり、「反小沢」では一致していた。党内では「海江田氏が1位となるものの、過半数には至らない」との見方が大勢だった。 「野田氏と前原誠司前外相の陣営はともに票の上積みに必死で、決選投票となった場合の戦略を立てるに至っていない」と見た江田氏は、野田、前原両陣営に「決選投票では野田、前原両氏のいずれか上位となった候補に投票する」という「海江田包囲網」を事前に打診し、両陣営も「当然の行動」と受け止めた。 野田グループも独自に「多数派工作」に動いた。 野田氏の選対本部長を務める藤村修幹事長代理は29日朝、鹿野氏の選対本部長である大畠国土交通相に対し、決選投票での「野田、前原、鹿野連合」の実現を要請した。 鹿野陣営には小沢グループの議員も多かったが、告示後には会合に顔を出さなくなったため、鹿野陣営は「小沢グループの引きはがし方はひどい」(大畠氏)と反発を強めていた。藤村氏の要請は、鹿野陣営に「あうんの呼吸」で受け入れられた。29日夜、鹿野陣営は、東京・赤坂の中華料理店で開いた「打ち上げ」に駆けつけた藤村氏を大きな拍手で招き入れた。 前原グループでは、仙谷由人代表代行(官房副長官)が、藤村氏や、小沢元代表を党員資格停止処分に追い込んだ岡田幹事長と連絡を取り合い、決選投票での糾合に力を入れた。 「行司役」という立場から表立った行動は控えていた岡田氏は、代表選終了後、周辺に笑顔でこう語った。 「僕らが描いたシナリオ通りになったな」 ◆誤算◆ 小沢元代表グループも露骨な多数派工作を行った。 「決選投票では海江田氏をお願いしたい。海江田氏に入れてくれれば、あなたの政務三役入りは約束する」 元代表の側近は、参院の中堅議員にポストを示して、支持を求めた。 29日朝には、決選投票に残れないと悟った馬淵氏が選対の会合で「決選投票では海江田氏を支持する」と表明したが、党内では「馬淵氏は、決選投票での『海江田氏支持』を条件に小沢グループから推薦人を借りていたのではないか」との見方も広がった。 小沢グループの手法には、「ポストを約束してくれるのは小沢グループだけだ」と歓迎する者もいれば、「古い自民党総裁選を見ているようだ」と反発を強める議員もいた。 (2011年8月29日21時19分 読売新聞) |
最後まで読んでくださってありがとう


 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね