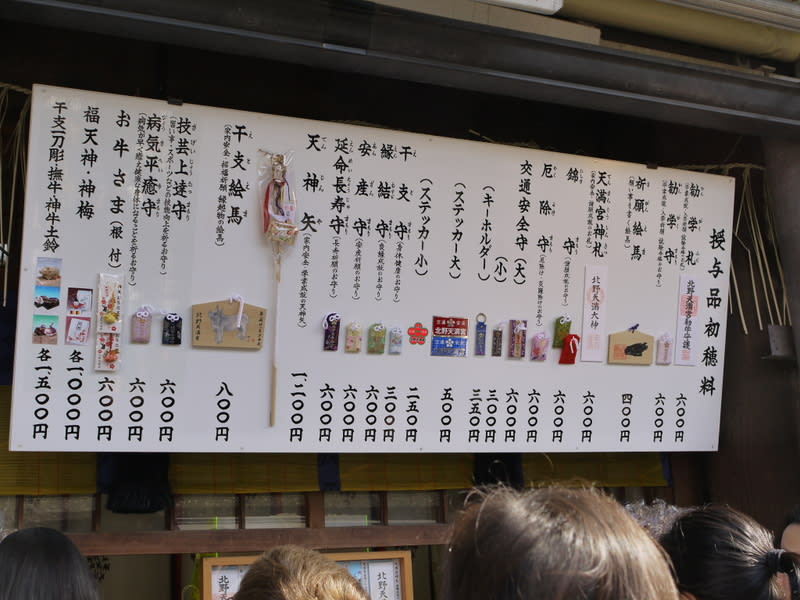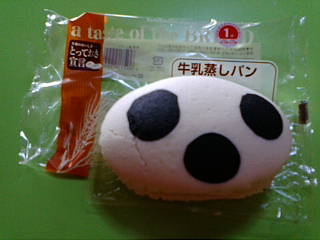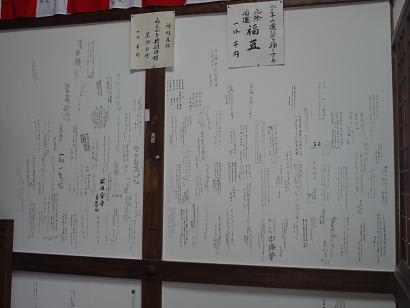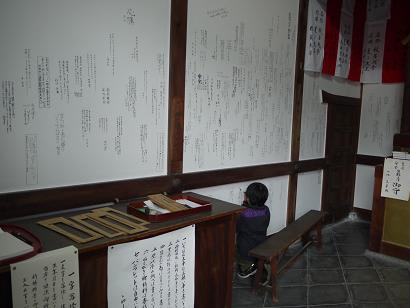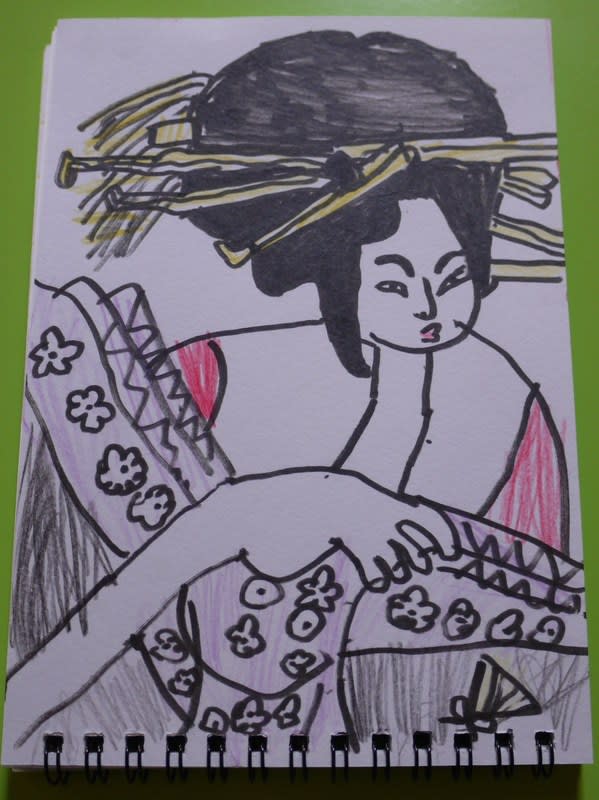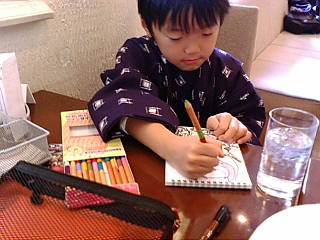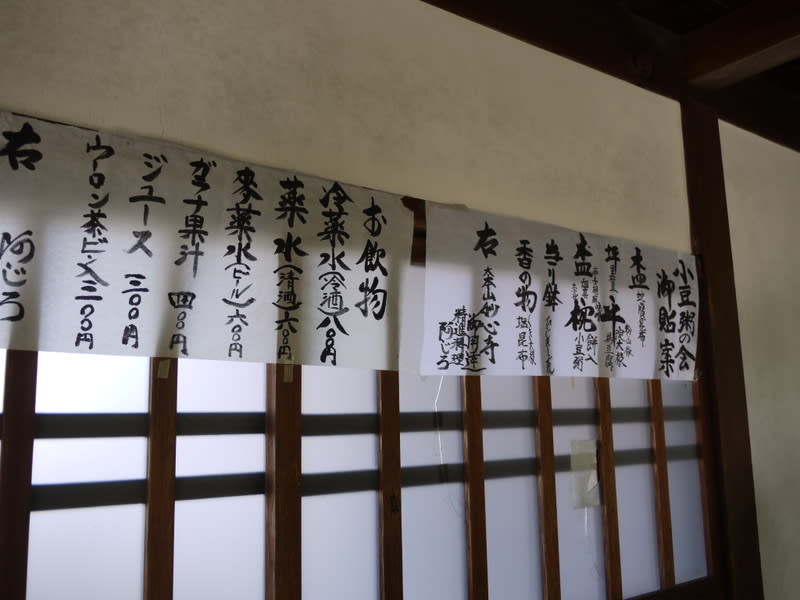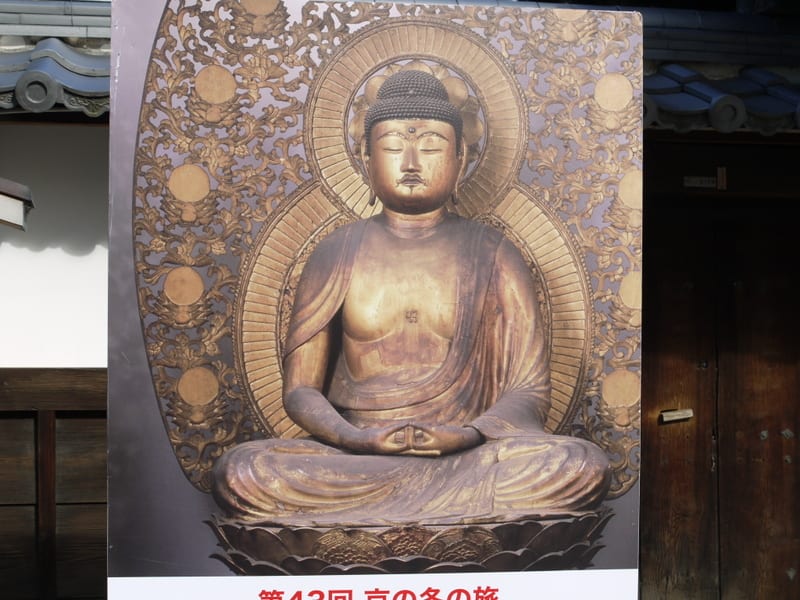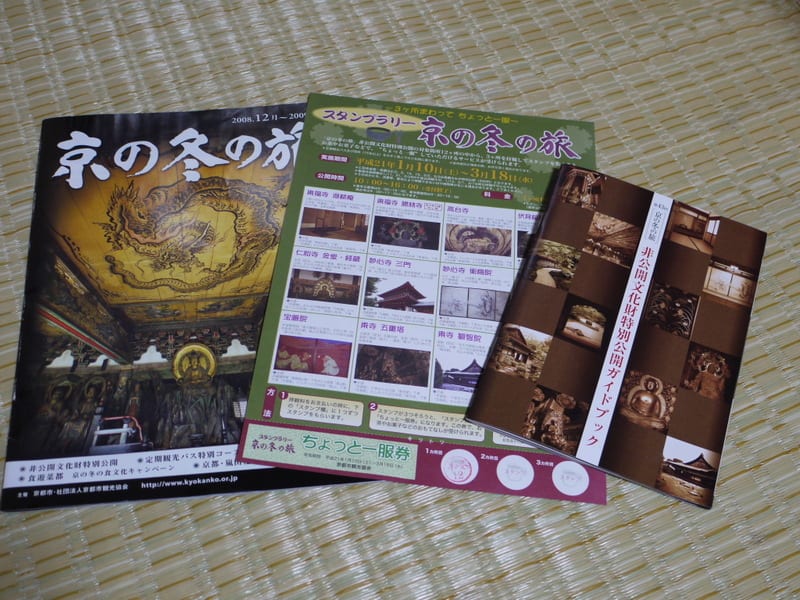昨日ブログの、もうすぐ節分に引き続き、もうすぐバレンタインデーですね・・・。あちこちでバレンタインの商品が並んでいます。今朝、京都駅へ行ったら、開店前の京都伊勢丹に行列が(@Д@;)なんのための行列なのか確かめなかったんですが・・・もしかして、今日から始まった「~パリ発、チョコレートの祭典~ サロン・デュ・ショコラ」目的なんでしょうか????毎年、私には無用かな?と思いつつも、どさくさで売り場に紛れ込むと、種類の多さや、パッケージの斬新さ、人の多さに、びっくりします。今年は1個ぐらい買ってみようかな、自分用に!(^m^)
ひとつめは、甘春堂さんのハートの和三盆(295円)です。ピンクと白のハートが合計7つ入っています。口に入れると、たちまち溶けて、上品な甘さが広がります。
甘春堂本店 http://www.kanshundo.co.jp/index.shtml
以前、同じシリーズの落雁をご紹介しています。いろんな形があって、見ているだけでも楽しいです。【前ブログ】
ふたつめは、京都嵯峨春秋庵の「ちょこっとハート:210円」です。ハート形のあげせんべいで、思ったよりふわっとやわらかな感じです。味はあっさり素材そのままの味です。この京都嵯峨春秋庵さんには、ほかにもハートのおせんべいやかきもちがたくさんあります。以前は、絵馬おかきをご紹介しています。【前ブログ】
京都嵯峨春秋庵 http://www.shunjuan.com/
おまけ:昨年、七條甘春堂さんのハート型のチョコようかんと、恋こはくをご紹介しています。【前ブログ】チョコようかんは、あまりの独創性に・・・食べきる事ができず、思わずパパにもおすそ分けしました。贈るとか、あげるじゃなくて・・・(^^;)恋こはくは、文句なくおいしかったです。独り占めしました。(^^)V
今年も恋こはくを食べたくて、昨日、伊勢丹に買いにいったら、まだ出ていませんでした。2月に入ってからの発売だそうです。楽しみです。ちなみに、チョコようかんも発売予定だそうです。なんか気になって、今年も買ってしまうかも。(^m^)