生誕140年 魯迅、日中友好 揺るぎない意志 「多喜二虐殺」知り怒り
北京魯迅博物館副館長 黄喬生(こうきょうせい)さんに聞く
9月25日は、中国の文豪、魯迅(ろ・じん、1881~1936年)の生誕140周年でした。魯迅は日本への留学経験もあり、上海にあった内山書店を通じて多くの日本人と交流するなど日本との関係も深い作家です。日本が中国への侵略を始める中、魯迅は当時の日本の人々とどのように親交を深めたのか、魯迅研究者である北京魯迅博物館の黄喬生副館長に聞きました。(北京=小林拓也)
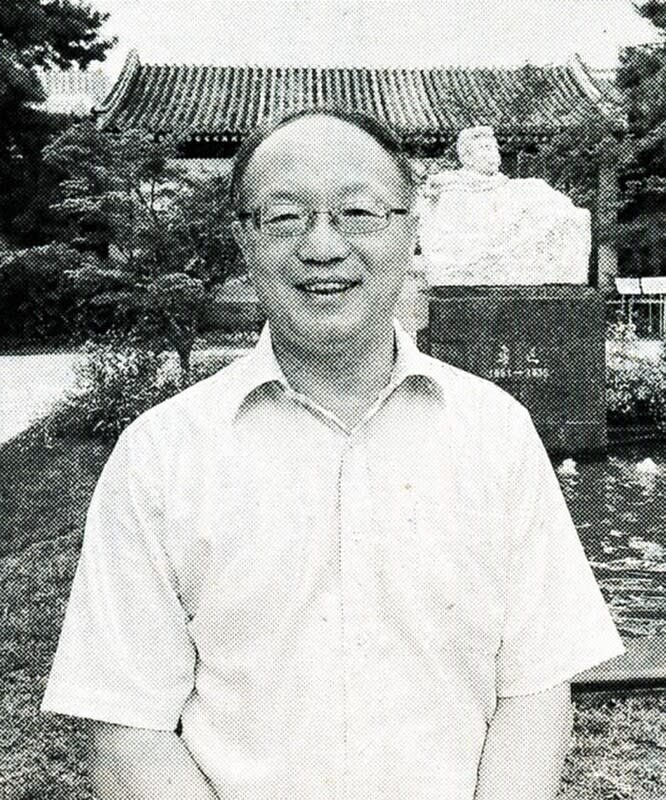
北京魯迅博物館の魯迅像の前に立つ黄喬生副館長(小林拓也撮影)
魯迅はどのような時でも、平和的で誠実な態度を保ち、尊大に振る舞うことも自分を卑下することもありませんでした。魯迅の生きた時代は、日清戦争(1894~95年)、満州事変(31年)、第1次上海事変(32年1月28日)など、中日関係が緊張状態にありました。
魯迅は青年時代に日本に留学し、藤野先生(注1)らと関係を築きました。帰国してから亡くなるまで、日本の民間人との交流の際、誠実で率直な態度を持ち続けました。例えば、増田渉氏(注2)とは深い師弟関係を結びました。また、野口米次郎氏(注3)に対しては誤解や歪曲(わいきょく)を批判し正しました。
魯迅が書いた「題三義塔」(33年)という詩の中にこういう一節があります。
「劫波(ごうは)を度(わた)り尽くして、兄弟在り。相逢(あ)いて一笑すれば、恩仇混(ほろ)ばん」(大災厄の波を渡り終えたさきに、両国の兄弟がいる。めぐりあって一笑すれば、古い仇恨〈きゅうこん〉は消滅するだろう)日本の軍国主義による侵略に憤慨する一方、民間の友好的な交流に希望を寄せ、平和を追求していたのです。
魯迅は、揺るぎない意志を持ちながら、思いやりの気持ちを持ち、その精神は偏狭でも過激でもありませんでした。中日両国の人民が学ぶ価値のある態度です。

魯迅 中国の作家・思想家。本名・周樹人。1881年9月25日生まれ。出身は漸江省紹興。1902~09年に日本に留学し、仙台では医学などを学びました。晩年は上海に住み、内山書店の店主、内山完造ら日本人と交流しました。代表作に「狂人日記」「阿Q正伝」など。
読者の支持得る
魯迅博物館には、「同志小林多喜二の死を聞いて」と題する魯迅が書いた文書を展示しています。日本共産党員の作家、小林多喜二が1933年2月20日に日本の特高警察によって虐殺されたことは、中国でも悲しみと怒りを呼びました。当時、小林多喜二の小説は中国でも翻訳、出版され、多くの読者の支持を得ていました。
魯迅や茅盾(ぼう・じゅん)、田漢(でん・かん)ら著名な文学者らは、小林多喜二の文学や業績を称賛する文章を発表し、遺族のための募金活動を呼びかけました。
魯迅は以下の文書を発表しました。

其の実証の一つ
「日本と支那の大衆はもとより兄弟である。資産階級は大衆をだまして其の血で界(さかい)をえがいた、又えがきつつある。しかし無産階級と其の先駆達は血でそれを洗っている。同志小林の死は其の実証の一つだ。我々は知っている、我々は忘れない。我々は堅く同志小林の血路に沿って前進し握手するのだ」
この文章は魯迅が自ら日本語で書いたものとされており、日本の雑誌でも紹介されました。
魯迅は、同志への思いと、正義のための憤怒の気持ちからこの文章を書いたと考えています。これは中日両国の大衆が鮮血で結んだ友情の証しです。
◆注1
藤野厳九郎(ふじの・げんくろう、1874~1945年)。医師、教育者で、魯迅が1904年から仙台に留学した際の恩師。当時の日本社会に中国を軽んじる風潮がある中、魯迅のノートを詳細に添削し、懇切に指導しました。魯迅の自伝的短編小説「藤野先生」で詳しく紹介されてい
ます。
◆注2
増田渉(ますだ・わたる、1903~77年)。中国文学者。1931年に上海で晩年の魯迅に師事。「中国小説史略」などの講義を受けました。
◆注3
野ロ米次郎(のぐち・よねじろう、1875~1947年)。詩人、小説家、評論家。1935年に上海で魯迅と会談。野口が、中国の国防と政治を外国に任せたらどうかと提起し、魯迅は「同じ財産をなくすなら、強盗にとられるよりはばか息子に使われた方がよい。同じ殺されるなら、自国の人の手に殺されたい」と答えたと記録されています。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年9月30日付掲載
魯迅の「狂人日記」「阿Q正伝」などは、若い時にかじり読んで、変わった文学作家とのイメージでしたが…。
小林多喜二の特高警察による虐殺を知り、魯迅が「日本と支那の大衆はもとより兄弟である。資産階級は大衆をだまして其の血で界(さかい)をえがいた、又えがきつつある。しかし無産階級と其の先駆達は血でそれを洗っている。同志小林の死は其の実証の一つだ。我々は知っている、我々は忘れない。我々は堅く同志小林の血路に沿って前進し握手するのだ」と語っていることは知らなかった。
改めて、日中友好の絆として魯迅を見直したい。
北京魯迅博物館副館長 黄喬生(こうきょうせい)さんに聞く
9月25日は、中国の文豪、魯迅(ろ・じん、1881~1936年)の生誕140周年でした。魯迅は日本への留学経験もあり、上海にあった内山書店を通じて多くの日本人と交流するなど日本との関係も深い作家です。日本が中国への侵略を始める中、魯迅は当時の日本の人々とどのように親交を深めたのか、魯迅研究者である北京魯迅博物館の黄喬生副館長に聞きました。(北京=小林拓也)
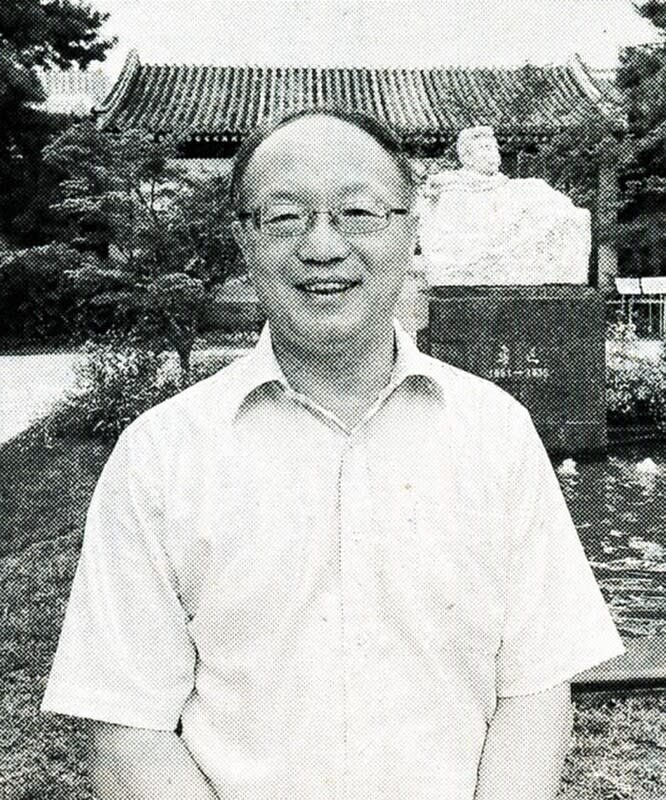
北京魯迅博物館の魯迅像の前に立つ黄喬生副館長(小林拓也撮影)
魯迅はどのような時でも、平和的で誠実な態度を保ち、尊大に振る舞うことも自分を卑下することもありませんでした。魯迅の生きた時代は、日清戦争(1894~95年)、満州事変(31年)、第1次上海事変(32年1月28日)など、中日関係が緊張状態にありました。
魯迅は青年時代に日本に留学し、藤野先生(注1)らと関係を築きました。帰国してから亡くなるまで、日本の民間人との交流の際、誠実で率直な態度を持ち続けました。例えば、増田渉氏(注2)とは深い師弟関係を結びました。また、野口米次郎氏(注3)に対しては誤解や歪曲(わいきょく)を批判し正しました。
魯迅が書いた「題三義塔」(33年)という詩の中にこういう一節があります。
「劫波(ごうは)を度(わた)り尽くして、兄弟在り。相逢(あ)いて一笑すれば、恩仇混(ほろ)ばん」(大災厄の波を渡り終えたさきに、両国の兄弟がいる。めぐりあって一笑すれば、古い仇恨〈きゅうこん〉は消滅するだろう)日本の軍国主義による侵略に憤慨する一方、民間の友好的な交流に希望を寄せ、平和を追求していたのです。
魯迅は、揺るぎない意志を持ちながら、思いやりの気持ちを持ち、その精神は偏狭でも過激でもありませんでした。中日両国の人民が学ぶ価値のある態度です。

魯迅 中国の作家・思想家。本名・周樹人。1881年9月25日生まれ。出身は漸江省紹興。1902~09年に日本に留学し、仙台では医学などを学びました。晩年は上海に住み、内山書店の店主、内山完造ら日本人と交流しました。代表作に「狂人日記」「阿Q正伝」など。
読者の支持得る
魯迅博物館には、「同志小林多喜二の死を聞いて」と題する魯迅が書いた文書を展示しています。日本共産党員の作家、小林多喜二が1933年2月20日に日本の特高警察によって虐殺されたことは、中国でも悲しみと怒りを呼びました。当時、小林多喜二の小説は中国でも翻訳、出版され、多くの読者の支持を得ていました。
魯迅や茅盾(ぼう・じゅん)、田漢(でん・かん)ら著名な文学者らは、小林多喜二の文学や業績を称賛する文章を発表し、遺族のための募金活動を呼びかけました。
魯迅は以下の文書を発表しました。

其の実証の一つ
「日本と支那の大衆はもとより兄弟である。資産階級は大衆をだまして其の血で界(さかい)をえがいた、又えがきつつある。しかし無産階級と其の先駆達は血でそれを洗っている。同志小林の死は其の実証の一つだ。我々は知っている、我々は忘れない。我々は堅く同志小林の血路に沿って前進し握手するのだ」
この文章は魯迅が自ら日本語で書いたものとされており、日本の雑誌でも紹介されました。
魯迅は、同志への思いと、正義のための憤怒の気持ちからこの文章を書いたと考えています。これは中日両国の大衆が鮮血で結んだ友情の証しです。
◆注1
藤野厳九郎(ふじの・げんくろう、1874~1945年)。医師、教育者で、魯迅が1904年から仙台に留学した際の恩師。当時の日本社会に中国を軽んじる風潮がある中、魯迅のノートを詳細に添削し、懇切に指導しました。魯迅の自伝的短編小説「藤野先生」で詳しく紹介されてい
ます。
◆注2
増田渉(ますだ・わたる、1903~77年)。中国文学者。1931年に上海で晩年の魯迅に師事。「中国小説史略」などの講義を受けました。
◆注3
野ロ米次郎(のぐち・よねじろう、1875~1947年)。詩人、小説家、評論家。1935年に上海で魯迅と会談。野口が、中国の国防と政治を外国に任せたらどうかと提起し、魯迅は「同じ財産をなくすなら、強盗にとられるよりはばか息子に使われた方がよい。同じ殺されるなら、自国の人の手に殺されたい」と答えたと記録されています。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年9月30日付掲載
魯迅の「狂人日記」「阿Q正伝」などは、若い時にかじり読んで、変わった文学作家とのイメージでしたが…。
小林多喜二の特高警察による虐殺を知り、魯迅が「日本と支那の大衆はもとより兄弟である。資産階級は大衆をだまして其の血で界(さかい)をえがいた、又えがきつつある。しかし無産階級と其の先駆達は血でそれを洗っている。同志小林の死は其の実証の一つだ。我々は知っている、我々は忘れない。我々は堅く同志小林の血路に沿って前進し握手するのだ」と語っていることは知らなかった。
改めて、日中友好の絆として魯迅を見直したい。
























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます