安保改定60年 第一部⑦ 「日米一体化」 隠された「米国基準」
戦後、米国が世界に張り巡らせた軍事同盟は、米軍の駐留権を確保すると同時に、同盟国に補完的役割を担わせることを特質としています。1950年の警察予備隊の創設以来、米軍に育成されてきた自衛隊も60年の日米安保条約改定を機に、「日本防衛」の第一義的な責任を負うと同時に、米軍の戦略に深く組み込まれていきます。
対領空侵犯措置
その第一歩と言えるのが、在日米空軍(第5空軍)から航空自衛隊への「防空」任務の移管でした。空自は、58年4月から、航空警戒監視および管制機能・組織の米照からの移管(60年)と併行して、領空侵犯の恐れのある彼我不明機に対する「対領空侵犯措置」を開始しました。
59年9月に締結された「日本の防空実施のための取極」(松前・バーンズ協定※)は、「米軍は安保条約のもと、日本に駐留し、日本の防空を日米それぞれの指揮系統において行う」としていますが、米軍は65年6月に対領空侵犯措置のための警戒待機を完了。実際は、自衛隊が「防空」の全面的な責任を負うことになります。
自衛隊法では、対領空侵犯措置の武器使用基準は警察官職務執行法に準拠しています。一方、外稲省が2013年に公開した外交文書によれば、米軍は,「『交戦』という概念で、すべての職闘行動を律して」おり、戦闘機は敵対行動をとる敵機に対し、「攻撃(先制攻撃含む)を加え、追撃する義務を有する」といいます。
しかし、政府は国会で、米軍と空自の対領空侵犯措置行動規範は「おおむね同じ」と答弁していました。真相はどうだったのか―。
※政府は松前・バーンズ協定について、非公開としていますが、実際には政府答弁の中で主要項目が詳細に述べられています。(『防衛研究所紀要第15巻第1号(2012・10)』―「航空警戒管制組織の形成と航空自衛隊への移管」)

那覇基地を緊急発進する空自F15戦闘機(航空自衛隊チャンネルから)
元空将補の証言
秘匿度高い規則
空自幹部として警戒管制部隊勤務の経歴を持つ林吉永・元空将補(国際地政学研究所事務局長)は、空自は「米軍から秘匿度の高い対領空侵犯措置実施規則を譲り受けた」と証言します。
米軍にとっては、空自への対領空侵犯措置移管の当時、朝鮮半島に接続する日本上空も戦場」でした。このため、「武器使用の権限」を「戦時基準の領空侵犯措置」において下位職責にまで委任。空自は、この「対領空侵犯措置規則」を引き継いだといいます。こうした事実は公にされていません。
その危険性があらわになったのが、1987年12月9日の「ソ連のTu16バジャー電子偵察機が沖縄本島や沖永良部島、徳之島を領空侵犯」した事件でした。
那覇基地を緊急発進離陸した空自F4戦闘機は、ソ連機の領空侵犯に対して20ミリ機関砲に混在している信号弾による警告射撃を行いました。外国軍に対する実弾の使用は、自衛隊史上初めて。対領空侵犯措置では、これが唯一の事例です。
87年、一触即発の警告射撃
「戦争抑止のため“迷え”」
信号弾は、熱効果で発光するもので、真後ろからでなければはっきり見えません。林氏は、「こうした『秘』扱いの『対領空侵犯措置要領』は、翌年(88年)5月のNHK『クローズアップ現代―ソ連機の沖縄領空侵犯』で詳細が放映されましたが、公開はされていません。国際法など万国共通の手順でもないので、信号弾による警告射撃を『撃たれた』と判断して撃ち返してくる危険な蓋然(がいぜん)性があります」と指摘します。
当事者として与座岳レーダーサイト(沖縄県糸満市)の司令だった林氏は、信号射撃の実施に否定的でしたが、南西航空混成団司令は、「対領空侵犯措置実施規則」に従って「信号射撃」を指示。林氏は、「相手が撃ち返してくるかもしれない一触即発の状況下の武器使用に、どのようなリスクがあるのか。大韓航空機を撃墜したソ連の反応には、『反撃の恐れ』が考えられるはず。『交戦状態に陥ったら』文民統制上も外交上も、きわめて深刻な問題がおきる。それを覚悟したのかが問われてしかるべきだ」といいます。

米原子力空母ロナルド・レーガン(奥)と並走する凋上目衛豚イージス艦「みょうこう」=2019年8月15日、フィリピン海(米海軍ウェブサイトから)
「攻撃目標」共有
戦後、米軍は自らの補完部隊として自衛隊を位置付け、「一体化」を図ってきました。これを阻んできたのが、「海外派兵・集団的自衛権行使の禁止」「米軍(他国)の指揮下に入らない」「米軍の武力行使との一体化を避ける」といった憲法9条の“制約”です。
しかし、現場では、すでになし崩しの“一体化”が進んでいます。空自の場合、米軍は自動警戒管制組織(BADGE)と米軍システムとの連接を要求してきましたが、後継システム(JADGE)は最初から連接を前提としています。
海自は戦術データリンクを通じて米海軍との情報共有を積極的に進めてきましたが、今後就役するイージス艦は、敵のミサイルや航空機の位置情報を共有するシステム「共同交戦能力(CEC)」を搭載。「攻撃目標」を米軍と共有することになります。
重大なのは、安倍政権が強行した安保法制の下、米艦船・航空機の「防護」が可能になり、武器使用の判断が現場指揮官に委ねられたということです。「平時の行動」でも、対応しだいでは、米軍の戦争に巻き込まれる危険が増しています。
平時だからこそ
いま、システム上は、「プログラムされたとおりに物事が進められるデジタル化(自動化)」が進み、アナログ的「迷いや逡巡(しゅんじゅん)」がうせることで、1987年のソ連機領空侵犯事件より、「手順の通り、当然のごとく信号射撃を行う」はるかに危険な状況にあります。林氏はこう訴えかけます。
「すべてがネットワーク化され、攻撃目標が自動的に設定されている中にあって、人間が戦争を抑止できる優れた唯一の点は、『迷う』こと。規則だからと反射的にボタンを押すのではなく、押せばどうなるのか。『平時だからこそ』逡巡してほしい。それが戦争や武力行使と無関係な『日本の国のかたちを維持する』時代精神になるはずです」
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年2月2日付掲載
「先制攻撃」がスタンダードの米軍と「専守防衛」の自衛隊が行動を「一体化」するとなると、必然と米軍の軍事行動に加担することになる。
コンピューターが勝手に戦争を始めることのないように、人間が迷うことが大事だと。
戦後、米国が世界に張り巡らせた軍事同盟は、米軍の駐留権を確保すると同時に、同盟国に補完的役割を担わせることを特質としています。1950年の警察予備隊の創設以来、米軍に育成されてきた自衛隊も60年の日米安保条約改定を機に、「日本防衛」の第一義的な責任を負うと同時に、米軍の戦略に深く組み込まれていきます。
対領空侵犯措置
その第一歩と言えるのが、在日米空軍(第5空軍)から航空自衛隊への「防空」任務の移管でした。空自は、58年4月から、航空警戒監視および管制機能・組織の米照からの移管(60年)と併行して、領空侵犯の恐れのある彼我不明機に対する「対領空侵犯措置」を開始しました。
59年9月に締結された「日本の防空実施のための取極」(松前・バーンズ協定※)は、「米軍は安保条約のもと、日本に駐留し、日本の防空を日米それぞれの指揮系統において行う」としていますが、米軍は65年6月に対領空侵犯措置のための警戒待機を完了。実際は、自衛隊が「防空」の全面的な責任を負うことになります。
自衛隊法では、対領空侵犯措置の武器使用基準は警察官職務執行法に準拠しています。一方、外稲省が2013年に公開した外交文書によれば、米軍は,「『交戦』という概念で、すべての職闘行動を律して」おり、戦闘機は敵対行動をとる敵機に対し、「攻撃(先制攻撃含む)を加え、追撃する義務を有する」といいます。
しかし、政府は国会で、米軍と空自の対領空侵犯措置行動規範は「おおむね同じ」と答弁していました。真相はどうだったのか―。
※政府は松前・バーンズ協定について、非公開としていますが、実際には政府答弁の中で主要項目が詳細に述べられています。(『防衛研究所紀要第15巻第1号(2012・10)』―「航空警戒管制組織の形成と航空自衛隊への移管」)

那覇基地を緊急発進する空自F15戦闘機(航空自衛隊チャンネルから)
元空将補の証言
秘匿度高い規則
空自幹部として警戒管制部隊勤務の経歴を持つ林吉永・元空将補(国際地政学研究所事務局長)は、空自は「米軍から秘匿度の高い対領空侵犯措置実施規則を譲り受けた」と証言します。
米軍にとっては、空自への対領空侵犯措置移管の当時、朝鮮半島に接続する日本上空も戦場」でした。このため、「武器使用の権限」を「戦時基準の領空侵犯措置」において下位職責にまで委任。空自は、この「対領空侵犯措置規則」を引き継いだといいます。こうした事実は公にされていません。
その危険性があらわになったのが、1987年12月9日の「ソ連のTu16バジャー電子偵察機が沖縄本島や沖永良部島、徳之島を領空侵犯」した事件でした。
那覇基地を緊急発進離陸した空自F4戦闘機は、ソ連機の領空侵犯に対して20ミリ機関砲に混在している信号弾による警告射撃を行いました。外国軍に対する実弾の使用は、自衛隊史上初めて。対領空侵犯措置では、これが唯一の事例です。
87年、一触即発の警告射撃
「戦争抑止のため“迷え”」
信号弾は、熱効果で発光するもので、真後ろからでなければはっきり見えません。林氏は、「こうした『秘』扱いの『対領空侵犯措置要領』は、翌年(88年)5月のNHK『クローズアップ現代―ソ連機の沖縄領空侵犯』で詳細が放映されましたが、公開はされていません。国際法など万国共通の手順でもないので、信号弾による警告射撃を『撃たれた』と判断して撃ち返してくる危険な蓋然(がいぜん)性があります」と指摘します。
当事者として与座岳レーダーサイト(沖縄県糸満市)の司令だった林氏は、信号射撃の実施に否定的でしたが、南西航空混成団司令は、「対領空侵犯措置実施規則」に従って「信号射撃」を指示。林氏は、「相手が撃ち返してくるかもしれない一触即発の状況下の武器使用に、どのようなリスクがあるのか。大韓航空機を撃墜したソ連の反応には、『反撃の恐れ』が考えられるはず。『交戦状態に陥ったら』文民統制上も外交上も、きわめて深刻な問題がおきる。それを覚悟したのかが問われてしかるべきだ」といいます。

米原子力空母ロナルド・レーガン(奥)と並走する凋上目衛豚イージス艦「みょうこう」=2019年8月15日、フィリピン海(米海軍ウェブサイトから)
「攻撃目標」共有
戦後、米軍は自らの補完部隊として自衛隊を位置付け、「一体化」を図ってきました。これを阻んできたのが、「海外派兵・集団的自衛権行使の禁止」「米軍(他国)の指揮下に入らない」「米軍の武力行使との一体化を避ける」といった憲法9条の“制約”です。
しかし、現場では、すでになし崩しの“一体化”が進んでいます。空自の場合、米軍は自動警戒管制組織(BADGE)と米軍システムとの連接を要求してきましたが、後継システム(JADGE)は最初から連接を前提としています。
海自は戦術データリンクを通じて米海軍との情報共有を積極的に進めてきましたが、今後就役するイージス艦は、敵のミサイルや航空機の位置情報を共有するシステム「共同交戦能力(CEC)」を搭載。「攻撃目標」を米軍と共有することになります。
重大なのは、安倍政権が強行した安保法制の下、米艦船・航空機の「防護」が可能になり、武器使用の判断が現場指揮官に委ねられたということです。「平時の行動」でも、対応しだいでは、米軍の戦争に巻き込まれる危険が増しています。
平時だからこそ
いま、システム上は、「プログラムされたとおりに物事が進められるデジタル化(自動化)」が進み、アナログ的「迷いや逡巡(しゅんじゅん)」がうせることで、1987年のソ連機領空侵犯事件より、「手順の通り、当然のごとく信号射撃を行う」はるかに危険な状況にあります。林氏はこう訴えかけます。
「すべてがネットワーク化され、攻撃目標が自動的に設定されている中にあって、人間が戦争を抑止できる優れた唯一の点は、『迷う』こと。規則だからと反射的にボタンを押すのではなく、押せばどうなるのか。『平時だからこそ』逡巡してほしい。それが戦争や武力行使と無関係な『日本の国のかたちを維持する』時代精神になるはずです」
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年2月2日付掲載
「先制攻撃」がスタンダードの米軍と「専守防衛」の自衛隊が行動を「一体化」するとなると、必然と米軍の軍事行動に加担することになる。
コンピューターが勝手に戦争を始めることのないように、人間が迷うことが大事だと。












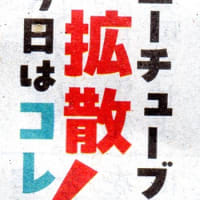











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます