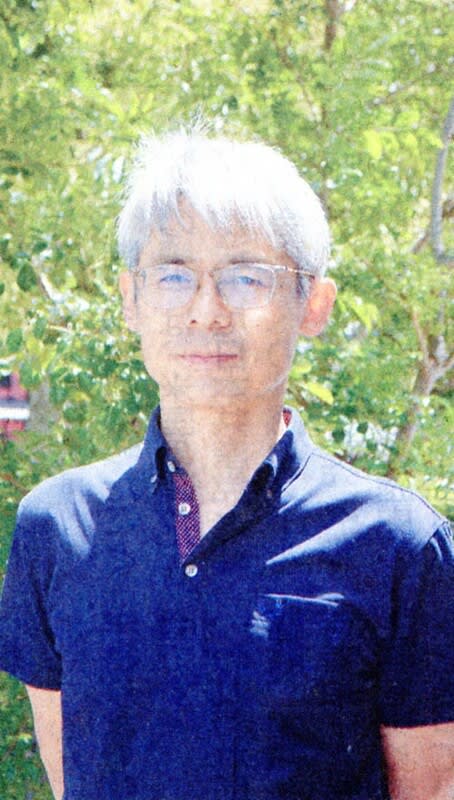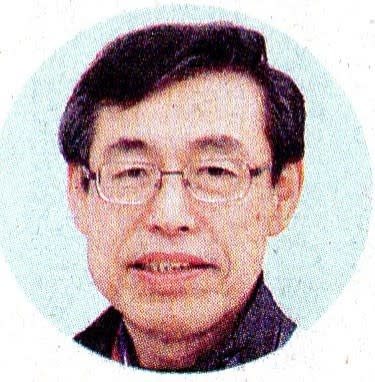「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。
どう見る原発コスト② 再エネ100%の日本に
龍谷大学教授 大島堅一さんに聞く
―経産省の審議会では、再生可能エネルギーの大量導入に伴う費用が高くつくことで、電気代が数倍になるなどの試算を出しています。
今までのシステムは、大規模集中型の石炭火力や原発を前提に系統などの電力システムを組んでいました。再エネを主力電源にするために新しい仕組みに入れ替える費用が発生するのは当然です。システムとして入れ替えるための費用で、再エネのコストにだけのせる議論はおかしいです。
【エネルギー基本計画】
電力や資源についての政府の中長期的な方針を示す計画。3年に1度改定し、現行計画は2018年に閣議決定しました。このほど出た次期計画素案では、2030年度の総発電量は、現行計画から1割程度少ない9300億~9400億キロワット時と想定。総発電量に占める再生可能エネルギーは、現行計画の22~24%から36~38%に。石炭火力は、現行計画の26%から19%としています。
 原発は高費用
原発は高費用
安定供給のための費用ということであれば、原発にも必要です。原発は、1基の発電量が大きいので、動かなくなった時のバックアップがたいへん大きくなります。実際、今年の1月の電力価格の高騰の引き金を引いたのは、関西電力の原発に定期点検で不具合がみつかり、点検期間が予定外に延びたこと、LNG(液化天然ガス)の調達の遅れです。
それが原発を電源にすることで必要になる費用です。審議会の議論は、それを全く考えないバランスを欠いた議論です。
しかも、大規模なバッテリーなどの価格がどんどん安くなっていて、再エネの導入に新たな費用もいらないぐらいになってきます。
―どうシステムを変えていくかという議論をしないといけないということですか。
そうです。原発は現在、全体の6%しか発電していない。6%を20~22%に引き上げるのは相当の努力が必要ですが、再エネはいま20%を超えていますから、原発がなくても問題はありません。
しかし一度、原発を20~22%にするという目標ができてしまうことの不幸は、それに向けて、いろんな政策が作られることです。再エネのブレーキを踏むことになります。
原子力に対して後押し、ないしは優遇しない限り、そこまで発電量が伸びることはない。それは国民の大きな負担です。できるだけ早く再稼働させようとか、できるだけ長く使おうとすれば、国民を危険にさらすことにもなります。やるべきではありません。エネルギー基本計画に原発について、「必要な規模を持続的に活用していく」という内容が入ること自体が不幸を生むと思います。
カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の実現は、省エネと再生エネルギーを中心とした社会でまかなうべきであって、原発なんてありえません。
次世代に被害
放射性廃棄物のこともあり、長期的に見れば、今の現役世代が払えない膨大なコストと膨大な放射性廃棄物を次世代の若者に手渡すことが運命づけられている、不公正そのものだからです。
これは気候変動と同じです。気候変動も今の世代や過去の世代が、全然排出したことがない将来の世代に被害を及ぼすのですから。
カーポンニュートラルとともに、環境保全型社会を作るということが必要です。省工ネを徹底して再エネ100%の日本をつくるということだと思います。
(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年8月14日付掲載
原発は現在、全体の6%しか発電していない。6%を20~22%に引き上げるのは相当の努力が必要。逆に、再エネはいま20%を超えていますから、原発がなくても問題なし。原発の発電量を増やすことは、再エネの普及を抑え込むことになります。
原発の発電量を無理に増やさず、LNGなどで中継ぎをして、再生可能エネルギー100%へ。石炭火力などは、もちろん論外です。
どう見る原発コスト① 隠せなくなった高費用
龍谷大学教授 大島堅一さんに聞く
経済産業省は「第6次エネルギー基本計画(素案)」をとりまとめました。2030年に総発電量に占める原発の比率は現行通り20~22%と、相変わらず原発に固執しています。同省はまた、15年以来6年ぶりに電源別の発電コストの検証結果も発表しました。原発のコストに詳しい龍谷大学の大島堅一教授に原発コストの実態、エネルギー基本計画の問題点について聞きました。(松沼環)
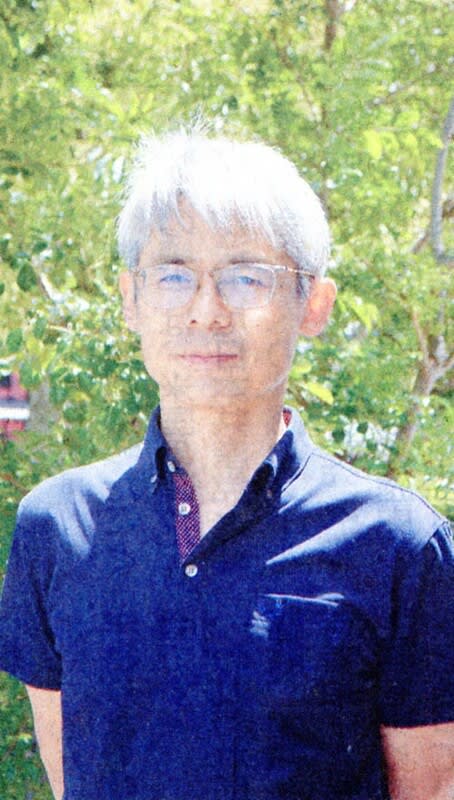 ―今回の原発コストの評価をどう見ますか。
―今回の原発コストの評価をどう見ますか。
30年時点の原発発電コストは、1キロワット時当たり「11・7円以上」と発表されました。15年の検証では、原発は1キロワット時当たり「10・3円以上」でした。
東京電力福島第1原発事故の費用や追加的安全対策費用をコストに加えましたから、原発が安くないことを覆い隠すことができなくなりました。
しかし、おかしいのは、事故の計算方法と追加的安全対策の計算方法です。
福島原発事故の費用に関しては、放射性廃棄物の廃棄にかかる費用が入っていません。
福島原発事故の廃炉で出てくる放射性廃棄物の量は、原子力学会の報告書によれば、原発の廃炉などで発生する比較的放射性レベルの高い廃棄物(L1廃棄物)で比べると、通常の原発1基を廃炉する場合の1000倍を優に超えています。
国内の約50基の原発の処分も見通しがありませんが、1000基分以上の廃棄物が追加されたのです。安いとか高いとかではなく、国家の危機です。
追加的安全対策費では、各電力会社に聞くと平均2000億円となりました。しかし経産省の評価では、原発を新設する場合は最初から設計で取り込めるからと、対策にかかる多くの費用を除外して約1400億円になったとしています。しかし、除外される根拠が全く分かりません。ここにも大きな穴があります。
どちらにしても建設費に関連する資本費の部分にかなりのごまかしがあるので、実態はもう少し高くなります。
■2030年電源別発電コストの経済産業省試算結果(円/キロワット時)
| 石炭火力 | 13.6~22.4 |
| LNG火力 | 10.7~14.3 |
| 原子力 | 11.7~ |
| 陸上風力 | 9.9~17.2 |
| 太陽光(事業用) | 8.2~11.8 |
| 太陽光(住宅) | 8.7~14.9 |
前提崩れても
―同省審議会で示された発電コストは、モデルプラントを新たに建設した場合の計算ですが、既存の原発の発電コストはどう見ますか。
15年の同省作業部会で公開された方法を基本に計算すると、11年以降にかかったお金と、かかるだろうお金だけを積み上げて発電量で割るとものすごく高いことが分かりました。
発電コストは総費用を総発電量で割って単価を求めるのですが、安全対策費が大変高くなっています。東電柏崎刈羽原発(新潟県)では2基の再稼働のために1兆円を超えるお金を出しています。
再稼働をしていない原発もありますが、今後再稼働をしたとしても残された運転期間が短くなっているので、発電量が少なくなります。
前回の18年のエネルギー基本計画では、既存の原発について原発は低廉であることを前提に再稼働を進めると書いてありましたが、実際には既存の原発でも、経済的にまったく割に合わない。方針自体が間違っていたということがはっきりしたにもかかわらず、今回の素案にも同様の表現が踏襲されています。
国民を危険に
―電力会社などが今、運転期間を通常40年から60年にのばすとか、定期点検や安全対策をしている期間を発電期間から外すべきだと要望していますが。
そういう要望が出てきていることを非常に危惧しています。法改正を含めた検討の可能性が懸念されています。
しかし、止まっている期間が長すぎて、見込み違いだっただけです。
失敗したら自分で責任をとる、それが資本主義のルールです。失敗した経営方針では競争にさらされてその業者は倒れる、あるいはそういう技術はなくなっていくというのが、資本主義です。見込み違いを、国民を危険にさらすことで解消しようとしています。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年8月13日付掲載
原発の発電コスト。2011年以前と以降で大きく変化。安全対策費や廃炉にかかる費用が上積みされて発電コストがアップ。
失敗したら自分で責任をとる、それが資本主義のルール。それなら、原発から撤退するべきです。
運転期間を通常40年から60年にのばすとか、定期点検や安全対策をしている期間を発電期間から外すべきだなどとセコイことを考えない事。
政府の次期エネ基本計画 「脱炭素」口実に原発固執 再エネ優先への転換こそ急務
経済産業省は、次期エネルギー基本計画の根幹となる2030年度の電源構成で「脱炭素電源」の比率を6割程度とする検討に入りました。しかし「脱炭素」の名目で、原子力発電の割合も2割程度とし、再生可能エネルギーの導入と合わせた原発再稼働の姿勢を見せています。(嘉藤敬佑)
同計画は、50年までに二酸化炭素など温室効果ガス排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」を達成するため、30年に向けた政策対応です。現在、国内の電源は火力発電が中心で、発電時に二酸化炭素を排出しない電源の整備は急務となっています。
政府は24日、気候変動対策の有識者会議を開き、出席した委員から、再生可能エネルギー普及のための規制見直しのほか、原発の新増設や建て替えの必要性を指摘する意見が出たといいます。
経産省は昨年10月に公表した、エネルギー基本計画の見直しに向けてとする資料で、30年の取り組み目標として、再エネ電源の比率を22~24%にするとしており、今回の検討ではさらにその比率を引き上げる形です。
 気候変動対策推進のための有識者会議で発言する菅義偉首相(右端)=5月24日、首相官邸
気候変動対策推進のための有識者会議で発言する菅義偉首相(右端)=5月24日、首相官邸
2割確保狙う
ただ同時に、現在は全電源に占める割合が6%の原発も2割程度にするとしており、「脱炭素」の名のもとで、原発の再稼働も狙っています。
さらに、今年4月の日米首脳会談でも、菅義偉首相とバイデン米大統領は「30年までに確固たる気候行動をとる」ことを約束。その中で、再生可能エネルギーの普及と同時に「革新原子力等」のイノベーションも行うとしています。
日本共産党はこれまで国会質問で、「脱炭素」が原発再稼働の口実になっていることを指摘したうえで、「再エネ最優先にかじをきるべきだ」「国民世論に反し、脱炭素を口実にした原発再稼働は許されない」とたびたび政府の姿勢をただしてきました。
ところが、梶山弘志経産相は「今の時点で原子力を放棄するという選択肢はない」「確立した脱炭素電源である原子力の活用は欠かせない」などと答弁し、原発への強い固執を示しています。
法案共同提出
日本共産党は、政府のエネルギー政策について「脱炭素」などを名目にした「新型炉」の研究開発など、原発を温存、支援する余地を残していることを厳しく批判しています。
また、日本で再エネの普及が進まないのは、原発が動けば動くほど、再エネの受け入れ量が減るような原発最優先のルールがあるためだと強調。エネルギー政策の中心に再エネを据えてこそ、再エネ産業が発展し導入も進むと訴えてきました。
原発の維持にかかるコストについても、経済的に成り立たず、避けられないリスクを抱え、将来世代に膨大な重い負担をかけることになると指摘。将来世代に負担をかけない、別の道を選ぶべきだと求めてきました。
日本共産党、立憲民主党、社民党、自由党(当時)の野党4党は、原発ゼロにかじをきり、電源は再エネを中心にすえるための「原発ゼロ基本法案」を共同提出しています。
世界最悪の原発事故を起こした日本こそ、率先して脱原発に進む責任があります。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年5月29日付掲載
経産省は、エネルギー基本計画の見直しで、30年の目標として不十分ながらも再エネ電源の比率を22~24%をさらに引き上げる計画。
その一方で原発を2割程度とする計画。原発には異次元のリスクやコストがあります。
日本共産党、立憲民主党、社民党、自由党(当時)の野党4党は、原発ゼロにかじをきり、電源は再エネを中心にすえるための「原発ゼロ基本法案」を共同提出。野党連合政権の実現で原発のない日本を!
汚染水海洋放出 何が問題か 高橋千鶴子衆院議員に聞く
政府が漁業関係者をはじめ地元の強い反対の声を無視して、東京電力福島第1原発で増え続ける放射能汚染水を処理した後の高濃度のトリチウム(3重水素)を含む汚染水の海洋放出方針を決定しました。日本共産党国会議員団福島チーム責任者の高橋千鶴子衆院議員に何が問題なのか、聞きました。(聞き手・三木利博 写真・佐藤研二)
 高橋千鶴子衆院議員
高橋千鶴子衆院議員
「薄めて流せ」言うが…
500倍の希釈でも500倍流せば同じ
―「薄めて海に流せばいい」という政府に対し、海洋放出を決定する前日の国会で、放出反対の立場から菅義偉首相らに質問し、「海洋放出しても40年かかる。それだけの時間があれば、(放射性物質が半分に減る半減期が約12年の)トリチウムはもっと減衰し、新たな道も決まる」と指摘しましたね。
高橋 政府の中長期ロードマップで「復興と廃炉の両立」を大原則に、汚染水対策は廃炉と一体としています。そして福島第1原発の廃止措置は終了まで30~40年としています。仮に海洋放出したら何年かかるのか。海洋放出は仕方ないとか、海洋放出すれば目の前からタンクがたった数年でなくなると考える人も多い。でも40年、タンクはなくならないのです。
放出量では、福島第1原発の事故前のトリチウムの年間放出管理基準が22兆ベクレルです。今たまっている総量が860兆ベクレルなので、単純計算で約40年分です。東電の文挟(ふばさみ)誠一副社長に、現在のタンクがなくなるのに何年かかるかとただすと、福島第1原発の廃止措置に要する30~40年を使うと答弁しました。私は、そのくらい時間がかかるのだったら、急いで放出する必要はないと指摘しました。
しかも、放出するトリチウム濃度を1リットル当たり1500ベクレルの水準に下げるというのが政府の方針です。この値は、原子炉建屋への汚染水の流入量の増大を抑えるとして設置された建屋周辺の井戸(サブドレン)からくみ上げた地下水の放出を認めた時(2015年)の政治決着で決められたものです。仮に容量約1千トンのタンク1基分の処理後の水を薄めるのに500基分の海水が必要なのです。
実際、タンクを使うわけではないでしょうが、1基分だけで、今、敷地を埋めるタンク約1000基の半分に当たる量の海水を使う計画です。500倍に薄めても500倍の量を放出したら同じことじゃないかと質問すると、梶山弘志経済産業相は反論できませんでした。
 敷地内の汚染水タンク群。奥に並んでいるのは(左から)炉心溶融を起こした1~3号機原子炉建屋=2月5日、福島第1原発(本紙チャーター機から)
敷地内の汚染水タンク群。奥に並んでいるのは(左から)炉心溶融を起こした1~3号機原子炉建屋=2月5日、福島第1原発(本紙チャーター機から)
「タンクが満杯になる」
燃料デブリ800トン 具体策これから
―政府・東電はタンクの設置場所が足りない、22年秋ごろにはタンクが満杯になるから、放出はやむを得ないといっています。
高橋 タンクの置き場が満杯になるからと、そこだけが強調されていますが、資源エネルギー庁や東電は国会で、炉心溶融で溶け落ちた燃料デブリなどの一時保管施設や廃棄物の保管施設を建設するためのスペースが必要だというのです。そのためのスペースを空けることが大きな理由です。でも、総量800トン程度といわれる燃料デブリは極めて高線量で、取り出しができるのかわかっていません。いったい取り出した後の置き場所などつくれるのかと東電に聞くと、「具体的な検討はこれから」ということです。
結局、これまでの政府・東電の議論は「放出ありき」で説得しようとして、漁業関係者をはじめ国民の納得を得られなかったということではないでしょうか。トリチウムは国内外の原発からも放出されていると強調していますが、そもそもトリチウムの総量規制がなく、原発ごとに基準が違うことや、「京」単位のトリチウムを放出する再処理工場には基準さえないことを指摘してきました。
事故を起こした原子炉を通った汚染水にはトリチウム以外に62種の放射性物質があり、トリチウムの濃度や組成はタンクによって均一ではなく、通常の原発のものとは同一ではありません。現在タンク約1000基の7割に未処理のまま残っているトリチウム以外の放射性物質は2次処理して基準を下回るようにするといっています。以上のことから海洋に放出するのは「汚染水」ではないと政府は言い逃れしていますが、最後まで監視する必要があるのは言うまでもありません。
流さぬ立場で知見集めて
―問題の解決にはどうすればいいですか。
高橋 何より海に流さない立場に立って、科学的知見を集めて対応することで、新たな道も決まると思います。40年の間にタンクも建て替えなくてはいけないこともあるでしょう。その際に大型のタンクにするとか。トリチウムの分離技術の開発なども時間をかけられます。
―国会では漁民の声を代弁していました。
高橋 2月に宮城県に近い新地町沖でクロソイという魚から国基準の5倍のセシウムが見つかり、驚きました。事故から10年にもなるのに。福島県の漁師は原因を突き止めてほしいと言っています。被害の実態が正確に知られていないことがあるのではないでしょうか。
菅義偉首相は、福島の復興なくして日本の復興なしといいます。私は国会で、漁師をしたいという息子のいる漁師の言葉を伝え、「若い人たちが引き継いでいけなければ、復興なんてありえない。若い人に漁師を続けてもよいと言えますか」と求めたのに、首相から答えは最後までありませんでした。船を出してこそ漁師です。賠償では後継ぎはできません。政治の転換を強く思います。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年4月16日付掲載
東電の本音は、汚染水を貯めるタンクが一杯になることよりも、とりだしたデブリの置き場所の確保を考えているとのこと。
何より海に流さない立場に立って、科学的知見を集めて対応することで、新たな道も決まる。40年の間にタンクも建て替えなくてはいけないこともあるでしょう。その際に大型のタンクにするとか。トリチウムの分離技術の開発なども時間をかけらる。
地震大国で動かすな 福島事故10年 原理力施設林立の青森県
原発施設に核燃料再処理工場、中間貯蔵施設、MOX燃料工場(建設中)と、あらゆる危険な原子力施設を立地する青森県。
東京電力福島第1原発事故から10年にあたり、「核燃料サイクル施設立地反対連絡会議」の事務局長の谷崎嘉治さんに話を聞きました。(青森県・藤原朱)
核燃料サイクル施設立地反対連絡会議事務局長 谷崎嘉治さんに聞く
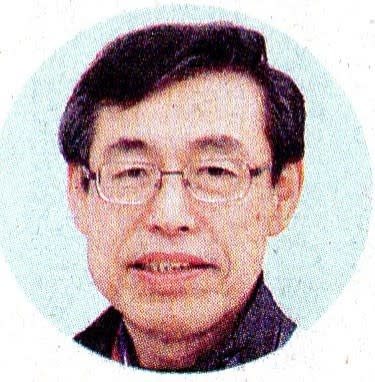 「福島第1原発事故10年全国世論調査」(日本世論調査会)の結果が6日発表され、「“脱原発”志向76%、安全性への懸念強く」「高レベル処分に不安79%」―と国民が脱原発へ向かっていることが示されました。
「福島第1原発事故10年全国世論調査」(日本世論調査会)の結果が6日発表され、「“脱原発”志向76%、安全性への懸念強く」「高レベル処分に不安79%」―と国民が脱原発へ向かっていることが示されました。
10万年の管理
日本原燃の六ケ所再処理工場(青森県六ケ所村)に保存されている高レベル放射性廃棄物のガラス固化体は、隣に人が居ると20秒で即死すると言われます。国は300メートルの地下で東京ドーム100個分ほどの面積に最終処分するとしていますが、10万年の管理が必要とされています。
2008年3月14日の閣議決定で、「平成40年代後半を目途に、最終処分を開始する」としましたが、残り16年しかないのです。
再処理を委託したフランスからのガラス固化体の最初の返還は、1995年4月26日です。日本原燃は青森県などと「50年後の六ケ所再処理工場からの搬出」と約束していますが、残りは24年です。
最終処分法で定められた処分地選定プロセスでは、文献調査2年、概要調査4年、精密調査14年、建設に10年の計30年が必要とされています。
現・三村申吾知事までの3代にわたる県知事が「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない」との確約書を歴代大臣と締結。県・六ケ所村・日本原燃との協定もそうなっていますが、約束が破られることは目に見えています。
2016年12月21日、原子力関係閣僚会議は「もんじゅ」の廃止方針を決定。核燃料サイクル事業は破たんしたのですが、核燃料が増殖しない高速炉開発なるものを、突如持ち出してきました。
絵にかいた餅
しかし、頼みの綱としたフランスの高速炉アストリッドの開発計画も中止に追い込まれ日本の開発は絵にかいた餅となる始末です。経済産業相が代わるたびに青森県知事が面会に出かけ、国の「核燃サイクル路線の堅持」を公言させる様は、滑稽さを通り越しています。
さらに、プルサーマルの使用済みMOX燃料や、むつ市中間貯蔵施設に搬入する使用済み核燃料を処理するはずの第2再処理工場は話題にも上りません。
東票電力福島第1原発事故10年を経て、最も危険な「核燃料デブリ」をどこに処理するか、現実の問題として浮上しています。「核のゴミ」問題に答えを出せないうちは、一切の原子力施設を動かしてはなりません。また、地震大国日本に原発・核燃施設を造ってはならないことを、原発事故が教えてくれました。
私たちの子ども、孫、その先々の世代への責任を果たすために、全国の仲間と手をつなぎ、原発ゼロ基本法案の成立へ政権交代を実現させましょう。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年3月27日付掲載
現・三村申吾知事までの3代にわたる県知事が「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない」との確約書を歴代大臣と締結。その一方で、経済産業相が代わるたびに青森県知事が面会に出かけ、国の「核燃サイクル路線の堅持」を公言させている矛盾。
これ以上、核のゴミを増やさないためにも、原発の再稼働はすべきではない。