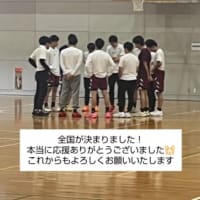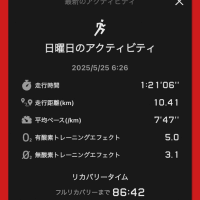思うことを。
合宿で指導をさせてもらいました。こういう機会があるというのは本当にありがたいなと思います。指導することで見えてくることもあります。選手が「強くなりたい」と思って学ぼうとする姿勢はこちらのモチベーションを上げる。逆に「言われたからやる」という選手に対して細かく指導をすることができません。人数が多いので。私の指導スタイルとしては大人数への指導は向かないかもしれないですね。
うちの選手、合宿でやったことに関してはほぼ毎日用のようにやっています。このことをどうとらえるか。慣れている部分があるので「やっていること」がどうなのかわかっていないかもしれない。今回の合宿で私自身が感じたことは「きちんと意識してやっていけば数日間でも動きは変わる」ということ。もちろんこれが定着するかどうかは別問題。動きが崩れたときに修正できるのかどうか。狙いとする動きが分かる指導者が側にいるとここができる。
技術的な指導をすると「もっと動きを良くしたい」と貪欲に取り組む選手の姿が目につきます。ある選手はしつこくSoに質問していました。更に何度も動きを見てもらってアドバイスをもらっていました。このチャンスを逃さないようにしたいという姿勢が出ていました。私自身、「隣の芝生は青く見える」というのがあるかもしれません。うちの選手にはない「取り組みの姿勢」がかなり印象に残りました。うちの選手は基本的に受け身。理由は簡単。「待っていたら与えられるから」です。
練習計画に関しても自分では何も考えなくても私が出します。そのメニューに従ってルーティンのようにやっていけばある程度の結果につながります。しかし、それは本当にいいことなのか。他校の選手を見ていると「普段専門的な指導が受けられないから」という感じで「見てください」とか「~が出来ないのですがどういう練習をしたらいいですか」と質問してくる。こういう感じになると「教えない」とは言いにくい。限られた時間で「得られるものはすべて得よう」という姿勢がありました。これは全てに繋がっていくと思います。強くなる可能性がかなり高い。悔しいですが・・・。
うちの選手はどちらかというと「小さくまとまっている」という感じがありました。自分たちの枠の中でやっている感じがある。元々積極的に質問をするという選手はいないのですが。それでも本当に競技力を上げようと思えばやはり「自ら動く」という部分は必須だと思います。NMも今はそれなりに走っています。が、今のままの姿勢では大人数の中で練習をすると埋もれてしまう危険性がある。これは今の私がきちんと伝えていかなければいけないことだと思っています。大学で競争をするということになったときに明らかに不利。性格的なものもあります。それでもこれから先を考えればやらなければいけない部分。変わってもらわないといけないと思います。
下の学年は「存在感がない」という感じでした。勿体ないなと。3年生に頼って練習をしている部分があります。うちは2年生で合宿に参加している選手がNa1人でした。そいう言う意味でも3年生に頼る部分が大きい。Naは自分に自信が持てない。それが行動に出ます。なんだかんだ言ってもうちで2年間しっかりと練習をしています。「陸上競技が好き」という部分は他の選手には絶対に負けていないと思います。だからこそ行動を変えなければいけない。それが出来なければこれから先のチーム作りは厳しい。負担は大きいですが。
これも記事に書きましたが全体が「前に出たい」という話をしていました。それは「そうやって言うことで意欲があることを認めてもらいたい」という雰囲気に感じました。本来的な話とは異なる。本当は「自分が強くなろうと思って話を聞きたい」から前に出るだけの話。後ろにいると聞こえないので。「前に出る」ことが求められているわけではない。自分の「想い」の結果が行動に出てくるだけです。「意欲的になろう」と思ってなるのではない。自分がやろうと思って行動したときに「意欲的だ」と相手に伝わるだけなのです。目的が違ってくる。
我々の希望としては「内から湧き上がってくる想い」の中で活動してもらいたいと思っています。与えられるモチベーションではない。話を聞こうと思えば前のめりになって身体を乗り出して聞く。寸暇を惜しんで動きの確認をする。言われてからやるというのではない。そう考えてみると前任校で劇的に伸びた男子は言われなくてもシャフト補強の間にドリルをやっていました。その事を何度紹介しても一時的な話では終わってしまう。こういう部分だと思います。
うちにはうちの良さもあると思います。しかし、他校から学ぶことはたくさんある。そこに気づくことができるかどうか。今うちに足りなくてもこれから身につけていけばいい。その感覚を持てるかどうか。技術的なモノを支えるのはやはり「取り組みの姿勢」だと思います。これも与えられれモノではなく自分達の中から出てくるモノでなければいけない。
今回の様子を客観的に見れれば良かったのですが。指導するという中ではどうしても主観的に見てしまう部分が出てしまう。足りないなと感じることが先に見えてしまうので。
それぞれがどう感じでくれるか。今後につながってくれる事を大きく期待したいと思います。
合宿で指導をさせてもらいました。こういう機会があるというのは本当にありがたいなと思います。指導することで見えてくることもあります。選手が「強くなりたい」と思って学ぼうとする姿勢はこちらのモチベーションを上げる。逆に「言われたからやる」という選手に対して細かく指導をすることができません。人数が多いので。私の指導スタイルとしては大人数への指導は向かないかもしれないですね。
うちの選手、合宿でやったことに関してはほぼ毎日用のようにやっています。このことをどうとらえるか。慣れている部分があるので「やっていること」がどうなのかわかっていないかもしれない。今回の合宿で私自身が感じたことは「きちんと意識してやっていけば数日間でも動きは変わる」ということ。もちろんこれが定着するかどうかは別問題。動きが崩れたときに修正できるのかどうか。狙いとする動きが分かる指導者が側にいるとここができる。
技術的な指導をすると「もっと動きを良くしたい」と貪欲に取り組む選手の姿が目につきます。ある選手はしつこくSoに質問していました。更に何度も動きを見てもらってアドバイスをもらっていました。このチャンスを逃さないようにしたいという姿勢が出ていました。私自身、「隣の芝生は青く見える」というのがあるかもしれません。うちの選手にはない「取り組みの姿勢」がかなり印象に残りました。うちの選手は基本的に受け身。理由は簡単。「待っていたら与えられるから」です。
練習計画に関しても自分では何も考えなくても私が出します。そのメニューに従ってルーティンのようにやっていけばある程度の結果につながります。しかし、それは本当にいいことなのか。他校の選手を見ていると「普段専門的な指導が受けられないから」という感じで「見てください」とか「~が出来ないのですがどういう練習をしたらいいですか」と質問してくる。こういう感じになると「教えない」とは言いにくい。限られた時間で「得られるものはすべて得よう」という姿勢がありました。これは全てに繋がっていくと思います。強くなる可能性がかなり高い。悔しいですが・・・。
うちの選手はどちらかというと「小さくまとまっている」という感じがありました。自分たちの枠の中でやっている感じがある。元々積極的に質問をするという選手はいないのですが。それでも本当に競技力を上げようと思えばやはり「自ら動く」という部分は必須だと思います。NMも今はそれなりに走っています。が、今のままの姿勢では大人数の中で練習をすると埋もれてしまう危険性がある。これは今の私がきちんと伝えていかなければいけないことだと思っています。大学で競争をするということになったときに明らかに不利。性格的なものもあります。それでもこれから先を考えればやらなければいけない部分。変わってもらわないといけないと思います。
下の学年は「存在感がない」という感じでした。勿体ないなと。3年生に頼って練習をしている部分があります。うちは2年生で合宿に参加している選手がNa1人でした。そいう言う意味でも3年生に頼る部分が大きい。Naは自分に自信が持てない。それが行動に出ます。なんだかんだ言ってもうちで2年間しっかりと練習をしています。「陸上競技が好き」という部分は他の選手には絶対に負けていないと思います。だからこそ行動を変えなければいけない。それが出来なければこれから先のチーム作りは厳しい。負担は大きいですが。
これも記事に書きましたが全体が「前に出たい」という話をしていました。それは「そうやって言うことで意欲があることを認めてもらいたい」という雰囲気に感じました。本来的な話とは異なる。本当は「自分が強くなろうと思って話を聞きたい」から前に出るだけの話。後ろにいると聞こえないので。「前に出る」ことが求められているわけではない。自分の「想い」の結果が行動に出てくるだけです。「意欲的になろう」と思ってなるのではない。自分がやろうと思って行動したときに「意欲的だ」と相手に伝わるだけなのです。目的が違ってくる。
我々の希望としては「内から湧き上がってくる想い」の中で活動してもらいたいと思っています。与えられるモチベーションではない。話を聞こうと思えば前のめりになって身体を乗り出して聞く。寸暇を惜しんで動きの確認をする。言われてからやるというのではない。そう考えてみると前任校で劇的に伸びた男子は言われなくてもシャフト補強の間にドリルをやっていました。その事を何度紹介しても一時的な話では終わってしまう。こういう部分だと思います。
うちにはうちの良さもあると思います。しかし、他校から学ぶことはたくさんある。そこに気づくことができるかどうか。今うちに足りなくてもこれから身につけていけばいい。その感覚を持てるかどうか。技術的なモノを支えるのはやはり「取り組みの姿勢」だと思います。これも与えられれモノではなく自分達の中から出てくるモノでなければいけない。
今回の様子を客観的に見れれば良かったのですが。指導するという中ではどうしても主観的に見てしまう部分が出てしまう。足りないなと感じることが先に見えてしまうので。
それぞれがどう感じでくれるか。今後につながってくれる事を大きく期待したいと思います。