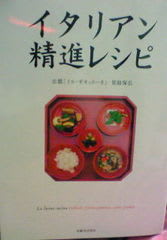青江美智子 著 「お寺に嫁いでしまった」扶桑社
青江美智子 著 「お寺に嫁いでしまった」扶桑社普通のOL生活から浄土真宗寺院(東京・浅草)の住職後継者と結婚し、まだ少々、戸惑いながら生活されている若坊守さんの著書です。
インターネット寺院「彼岸寺」のブログをまとめられたものです。超宗派の僧侶達のインターネット寺院「彼岸寺」の僧侶仲間のお一人が著者の夫・若住職さんなのですが・・・
今回、拝読するまで私、「彼岸寺」のことを知りませんでした。
「彼岸寺」の中心人物に「松本圭介」師のお名前を見て、私オバサン、ハッと思い出しました

 彼(松本圭介)の著書「お坊さん、はじめました」ダイアモンド社
彼(松本圭介)の著書「お坊さん、はじめました」ダイアモンド社を読んだことがあったからです。
彼は、1979年生まれの若い本願寺派僧侶・布教使です。
東大(文学部哲学科)卒業後、お寺の息子じゃないのに、お坊さんになった方です。
著書にもなった彼のブログから発展して「彼岸寺」が設立されたようです。
お寺での音楽会「誰そ彼」や、無線LAN完備の寺院内カフェ「ツナガルオテラ 神谷町オープンテラス」のことも何かで目にしたことがありましたが、それを運営しているのが、彼だったんですねえ~。
お寺を人が集まる場所に・・・、そして、これからの仏教伝道を「どげんかせんと、いかん
 」と立ち上がり、活動しておられる、若い僧侶の皆さんや若坊守さん方のやる気に、感動しています。
」と立ち上がり、活動しておられる、若い僧侶の皆さんや若坊守さん方のやる気に、感動しています。










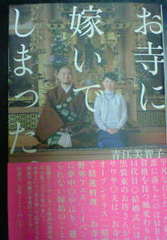


 )
) また、それが、お寺を預かっている「寺の者」のつとめだと思っています。
また、それが、お寺を預かっている「寺の者」のつとめだと思っています。
 「この人に聞く・ひとすじの道」で紹介されている方は、
「この人に聞く・ひとすじの道」で紹介されている方は、 それにしても半年の約束がもうすぐ30年。なぜ、こんなに長く? とたずねると、
それにしても半年の約束がもうすぐ30年。なぜ、こんなに長く? とたずねると、

 、「はたらく」
、「はたらく」 、そういう「はたらき」に成ることを意味します。
、そういう「はたらき」に成ることを意味します。 」と悲壮感漂わせ・・・あるいは、義務感で眉間にしわをよせて・・・仕方なく働くのではなく、
」と悲壮感漂わせ・・・あるいは、義務感で眉間にしわをよせて・・・仕方なく働くのではなく、 ・・・人の笑顔がうれしいから
・・・人の笑顔がうれしいから ・・・自分がそうしたいから・・・
・・・自分がそうしたいから・・・





 でした。この新年会は、毎年、法専寺を離れ、料亭にて開催。
でした。この新年会は、毎年、法専寺を離れ、料亭にて開催。




 今朝の佐賀市の最低気温は氷点下でした。
今朝の佐賀市の最低気温は氷点下でした。