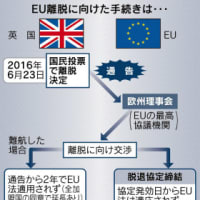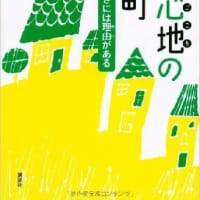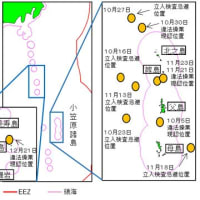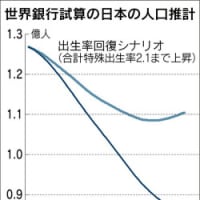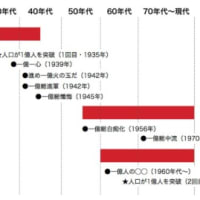バルサのボール奪取は素晴らしかった。前半36分の先制点は左外で相手を囲んだボール奪取が起点となった。横浜国際の正面2階、右手ゴールラインより少し内側の席で見ていると、アウベスの右からのクロスを左のネイマールがヘッドの折り返し、中央のメッシに届いたことは、何とか判った。しかし、最後の得点シーンが良く判らなかった。
大型画面に再生録画が映って、回りの守備者が足を出せない腰辺りのボール、メッシが左足アウトで正確に突いたのが判った。瞬時の判断、リラックスした身体、膝の柔らかさが相俟って、思いがけない見事なシュートが生まれた。
後半になると、ルーズボールの取り合いは、バルサがリバープレートを圧倒していた。中盤のブスケツ、ラキティッチ、イニエスタを中心に、バルサはチームとしての“具体的な状況判断の方法論を確立”していたかの様である。
即ち、典型的にはルーズボールの状態だ。この時、状況は瞬時、瞬時に変わり、判断も都度、変える必要がある。しかし、ボールが出てくる間、次のプレーの判断が難しい状態もある。通常は判断を停止して次の瞬間を待つ。
良く言われる“ボールウォッチング”の状態だ。
バルサの方法論は、チーム全員で共通のコンセプトを持ち、ルーズボールの状態においても、瞬時の判断を変えながら持続し、その実行に見合った具体的なプレーをこれも全員で、特にボールの周辺地域で連携して、続けていくことにあると筆者は感じた。それを敵の選手が判断停止になった瞬時において実行し、その瞬時の分だけ速くプレーをすることになる。その瞬時を全員で積分し、パスを繋いでいけば、空間的にフリーでボールを受ける選手が出てくる。
即ち、“判断時間を自由空間”に変換することだ。別の眼でみれば、バルサは網を張って仕掛けているようだが、本質は判断時間の創出だ。
後半開始直後、スアレスがディフェンスの裏に走り抜け追加点を生んだ速攻も中盤でボールを相手方から奪い取ったことから始まった。前半の1点が効いて、リバープレートが攻勢の体勢を取ったことが中盤でのスペースを生んだ。スアレスの素早い反応に対して正確なフィードがイニエスタから横パスを受けたブスケツから送られた。
結局、スアレスがネイマールの足下からのフワッとした短いパスを守備陣の裏に下がりながらヘッドで決めて、クラブワールドカップ決勝(12/20夜)は、バルサがリバープレートに3対0で快勝し、3度目のクラブ世界一に輝いた。
 FIFA
FIFA
3点は共にバルサの知性的なサッカーを象徴する。しかし、サッカーは力と技術が伴った体を使い、それがチームプレーとして表現されるスポーツだ。それは野性の中で集団として獲物を捕らえる動物、ハイエナに似ている。
先の記事でJリーグ・サガン鳥栖のゲームにハイエナ的なプレーを感じた。
「…素早く敵に寄り、仕掛ける体勢を採り、相手を追い詰める。少しのボールコントロールの乱れを突いてタックルに入る。繋ぎの横パスを出させて、その受け手に次の守備者が詰め寄る…」
『ハイエナ的野性を持つ「サガン鳥栖」のボール奪取~尹晶煥前監督の指導150524』
これは従来の戦術を徹底したものだ。それでも、今のJリーグでは貴重なアプローチだ。しかし、バルサの戦略は、単に包囲網を構成するのとは異なった新たな次元に入ったと考える。その基本は野性動物が持つ強靱でしなやかな体を基盤にするものだ。そして、それはサッカーを面白くすると共に素晴らしさを新たに示すことでもある。
大型画面に再生録画が映って、回りの守備者が足を出せない腰辺りのボール、メッシが左足アウトで正確に突いたのが判った。瞬時の判断、リラックスした身体、膝の柔らかさが相俟って、思いがけない見事なシュートが生まれた。
後半になると、ルーズボールの取り合いは、バルサがリバープレートを圧倒していた。中盤のブスケツ、ラキティッチ、イニエスタを中心に、バルサはチームとしての“具体的な状況判断の方法論を確立”していたかの様である。
即ち、典型的にはルーズボールの状態だ。この時、状況は瞬時、瞬時に変わり、判断も都度、変える必要がある。しかし、ボールが出てくる間、次のプレーの判断が難しい状態もある。通常は判断を停止して次の瞬間を待つ。
良く言われる“ボールウォッチング”の状態だ。
バルサの方法論は、チーム全員で共通のコンセプトを持ち、ルーズボールの状態においても、瞬時の判断を変えながら持続し、その実行に見合った具体的なプレーをこれも全員で、特にボールの周辺地域で連携して、続けていくことにあると筆者は感じた。それを敵の選手が判断停止になった瞬時において実行し、その瞬時の分だけ速くプレーをすることになる。その瞬時を全員で積分し、パスを繋いでいけば、空間的にフリーでボールを受ける選手が出てくる。
即ち、“判断時間を自由空間”に変換することだ。別の眼でみれば、バルサは網を張って仕掛けているようだが、本質は判断時間の創出だ。
後半開始直後、スアレスがディフェンスの裏に走り抜け追加点を生んだ速攻も中盤でボールを相手方から奪い取ったことから始まった。前半の1点が効いて、リバープレートが攻勢の体勢を取ったことが中盤でのスペースを生んだ。スアレスの素早い反応に対して正確なフィードがイニエスタから横パスを受けたブスケツから送られた。
結局、スアレスがネイマールの足下からのフワッとした短いパスを守備陣の裏に下がりながらヘッドで決めて、クラブワールドカップ決勝(12/20夜)は、バルサがリバープレートに3対0で快勝し、3度目のクラブ世界一に輝いた。
 FIFA
FIFA3点は共にバルサの知性的なサッカーを象徴する。しかし、サッカーは力と技術が伴った体を使い、それがチームプレーとして表現されるスポーツだ。それは野性の中で集団として獲物を捕らえる動物、ハイエナに似ている。
先の記事でJリーグ・サガン鳥栖のゲームにハイエナ的なプレーを感じた。
「…素早く敵に寄り、仕掛ける体勢を採り、相手を追い詰める。少しのボールコントロールの乱れを突いてタックルに入る。繋ぎの横パスを出させて、その受け手に次の守備者が詰め寄る…」
『ハイエナ的野性を持つ「サガン鳥栖」のボール奪取~尹晶煥前監督の指導150524』
これは従来の戦術を徹底したものだ。それでも、今のJリーグでは貴重なアプローチだ。しかし、バルサの戦略は、単に包囲網を構成するのとは異なった新たな次元に入ったと考える。その基本は野性動物が持つ強靱でしなやかな体を基盤にするものだ。そして、それはサッカーを面白くすると共に素晴らしさを新たに示すことでもある。