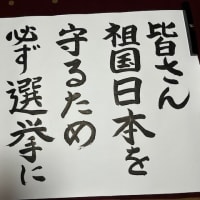ブログの開設にあたって、親切な若者のお世話になりました。ポツポツとようやく文字を打っている私なので、処々ミスもあろうかと思いますが、お読み下さる方のご寛容にすがりたい。宜しく。
11月13日(日)【供養記】
今日は二十代の青年の七七日忌で納骨である。若い人のご供養はことさらに責任が重い。家族の悲しみが深いことが伝わってくる。
七七日忌はご葬儀とは違う意味で大事な供養だ。ご葬儀の時は遺族も亡くなった本人も、その死が信じられないような、夢のような時の流れの中で夢中であろう。しかし七七日忌はご葬儀のときとは違い、遺族は故人の死を実感しつつ四十九日間を過ごしたあとの供養である。故人自身にとっても四十九日の間、この世の者からは見えなくとも、縁あった人々を訪ねてお別れをして過ごした後に迎える供養である。そしていよいよこの世にあった気が薄れていくお別れの時であると、私は実感している。
四十九日の間は軒端にいる、昔からそう言われたものであるが、この頃の若い人は知っているだろうか。キリスト教の友人に尋ねたところキリスト教でも"FIFTY DAYS"という固有名詞のついた供養日があるという。神道では「五十日祭」と書いて「いとかさい」と読むが、やはり死後五十日後の供養がある。いずれも死後五十日ぐらいに特別な供養日をもうけているということは、やはりこのくらいの期間が、死者にとって特別な意味がある期間であるといえよう。仏教ではこの間は中有にあるという。この世とあの世の間を中有というのである。四十九日の後、死者はどのようになるか、私には確信はないが、この四十九日の間は、死者は縁ある人たちに、お別れをしているということを、私は実感している。
そうであるから、私は四十九日の供養は特に大切であることを伝えたいと思っている。この世の者も、あの世に帰りゆく者もお互いにお礼を言い合い、別れを惜しみたいと思うのである。僧侶は事あるごとにこのことを伝えたいものだと、私は思う。生きている時に聞いておけば、自分にいよいよその時がきたら、よりしっかりと挨拶回りができるというものだろう。そしてこの世の者もせめて四十九日ぐらいは喪に服して、静かにすごしたいものだ。あの世の者のかそけき気配を感じるためにも。せっかくあなたにお別れに来ている人の気配を感じられなくては残念というものだから。二度と無いことなのだから。
青年に対しての誦経が終わった時、「楽になったァ」と声が、私の胸に飛びこんできた。
法話の時にそのことをそれとなくお伝えしたら、「苦しんでいるんじゃないんですか」とご両親は聞きかえされた。病気で苦しんでいたのではないかと思っていたのであろう。「いいえ、楽になったようですよ。」と私は再び伝えた。「楽になりました」というのでなく「楽になったァ」という言葉が、私には本当に楽になったのだな、という感じがした。
四十九日の間であると、私も時々故人の言葉が聞こえるような気がする。証明ができるわけではないのであるが、その人の言葉としか思えない言葉であるのが、証明のようなものである。その言葉はポンと飛んでくるような感じがするので、私が心に思うこととは別なのだ。まあ、しかし、証明はできないので気のせいと言っておこう。
11月13日(日)【供養記】
今日は二十代の青年の七七日忌で納骨である。若い人のご供養はことさらに責任が重い。家族の悲しみが深いことが伝わってくる。
七七日忌はご葬儀とは違う意味で大事な供養だ。ご葬儀の時は遺族も亡くなった本人も、その死が信じられないような、夢のような時の流れの中で夢中であろう。しかし七七日忌はご葬儀のときとは違い、遺族は故人の死を実感しつつ四十九日間を過ごしたあとの供養である。故人自身にとっても四十九日の間、この世の者からは見えなくとも、縁あった人々を訪ねてお別れをして過ごした後に迎える供養である。そしていよいよこの世にあった気が薄れていくお別れの時であると、私は実感している。
四十九日の間は軒端にいる、昔からそう言われたものであるが、この頃の若い人は知っているだろうか。キリスト教の友人に尋ねたところキリスト教でも"FIFTY DAYS"という固有名詞のついた供養日があるという。神道では「五十日祭」と書いて「いとかさい」と読むが、やはり死後五十日後の供養がある。いずれも死後五十日ぐらいに特別な供養日をもうけているということは、やはりこのくらいの期間が、死者にとって特別な意味がある期間であるといえよう。仏教ではこの間は中有にあるという。この世とあの世の間を中有というのである。四十九日の後、死者はどのようになるか、私には確信はないが、この四十九日の間は、死者は縁ある人たちに、お別れをしているということを、私は実感している。
そうであるから、私は四十九日の供養は特に大切であることを伝えたいと思っている。この世の者も、あの世に帰りゆく者もお互いにお礼を言い合い、別れを惜しみたいと思うのである。僧侶は事あるごとにこのことを伝えたいものだと、私は思う。生きている時に聞いておけば、自分にいよいよその時がきたら、よりしっかりと挨拶回りができるというものだろう。そしてこの世の者もせめて四十九日ぐらいは喪に服して、静かにすごしたいものだ。あの世の者のかそけき気配を感じるためにも。せっかくあなたにお別れに来ている人の気配を感じられなくては残念というものだから。二度と無いことなのだから。
青年に対しての誦経が終わった時、「楽になったァ」と声が、私の胸に飛びこんできた。
法話の時にそのことをそれとなくお伝えしたら、「苦しんでいるんじゃないんですか」とご両親は聞きかえされた。病気で苦しんでいたのではないかと思っていたのであろう。「いいえ、楽になったようですよ。」と私は再び伝えた。「楽になりました」というのでなく「楽になったァ」という言葉が、私には本当に楽になったのだな、という感じがした。
四十九日の間であると、私も時々故人の言葉が聞こえるような気がする。証明ができるわけではないのであるが、その人の言葉としか思えない言葉であるのが、証明のようなものである。その言葉はポンと飛んでくるような感じがするので、私が心に思うこととは別なのだ。まあ、しかし、証明はできないので気のせいと言っておこう。