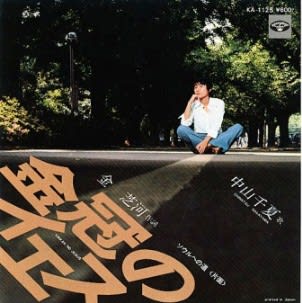10数年前に観た時には記憶に残っていなかった韓国映画「鯨とり ナドヤカンダ」中の乞食親分ミヌ(アン・ソンギ)が歌う<乞食節>。この映画について書かれた多くのブログにとり上げられています。
ミヌが村の子どもに乞食節を歌ってくれと言われて歌い踊ります。ということは、乞食節はミヌの個人芸ではなく、子どもも知っているほどの乞食一般の芸だということがわかります。
原語では<거지타령(コジタリョン.乞食打令)>です。
<거지타령>を動画検索すると、興味深い動画がいくつもヒットします。
ところが、そのタイトルは<거지타령>以外にも<각서리타령(カクソリ打令)>、<품바타령(プンバ打令>、あるいは<장타령(チャン打令)>となっているのもあります。しかし内容的には、大体が大道芸人が人々の笑いをとるような歌(+語り)で、どれも同じようなものです。
その中で、忠清北道・チャゲ芸術村の公演の出し物の、なかなか芸達者なオジサンの<プンバ打令>の動画を見つけました。歌詞や節回し等は映画の乞食節とよく似ています。
【 1:58からプンバ打令が始まります。】
この他にも、民謡風のものをステージで演じているカクソリ打令、ステージ歌謡のカクソリ打令(チャン打令)や、祭等の際に屋外で大道芸人が演じているもの等があります。
NAVER辞典等で、上記の言葉の意味を調べた結果は次の通り。
・장타령꾼(チャンタリョンクン)=各地の市場を廻って、장타령を歌いながら物乞いをする人。
・각설이(カクソリ)=장타령꾼の蔑称。
・품바(プンバ)=市場や往来を廻って物乞いをする人
・・・つまり、ほぼ同じような意味のようですね。
ただ、プンバという言葉は、大邱で開かれた「プンバ祝祭」や、木浦文化芸術会館でのマダン劇の公演のタイトル「プンバ、プンバ」等々、多くの例にあるように、そんなに抵抗感なく、一般的に用いられる言葉のようです。
【2009年8月大邱Wカップ競技場での第1回プンバ祝祭より。約21分と長いですが、14:15から例の「カクソリ打令」が始まります。】
カクソリ打令の歌詞は、たとえばコチラに載っていますが、これはあくまでも一例。
ただ、冒頭の一節は共通しています。
얼씨구 씨구 들어간다 절씨구 씨구 들어간다
작년에 왔던 각설이가 죽지도 않고 또왔네
(試訳)エッサカエッサカ やってくる ホイサカホイサカ やってくる
去年来ましたカクソリが 死にもしないでまた来たよ
・・・こんな感じですかねー。踊りの方も、手の振り方とか一定の型があるようですね。
ネット内をいろいろ探っていくうちに、<デジタル公州文化大全>というサイト中に<カクソリ打令>についての詳しい説明記事をみつけました。
そこには、「文化財庁から刊行された研究書によると、カクソリ打令は公州と礼山一円で発生したという」とあり、カクソリ打令の定義からして「忠清南道公州市一円で歌われた乞人の歌の通称」としています。
また、公州市では、カクソリたちが歌っていた歌を次のように分類しています。
①プンバ打令・・・乞人たちが物乞いをする時に歌う歌。
②乞食私説(거지 사설.コジサソル)・・・乞人たちが自分の人生や世の中を嘆いたり称えたりする歌。
③チャン打令・・・5日市が立った市場の名称を歌う。「コリ(고리.輪)打令」「タリ(다리.足)打令」も同類。
以下、さらに細かな分類が記されていますが、煩瑣になるので略します。つまりは、これらを総称してカクソリ打令としているわけですね。(公州市としては・・・。)
※上記の「私説」に関連して、「私説遊び(사설놀이)」と銘打った動画がありました。→コチラ。(「私説」と記しましたが、「邪説」かも・・・。)
なお、この記事中で興味深いのは次の部分です。
現代のカクソリ打令は物乞いの時歌う楽しい歌だが、公州では哀しいカクソリ打令は1970年代までよく歌われた。2000年までもこの歌をよく歌ったが、今はあまり歌われない。
時代の変遷とともに、カクソリ打令を歌って物乞いをする本物の乞食も姿を消したということなんでしょうね。映画「鯨とり」のように、子どもが乞食に乞食節をリクエストする、というのも昔の話になったといっていいのかも・・・。
日本でも、大道芸人やいろんな物売りが見られたのはほぼ60年代までだったし・・・。
さて、最後になりましたが、映画「鯨とり」についてのオドロキの韓国サイトを発見しました。
まさにオドロキの詳述+動画+画像+音声です。アン・ソンギの「乞食節」の音声も流れているし「傾けると水着が脱げるボールペン(笑)」の動画もありますよ。これは必見! →コチラ。(→日本語自動翻訳)
ミヌが村の子どもに乞食節を歌ってくれと言われて歌い踊ります。ということは、乞食節はミヌの個人芸ではなく、子どもも知っているほどの乞食一般の芸だということがわかります。
原語では<거지타령(コジタリョン.乞食打令)>です。
<거지타령>を動画検索すると、興味深い動画がいくつもヒットします。
ところが、そのタイトルは<거지타령>以外にも<각서리타령(カクソリ打令)>、<품바타령(プンバ打令>、あるいは<장타령(チャン打令)>となっているのもあります。しかし内容的には、大体が大道芸人が人々の笑いをとるような歌(+語り)で、どれも同じようなものです。
その中で、忠清北道・チャゲ芸術村の公演の出し物の、なかなか芸達者なオジサンの<プンバ打令>の動画を見つけました。歌詞や節回し等は映画の乞食節とよく似ています。
【 1:58からプンバ打令が始まります。】
この他にも、民謡風のものをステージで演じているカクソリ打令、ステージ歌謡のカクソリ打令(チャン打令)や、祭等の際に屋外で大道芸人が演じているもの等があります。
NAVER辞典等で、上記の言葉の意味を調べた結果は次の通り。
・장타령꾼(チャンタリョンクン)=各地の市場を廻って、장타령を歌いながら物乞いをする人。
・각설이(カクソリ)=장타령꾼の蔑称。
・품바(プンバ)=市場や往来を廻って物乞いをする人
・・・つまり、ほぼ同じような意味のようですね。
ただ、プンバという言葉は、大邱で開かれた「プンバ祝祭」や、木浦文化芸術会館でのマダン劇の公演のタイトル「プンバ、プンバ」等々、多くの例にあるように、そんなに抵抗感なく、一般的に用いられる言葉のようです。
【2009年8月大邱Wカップ競技場での第1回プンバ祝祭より。約21分と長いですが、14:15から例の「カクソリ打令」が始まります。】
カクソリ打令の歌詞は、たとえばコチラに載っていますが、これはあくまでも一例。
ただ、冒頭の一節は共通しています。
얼씨구 씨구 들어간다 절씨구 씨구 들어간다
작년에 왔던 각설이가 죽지도 않고 또왔네
(試訳)エッサカエッサカ やってくる ホイサカホイサカ やってくる
去年来ましたカクソリが 死にもしないでまた来たよ
・・・こんな感じですかねー。踊りの方も、手の振り方とか一定の型があるようですね。
ネット内をいろいろ探っていくうちに、<デジタル公州文化大全>というサイト中に<カクソリ打令>についての詳しい説明記事をみつけました。
そこには、「文化財庁から刊行された研究書によると、カクソリ打令は公州と礼山一円で発生したという」とあり、カクソリ打令の定義からして「忠清南道公州市一円で歌われた乞人の歌の通称」としています。
また、公州市では、カクソリたちが歌っていた歌を次のように分類しています。
①プンバ打令・・・乞人たちが物乞いをする時に歌う歌。
②乞食私説(거지 사설.コジサソル)・・・乞人たちが自分の人生や世の中を嘆いたり称えたりする歌。
③チャン打令・・・5日市が立った市場の名称を歌う。「コリ(고리.輪)打令」「タリ(다리.足)打令」も同類。
以下、さらに細かな分類が記されていますが、煩瑣になるので略します。つまりは、これらを総称してカクソリ打令としているわけですね。(公州市としては・・・。)
※上記の「私説」に関連して、「私説遊び(사설놀이)」と銘打った動画がありました。→コチラ。(「私説」と記しましたが、「邪説」かも・・・。)
なお、この記事中で興味深いのは次の部分です。
現代のカクソリ打令は物乞いの時歌う楽しい歌だが、公州では哀しいカクソリ打令は1970年代までよく歌われた。2000年までもこの歌をよく歌ったが、今はあまり歌われない。
時代の変遷とともに、カクソリ打令を歌って物乞いをする本物の乞食も姿を消したということなんでしょうね。映画「鯨とり」のように、子どもが乞食に乞食節をリクエストする、というのも昔の話になったといっていいのかも・・・。
日本でも、大道芸人やいろんな物売りが見られたのはほぼ60年代までだったし・・・。
さて、最後になりましたが、映画「鯨とり」についてのオドロキの韓国サイトを発見しました。
まさにオドロキの詳述+動画+画像+音声です。アン・ソンギの「乞食節」の音声も流れているし「傾けると水着が脱げるボールペン(笑)」の動画もありますよ。これは必見! →コチラ。(→日本語自動翻訳)