
ぼくのお話聞いて聞いてと喚きしのち子は考えるぼくのお話
本を読み文字を活字に置き換えて消費されゆくわが年月は
ほととぎす死にたいなどと子が啼けば躾と虐待あやめも知らず
締切は守ってほしいなり夫荒れて子供が泣いて週末暗澹
ああ今日も何も出来ずと思うとき子供と遊んだこと忘れおり
男性歌人の歌集の中に子供らはいともたやすく育ちてゆきぬ
みかんの香他人の子供に感じおり生(な)しし子全て逝かせし利玄
はしきやしいとも小さきパンツにはいとも小さきピカチュウ笑まう
母が私を育てたように子を育て ていればいいのかデンファレ揺れる
報酬の欲しさに影を売り渡し教壇に立つ二十数年
もう一度赤児になってほしいなとランドセル背負(しよ)う背中見てゐる
(川本千栄 日ざかり ながらみ書房)
********************************
川本千栄『日ざかり』から。
四首目。松村正直氏は塔短歌会の編集長なので、詠草など原稿の締め切りを守らない人がいると、イライラして家の中が暗澹とした状態になるという歌。リアルにわかり同情してしまう。よその結社のことはわからないが、どこの短歌結社もほぼボランティアで編集作業が行われていると思う。勉強になると思えば、そうなのだが、ボランティアで家庭を犠牲にするようなことはキツイ。結社に長くいたり、試行錯誤するうちに、だんだんどうすれば物事がスムーズにすすむか、迷惑をかけないか、わかってくるが、締切を守るのは、最低の約束事。村上春樹は、必ず締切を守って、早めに原稿をトントンと揃える人だとどこかで読んだがいまでもそうなのだろうか。破滅型の人の方が、短歌や小説など芸術関係では才能があるという考えもある。わたしのような凡人は、せめて締切を守ること、休まないことくらいしか出来ない。あす12日は短歌人の締切日。いまごろ原稿を書いている人もいるのだろうか。いま書いているのでは、間に合わないな。締切というのは「余裕」を持って設定されているのだろうか。いろいろ考えてしまう。
六首目。歌人であれ、別の職業であれ、子供に関わることでは、母親の方に重心がかかってしまうのが現状。男性歌人で子育ての歌、子供をなくした歌を書く人もいるが、やはり女性の方が切羽詰まった感じがする。世の中に子育てが楽しくて幸せだと、いつも思っている女性はいるのだろうか。居ればそれは稀な幸福な人だと、わたしは感じる。
九首目。「育て て」と一字開けがある。ここに作者の峻順が感じられる。時代がちがうので、母親が自分を育ててくれたようには、わが子を育てることはできない。結句に子育てと関係のない花の名前を持ってきたことで、ふっと息が抜ける気がした。
最後の一首。それでも子供が成長してランドセルを背負う姿を見ると、まぶしくもあり、もっと小さかったころを懐かしむ気持ちもわいてくる。素直に共感できる。
本を読み文字を活字に置き換えて消費されゆくわが年月は
ほととぎす死にたいなどと子が啼けば躾と虐待あやめも知らず
締切は守ってほしいなり夫荒れて子供が泣いて週末暗澹
ああ今日も何も出来ずと思うとき子供と遊んだこと忘れおり
男性歌人の歌集の中に子供らはいともたやすく育ちてゆきぬ
みかんの香他人の子供に感じおり生(な)しし子全て逝かせし利玄
はしきやしいとも小さきパンツにはいとも小さきピカチュウ笑まう
母が私を育てたように子を育て ていればいいのかデンファレ揺れる
報酬の欲しさに影を売り渡し教壇に立つ二十数年
もう一度赤児になってほしいなとランドセル背負(しよ)う背中見てゐる
(川本千栄 日ざかり ながらみ書房)
********************************
川本千栄『日ざかり』から。
四首目。松村正直氏は塔短歌会の編集長なので、詠草など原稿の締め切りを守らない人がいると、イライラして家の中が暗澹とした状態になるという歌。リアルにわかり同情してしまう。よその結社のことはわからないが、どこの短歌結社もほぼボランティアで編集作業が行われていると思う。勉強になると思えば、そうなのだが、ボランティアで家庭を犠牲にするようなことはキツイ。結社に長くいたり、試行錯誤するうちに、だんだんどうすれば物事がスムーズにすすむか、迷惑をかけないか、わかってくるが、締切を守るのは、最低の約束事。村上春樹は、必ず締切を守って、早めに原稿をトントンと揃える人だとどこかで読んだがいまでもそうなのだろうか。破滅型の人の方が、短歌や小説など芸術関係では才能があるという考えもある。わたしのような凡人は、せめて締切を守ること、休まないことくらいしか出来ない。あす12日は短歌人の締切日。いまごろ原稿を書いている人もいるのだろうか。いま書いているのでは、間に合わないな。締切というのは「余裕」を持って設定されているのだろうか。いろいろ考えてしまう。
六首目。歌人であれ、別の職業であれ、子供に関わることでは、母親の方に重心がかかってしまうのが現状。男性歌人で子育ての歌、子供をなくした歌を書く人もいるが、やはり女性の方が切羽詰まった感じがする。世の中に子育てが楽しくて幸せだと、いつも思っている女性はいるのだろうか。居ればそれは稀な幸福な人だと、わたしは感じる。
九首目。「育て て」と一字開けがある。ここに作者の峻順が感じられる。時代がちがうので、母親が自分を育ててくれたようには、わが子を育てることはできない。結句に子育てと関係のない花の名前を持ってきたことで、ふっと息が抜ける気がした。
最後の一首。それでも子供が成長してランドセルを背負う姿を見ると、まぶしくもあり、もっと小さかったころを懐かしむ気持ちもわいてくる。素直に共感できる。










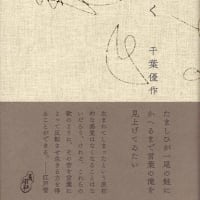
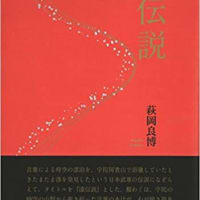
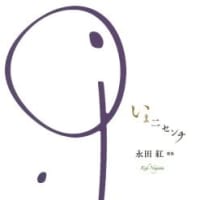
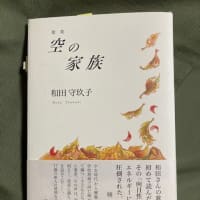
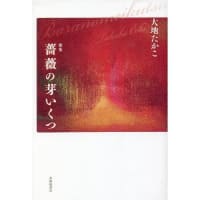
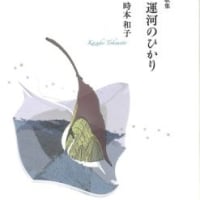
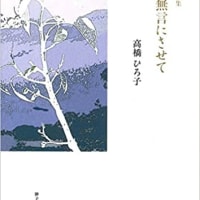
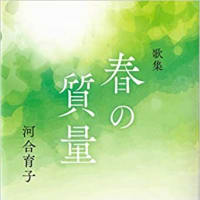
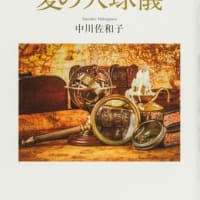
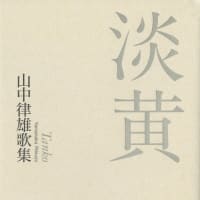
みかんの香他人の子供に感じおり生(な)しし子全て逝かせし利玄
下句のような内容を持った歌を私は、良く見つけましたね歌、と便宜上よんでいます。小池、竹山、島田、石田さんなどが、ときどき作られますよね。その場合、上句下句の全体で良く見つけましたね、の内容を歌った作品が多いようにおもいます。そういう意味では、女性特有というか、新しい歌かもしれません。全は、ひらがななら見た感じが少しやわらかいかもしれません。
木下利玄の歌「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」と、四人の子供をすべて亡くしたという不運の人生を踏まえた歌ですね。川本さんは評論も書かれる方なので、調べものをしているときに見つけられたのでしょう。わが家にある『近代短歌の鑑賞77』で利玄のところを読むと享年は40歳。わたしたちよりずっと若くで亡くなっているのですね。
木下利玄については、以前、如月桂さん(現矢野佳津さん)が評論を書かれて、短歌人の評論エッセイ賞をとられたことがありました。あれは四四調などリズムについてのことが主なテーマだったと思います。矢野さんとは親しいので機会があれば、聞いておきます。
古本まつりを今やっていて、行きたいのですが、家族の用事が先なので、行けるかどうかわかりません。もし茂吉全集のバラ売りを見つけたら、27、28巻を探してみます。
みな、それぞれオタクですよね。わたしも相当変わった主婦です。主婦業はまったくダメで自信なし。これから墓参りに行きます。