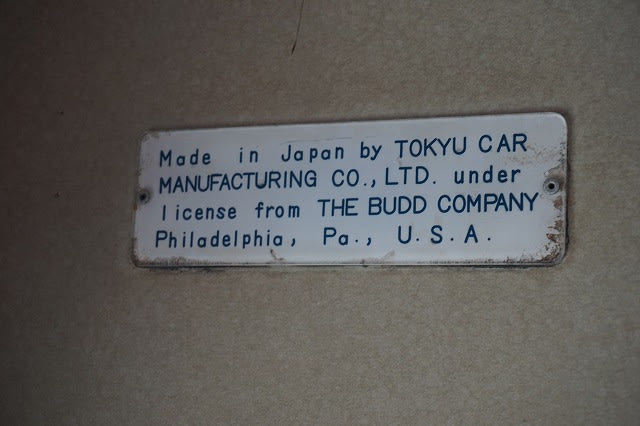2017年7月15日。
特に特別な動機はなかったですが、富士急行の電車の撮影をしたくなったので行くことにしました。はじめに駿河小山駅へ遠回りして、たまたま居合わせた(棒)ZBSを拉致。
そしたら国道138号線を走って河口湖へ行き、いつもの店で吉田うどんを食べたら富士急の河口湖駅へ。

事前に知らなかったのですが、何やら今日は河口湖駅で撮影会をやっているんだそうな。入場券を買うだけで参加できるので入りました。
撮影会の時間まではホームに停まっている電車を撮ります。205系こと6000系ですが、なんか瑞雲師匠のヘッドマークが付いていますね。
ちょうど瑞雲祭りをやっている時期なのでした。そっちには行きませんでしたけど。

戸袋の部分にも立ち絵のフィルムが貼られてます。まあ、今や電車のラッピングくらいでは驚きませぬ。

隣には371系こと8500系。改造後の姿は初めて見ました。まさか再びRSEと同じ線路を走るとは思わなんだ。
改造後の姿は色々言われてますが、現物が残っているだけでも結構なことだと思いますよ。

ただまあ、371系の魅力だった窓の天地の高さを潰してしまったのは「あぁ、そうですか・・・」という具合の顔になりましたけど。

5000系こと1000系。マッターホルン号と富士登山電車です。これもいまや半分以下の勢力になってしまいました。

表に出てバス撮影。
富士急シティバスの日デスペースウィングI+富士1S(E8231)。路線バスだけどハイデッカー構造です。観光バスのお下がりなのかも。
富士重工ボディの高速バス車も少なくなってきているような印象があります。

なんか変わったボンネットバスが。エアロミディを改造したという観光用周遊バス(F5969)です。
ボンネットはハリボテ。ホイールベースも変わってないですから、本来ボンネットにあるはずの前輪も無いです(でもフェンダーのような形状は作ってあるのだ)。でも凝った作りをしてますし、車体本体もフロントガラスの傾斜や方向幕周りの形状に原型との差異がありますから、ここには改造が及んでいるのではないでしょうか。
さらに後部には燃焼炉のハリボテが付けられていることから、このバスは薪バスという設定なのでしょう。薪バスが分かる人少ないだろうに、見るほどに凝ってるなと思います。

そういえばこんなポスターも貼ってありましたね。七駆がまぶしい。

では撮影会会場へ。構内の留置線が会場です。並んでいるのは183系、E233系、485系「やまどり」、ついでにE259系。どれもJRの電車じゃん。

E259系。「成田エクスプレス」用の電車ですが、数が余り気味なのか土休日には河口湖駅まで顔を出しています。なので撮影会に合わせて呼ばれたわけではなく、ちゃんとした運用でここにいます。
しかし2019年のダイヤ改正でJRから富士急行へ直通する特急/快速はE353系の特急「富士回遊」に統一されてしまったので、今はここまで来なくなってしまいました。

主役の3本。型式も用途も異なる電車同士です。

左側が183系。ご存知国鉄型特急電車です。この頃にはすでに廃車の噂は立っていて、今日原稿を書くまでの間に既に廃車になってしまっています。あずさ色の塗装も過去帳入りだし、ホリデー快速富士山ももうありません。

中央はE233系。ご存知JR東の主力通勤型電車。
風防左下の編成番号を見てみると青669編成でした。いわゆる青編成は通常青梅線か五日市線での走行に限られています。過去にも青編成が富士急まで乗り入れた実績はあるみたいですが、珍しいっちゃ珍しいんじゃないでしょうか。

右側は485系「リゾートやまどり」。ご存知ジョイフルトレインです。今日は臨時列車としてはるばる高崎からやってきました。
今時珍しい茶色い電車。座席が広々しているようで、一度乗ってみたいなぁとは思ってますが果たして・・・。

正面から。架線柱も無いし、とてもスッキリした構図がありがたい。

横から。隣に並んでいる富士急の電車と一緒に。

ローアングラー。

隣に並んでいる富士急の電車。撮影会の被写体にはなっていないので少し奥にいます。
6000系が2本、1000系が1本。6000系のマッターホルンは初見だったのですがこの日は動いておりませんでした・・・。
撮影会を出たところで今回はここまで。