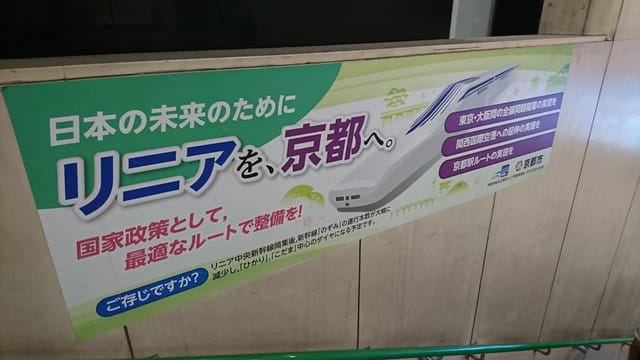第37走者:泉北高速鉄道準急難波行(5000系)和泉中央13:57→新今宮14:29
和泉中央駅は行き止まりなので、難波方面へと戻ります。乗るのは来たときと同じ5000系。

隣には到着した7000系。これはかっこいい電車。京王8000系みたい。

新今宮駅でJRに乗り換え。乗り換え待ちの時にやってきた201系を撮影。まだいなくなる気配は見せませんが、できるうちに記録しておくものです。この頃はまだおおさか東線の主力になるとは思いもせず。

第38走者:JR大和路線「大和路快速」加茂行(221系)新今宮14:42→加茂15:34
大和路線に乗り換え。この221系、更新工事は受けてるけど先頭の転落防止幌が付いてないわけですが、この先頭車には増結しないから必要ないってことですかね?
221系更新車は座席が少し減っているのが残念ポイントですが空いていたので無問題。

加茂駅到着。駅に着く前、右手の車窓に蒸気機関車の静態保存車が見えるんですが、いつも見に行けずじまい。

第39走者:JR関西本線普通亀山行(キハ120形)加茂15:42→柘植16:36
おなじみのキハ120に乗り換え。関西本線のキハ120は親の顔より見たことのある気動車です。2両編成だったので座れました。

柘植駅で下車。ここで反対の列車とすれ違いです。見た目は貧相だけど悪くない車両だよねというのが何回か乗ってみての印象。

後追い。関西本線はローカル線に成り下がってますけど、その設備にはかつての幹線・・・というか関西鉄道の残滓を感じられます。

レンガ造りの油庫。昔ながらの駅にはおなじみの設備。屋根が波形ストレートになって入り口はシャッターになってるけど、今も物置くらいには使ってるんでしょうかね?

自分はバレてないと思ってニンニンしてるんだろうけど、バレバレだぞ。まだまだ修行が足らぬな。

第40走者:JR草津線普通京都行(113系)柘植16:46→貴生川17:06
草津線の乗り換え。みんな大好き113系に乗ります。
乗っていると走行中びよんびよんと跳ねながら走りましてですね。これ、軌道がしょぼいと言うより電車の台車のバネが悪さしているように思えまして。
自分はたまにしか乗らないからいいですけど、毎日通勤通学で乗るとなったら結構疲れるんじゃないかな・・・?やはり古い電車なのだなと。

第41走者:近江鉄道本線高宮行(800系)貴生川17:11→八日市17:59
近江鉄道に乗り換え。貴生川から乗るのは初めてだし、そうでなくたってここから乗ることはそんなになさそう。

途中、日野駅で10分弱の停車。外に出てみます。中線を挟んだ対向式ホーム、構内踏切、そして経年の経っていそうな駅舎。なかなか面白い駅です。
駅舎については自治体の日野町も価値があると認めていて、資金を集めて立て直しの上で使用を続けています。いい話だ。

いいですね、ほんと。趣深い。

800系も撮影。健診に行けよ!という広告でした。

反対方向からも800系が到着。こっちは標準塗装。
絵になりますね。ホームも当初からだいぶ嵩上げしたのだなと。

八日市駅に着きました。留置線には820系の赤電塗装車が停まっていました。820系は元西武鉄道車なのでそれにちなんだ復刻塗装です。

反対には100形貴生川行が停まっていました。これも西武の中古電車ですが、ほぼ西武時代のまんまです。かつては中古電車に大改造をしてから運用を始めていた近江鉄道も今ではそういった技術も経済的余裕もないのかも知れませぬ。

八日市駅で9人目の鉄道むすめ、豊郷あかねをゲット。この人も電車にイラストがバーンと貼られたりグッズがたくさん出てたりして露出が多いです。

跨線橋からの眺め。ここでも長い時間停まっていますが、これは近江八幡方面からやって来る電車の接続待ちをしているため。

第42走者:近江鉄道八日市線近江八幡行(800系)八日市18:10→近江八幡18:29
その近江八幡からやって来た電車の折返しに乗ります。

近江八幡駅に着きました。乗換通路に不動産会社(?)の広告があったんですけど、右に書かれてるコイツ。
お前、球団をクビになった後ここに再就職してたのか・・・。

第43走者:JR琵琶湖線新快速播州赤穂行(223系)近江八幡18:36→大阪19:42
これで関西地区の鉄道むすめは制覇しました。ということでこれにて終了。ZBSとはお別れ。また会おうメイトリクス。
私は新快速に乗って大阪へ戻ります。

梅田では少し前に架かったという大阪駅とヨドバシカメラをかけるいわゆるヨドバシ橋を見に来ました。ちょっと頼りないかな・・・という感じ。工期が短かったのかも。

夕飯は地下街で明石やk・・・もとい卵焼き。おいちい。

でも足りなかったので焼きスパゲッティも食べてしいました。コスパが良い。

最終走者:大阪市営地下鉄御堂筋線千里中央行 梅田→江坂
昨日と同じホテルに戻って2日目終了。その途中にあった信号機ですけど、もしかして「止まれ」と文字で指示されないと止まれない人たちが運転しているんですか?
スタンプラリーはひとまず終わりですが、明日はまた違う目的を果たしに行きます。
というところで今日はここまで。
翌日へ続く→