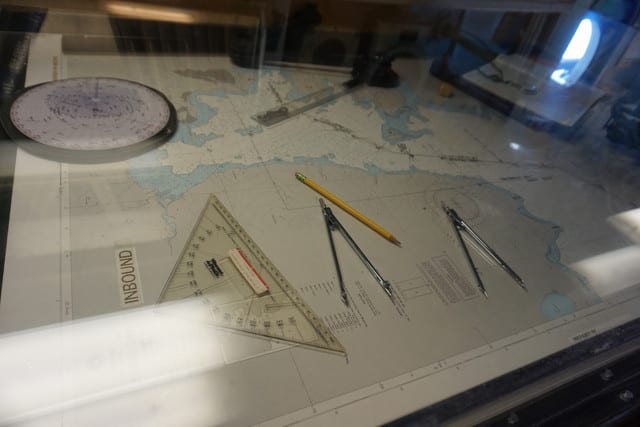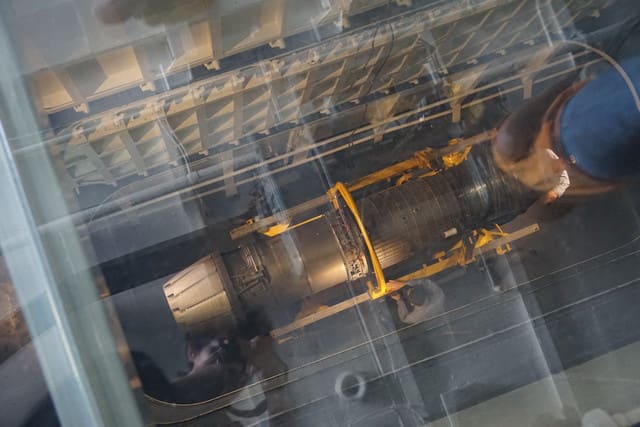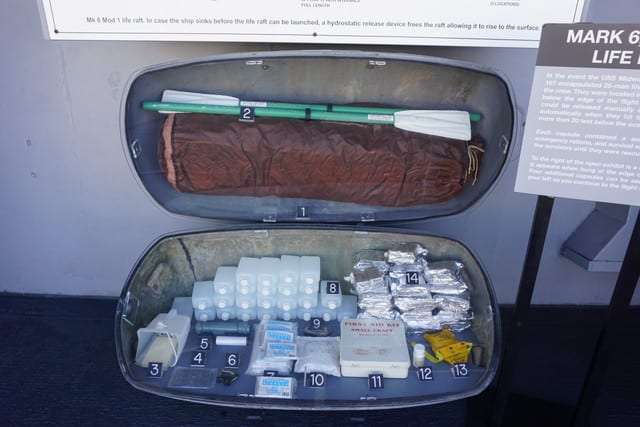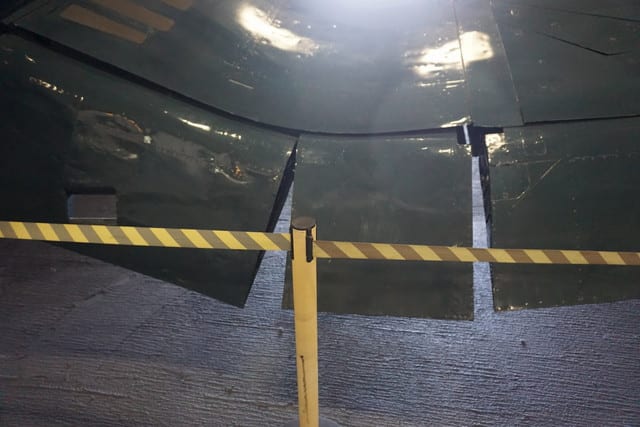USSミッドウェイのアイランド見学のツアーの後は、そのまま今度は艦内のツアーに移行します。
艦内住所(ブルズアイ)でいうと「B 0211 1L 6 FR 107 109 MAR DET」となっていますが、やはり分かりません。

「フラッグオフィサー」こと提督が過ごす部屋。さすが提督となるとこのくらい豪華になります。

ボーイングのレリーフが飾ってありましたけど、USSミッドウェイのスポンサーになっているんでしょうかね?

提督のベッド。意外と狭いかな。1人用ベッドにしては広いですけど。

提督付参謀長の専用室。会議室みたいな感じです。

参謀長部屋用の厨房。部屋の隣りにあります。将軍級になると余裕ある造りですよね。厨房にはアーロン(仮名)が参謀長に出すポタージュを温めてます。

タイプライターを打っているジョニー(仮名)。これも参謀長部屋付きの通信室ですかね。

作戦室です。英語だとWar roomで直訳すると戦争部屋です。戦略的な事項を決定する時に使う部屋だそうな。

これ、湾岸戦争ですかね。

ご存知CICです。「トップガン」で見たことある薄暗い部屋です。

電照式のボード。書いてある内容はテキトーなのかな。OKINAWAとか書いてあるし。

無線通信部屋。通信の送受信がここで行われます。送信に関しては、テキストを暗号通信に変換して送信しますが、これは自動変換されるようです。
今のこの通信部屋は、アマチュア無線家が有事の際にアメリカ軍の通信を補助するための機関MARS(Military Auxiliary Radio System)の基地のひとつとして活用されています。空母の艦内で無線をいじれるのは楽しそうです。

空気圧式の伝声管です。現場では「バニーチューブ」(うさぎの管)と呼ばれてたそうな。
たぶん声を上げて伝えるのではなくて、管についているシンバルみたいなものを叩いて符号化した状態で伝えるのかしらね。でも受信はどうなってるのかな・・・?

通信制御室。
通信設備の制御室です。通信に関しては知っていることはほぼ無いので何も言えません。

モールス通信を打つのを体験する機械。君の送信技術を試してみよ!

海兵隊用のお部屋。アメリカ海軍の空母に海兵隊が乗り込むの?という感想が出てきますが、これはうろ覚えですが艦内の治安維持のために海兵隊が派遣されていたみたいです、たしか。その海兵隊の長の部屋ですね。

トイレとシャワー付き。

そして最後にやってきたのが艦長室です。普通にオフィスだ。さすが正規空母だとこれだけ広いのね。ここまで広くする必要あるの?って感じもしますが。一般兵との格差が凄まじい。
ただ常時ここで過ごすわけじゃないようで、主に入港時に過ごす部屋だそうです。他の部屋は前回見たアイランドの艦橋にある部屋。他にも隠し部屋がありそう。

艦長のエルンスト(仮名)。ちゃんと執務中なんですよ。下敷きの上に書類は何も置いてないけども。

艦長となるとやはり一般兵とは別格ですから、実はからくり人形になっていて動きますし喋ります。こんなところからも海軍の格差社会が感じられるのです。

一方、艦長室付きの厨房で棒立ちの刑に処されているコックのカール(仮名)。俺にだって、ポタージュに胡椒をかける動作をするからくりを仕込んだっていいじゃないか・・・!

たぶん艦長にお昼のハンバーガーを作っていたところですね。
紅茶のカップは7人分あるのにハンバーガーは1つだけ。自分だけハンバーガーを食べるつもりなのかな?

以上をもってUSSミッドウェイの見学は終了です!お、終わった・・・。
空母の何たるやが少しわかった気がしますよ(気がするだけ)
正規空母の記念艦は日本では逆立ちしたって建つことのない博物館ですので、一度は行ってみていいと思いますよ。その設計思想と運用思想を自分の目で見れば何かしら得るものはあるでしょう。
空母の博物館は他にもサンディエゴの他にサンフランシスコとニューヨークなどにもあるので、割と行きやすいのです。
これでもう、観光らしい観光はすべて終了。あとは帰るだけですね。次回からこの旅行もいよいよ終盤です。