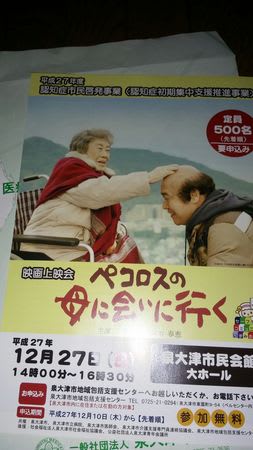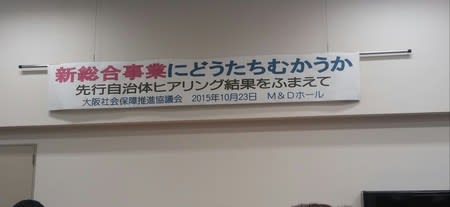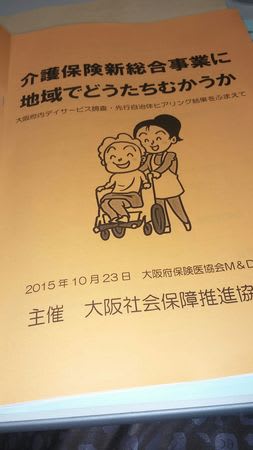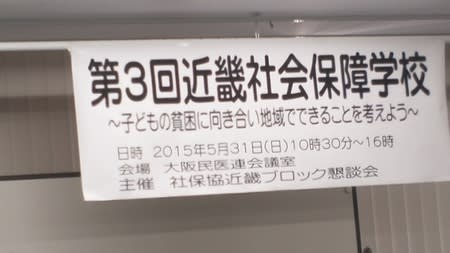新日本婦人の会泉大津支部のスプリングフェスタ。
フラダンス、着付け、古布リフォーム、パッチワーク、太極拳、コーラス、習字、俳画、短歌、レザークラフトなど、小組の発表が続きます。
「みんなで考えよう 泉大津の介護」というテーマで私の話も聞いていただきました。
持ち時間20分。なかなか難しい時間でした。5分~10分なら、いくつかのエピソードを交えた「あいさつ」。30分以上なら、制度解説も含めた「問題提起」。20分は、「制度解説」だけでも時間切れになりそう。
会員でもある、この集いでの出番のお話、いただいたのは確か、昨年末でした。
そして「介護の話で・・・」とテーマがしぼられたのは1ヶ月半ほど前でした。
いろいろ考えてはきましたが、一般質問が前々日だったので、結局、資料を用意したのは当日の朝になりました。
20分(2分ほどオーバーしました。)でお話させていただいたのは大要、以下の内容です。
要支援1・2の方の訪問介護とデイ・サービスが、保険給付からはずれて市町村の「総合事業」に。(2016年度は「猶予期間」の最終年度)
・・・という問題を中心に(特別養護老人ホームの新設計画もあり、「保険料高すぎ!何とかして!!」という会員さんの声もあり、問題山積ですが「持ち時間20分」ですので「総合事業」に的をしぼりました。)
(その1)この問題の背景・・・国は2025年度(団塊の世代が75歳以上に)に向けて何を考えているのか?
「少子高齢化」で「社会保障費の増大が見込まれる。と言いますが、厚生労働省の試算によれば「年金・医療・介護・子育て支援」の中で、年金、子育てはあんまり心配していないようです。(要するに、拡充する気がないよう。これも問題ですが)医療は1.5倍に、介護は2・5倍に(2011年度比)膨れあがるという試算のもと、「持続可能な制度」にするために、医療・介護の総費用を抑制しなければならない!!と言います。
そのために始まっている、そして、これからやろうとしている、医療費、介護保険の負担増。

「70歳~74歳の医療を1割から2割へ」(2014年4月)、「介護保険の利用料1割から2割へ(所得160万以上)」(2015年8月)から始まり、今後、段階的に「医療も介護も所得制限なしに2割に」しようと動き出している。
要支援の方のサービスの「総合事業」への移行で一体どうなるのか???不安がいっぱいな中で、さらに要介護1・2まで保険給付からはずそうとしています。
要支援の「保険給付から総合事業へ」はこういうなかで、おきている問題です。
(その2)「新総合事業」とは何か?
全国一律の基準の「保険給付」と違い、サービスの内容も利用料も市町村が独自に決めます。大阪市や堺市の案が発表されていますが、利用者にとっても事業者にとってもずいぶん不安。生活援助のヘルパーは「無資格者でもOK。3時間未満の短時間ディサービスなど。)
泉大津の具体案は「ただいま検討中。遅くとも今年の10月までに示す」という議会での答弁でした。
(その3)わが町の「安心・安全の暮らし」をどうつくるか?(私の提案)
①地域で見守り支えあう仕組みづくり(担い手、支え手を広げ、つなげる。)
配食サービスを充実し、せめて1日1食はバランスのとれた温かい食事を安否確認を兼ねて。「家から目的地への外出支援サービス」で「行きたいところへ行きたいときに出かけられる暮らし」を。「閉じこもりにならず、おしゃべりしたり、大声で笑ったり、感動したり・・・」の「居場所づくり」を無数に。・・・介護認定に関わらず全ての高齢者を対象にした豊かな「支えあい」活動を創っていきたい。新婦人が月に1回、ずっと続けていた“ほのぼのお食事会”も、そのひとつ。
②「現行相当サービス」と言われる専門職による介護は、これからも必要な全ての人に保障すること。「家事援助」であってもヘルパーさんの役割はボランティアに置き換えることはできません。心ある事業所、介護従事者の皆さんとともに介護サービスの基盤を守ること。「軽度」の段階できちんとした専門職による介護を保障してこそ、重度化を防ぎ、結果として介護の総費用も抑制することに。
フラダンス、着付け、古布リフォーム、パッチワーク、太極拳、コーラス、習字、俳画、短歌、レザークラフトなど、小組の発表が続きます。
「みんなで考えよう 泉大津の介護」というテーマで私の話も聞いていただきました。
持ち時間20分。なかなか難しい時間でした。5分~10分なら、いくつかのエピソードを交えた「あいさつ」。30分以上なら、制度解説も含めた「問題提起」。20分は、「制度解説」だけでも時間切れになりそう。
会員でもある、この集いでの出番のお話、いただいたのは確か、昨年末でした。
そして「介護の話で・・・」とテーマがしぼられたのは1ヶ月半ほど前でした。
いろいろ考えてはきましたが、一般質問が前々日だったので、結局、資料を用意したのは当日の朝になりました。
20分(2分ほどオーバーしました。)でお話させていただいたのは大要、以下の内容です。
要支援1・2の方の訪問介護とデイ・サービスが、保険給付からはずれて市町村の「総合事業」に。(2016年度は「猶予期間」の最終年度)
・・・という問題を中心に(特別養護老人ホームの新設計画もあり、「保険料高すぎ!何とかして!!」という会員さんの声もあり、問題山積ですが「持ち時間20分」ですので「総合事業」に的をしぼりました。)
(その1)この問題の背景・・・国は2025年度(団塊の世代が75歳以上に)に向けて何を考えているのか?
「少子高齢化」で「社会保障費の増大が見込まれる。と言いますが、厚生労働省の試算によれば「年金・医療・介護・子育て支援」の中で、年金、子育てはあんまり心配していないようです。(要するに、拡充する気がないよう。これも問題ですが)医療は1.5倍に、介護は2・5倍に(2011年度比)膨れあがるという試算のもと、「持続可能な制度」にするために、医療・介護の総費用を抑制しなければならない!!と言います。
そのために始まっている、そして、これからやろうとしている、医療費、介護保険の負担増。

「70歳~74歳の医療を1割から2割へ」(2014年4月)、「介護保険の利用料1割から2割へ(所得160万以上)」(2015年8月)から始まり、今後、段階的に「医療も介護も所得制限なしに2割に」しようと動き出している。
要支援の方のサービスの「総合事業」への移行で一体どうなるのか???不安がいっぱいな中で、さらに要介護1・2まで保険給付からはずそうとしています。
要支援の「保険給付から総合事業へ」はこういうなかで、おきている問題です。
(その2)「新総合事業」とは何か?
全国一律の基準の「保険給付」と違い、サービスの内容も利用料も市町村が独自に決めます。大阪市や堺市の案が発表されていますが、利用者にとっても事業者にとってもずいぶん不安。生活援助のヘルパーは「無資格者でもOK。3時間未満の短時間ディサービスなど。)
泉大津の具体案は「ただいま検討中。遅くとも今年の10月までに示す」という議会での答弁でした。
(その3)わが町の「安心・安全の暮らし」をどうつくるか?(私の提案)
①地域で見守り支えあう仕組みづくり(担い手、支え手を広げ、つなげる。)
配食サービスを充実し、せめて1日1食はバランスのとれた温かい食事を安否確認を兼ねて。「家から目的地への外出支援サービス」で「行きたいところへ行きたいときに出かけられる暮らし」を。「閉じこもりにならず、おしゃべりしたり、大声で笑ったり、感動したり・・・」の「居場所づくり」を無数に。・・・介護認定に関わらず全ての高齢者を対象にした豊かな「支えあい」活動を創っていきたい。新婦人が月に1回、ずっと続けていた“ほのぼのお食事会”も、そのひとつ。
②「現行相当サービス」と言われる専門職による介護は、これからも必要な全ての人に保障すること。「家事援助」であってもヘルパーさんの役割はボランティアに置き換えることはできません。心ある事業所、介護従事者の皆さんとともに介護サービスの基盤を守ること。「軽度」の段階できちんとした専門職による介護を保障してこそ、重度化を防ぎ、結果として介護の総費用も抑制することに。