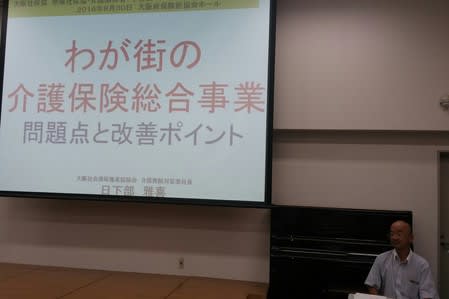議会の直前でも、最中でも、というよりそういう時こそ、市民の方から相談の声がかかります。
何度お聞きしても悲しいのは、人生の先輩の皆さんが、どれだけつつましく暮らしながら、どれだけ切ない思いをしておられるかということ。
今日、お会いした方もその一人。
電話の声もハリがあり、歩く姿勢も背筋が伸びて、でもお年を聞けば、80代半ば。
お連れ合いは、入退院を繰り返し、今は入院中。
平均よりは多い年金収入があっても、そのほとんどは入院の費用に消える。
家賃と、在宅で一人暮らす生活費は貯えを少しずつ取り崩し。
その貯えが、もう底をつく。
「生活保護を受けるのは恥だ」と、親に言われて育ったとおっしゃる。
80代の方のご両親だから、明治のお生まれかもしれない。
「健康で文化的な生活を全ての国民に約束した日本国憲法」の下で、生活保護制度を活用して、どうか身も心も安らかに暮らしていただきたいと思う。
安心して、医者に行っていただきたいと思う。
堅実に生きて、税金も年金保険料も、国保料も納めてこられた80代の方々に、生きていくために足りない年金を生活保護の支給で補うことを「恥ずかしい」と感じさせる政治と社会こそ恥ずかしい。