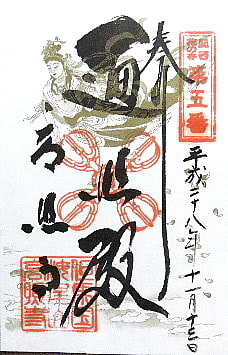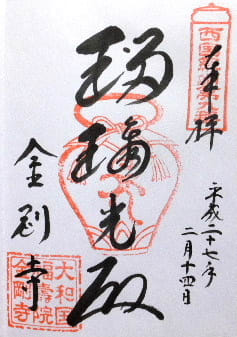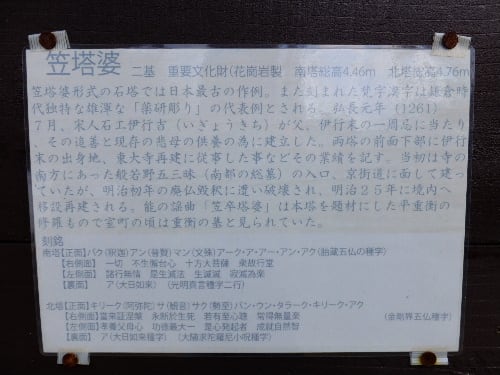久安寺参拝も丁度折り返しで後半に突入です。
【朱雀池】

蓮は少しだけ咲いていました。
【両果の道】

この道の雰囲気が良いんだよなぁ。
【バン字池】

【舞台】


舞台の上から本堂裏手を望む。
ここから見る庭園はいいね~。(^^
気候が良かったらここで弁当でも食べたら美味さ倍増やね。
【修行大師像】

【愛宕地蔵尊】

【本堂】

【地蔵尊】

【三光社】
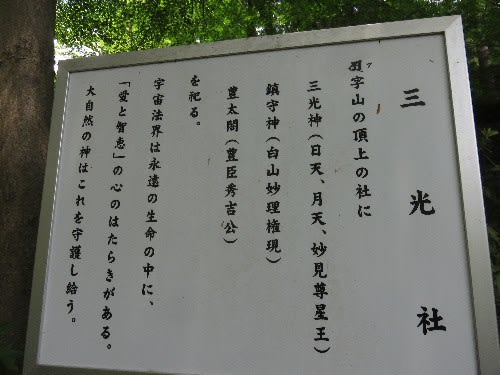


【薬師堂】

西国薬師霊場の札所であり、
葬儀法要等を行う仏教会館を兼ねている薬師堂。
またの名を瑠璃光殿と呼びます。

中心に阿閦薬師如来が祀られていますが、
月光、日光菩薩は絵でした。
【芳泉庭】


【仏足石】

【本堂】

摂津国三十三所霊場札所。

ようやく本堂に参拝です。


四天王に守られた御本尊は秘仏で、
御前立がいらっしゃいました。
【鐘楼堂】



【豊臣秀吉腰掛石】


【御朱印】

御朱印は四種類ありました。

こちらは関西花の寺札所の書置きの御朱印です。
予想以上に見所たっぷりで素晴らしいお寺でした。
大阪にこれほどの庭園と花の名所のお寺があるとは。
まだまだ見知らぬ寺社が大阪にもあるんだね。
【朱雀池】

蓮は少しだけ咲いていました。
【両果の道】

この道の雰囲気が良いんだよなぁ。
【バン字池】

【舞台】


舞台の上から本堂裏手を望む。
ここから見る庭園はいいね~。(^^
気候が良かったらここで弁当でも食べたら美味さ倍増やね。
【修行大師像】

【愛宕地蔵尊】

【本堂】

【地蔵尊】

【三光社】
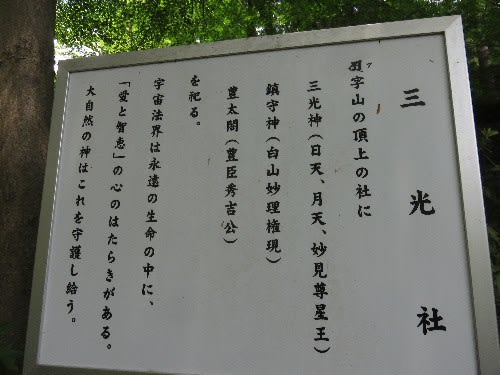


【薬師堂】

西国薬師霊場の札所であり、
葬儀法要等を行う仏教会館を兼ねている薬師堂。
またの名を瑠璃光殿と呼びます。

中心に阿閦薬師如来が祀られていますが、
月光、日光菩薩は絵でした。
【芳泉庭】


【仏足石】

【本堂】

摂津国三十三所霊場札所。

ようやく本堂に参拝です。


四天王に守られた御本尊は秘仏で、
御前立がいらっしゃいました。
【鐘楼堂】



【豊臣秀吉腰掛石】


【御朱印】

御朱印は四種類ありました。

こちらは関西花の寺札所の書置きの御朱印です。
予想以上に見所たっぷりで素晴らしいお寺でした。
大阪にこれほどの庭園と花の名所のお寺があるとは。
まだまだ見知らぬ寺社が大阪にもあるんだね。