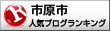今日は昨日とは打って変わっていいお天気に!むしろ、暑いぐらいでしたね。
国府祭り二日目もますます盛り上がったことと思いますが、
今日はこちらに出席。
八幡地域の敬老会です。

式典の後の「演芸の部」では、地元の八幡小、石塚小、八幡中の児童生徒たちが、参加者の皆さんに敬意と感謝を込めた、素晴らしいパフォーマンスを披露してくれました。
上の写真は、石塚小の音楽部による演奏。
そしてこちらは、八幡中の有志チームによるエイサー。

市原市内の75歳以上の方は、今年8月時点で35428名。
うち100歳以上の方は205名で、そのうち男性が29名、女性が176名なのだそうです。
う~ん、女性は強し。男性の6倍か・・・(^^ゞ
そして午後は事務所で、大和田一紘先生(多摩住民自治研究所理事)をお招きしての財政講座。
4回シリーズで企画したうちの3回目。9月は議会のため時間が取れなかったので、久々の開講です。

今回のお題は、市民の皆さんが最も身近に感じ興味深い「歳出」について。つまり、税金の使われ方ですね。
主に市原市の決算カードを使って、その読み解き方を基礎から応用まで教えていただきました。
ちょっと独特の用語が多いので慣れないと難しいのですが、参加された市民の皆さんはとても熱心に耳を傾けていました。
質問も多く飛び出し、大和田先生もまだまだ言い足りないことがありそうだったので、急きょ4回シリーズをもう1回増やし、5回シリーズにすることに決定!
次回(4回目)は8日(土)13時半からです。初めての方もお気軽にご参加ください(^^)/
国府祭り二日目もますます盛り上がったことと思いますが、
今日はこちらに出席。
八幡地域の敬老会です。

式典の後の「演芸の部」では、地元の八幡小、石塚小、八幡中の児童生徒たちが、参加者の皆さんに敬意と感謝を込めた、素晴らしいパフォーマンスを披露してくれました。
上の写真は、石塚小の音楽部による演奏。
そしてこちらは、八幡中の有志チームによるエイサー。

市原市内の75歳以上の方は、今年8月時点で35428名。
うち100歳以上の方は205名で、そのうち男性が29名、女性が176名なのだそうです。
う~ん、女性は強し。男性の6倍か・・・(^^ゞ
そして午後は事務所で、大和田一紘先生(多摩住民自治研究所理事)をお招きしての財政講座。
4回シリーズで企画したうちの3回目。9月は議会のため時間が取れなかったので、久々の開講です。

今回のお題は、市民の皆さんが最も身近に感じ興味深い「歳出」について。つまり、税金の使われ方ですね。
主に市原市の決算カードを使って、その読み解き方を基礎から応用まで教えていただきました。
ちょっと独特の用語が多いので慣れないと難しいのですが、参加された市民の皆さんはとても熱心に耳を傾けていました。
質問も多く飛び出し、大和田先生もまだまだ言い足りないことがありそうだったので、急きょ4回シリーズをもう1回増やし、5回シリーズにすることに決定!
次回(4回目)は8日(土)13時半からです。初めての方もお気軽にご参加ください(^^)/